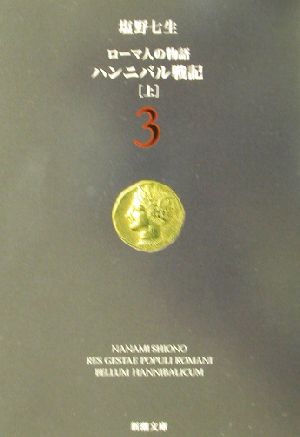ローマ人の物語(3) の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
ローマがシチリアを巡りカルタゴ(今のリビア)と争う。 そのカルタゴにハンニバルが現れる前の第一次ポエニ戦役。 ローマは大きくなるために多くの戦争を勝ち抜き、その中で戦役をシステムとして扱った。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
第1次ポエニ戦争。シチリアの都市メッシーナからの救援要請。シラクサ、カルタゴとの戦いに突入。シラクサ僭主ヒエロンとの講和。海軍を持たないローマによる海軍設立。連勝するローマ海軍。台風などで失われるローマ海軍。カルタゴに上陸したローマ軍。カルタゴに雇われたスパルタ人傭兵隊長クサンティッポに敗れるローマ軍。有利になったカルタゴに解雇されたクサンティッポ。再び戦況はローマ有利に。シチリアに派遣されるハミルカル。講和条約。シチリアを失ったカルタゴ。傭兵たちの反乱。ハミルカルによる鎮圧とスペイン入植。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
有名なポエニ戦争を扱ってます。 有名なハンニバルやスキピオ(アフリカヌス)が登場する前、父親たちが主役の時代。 ようやくイタリア半島を統一したローマが強国カルタゴに挑む!
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
購入者:丸橋(2012.3.1) GKに需要があるのか不安なシリーズ第三巻。「ハンニバル戦記」と銘打たれているが、そのお父ちゃんの時代。シチリア島を舞台にした第一次ポエニ戦役の動乱、その原因〜解決まで。敗軍の将は罰せず、時には挽回のチャンスを与える古代ローマのおおらかさと政治のシステム、カルタゴとの対比がおもしろいです。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
古代ローマ版、銀河英雄伝説といった感じでした。 (本当はその逆なんだろうけれども) 一つ一つの会戦にドラマがあって、お互いの立場を超越した スキピオとハンニバルの戦でつながる絆とでも言えばいいのでしょうか。 そういったロマンにこれでもかというぐらいに、読み手は打ちのめされます。 大国カルタゴの栄枯盛衰であったり、ハンニバル→スキピオへのシーソーゲームとも言うべき、地中海の覇権をめぐる大戦は大いなる人間ドラマ以外の何物でもありません。 世界史に疎い人でもこれは読むべき。
Posted by
高校の時にネロが載ってる巻を読んで以来。5月祭で50円で売ってた。 第一次ポエニ戦争後までが書いてある。ハミルカル、ハンニバル父子がイスパニアに渡ったとこで終わるので次も読みたくなる。 ローマ軍の制度がものすごく詳しく書いてあってさすがにそのへん(とくに最後のほう)は全部ちゃ...
高校の時にネロが載ってる巻を読んで以来。5月祭で50円で売ってた。 第一次ポエニ戦争後までが書いてある。ハミルカル、ハンニバル父子がイスパニアに渡ったとこで終わるので次も読みたくなる。 ローマ軍の制度がものすごく詳しく書いてあってさすがにそのへん(とくに最後のほう)は全部ちゃんと読もうとはしなかったけど、それでも面白く読ませるのがすごいなあ。 三段櫂船と五段櫂船、カラスの話は面白かった。 鐙は中世まで存在せず重装歩兵が主力だったと書いてあったので、『グラディエーター』の冒頭シーンみたいなのはなかったみたいですな。
Posted by
2012 10/5読了。秋葉原のブックオフで購入(古書)。 『ジュリアス・シーザー』を読んでて久々に古代ローマ熱が高まり、文庫に手を出し始めてしまった。 それもいきなりハンニバル戦記から読み始める、という。 とはいえこの巻はまだハンニバルは活躍しない、第1次ポエニ戦役メイン。 塩...
2012 10/5読了。秋葉原のブックオフで購入(古書)。 『ジュリアス・シーザー』を読んでて久々に古代ローマ熱が高まり、文庫に手を出し始めてしまった。 それもいきなりハンニバル戦記から読み始める、という。 とはいえこの巻はまだハンニバルは活躍しない、第1次ポエニ戦役メイン。 塩野七生節に慣れるのに良い感じ。あと古代ローマの制度とかを思い出すにも。
Posted by
第1次ポエニ戦役と戦役後(紀元前264年~前219年)の話。戦役とあるだけに、ほとんど戦いの話だが、両民族の考え方の違いから書かれていて面白い。歴史はプロセスにある、と序章に作者が書いているように、なぜそうなったのか、がよく描かれている。3,4,5巻で「ハンニバル戦記」になるのだ...
第1次ポエニ戦役と戦役後(紀元前264年~前219年)の話。戦役とあるだけに、ほとんど戦いの話だが、両民族の考え方の違いから書かれていて面白い。歴史はプロセスにある、と序章に作者が書いているように、なぜそうなったのか、がよく描かれている。3,4,5巻で「ハンニバル戦記」になるのだが、高校の教科書ではこの内容は5行でしかないらしく、確かに、オトナのための歴史といえる。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
P11 2つの歴史への対し方①アッピールしたいことの例証として、歴史を使うやり方 e.g.)マキアヴェッリ ②叙述(彼らにとっては、これは目的であり手段ではない) e.g.)モムゼン、ギボン 後者の分量が多くなるのは、プロセスを追っていくことではじめて、歴史の真実に迫ることも可能になると考えるから→戦争くらい、当事国の民を裸にして見せてくれるものはない P14 "裁く"としたら、「時代の要求に応えていたかどうか」 RES GENTAE POPULI ROMANI(ローマ人の諸々の所行) P45 海運の伝統がなかったからこそ、「カラス」を発案できたローマ人 苦手なフィールドを、得意分野に持ち込む P62 約束通りにカルタゴに戻ったレグルスを、カルタゴ人は、丸い籠の中に押しこめ、それを象たちがフットボールするというやり方で殺した P62 名誉挽回の機会を与えてやろうという温情ではない、失策を犯したのだから、学んだにもちがいない、というのであったのだから面白い←戦中の日本軍とのちがい? P67 執政官メテルス 象の恐怖を払しょくさせることに成功 P73 クラウディウス・プルクルスは、敗北ではなく、リーダーには許しがたき浅慮、を罰せられたのである P80 戦時国債…有産階級、元老院議員、政府要職のみ P104 ローマ人の面白いところは、何でも自分たちでやろうとしなかったところであり、どの分野でも自分たちがナンバー・ワンでなければならないとは考えないところであった P115 累進課税の制度もなく一律に収入の十分の一だけを払えばよいとなれば、私でも喜んで払う。経費とか所得とか言い始めるから、人間は悪知恵を働かせるようになるのである。一律十分の一となると、国税庁の規模は半減するであろうけれど。 P117 ローマはしかし、覇権国家であった。覇権国家は、傘下にある国々を防衛する義務を負うとともに、それらの国の人々の利益を守る義務も負う P118 ローマは、イリリア族の王の許に使節を派遣し、海賊行為をやめるよう要請した←国が違っても同じようなことが P127 17~45歳(現役)…ユニオーレス(ジュニアの語源) 46~60歳(予備役)…セニオーレス P142 マミュアル化好きのローマ人 宿営地建設も←毎年指揮官から兵から変わるのだから必要であった
Posted by
第一次ポエニ戦役を記した第3巻。これだけでも45年経過している。 戦闘に負けても次の機会を与えるローマと、1回負けただけで処刑してしまう大国カルタゴの差を著者は説く。建国の歴史が浅く、まだ弱かったローマはそうせざるえない事情があったのだろうが、いざやってみる有効であるとみなされ、...
第一次ポエニ戦役を記した第3巻。これだけでも45年経過している。 戦闘に負けても次の機会を与えるローマと、1回負けただけで処刑してしまう大国カルタゴの差を著者は説く。建国の歴史が浅く、まだ弱かったローマはそうせざるえない事情があったのだろうが、いざやってみる有効であるとみなされ、システム化されていったのだろう。ローマ人の気質にもあっていたのだろう。 第3巻ではハンニバルの父の物語もあり、スペインの開拓の描写もあり興味深い。後のカエサルの相手であるガリア人の話もあり、多くの重要な事項の前段階の時代描写がある。
Posted by