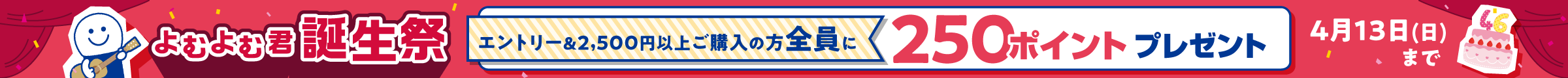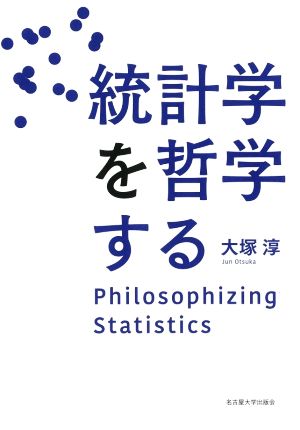- 書籍
- 書籍
統計学を哲学する
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
統計学を哲学する
¥3,520
在庫あり
商品レビュー
4.4
11件のお客様レビュー
深層学習をベースにした技術が世間を席巻する中、そこから導き出される結果や理論を信用する根拠はどういうところにあるのか認識論的な課題を投げかける本。 何もかもが確率統計で答えが出せるように見えて、その因果関係が正しいと言える前提は成り立っているのか。成り立ってていないとしても...
深層学習をベースにした技術が世間を席巻する中、そこから導き出される結果や理論を信用する根拠はどういうところにあるのか認識論的な課題を投げかける本。 何もかもが確率統計で答えが出せるように見えて、その因果関係が正しいと言える前提は成り立っているのか。成り立ってていないとしてもそれを人が信用するのはなぜなのか。 確率によって導き出される結論が正しいとするためにはその仮定として自然の斉一性(試行をすべて試すことができ、そこに異常な偏りがないこと)を必要とする。 つまり2022年11月に世界を席巻し始めたChatGPTを始めとするLLMの提示する答えや結論に対して因果関係の成立を待たずに信用することに対して認識論的には課題が残っているのではないかと課題を投げかける。 くしくも2024年末ころからLLMの中には推論エンジンと言って旧来からあるQA対応するシンプルなLLMではなく多少時間がかかっても良いから多くの情報を調査しそこからあたかも因果関係を考慮しながら考えた結果を提示するような仕組みが提供され始めている。まるでIQの高い人間が長い時間かけて考えたかのように。 この推論エンジンは因果推論を保留して日常的に使われるようになったLLMつまりAIがなぜ正しいのかを説明し、自己証明する仕組みになりうるのかどうか。本書の深層学習に対する期待と疑問を読みながらそのようなことを考えた。
Posted by 
確率や統計に接していて常々疑問に思っていたことが、本書で述べられていた。本書の読了後、統計処理をしていていろいろと腑に落ちることが多くあった。
Posted by 
哲学者というのは99%は価値のない研究をしているが、数学や物理学(特に量子力学)を対象とするとなんかすこしカッコよい感じがする。まったくの勘違いなのであるが。 高度に抽象化された数学は哲学と同一視されるという暴論をよく聞くが、全くのお門違いであると言いたい。 本書は対象が確率で...
哲学者というのは99%は価値のない研究をしているが、数学や物理学(特に量子力学)を対象とするとなんかすこしカッコよい感じがする。まったくの勘違いなのであるが。 高度に抽象化された数学は哲学と同一視されるという暴論をよく聞くが、全くのお門違いであると言いたい。 本書は対象が確率である。なるほど、確率ほど数学が哲学チックになる分野はないね。 「明日の天気は30%の確率で雨です。傘を念のため持っていくと良いでしょう」とお天気キャスターはいう。 30%の確率で雨。 これはいったい何を主張しているのだろうか。 仮に明日を何回も試すと(数学では試行と呼ぶ)、10回中3回は雨になる、といっているのであろうか。 それとも、今日の気圧配置を時間発展させると(つまり時間依存の方程式を数値的に解く)100回のシミュレーションで30回は雨になりました、ということでしょうか。 哲学者が良く使う難解な言葉でけむに巻く論調。正直言ってもううんざりです。 そんな時間があるのであれば哲学よりも数学を学びましょう。
Posted by