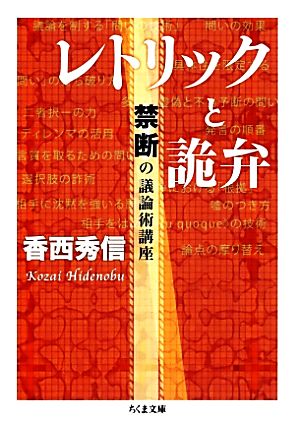
- 中古
- 書籍
- 文庫
- 1224-18-13
レトリックと詭弁 禁断の議論術講座 ちくま文庫
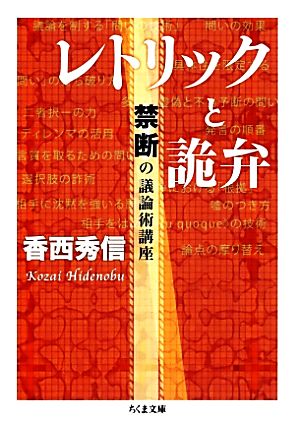
定価 ¥814
605円 定価より209円(25%)おトク
獲得ポイント5P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 筑摩書房 |
| 発売年月日 | 2010/05/01 |
| JAN | 9784480427083 |
- 書籍
- 文庫
レトリックと詭弁
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
レトリックと詭弁
¥605
在庫なし
商品レビュー
4
33件のお客様レビュー
印象に残った事 ↓↓↓ ・問いを出す者は、主導権を握る 論争という特殊な条件の下で、論者が聴衆を自分たちの側に取り込もうとするとき、問いの機能が本質的に変わってしまう。 それは、問題の要点を明らかにするためというよりは、論敵をまごつかせ、聞き手に彼の議論に対する不審の念を抱かさせ...
印象に残った事 ↓↓↓ ・問いを出す者は、主導権を握る 論争という特殊な条件の下で、論者が聴衆を自分たちの側に取り込もうとするとき、問いの機能が本質的に変わってしまう。 それは、問題の要点を明らかにするためというよりは、論敵をまごつかせ、聞き手に彼の議論に対する不審の念を抱かさせるため、あるいはその立場に賛成できないことを遠回しにしめすためのものとなる。 こうした場合の問いは、何かわからないことについての説明を求めるという体裁をとりながら、痛烈な反論として、あるいは聞き手に与える論拠として用いられる。 つまり、問いは作った方が優位に立てる。 ・「答える」ではなく、「言い返す」 「はい」か「いいえ」を要求する問いにたいして、「はい」か「いいえ」で答えるのであれば、その問いの妥当性を、あるいはそれを問うという行為の是非を問題とする。 ・相手の言葉を封じてしまう「修辞疑問」 応答を期待せず、聴衆や読書に、心の中で分かりきった返事を示唆するだけのために出される問い。 話し相手が、問いかけられ、話し合いへの参加を求められているにもかかわらず、沈黙してしまうような対話を形成する。 修辞疑問は、問いのかたちを取るが、それは疑念を表したり、返答を引き出すためではなく、反対に、こちらの強固な確信を示し、話し相手に、否定できまい、返答することさえできまいと申し渡すためのもの。 例えば、「誰がそんなことをやれといった」 「何を考えているんだ」など ・問いに答えられないことは、議論では致命的になる。 沈黙することは、何の異論も反論も見出せないか、あるいは問題が議論の余地がないことの証拠とみなされる。 ・「お前も同じではないか」という論法 相手からこちら側の行為について批判されたとき、類似した行為を相手もまた犯していることを指摘して、批判を封じこめる。 ・「後出し」 議論においては、1番最後に喋る者は聴衆に強い印象を残し、相手の反論がないため優位にたてる。 ・都合のよい具体例のみが説得力をもつ 何かを説明するとき、具体的によって説明しようとする。その具体例が、判断の正しさを論証する根拠となっているとき、そのための一連の操作を「例証」と呼ぶ。 そうした具体例も自分に都合の良いものを自由に選ぶことができる。 感想 ↓↓↓ 自身も知らないうち使っていたような詭弁もあったので改めたいと思う。 相手を落とし入れるためではなく、自身の防御策 として利用しようと思う。
Posted by 
議論術に関するエピソード集といったところ。 著者は国語教育学の研究者で、国内外の様々な文学作品を引用しながら、議論術について語っている。 普段、無意識的に使っているテクニックなどもあって、面白く読むことができました。
Posted by 
「問いは議論を制す」というテーゼ?は特に敵対的交渉に威力を発揮しそうで、役に立ちそう。ノーベル賞作家の大江健三郎はある意味「バカ」だったというのも考えさせられる。他方で、2000年以上前のアリストテレスの方が偉大であったというのも、万人に備わっているとされる「理性の使い方」の重要...
「問いは議論を制す」というテーゼ?は特に敵対的交渉に威力を発揮しそうで、役に立ちそう。ノーベル賞作家の大江健三郎はある意味「バカ」だったというのも考えさせられる。他方で、2000年以上前のアリストテレスの方が偉大であったというのも、万人に備わっているとされる「理性の使い方」の重要性を思い知らされる。
Posted by 



