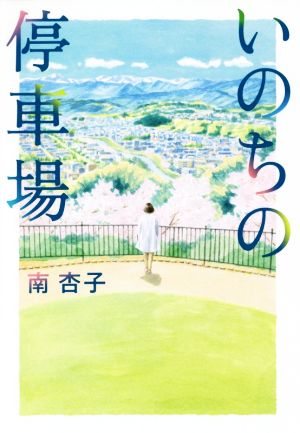いのちの停車場 の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
救命救急医だった咲和子が 故郷で在宅医療に携わる話。 医療の違いに戸惑いながらも 日々の在宅医療の様子を書かれていきます 問題を抱えた患者も多く 自分の知らなかった現状も知れました 6歳の子の話は 涙なしには読めませんでした…… 日本の医療が抱える問題はまだ多く それを突きつけられるような作品でした 終盤は自分の父親の 積極的安楽死についてという かなり重たい内容へとシフトされます 普段あまり病気や介護のことなど 考えていなかったですが 日本人の3人に1人が高齢者の中 全く他人事とは言えないと感じました 特にお父さんの病状の悪化の様子は ただの骨折が…と思わずにはいられません。 自分の親の介護、 自分が高齢者になったとき、 子どものこと、 いろいろ考えさせられました 特にラストは、、、
Posted by
新聞で紹介されているのをみてずっと読みたかった本。期待が大きすぎたせいか「こんなもん?」感もあるが、読んでよかった一冊だとは言える。訪問医療について知ることが出来たのが一番の収穫かな。
Posted by
映画化された作品 どこか幻想的に終末期医療を描いた「ライオンのおやつ」に対し、こちらは医師が書いたということもあり現実的に描かれています 実際の在宅医療は難しいことが多いのだろうと思います 作品はやや理想的に描かれているとは思いますが、いろいろと感じ入るところがありました ...
映画化された作品 どこか幻想的に終末期医療を描いた「ライオンのおやつ」に対し、こちらは医師が書いたということもあり現実的に描かれています 実際の在宅医療は難しいことが多いのだろうと思います 作品はやや理想的に描かれているとは思いますが、いろいろと感じ入るところがありました 最終的な判断は本人ではなく、残される者に委ねられることになる、いざその時どのような決断をするのか、難しいことですね
Posted by
南さんの本はこれで2冊目。1冊目のサイレントブレスもいのちの停車場も在宅医療のお話。いのちの停車場は終末期医療の話だけではなくいろいろな家族や患者の生きていく話もある。考えさせられる本だった。ただ最後の話はとても辛い話だった。患者の思い、家族の思い、医療者の思い いろいろな想いを...
南さんの本はこれで2冊目。1冊目のサイレントブレスもいのちの停車場も在宅医療のお話。いのちの停車場は終末期医療の話だけではなくいろいろな家族や患者の生きていく話もある。考えさせられる本だった。ただ最後の話はとても辛い話だった。患者の思い、家族の思い、医療者の思い いろいろな想いを描いている。やっと死ねるという気持ちで死なせないためには今後この問題をしっかり考えていかないといけないと思う。
Posted by
東京の救命救急センターで医師として働いていた咲和子は小さなミスを犯し辞める事に。生まれ故郷の金沢に戻り訪問医療、在宅医療をする。昔は家で終末期を迎え家族に看取られ亡くなった。本当は住み慣れた家で最後を迎えたい。でも今は中々難しい。救急医療、在宅医療について考えさせられた。
Posted by
都下の医科大病院救命救急センターで副センター長を勤める白石咲和子62は不意の大規模交通事故で夜間受け入れを独断し多くの救命を成す。が些細な点から責任を問われ病院を辞し故郷金沢に帰り、ひょんな縁から在宅訪問診療所で勤め始める。そこで遭遇する色々な患者の生き様から医療の何たるかに思い...
都下の医科大病院救命救急センターで副センター長を勤める白石咲和子62は不意の大規模交通事故で夜間受け入れを独断し多くの救命を成す。が些細な点から責任を問われ病院を辞し故郷金沢に帰り、ひょんな縁から在宅訪問診療所で勤め始める。そこで遭遇する色々な患者の生き様から医療の何たるかに思いを致す日々が6話綴られていてそれぞれ興味深い問題点も提起している。極め付けは咲和子の実父(もと勤務医)が突然の転倒から病に臥して急速に悪化していく件りで施療側と患者側更に患者家族の悩み苦しみを体感する章。ここで提起された尊厳死安楽死の問題がズンと来る!とても緊張して読まされる作品でした。柔らかい表紙絵とシビアな中身とのギャップが大きいですね♪ さっそく映画化された作品ですが観ていませんし、たぶん観ない方が良い気がします。これだけの内容を映像化すると稀薄なモノになってしまうでしょうから。
Posted by
在宅医療の現場の様子がよくわかる。 在宅医療は、医療面よりも福祉の面が強いのかも。 いかにその人らしく生きるか。 徹底的に生きたい人には、最新医学も視野に入れた手段で治療する。その一方で、苦しくない終末期の日々を支えるケアも行う。 在宅医療の重要性を表した言葉だと思う。 でも...
在宅医療の現場の様子がよくわかる。 在宅医療は、医療面よりも福祉の面が強いのかも。 いかにその人らしく生きるか。 徹底的に生きたい人には、最新医学も視野に入れた手段で治療する。その一方で、苦しくない終末期の日々を支えるケアも行う。 在宅医療の重要性を表した言葉だと思う。 でも最後は、えっ?となった。 何が正しいかはわからない。賛否両論あるはずだし。 でも人の死に関することなのだから、簡単に答えは見つかるはずがない。そもそも正解があるのかもわからないが。
Posted by
金沢が舞台の在宅医療現場。 在宅医療対象は高齢が多いが今回は経営者や子供もいる。配偶者が世話するパターンが多く、患者はもちろん介護者も相当疲弊するため溜め込まない、緩和させるためのケアも必要。町名が載っていたため「あぁ、あのあたりか」と想像もしやすく、随所にくどいくらい方言も散り...
金沢が舞台の在宅医療現場。 在宅医療対象は高齢が多いが今回は経営者や子供もいる。配偶者が世話するパターンが多く、患者はもちろん介護者も相当疲弊するため溜め込まない、緩和させるためのケアも必要。町名が載っていたため「あぁ、あのあたりか」と想像もしやすく、随所にくどいくらい方言も散りばめられており、こそばゆい。。 映画観よっと。 213冊目読了。
Posted by
東京の救命センターで副センター長として働く白石咲和子は問題の責任を取って退職し、故郷金沢で在宅診療を手伝うことになる。 医療ものですが、多分に感動系に持っていかず比較的淡々と各患者たちのストーリーが書かれている。 脳卒中を起こすと、その後「感覚過敏」「異痛症」に分類される頭の中...
東京の救命センターで副センター長として働く白石咲和子は問題の責任を取って退職し、故郷金沢で在宅診療を手伝うことになる。 医療ものですが、多分に感動系に持っていかず比較的淡々と各患者たちのストーリーが書かれている。 脳卒中を起こすと、その後「感覚過敏」「異痛症」に分類される頭の中が原因の痛みを感じるという。どちらになっても激しい痛みが日夜続くというのだから辛いところ。 いつ終わるとも知れない地獄のような中病院で延命させるのは本人のためなのか、家族に死なれたくない自分のためなのか… 治すのではなく看取ることの多い現場で、患者達、病状が悪くなっていく父と咲和子がどう向き合うかを通して、これからの在宅医療や安楽死の在り方を強く訴えかけられるような一冊だった。
Posted by
とてもよかった。 在宅医療の現実というものが勉強になった。 在宅医療に切り替えるのは、当人やその家族によって千差万別。 生きること、死を考えること その家族がそれに向き合うこと 在宅医療の現場では医師もその現実に向き合い、サポートする。 幸せとは何なのかを考えるきっかけとなった。
Posted by