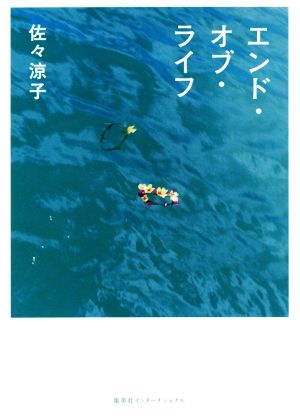エンド・オブ・ライフ の商品レビュー
数々の終末期の在宅診療の様子について書かれたノンフィクション。 自分に残された時間をある程度自覚しながら生きることについて考えさせられるが、それは、いま健康な人間にもできることだよな、と思った。
Posted by
初めて読む作者 佐々涼子氏の本である。 この本は、少し以前に読んだ本の中で、紹介されていた本で、図書館から借りて来た。 いつもなら、すいすいと、本を読んで行くのだが…… 私も、ガンではないが、3回の手術で、病院の生活もわかる。 しかし、読んでいて、何故か、涙が止まらない。 ...
初めて読む作者 佐々涼子氏の本である。 この本は、少し以前に読んだ本の中で、紹介されていた本で、図書館から借りて来た。 いつもなら、すいすいと、本を読んで行くのだが…… 私も、ガンではないが、3回の手術で、病院の生活もわかる。 しかし、読んでいて、何故か、涙が止まらない。 ノンフィクションと、思うから、余計になのかもしれない。 在宅治療の難しさ、この本の中のような親切なナースだけで無い人もいる。 赤ちゃんの誕生は、日にちが、ある程度想定される。 しかし、あの世への橋を渡るのは、誰も想像つかない。 前世で、何も悪いことをした訳でもないのに、惜しまれながら、この世を去らなければいけない。 まだ、小さい子供達を守ってやりたいのに、その願いも叶わないまま、旅立つ用意をしなければならない。 読んでいて、胸が締め付けられる。 自分の死と、向き合い、残った時間、なにをしたいか? この本に登場する人物は、身体の不自由さがあっても、気力があるのが、読んでいても、嬉しい。 自分だったら、無気力感で、一杯だろう。 チベットの子供達は、産まれた時から死ぬ為の準備をすると、……どのように死んで行くか?……正解は無い。 しかし、思い出した言葉がある。 ネイティブインディアンの言葉であるが、 人間産まれた時は、自分は泣いて誕生する。その時周りの者は笑っている。 そして、自分が死ぬ時は、自分は笑って、周りが、泣いてくれる………そんな人生を送りたい。………というような内容だった思う。 ピンピンコロリという言葉も、、流行したけど、周りの介護する側から見ると、それが、良いのかも… 本人も、苦しまずにいけるし、…… この作者のご尊父のような、介護をされる方も、いないだろう。 病院に入院した時に、看護婦のマニュアル的態度も、実際の話であるから、…… そんなことの無いように気を遣う、作者の腹立ちが、よくわかる。 7年間の記述だが、書き切れない事柄が、沢山あるだろうけど、この本を読むのに、長い時間かかった。 終末の終わり方を考えさせられた。 今は元気であっても、いずれ行く道、子供達に伝えておくべき事、自分が、やって置きたい事、……を、病院通いながら、考えている私であった。
Posted by
すごく参考になりました(笑) 父が在宅で、かなり似たような状況で亡くなりましたので、すごくよくわかりました。 わたし自身、現在は余生で、ご褒美の時間だと思っているので、次は自分の番だと自覚しています。 母を看取り、父を看取り、大きな愛犬も膝の上で看取りましたので、変な言い方だけど...
すごく参考になりました(笑) 父が在宅で、かなり似たような状況で亡くなりましたので、すごくよくわかりました。 わたし自身、現在は余生で、ご褒美の時間だと思っているので、次は自分の番だと自覚しています。 母を看取り、父を看取り、大きな愛犬も膝の上で看取りましたので、変な言い方だけど、死に方がわかる…というか。 でも、この本の中で、実際に自分がこの立場になるとわからない…とあったので、その点がちょっと心配。 わたしの理想は、 「なんでもっと早く受診しなかった? もう、治療のしようがない…」 という状況で、癌が見つかって、何も治療せずにギリギリまで普通に過ごして、 食べられなくなるか、自分でトイレに行けなくなったら、ホスピスに入って、 痛みを取り 息苦しさを取り 眠らせてもらう! これが理想なんだけど、ダメかな?
Posted by
自分はこんなふうに生ききれるだろうか。 人間ドックでひっかかった状態で読んだから、より、リアルにどきどきしながら考えてしまった。 リアル過ぎて、読むのが、怖かった。 怖がりながら読んだ。 自分に検査で引っかかるとか、そういうリアルな出来事が起きないと、なかなか深刻な病がある...
自分はこんなふうに生ききれるだろうか。 人間ドックでひっかかった状態で読んだから、より、リアルにどきどきしながら考えてしまった。 リアル過ぎて、読むのが、怖かった。 怖がりながら読んだ。 自分に検査で引っかかるとか、そういうリアルな出来事が起きないと、なかなか深刻な病があると告げられたときの衝撃は想像できない。 想像できないのに、読んでも、やっぱり本当には全然わからない。 この本をいい本だなとか、誰かに勧めたいとか言える人は自身に死が迫っているなんて露とも思わなくて済んでいる人なんだろうなとかも思ってしまう。 この前検査に引っかかってMRIまでいってしまって、とても怖いからこんな感想になっているわけだけど。 でも、いざ自分に突然死が身近に迫ってきた時に、この本の人たちの凄さがわかるのかもしれない。 星とかは、つけられなかった。 「たいていは生きてきたように死ぬ」 「急に患者になる」 「そうしたら、『患者』として周りから見られるようになる」 という言葉が印象に残った。 とりあえず、再検査は〝とりあえず悪性ではない可能性が高い〟と言われて、本当にほっとした。 そうでないと、感想すらきっと書けていないだろうな、うろたえてしまって。 本当に死がそこに、近くに、あるかもしれないと思い知ったからか、ただ、毎日無事に過ごせることが嬉しくてしょうがない。
Posted by
在宅医療はそんな簡単ではないと思いますが、それでもその選択をしても後悔しない何かがあることを知りました。命と向き合う物語に出会えて良かったです。自分の生き方を見つめ直してみようと思います。
Posted by
死ほどパーソナルなものはないのに、自分の死に際して思いを分かち合える相手がいる人は少ないだろう。 読み始めてすぐに、自分の身内を看取った経験を思い出した。がんと闘おうとせず、淡々と死を受け入れている身内が家族として歯がゆくて、「もっと頑張ろうよ、絶対治るから」と励まし続けたが、...
死ほどパーソナルなものはないのに、自分の死に際して思いを分かち合える相手がいる人は少ないだろう。 読み始めてすぐに、自分の身内を看取った経験を思い出した。がんと闘おうとせず、淡々と死を受け入れている身内が家族として歯がゆくて、「もっと頑張ろうよ、絶対治るから」と励まし続けたが、それは果たして正しかったのか。 本書に登場する看護師の森山さんは、何人もの最期に立ち会ってきたプロである。でも自分ががんに直面したとき、決して聖人みたいに達観しているわけではなく、気持ちがブレたり揺れたり、もがき苦しんだりする。 著者の佐々さんは、彼の友人でもあった。病と向き合った友人の最期を書く。普通ならできるだけキレイに、どれほど素晴らしい人だったかに終始してしまうと思うのだけど、森山さんのリアルな感情の揺れ、死との折り合いがなかなかつかないさまが美化されずに書かれててすごいと思った。 森山さんが看護師として関わった方々の最期の様子も描かれるが、当然ながらきれい事では済まない死もある。「生きてきたようにしか死ねない」という言葉は残酷さを含んでいる。 わたしの身内もまた、病と闘わないと決めた胸のうちの実際はどうだったのだろう、ただただ死なないでほしいと思い、伝え続けたことを許してくれるだろうか、などと思ってしまった。
Posted by
ここ最近、「最期」に関係する本をよく読んでいる。 小説が多いのだけど、ずっと読みたかったこの本はノンフィクション。 「現実は小説より奇なり」の言葉通り、まさにドラマのようなエンドオブライフが描かれていた。 人それぞれの寿命は決まっているという考え、この手の本を読むようになり、最...
ここ最近、「最期」に関係する本をよく読んでいる。 小説が多いのだけど、ずっと読みたかったこの本はノンフィクション。 「現実は小説より奇なり」の言葉通り、まさにドラマのようなエンドオブライフが描かれていた。 人それぞれの寿命は決まっているという考え、この手の本を読むようになり、最近はすっかり自分の中に浸透している。 今回新たに考えさせられたのは、「病気になった途端に、人は患者さんになってしまう」という部分。 それまで普通に自分の人生を歩んでいたのに、急に「患者」になり、身体面はもちろん精神面も制約を受ける。その人自身は変わっていないのに…。 こういう部分が苦しみの一つなのかなと思う。 自分や家族が何か病気になったとしても、その人らしさを持ち続けられるようにしたいなと思った。
Posted by
読みながら参考になる箇所にふせんを貼っていたら30程にもなってしまいました。いつか自分が死に至る病になった時に参考にしたいと思います。 在宅医療での“命の閉じ方”を、著者の笹さんが7年の歳月取材してまとめたものです。 プロローグは、訪問看護師の森山文則さん(40代)の身体の異...
読みながら参考になる箇所にふせんを貼っていたら30程にもなってしまいました。いつか自分が死に至る病になった時に参考にしたいと思います。 在宅医療での“命の閉じ方”を、著者の笹さんが7年の歳月取材してまとめたものです。 プロローグは、訪問看護師の森山文則さん(40代)の身体の異変に気付くところから始まります。彼は京都の西賀茂診療所で在宅医療に携わっていて、真夜中でも早朝でも電話したらいつでも患者さんのお宅にすぐに来てくれる頼もしい看護師でした。しかしCT診断の結果、すい臓がんステージⅣであることがわかります。 この 森山さんのことを主軸に、数人の方々の在宅医療での看取りまでを追いかけていきます。 時に、思わず嗚咽してしまうほど感動的な死に方の患者さんがいらっしゃったり、激しい痛みを伴いながら苦悶の死に様を迎える患者さんがいらっしゃったり、怯えてページを捲る手が止まってしまうこともありましたが、いつか自分にも、大切な人にもやってくる「死に際」を予行演習 させてくれるような内容に、しっかり胸に刻みつけておきたいと心してページを進めました。 死期が迫った人の在宅医療という重い内容であるにもかかわらず、スルスルと胸に染み入るような筆致がいいです。 特に、著者である笹さんのお母様を、献身的に介護したお父様の究極の介護の描写は、神々しいとすら感じました。 読み終わって強く思ったのは、在宅であれ、病院であれ、病状が悪化して最後を迎える時、激しい痛みに苦しみながら死を迎えるのは辛い、ということです。 「医師は助からないとわかると興味を失う」ので「苦痛を取り除くことに関心がない」という言葉が心に突き刺さります。 緩和ケアの専門医、蓮池史画先生の痛みを抑える末期医療、京都の西賀茂診療所のように患者の側に寄り添う訪問医療、これらは朗報として心に深く残りました。 ※2020年 Yahoo!ニュース/本屋さん大賞 ノンフィクション大賞 受賞
Posted by
人の死に立ち会うとはどんなに過酷なんだろうと思っていました。病気で余命宣告されている人たちに寄り添うということは辛く自分を擦り減らすことだと思っていました。 そういった部分も書かれていますが、この本を読んで、亡くなって行く人は遺される人たちの人生に影響を与える、という所が心に残り...
人の死に立ち会うとはどんなに過酷なんだろうと思っていました。病気で余命宣告されている人たちに寄り添うということは辛く自分を擦り減らすことだと思っていました。 そういった部分も書かれていますが、この本を読んで、亡くなって行く人は遺される人たちの人生に影響を与える、という所が心に残りました。 亡くなっても関わった人たちにプレゼントをくれることがある。人は亡くなっても生きている人に影響を与え続けているのだな。それなら今生きている自分の生き方を考えなくちゃなと思いました。 佐々さんを通して私もそんなプレゼントを頂きました。
Posted by
鋭い悲しみではなく、もっと肌触りの柔らかいお別れ。樹々から自然と実が落ちて離れるようなさよならの方法があるのだと、私は教えられていた。
Posted by