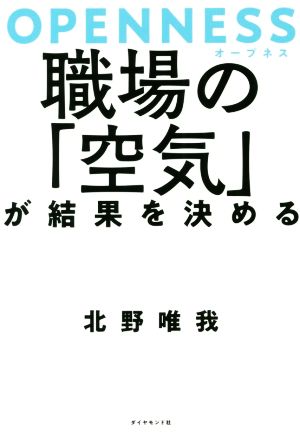OPENNESS 職場の「空気」が結果を決める の商品レビュー
2022年9月18日読了。職場の士気・成果や業績を決める「オープネス」の概念・有効性を、オープンワーク社のデータなどを用いて説明する本。オープネスは「なかよしクラブ」と同じことを意味しない、社員に共通の目標があり社会や組織への貢献を実感でき、心理的安全性が確保されていて自由に意見...
2022年9月18日読了。職場の士気・成果や業績を決める「オープネス」の概念・有効性を、オープンワーク社のデータなどを用いて説明する本。オープネスは「なかよしクラブ」と同じことを意味しない、社員に共通の目標があり社会や組織への貢献を実感でき、心理的安全性が確保されていて自由に意見が出せる環境であるということ、か。GAFAなどの企業は人為的にそういう文化を作り出していると思うが、日本にあるのは一部の宗教がかった強烈な文化を持つ老舗企業か、ベンチャーくらいしかないのかもしれないな。自分のいた外資系の大企業は、決してオープネスが低い場所ではなかったが、もっとオープネスが高く、それが業績と成長につながっている職場はあるのかもしれない。
Posted by
経営者目線で書かれた本なので、管理職ではない人にとっては明日から使えるテクニックが書かれた本ではないですが、この先管理職になる時に備えて、こういった組織論を身につけておくためには良書だったと思います。 あとがきに書いてある、組織戦略は「人間の弱さを前提にして設計」し、オープネス...
経営者目線で書かれた本なので、管理職ではない人にとっては明日から使えるテクニックが書かれた本ではないですが、この先管理職になる時に備えて、こういった組織論を身につけておくためには良書だったと思います。 あとがきに書いてある、組織戦略は「人間の弱さを前提にして設計」し、オープネスな組織を作っていくという言葉がとてもよかったです。 「人間の弱さ」というところを意識してもう一度読み返してみたいです。 それにしても前半に書いてあった唯我さんが「株価当てゲーム」を遊びとしてハマっていて、そこから社長の傾向などの理論モデルを作った っていうのを読んで「マジかよ」ってなりました。とうてい真似できそうにもありません。 「動物の生存戦略」を会社の組織に転用するという発想もそうですが、唯我さんの思考の凄さを実感した本でした。
Posted by
日本が立ち行かなくなっている理由の一つは職場のオープネスの低さにあり、高めることの難しさは人間の心の弱さにある。 オープネスの要素は、経営開放性、情報開放性、自己開示性であり、オープネスが高い企業は、風通しの良さ、20代の成長環境、社員の士気が高いことが特徴。 人間の弱さを前提に...
日本が立ち行かなくなっている理由の一つは職場のオープネスの低さにあり、高めることの難しさは人間の心の弱さにある。 オープネスの要素は、経営開放性、情報開放性、自己開示性であり、オープネスが高い企業は、風通しの良さ、20代の成長環境、社員の士気が高いことが特徴。 人間の弱さを前提に設計することが重要で、「成果を生み出すために、健全に意見をぶつけ合える場」がその真価を発揮する。 また、ウサギの生存戦略は危機察知能力である、ということが印象的。 26冊目読了。
Posted by
期待した以上にいい本でした。 企業の強さは個人ではなく組織の強さであって、それには各人が『自分はこの組織の一員である』と自覚できる程度にはオープンというか、組織の上から下まで通じている感じが必要なんだなと改めて感じた。 ルーティンワークとプロジェクトワークの比率など、脳内に漠然と...
期待した以上にいい本でした。 企業の強さは個人ではなく組織の強さであって、それには各人が『自分はこの組織の一員である』と自覚できる程度にはオープンというか、組織の上から下まで通じている感じが必要なんだなと改めて感じた。 ルーティンワークとプロジェクトワークの比率など、脳内に漠然とあったイメージを言語化してくれた。 まぁ『組織は変えられる。社長が陣頭を仕切れば。』平社員にとっては絶望なのかな。管理職になれば自分の部署は変えられるのかもしれないけど。
Posted by
職場の空気と業績の相関性を定量的に示すというテーマに惹かれて購入 オープンワークという転職者の巨大データベースをもとに、関連度の高い具体的な項目と数値の紹介、 企業規模に関係なく相関性があり、また改善活動もしやすいとのこと オープンワークに登録する人=転職者、もしくは検討者=...
職場の空気と業績の相関性を定量的に示すというテーマに惹かれて購入 オープンワークという転職者の巨大データベースをもとに、関連度の高い具体的な項目と数値の紹介、 企業規模に関係なく相関性があり、また改善活動もしやすいとのこと オープンワークに登録する人=転職者、もしくは検討者=既に士気が落ちてる人なので、多少偏ったデータになる気もするが、 この切り口で、従業員士気を定量化して、改善や予防のためにKPIを落とし込んでアクション出来る様になる、それが今後の人事の常識になって欲しいと思った。
Posted by
総評 ハウツー感は比較的強めで、定義されるOPENNESS=開放性と業績の相関関係についても詳しく紹介されています。組織における最大の武器である「組織風土」「人間関係」を開放性とデータでわかりやすく向上させる手法が詰まっています。 オススメの読み方 自身の日々のマネジメントを振...
総評 ハウツー感は比較的強めで、定義されるOPENNESS=開放性と業績の相関関係についても詳しく紹介されています。組織における最大の武器である「組織風土」「人間関係」を開放性とデータでわかりやすく向上させる手法が詰まっています。 オススメの読み方 自身の日々のマネジメントを振り返りながら読み進めることをオススメします。管理職の方は担当部門を俯瞰してイメージしながら、中間管理職やOJTなどの指導役の方は具体的な部下・メンバーをイメージすることで内容がグッと入りやすくなると思います。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
データに基づき相関性を述べている点がとても面白かった。 筆者のほかの著書(転職本)はいまいちだったが、この本は非常に参考になりました。 「風通しの良さ」と「場の調和」のバランスを取るのが難しく、そこで大事なのはやっぱり相手の意見を傾聴する力、尊重する力であることを確信することができた。ただ、「尊重」と「仲良しグループ」の線引きも難しい。その点についても丁寧に触れられていてよかった。 組織が疲弊したときの「ダブルバインド」。心理学用語ではあるが、自分のようなぺーぺーにも噛み砕いてくれている。まさに自分の組織で起こっていることだったので何度も読んでしまった。
Posted by
オープネス。心理的安全性とも重なる部分や通ずる部分も多いが、この言葉も今後は一般常識になるかも。 風通しの良さ、社員の士気などが高い組織は結果につながっていることを根拠に、いかにそうした組織にできるか、そのために必要な開放性について著者の経験や例えも含めて述べられています。 職場...
オープネス。心理的安全性とも重なる部分や通ずる部分も多いが、この言葉も今後は一般常識になるかも。 風通しの良さ、社員の士気などが高い組織は結果につながっていることを根拠に、いかにそうした組織にできるか、そのために必要な開放性について著者の経験や例えも含めて述べられています。 職場の空気を変えたい方は一読の価値があると思います。 弊社も載ってました。 後半のウマとパンダとウサギの話が面白かった。 ウマは人に役立つことで、生き延びてきた。 パンダはとにかくかわいがられて、生き延びてきた。 ウサギは、危険察知能力の高さで、生き延びてきた。 組織の人員の中で自分がウマかパンダかウサギか。はたまたその上に立つヒトか。 いろいろ考えられるのが面白かったです。
Posted by
「OPENNESS(オープネス)=開放性」という考えがいかに組織にとって必要であるのか? オープネスを決める3つの要素である「経営開放性」「情報開放性」「自己開示性」それぞれについて詳細に説明した内容の本。 社員の期待値と会社実態とのギャップをどう埋めていくのか? アプローチの仕...
「OPENNESS(オープネス)=開放性」という考えがいかに組織にとって必要であるのか? オープネスを決める3つの要素である「経営開放性」「情報開放性」「自己開示性」それぞれについて詳細に説明した内容の本。 社員の期待値と会社実態とのギャップをどう埋めていくのか? アプローチの仕方としては当然両面あるが、このギャップを埋めることの重要性を痛感する内容。 それをしないと、パフォーマンスに影響するばかりか、最悪の場合離職していくことも当然考えられる。 そのためにはオープネスに拘り、一定以上の情報をキチンと開示、それをいつでも見られるようにする・・・ 至極当たり前ながらもここに拘っていく重要さを感じた。 一方でこのオープネスを妨げる要素も紹介されていたが、自分がこの障害にならないようにすることも必要。 特にある種の老害ともいえるトーションオブストラテジーには今後も注意する。 会社は仲良しクラブではない。ただ、楽しく働くことのできる環境は必要という点も大いに納得。 本書に書かれた「長期的に楽しく働いてもらうための12のアクション」は自身の業務にも今後の参考にできるものであった。
Posted by
オープネスが必要なのは、誰もが納得できる話だが、組織論目線だけで語られていない点が良かった。 具体的なデータに基づき、いかにオープネスが重要かを述べた上で、リーダーが組織に与える影響の話が役に立った。 白い嘘をつかず、これからの未来となる道筋を描くことを進めていきたいと思う。
Posted by