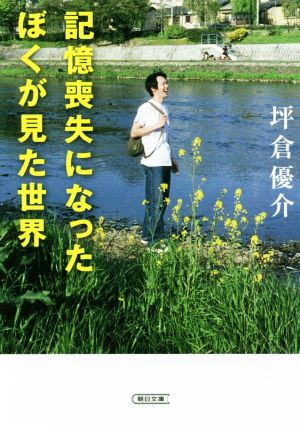記憶喪失になったぼくが見た世界 の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
著者は、18歳のとき交通事故により記憶を失ってしまう。人間関係だけでなく感性や言葉も分からない状態となり、数々の試練に直面する。最終的に記憶が戻ることはないものの、「新しい自分」として人生を一から歩んでいく著者の姿を描いた、壮絶なドキュメンタリーである。 本書の冒頭に「上を見ると、細い線が三本ついてくる。(略)この線はなんなのだろう。(略)がんばってついてくる線の動きがおもしろい。」という表現がある。これは著者が記憶をなくした直後に目にした光景の一部である。なんの先入観もない、ただまっすぐな感覚。大人になるにつれ我々は瑞々しい感覚を失ってしまう。著者が本書で描く景色や表現によって、忘れていたこの感覚が非常に懐かしく感じる。 本書の見所は、記憶を失った著者が見たありのままの世界や、著者が様々な苦労を背負いながらも芸術家への道を進んでいく過程は勿論、著者を支えた家族の心境にもある。著者の母親は、著者が記憶を失った3ヶ月後には大学に通わせる決意をする。我が子を心配する気持ちと、外の世界の厳しさを教えなければならないという義務感の錯綜は、読者の胸に刺さるものがある。 当時は過去の記憶を取り戻すことに固執していたと言う著者。しかし、12年が経った今では、記憶が戻ることが怖いという。事故から12年、彼は「新しい自分」として生きてきた。それはとても辛く険しい道程だったに違いない。周りに支えられながら生きていく。困難があっても力強く「自分」を生きる。その大切さを痛感した内容であった。
Posted by
事後により18年間の記憶を失った著者。 かなり壮絶な生き方だと思います。家族の支えや友人の支え、本人の努力がなかったら著者のような生き方は出来てなかったと思います。 担当した患者さんで似たような症状の方がいました。若くして、記憶の障害が出てしまう方です。その方とかぶって見えて...
事後により18年間の記憶を失った著者。 かなり壮絶な生き方だと思います。家族の支えや友人の支え、本人の努力がなかったら著者のような生き方は出来てなかったと思います。 担当した患者さんで似たような症状の方がいました。若くして、記憶の障害が出てしまう方です。その方とかぶって見えてしまいました。 大学まで行って、一人暮らしをして、仕事をしてと初めでは想像をしないぐらいたくましく生きています。 家族もかなり悩んでの決断だったと思いますが、このような援助の仕方は真似できないと思いました。 可能性はいくらでもあると勇気づけられる本でした。
Posted by
《自分らしく生きる方法は?》 事故で18年の記憶を失くした著者の、その後12年のストーリーです。 「生き直す」ことになった彼は、家族、友人に支えられて、師となる人と出会う。 『自分がやりたいことを真剣にやる』 誰にでも当てはめる、自分らしく生きる方法。 過去に捉われず、今を...
《自分らしく生きる方法は?》 事故で18年の記憶を失くした著者の、その後12年のストーリーです。 「生き直す」ことになった彼は、家族、友人に支えられて、師となる人と出会う。 『自分がやりたいことを真剣にやる』 誰にでも当てはめる、自分らしく生きる方法。 過去に捉われず、今を生きる。 その大切さが伝わってきました。
Posted by
名前や生活史などの記憶を超え、食べるという行為すら判らなくなる、これはいわゆる記憶喪失というレベルではないように思う。こういう状態になった人がどう感じているのか、滅多に聞けない体験記。 『アルジャーノンに花束を』とか、『自閉症の僕が跳びはねる理由』とかを思い出しながら読んだ。染め...
名前や生活史などの記憶を超え、食べるという行為すら判らなくなる、これはいわゆる記憶喪失というレベルではないように思う。こういう状態になった人がどう感じているのか、滅多に聞けない体験記。 『アルジャーノンに花束を』とか、『自閉症の僕が跳びはねる理由』とかを思い出しながら読んだ。染めの作品を見たい。
Posted by
事故によって逆行性健忘となった作者の実体験が書かれている。これはとても貴重な記録。分からないというのが、どういうことなのか。そういうことを考えさせられます。
Posted by
母親の手記で泣いてしまう。 お金もカウント出来ないのに大学に行かせるとか、事故の原因になったバイクに乗せるとか、ご飯も炊けない状態で一人暮らしさせるとか、つい自分だったら制限していただろうと考える。 その点、庇うほど自立出来なくなるとある程度突き放せる父性ってすごい。 なぜなぜ...
母親の手記で泣いてしまう。 お金もカウント出来ないのに大学に行かせるとか、事故の原因になったバイクに乗せるとか、ご飯も炊けない状態で一人暮らしさせるとか、つい自分だったら制限していただろうと考える。 その点、庇うほど自立出来なくなるとある程度突き放せる父性ってすごい。 なぜなぜ??を繰り返す著者。 純粋で無垢な感性。 そして絵や染物を通して自らを表現することで彼自身も救われている。
Posted by
記憶ってなんだろうと考えさせられた。 当たり前が当たり前でない世界。想像を絶するが、坪倉さんはそこから逃げずに乗り越えた。 とても素晴らしい作品だ。
Posted by
本書は、坪倉優介(1970年~)氏が、1989年、大阪芸大1年の時にスクーターで停車中のトラックに激突し、10日間昏睡状態が続いた後、意識は戻ったものの重度の記憶喪失となり、そこから新たな人生を生きる過程を、本人と母が綴った記録である。 2001年に『ぼくらはみんな生きている~1...
本書は、坪倉優介(1970年~)氏が、1989年、大阪芸大1年の時にスクーターで停車中のトラックに激突し、10日間昏睡状態が続いた後、意識は戻ったものの重度の記憶喪失となり、そこから新たな人生を生きる過程を、本人と母が綴った記録である。 2001年に『ぼくらはみんな生きている~18歳ですべての記憶を失くした青年の手記』として出版され(2003年文庫化)、本書は、2019年に改題して復刊されたものである。2003年にはテレビ朝日でドラマ化された。 坪倉氏は、事故後、大阪芸大工芸学科染織コースを卒業し、1996~2003年に京都の染工房夢祐斎(染色家・奥田祐斎の工房)で草木染め作家として活動。2004~05年にはヨーロッパ及び日本国内を旅し、2006年、大阪で「ゆうすけ工房」設立して、着物を中心に染色作品を制作している。 本書の読みどころは、大きく二つあると思われる。 一つは、ほぼ成人に近い人が、重度の記憶喪失になったときの、世界の見え方・捉え方がどういうもので、それを乗り越える過程の記録としてである。私は、医学的な知識は全く持たないが、記憶喪失の多くは固有の情報の喪失であって、生活における基本的な情報(文字や食べ物やお金や乗り物など)を喪失することはないとの先入観を持っていたのだが、著者のように、基本的な情報の大半を喪失した場合、まさに、18歳の赤ちゃんとして、世界が捉えられるということに、正直驚いた。(脳自体は発達しているので、再度教えれば、理解は赤ちゃんよりも急速に進むが) そして、著者が世界を捉える生き生きとした感覚は、子どもならみな持っているものの、それを表現できるような言葉を獲得した頃にはその感覚自体が失われてしまうものなのだ。そうした意味で、著者の綴るこの記録は貴重なものと言える。 そしてもう一つは、著者を含む家族の物語としてである。本書には、著者本人の著述の他に、時期ごとの母親の記憶が収められているのだが、この家族(父・母・弟・妹)と著者の絆(月並みであまり使いたくないワードだが)には、しばしば涙なしに読み進めることができない。著者が、なかなか昔のことを思い出せないもどかしさから、家を出て行こうとしたときに、無言の母親の目から止め処なく流れる涙を見て、今後家を出ていくことは止めようと自分に言い聞かせる場面など。。。 しかし、何より心に残るのは、著者が「あたらしい過去」を語った次の一節である。「何年か前までは、昔の自分に戻りたくて仕方がなかった。・・・今のぼくには失くしたくないものがいっぱい増えて、過去の18年の記憶よりも、はるかに大切なものになった。楽しかったことや、辛かったこと、笑ったことや、泣いたこと。それらすべてを含めて、あたらしい過去が愛おしい。今いちばん怖いのは、事故の前の記憶が戻ること。そうなった瞬間に、今いる自分が失くなってしまうのが、ぼくにはいちばん怖い。ぼくは今、この12年間に手に入れた、あたらしい過去に励まされながら生きている。」 重度の記憶喪失を乗り越えた、本人と家族の貴重なドキュメンタリーである。 (2020年6月27日了)
Posted by
俵万智が解説に書いていたけれど、 子どもの時の純粋な感情を、彼らは言語化する力がない 大人になると、その時の感性は失われてしまう ならば、言語化する力を持った上で記憶が無くなってしまったら… …いやでも筆者はあいうえおも忘れてるからなあ。 うーん。 読書の良さは、自...
俵万智が解説に書いていたけれど、 子どもの時の純粋な感情を、彼らは言語化する力がない 大人になると、その時の感性は失われてしまう ならば、言語化する力を持った上で記憶が無くなってしまったら… …いやでも筆者はあいうえおも忘れてるからなあ。 うーん。 読書の良さは、自分では体験できそうにないことも擬似体験できるということ。 いちばん怖いのは、事故の前の記憶が戻ること。そうなった瞬間に、今いる自分が失くなってしまうのが、ぼくにはいちばん怖い。 ぼくは今、この十二年間に手に入れた、あたらしい過去に励まされながら生きている。 この文で何かが救われた気がした。 優しい再生の物語。
Posted by
読み始めたとこ なんか面白そう 『いろいろな物が見えるけれど、それがなんなのか、わからない。だからそのまま、やわらかい物の上にすわっていると、とつぜん動き出した。外に見える物は、どんどんすがたや形をかえていく』 物忘れとは違う 記憶喪失とは、こういう状況のことか 、と新たに...
読み始めたとこ なんか面白そう 『いろいろな物が見えるけれど、それがなんなのか、わからない。だからそのまま、やわらかい物の上にすわっていると、とつぜん動き出した。外に見える物は、どんどんすがたや形をかえていく』 物忘れとは違う 記憶喪失とは、こういう状況のことか 、と新たに認識
Posted by