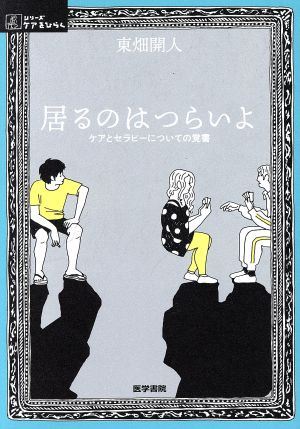居るのはつらいよ の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
ケアとセラピーについて凄く分かりやすく書いてあった。 ケアは傷つけない事、セラピーは傷に向き合う事。 線として先に進んでいくこと、円として留まり繰り返す事。こんな表現もすごく分かりやすい。 依存の話も面白かった。依存労働者が完璧にケアの仕事をこなしている時程、人には気付かれないし感謝もされない。でもケアされている人はその場に「居る」が出来る。 一度問題が起こるとこれは環境が悪いのか、問題に対応できない自分が悪いのかと考えてしまうけれど、そんな考えにも光を差してくれるような本だった。 環境が変われば人は変わるし、人が変われば環境も変わるし…どちらが悪いなんて一概には言えなくて…無理をし過ぎて壊れてしまうくらいならばケア(環境を変える)方をまずは選びたいと思ったし、自身にもセラピー(自分を変える)で自立していたいと思った。 最終章でデイケアは安全な場所という会話にあったみたいにケアすることは安全の欲求を満たすとても重要なことだと思う。人にはまずはケアの関わりをしていきたい。 効率、お金、意味にケアは脅かされていてそれとは全く別の場所に居ることが辛く無い、ケアの場所がある。 どちらが正しいとかで無く効率、お金、意味などとは他の場所で、「ただ、いる、だけ」の場所があれば良いと思う。
Posted by
ここ最近ずっと、自分の無能感に死にたくなっていたけど、第5章の「暇と退屈未満のデイケア」を読んでいて、自分が最近退屈できていないことに気づいた。 仕事をしていて何か空白の時間があると、悪い方向の思考が傾れ込んできて、手が止まってしまう。自分の妄想だ、とわかっていても、止められな...
ここ最近ずっと、自分の無能感に死にたくなっていたけど、第5章の「暇と退屈未満のデイケア」を読んでいて、自分が最近退屈できていないことに気づいた。 仕事をしていて何か空白の時間があると、悪い方向の思考が傾れ込んできて、手が止まってしまう。自分の妄想だ、とわかっていても、止められないまま、その間仕事ができなくなる。 そうして、何もできずにいる自分にさらに自己嫌悪し、上司から無能と思われているのではという妄想でまた手が止まるという悪循環を繰り返していた、という事実を外からの視点で眺められた。 第5章には、そういう脅威から身を守るための自我境界というものがあり、それがきちんと機能していれば、脅かされずにすむ、と書かれていた。 私は、過去に安心して生きられていた自分と、今の、他者の目線に恐怖して毎日が苦しい自分とは、何が違うのかがわからず、なんとなく、何も知らなかった頃は幸せだったからなのか、と考えていた。 知らない頃に戻ることはできないので、自分が幸せに生きられるような気持ちに戻ることもまた、できないように感じていたが、私が今知った気になっていることは、他者や、社会からの評価であり、それは自分とは別のものの中にあり、推しはかることなどできない、その評価の憶測を自分自身で作り上げて苦しんでいただけだ、ということになんとか気づけた。 精神的な危機に陥った人は、自己と他者の境界が曖昧になり、自分の内部の考えを他者に投影してしまう、と頭ではわかっていたが、自分自身の経験に当てはめられていなかった。 また、そういう自分は、もはや回復不能だと思っていたけど、円環的な繰り返しの生活の中で、時間によって変わっていくこともある、と書かれていて、希望が持てた。 また、この本を通底して出てくる、ケアがお金に換算されると、その機能がうまく働かなくなるという点について、自分はずっと違和感と、息苦しさをもっていたことにも気づいた。 私はとにかく大バカなので、子供の頃から、お金にならない、掃除や洗濯や料理といった家事労働が嫌いで、全くやってこなかった。意味がないと思っていた。 父も同じくで、母よりも家にいるにも関わらず、家事労働をしない人だった。 その結果(他にも色々と原因はあるが)、母が病気になってしまったのだと思う。 そうなった上にさらに年月を経て、ようやく自分が家事をするようになって、家事労働の意味がわかった。 私は今まで、生活を蔑ろにし続けてきたのだと思う。 家事をして初めて、私は今生活をしている、と思えた。 仕事をしている時には実感できない、生きているという実感が、家事をしている時にはありありと感じられる。 家事は別の意味や、価値には換算できない。 それ自体が生きることと同義だからだと思う。 ケアをする仕事をしていた時期もそのことで葛藤していた。 当たり前に生きることを、お金に換算するのは変だし、当たり前に生きる生活の一つ一つの何気ない動作に意味を見出して、それを進歩させようとするのは、おかしい。 この本でも語られているように、生活は円環であって、直線ではない。 それなのに、資本主義のもとに動く経済では、昨日よりも大きな成果、毎日成長し続けることが求められ続ける。 その原理の中では、どんな些細なことにも意味づけが求められる。本来、市場の中だけのはずの考え方が、だんだんと日常を侵蝕してきて、日々の暮らしが、些細な出来事全部が、意味あり・意味無しのジャッジをされ続けて、君は何ができるのか常に問いかけられ続けているような焦燥感が付きまとう。 そのせいで、私は毎日自分が何も進歩もない日常を送っていることに、必要のない罪悪感を抱えていたのだ。 実際私は、毎日虚空に向けて謝り続けていた。 両親にも、国にも、世界にも、生まれてきてすみません、と心の中で謝罪していた。 本当に生きているだけで申し訳ないような気持ちになっていた。 何も生み出さず、なんの役にも立たず、ただ生きることが、ただ居ることが、悪のように感じるなんて、本当はおかしいことだと、伝えてくれるこの本は、とても優しい。 この本が正しいと信じて、死なないで生きていきたい。 自分が生きていてもいい、と今だけでも思わせてくれたことが本当にありがたかった。
Posted by
ケアの現場で言われる自己覚知って、「私自身の習慣という形で、私自身がいかに統治されてるか」ってことを自覚することだ(ということは当然だが教育されない)、ということが、ケア実践の経験に基づき、分かりやすく書いている。
Posted by
■評価 ★★★✬☆ ■概要・感想■ ○ケアとセラピーを沖縄の実地で体験した医師の覚書。文章が非常に読みやすく、引き込まれる。それでいてケアとセラピーについても知ることができる本である。 ○個人情報保護のため、架空の登場人物のはずなのに、確かにそこに居る。それだけ引き込まれる。...
■評価 ★★★✬☆ ■概要・感想■ ○ケアとセラピーを沖縄の実地で体験した医師の覚書。文章が非常に読みやすく、引き込まれる。それでいてケアとセラピーについても知ることができる本である。 ○個人情報保護のため、架空の登場人物のはずなのに、確かにそこに居る。それだけ引き込まれる。 ○何もしないで「ただ、いる、だけ」を、穀潰しと思ってしまう著者は、生産性が高い人間なんだろう。「いる」ことは当たり前で、その上で「する」ことを考える。そうでない人々(ただ居ることがチャレンジングな人)に、価値観を押し付けるのではなく、ケアとして、接するに線を引いている。客観的だなと思う。
Posted by
臨床心理士となった筆者が「高度なセラピーを行うぞ!」と意気込んで行った職場では,実はケアのほうが主要かつ重要な業務だった….これはいったいどういうことなのか? そして,そんなに重要なケア労働が,なぜ低賃金労働とされているのか?等等を,現場の視点から面白おかしく(かつリアルに)語っ...
臨床心理士となった筆者が「高度なセラピーを行うぞ!」と意気込んで行った職場では,実はケアのほうが主要かつ重要な業務だった….これはいったいどういうことなのか? そして,そんなに重要なケア労働が,なぜ低賃金労働とされているのか?等等を,現場の視点から面白おかしく(かつリアルに)語った本です.読みやすく面白くためになる.なるほどと目からウロコです!
Posted by
とても面白く読み終えた。 若き心理士である著者が、沖縄の精神科デイケアに訪れる人達との関わりを書いた体験記でもあり、デイケアの課題やケアとセラピーのあり方について書かれた「学術書」でもある。 1つひとつエピソードが読ませる内容で時に笑えてしまうようなものもあり、そうやって読み進め...
とても面白く読み終えた。 若き心理士である著者が、沖縄の精神科デイケアに訪れる人達との関わりを書いた体験記でもあり、デイケアの課題やケアとセラピーのあり方について書かれた「学術書」でもある。 1つひとつエピソードが読ませる内容で時に笑えてしまうようなものもあり、そうやって読み進めていくと、後半~終盤の展開に呑み込まれた。 「物語」という体裁をとった著者が巧みで、この文体でしか伝わらない空気感と切実さがある。
Posted by
これは本当にためになった。 依存労働とかケアとセラピーの違いとか。 ケアをする人にも、ケアをする人こそケアしてくれる人が必要だとか。 専門的な内容も挿まれつつも、物語になっているのでとても読みやすいです。 どうしてこんなに、一人で頭の中でぐるぐる自分を責めているのかとか、はたから...
これは本当にためになった。 依存労働とかケアとセラピーの違いとか。 ケアをする人にも、ケアをする人こそケアしてくれる人が必要だとか。 専門的な内容も挿まれつつも、物語になっているのでとても読みやすいです。 どうしてこんなに、一人で頭の中でぐるぐる自分を責めているのかとか、はたから見ると「なんでだろう」と思うことも、「自我境界」という言葉で表してくれたり。 2つの幕間口上や、本終盤の「ケアを困難にさせる真犯人」についてもいろいろ納得させられる。 身近な人がメンタル落ち込んでいて、それを突然側でケアしなくてはならなくなった人、ずっとケアをして疲れている人にも読んでほしい本です。
Posted by
東畑開人さんの文章を新聞で読んでいて、面白い文章を書く方だなと思っていた。そんなところでこの本を知って、読んでみた。やっぱり面白い。ほぼ一気読み。 私が日々感じていたけど答えが出なかったことが、言語化されていた。 また、心の動きについても書いてあり、納得した。 この本を読んだこと...
東畑開人さんの文章を新聞で読んでいて、面白い文章を書く方だなと思っていた。そんなところでこの本を知って、読んでみた。やっぱり面白い。ほぼ一気読み。 私が日々感じていたけど答えが出なかったことが、言語化されていた。 また、心の動きについても書いてあり、納得した。 この本を読んだことで、大丈夫だよって言われてる気がした。 東畑さんの他の著作も読んでいく。
Posted by
序盤は沖縄ほのぼのエピソード。後半から打って変わって社会派ノンフィクションとホラー。 直前に読んだ本が「ザ・フォーミュラ 科学が解き明かした成功の普遍的法則」。当たり前だけど落差がすごい。
Posted by
居るのはつらいよ 物語風で読みやすくわかりやすかった。 デイケアを舞台に描かれているが、誰しも当てはまる内容。 最後の方は、少し読み進めるのが怖かったが一気に現実に引き戻される感じがなおよかった
Posted by