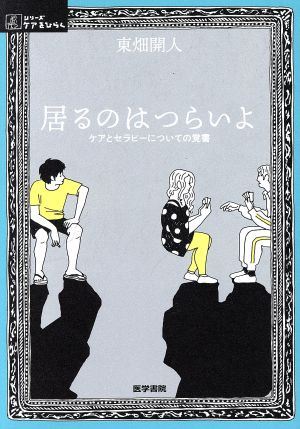居るのはつらいよ の商品レビュー
京都大で博士号を取り、臨床心理学を極めるべく就職先を探すが、カウンセリングがメインの仕事を探すと見つからない。やっと見つかったのは沖縄の精神科クリニックだった。実際に仕事を始めてみると、カウンセリングの仕事は少なく、ほとんどがデイケアの仕事だった。 ただそこに「居る」のだけでも...
京都大で博士号を取り、臨床心理学を極めるべく就職先を探すが、カウンセリングがメインの仕事を探すと見つからない。やっと見つかったのは沖縄の精神科クリニックだった。実際に仕事を始めてみると、カウンセリングの仕事は少なく、ほとんどがデイケアの仕事だった。 ただそこに「居る」のだけでも難しい仕事を通して、考えるセラピーとケアの違いとは何か・・・ TBSラジオの「荻上チキSession22」で紹介されていた。 読んでみると、デイケアに来る人の話、従業員の話を全く深刻にならないように、むしろ面白おかしく進めてくれる。そして精神療法とか、國分功一郎の著作を引用しつつ暇について考えさせてくれたりする。何とも不思議な本だった。
Posted by
非常に面白かった。 「居場所」というのは今一番興味のあるワードで、考えるうえですごく参考になりました。
Posted by
2022/2/1再読 ★4 2019年以来の再読。 前回は、まさに自分が悩んでいた部分への回答に、自分が一番惹かれたらしい。 「依存労働」 でも、今回は、そこに引っかかることなく、別の部分を考えながら読んでいた。 「いるとは何か?」 「居場所とは?」 「ケアとセラピーの違いと...
2022/2/1再読 ★4 2019年以来の再読。 前回は、まさに自分が悩んでいた部分への回答に、自分が一番惹かれたらしい。 「依存労働」 でも、今回は、そこに引っかかることなく、別の部分を考えながら読んでいた。 「いるとは何か?」 「居場所とは?」 「ケアとセラピーの違いとは?」 全体を通して書かれていることについて読んでいた。 「いる」って簡単なようで簡単にはいかない。 でも、その「いる」場所を確保しないと、人間は生きていかれない。 その「いる」場所こそ、「居場所」。 「ケアとセラピーの違い」は、本の中でリスト化されていたので、とてもわかりやすい。 でも、それがここに存在しているのではなく、どんな状況であっても、どんな立場であっても両方が存在すること。 数年後に再読をしたら、自分はどの部分に反応するんだろう? ちょっと楽しみ。 ------------------------------------------- 2019/4/29 ★×5 著者の名前をTwitterで見かけたことがあり、手に取った。 「いる」ってなに? という、人の存在に関することが最初から書かれていて、正直、初めは混乱した。 「いる」ってなに?と、何度も何度も考えながら読んだ気がする。 著者もエピローグで書いているが、舞台になっているのが精神科のデイケアだから、自分には関係ない話。と、前半だけでは思えてしまうかもしれないが、全てを読むとわかるのは、「居る」を支援する力、物、人の存在と、「居る」を阻害する力、物、人の存在。それは、人間社会のどこにでも転がっていて、かなり密接なものだということ。 読みながら、自分のことを振り返り、合点が行く部分をいくつも見つけた。 本文中にあるケアとセラピーの構成要素表。 これを見ると一目瞭然で、ケアとセラピーは、密接に関わり、表裏一体のもの。 また、この本で、「依存労働」という言葉を初めて知り、過去に自分がカウンセリングを受けた際、言われて言葉を思い出した。 あの頃言われた言葉は、クライアントである自分にとっては、受け入れがたいものだったけれど、「依存労働」のことを述べていたのだなと。 ただ、言われた言葉があまり良い表現ではなかったので、自分がクライアントにそれを告げる機会があったときは、違う言葉を使うけれど。
Posted by
セラピーとケアの違いをわかりやすく解いてくれた本。 ケアは低賃金、重労働と言われがち。 重労働の部分は身体的なものと考えがちだが、相手の全てを受け止め、受け入れるという精神的なものの方が大きいのだろうと本書を読み改めて感じた。 その反面、相手に精神的に助けられる部分もとても大き...
セラピーとケアの違いをわかりやすく解いてくれた本。 ケアは低賃金、重労働と言われがち。 重労働の部分は身体的なものと考えがちだが、相手の全てを受け止め、受け入れるという精神的なものの方が大きいのだろうと本書を読み改めて感じた。 その反面、相手に精神的に助けられる部分もとても大きいこともたくさん書いてあり、ほっこりする。 セラピーは大学院出てないと携われない職というだけあって専門職と捉えてもらえやすい。 人のすごく奥のたやすく触れないようなものに触れる仕事は専門性が必要。 でもそれは医療のように正解がはっきりしているものでないから、評価が難しいものでもあると思う。 だから心理士は非常勤だったり、主な仕事も心理検査だったりするのかな。 最後お金の問題に着地する。 これは対人職に就く人に陥りやすいジレンマの1つだと思う。 お金がないと生きていけないし、お金のためだけに仕事をするわけでもないし…でもこの人たちと接することでお金をもらっている事実。 「やってあげてる」と言う言葉は使いたくないけど、「やってあげてる」からお金がもらえちゃうのだろうか。
Posted by
前著の「日本のありふれた心理療法」においても西洋の輸入物である心理療法を日本の土着文化といかにすり合わせるかについての葛藤状況を述べた好著であった。本書は、著者の体験を述べる形で、それをフィクション化した形で、ケアとセラピー(キュア)について、現在の臨床(心理臨床だけではない)に...
前著の「日本のありふれた心理療法」においても西洋の輸入物である心理療法を日本の土着文化といかにすり合わせるかについての葛藤状況を述べた好著であった。本書は、著者の体験を述べる形で、それをフィクション化した形で、ケアとセラピー(キュア)について、現在の臨床(心理臨床だけではない)における葛藤状況において、それに対しての一つの答えを提示している。それは「ケアする人がケアすることを続けるために、ニヒリズムに抗して『ただ、いる、だけ』を守るために、それは語られ続けないといけない。そうやって語られた言葉が、ケアを擁護する。それは彼らの居場所を支えるし、まわりまわって僕らの居場所を守る」。そのような語りの文章であった。読ませる本で、今年の現時点で私のナンバーワン本である。
Posted by
ケア(ただ居ることを支える)は金にならないが、そこに光(市場原理)を当てると、セラピー(セラピー自体悪いものではないが、ここではただ居ることを強要することに近い)として変容し、ニヒリズムの渦に巻き込まれる。この切なさから、沖縄のデイケアを去ることになったという話。 江口先生オスス...
ケア(ただ居ることを支える)は金にならないが、そこに光(市場原理)を当てると、セラピー(セラピー自体悪いものではないが、ここではただ居ることを強要することに近い)として変容し、ニヒリズムの渦に巻き込まれる。この切なさから、沖縄のデイケアを去ることになったという話。 江口先生オススメの本
Posted by
感想 読んで自分に色々思い当たる節を書く。 『ケアとセラピーについての覚書』と最終章だけでも読んでよかった。 自分がケアを受けてても最終章みたいなことが頭に浮かんで冷めてしまって、たとえ吐くほど辛かろうがセラピーに行ってしまう。 筋トレ好きになるのも最終章あたりの事情が理...
感想 読んで自分に色々思い当たる節を書く。 『ケアとセラピーについての覚書』と最終章だけでも読んでよかった。 自分がケアを受けてても最終章みたいなことが頭に浮かんで冷めてしまって、たとえ吐くほど辛かろうがセラピーに行ってしまう。 筋トレ好きになるのも最終章あたりの事情が理由。 心理的なケアは受けても最初はともかく、回数重ねても全然安心感も進捗もない。受ける側も居るのが辛くなる。最終章のこともあるけど、自分の性格的にケアする側の傷がアドバイスから見えてしまい、自分が仕事でもないのに他人の心理的なケアする側に回ってしまって全く休まらないし、逆に重い。ケアしたがりはアドバイスしたがりだし、感謝されたがり、患者褒めたがり、持ち上げたがりっていうのもあるし、アドバイスからケアする側の傷が見えてしまうのもあって非常に落ち着かない。自分が褒められるのが非常に苦手というのもある。自分が、仕事の評価はともかく、流動的でいつでも変化しうる人を評価することに興味がないし、今日の自分が明日の自分と地続きである保障なんてどこにもなくて、そこを期待される感謝や賞賛が重いから。ケアは最終章にもあるように、実は経営的に患者本人のリピートが欲しいが為に、患者がちょろちょろ燃えているぐらいにしておきたいんだけど。ただ、それなら銭湯行ったりランニングするなりの自己完結した方法で行えばよい。ケアってまず金かけずに自分で出来る必要がある。 セラピーは時に患者に踏み込む必要がある。患者に踏み込み、患者の今を見える化し、患者に火をつけ完全燃焼させることで、患者のニーズを別のものに変えてしまう。先に人にケアをしてしまい、火を弱火のままで維持して患者の気づきを奪う方向とは全く違う踏み込み方。セラピーは目指すは自立なのだから、まず自分で自分の状態に気がつくことが必要。そしてセラピーは患者を労うことはあっても、実は褒めない。患者を褒めるのはまず自分の物差しを持つ努力をしている患者自身だから。 ガチのセラピー関連の支援職というのはセラピーみたいな方が、たとえ患者が自立してセラピーを提供する場所を離れても、評判で他の患者を連れてきたり、一年に一回ヘルスチェックで立ち寄ったりするんじゃないんですかね。本当のセラピーの支援職には結構なお金払ったりもするのは、患者に火をつけるというのは支援職側にも火がついてめちゃくちゃにある可能性があるから、そこに保険をかけるようなもので必要経費なんですよね。しかも、わかりやすい身体的な技能だけならプロアスリート相手のトレーナーの方があったりするし、彼らはエビデンスがバックにある最新技術を用いた科学的アプローチをしたりするけど、セラピストってセラピストを守ってくれるエビデンスもあまりなく、仕事の成果の再現性をアプローチしずらいから、火を守る盾がない状態で仕事しているようなもの。 あと、全般的にレジャーのような運動に関連する描写が多く、『「こらだ」に触る』章でも触れられているが、心と体というのはわけらない。心理的なケアというと大袈裟だが、心理的なものも包括した全般的なケアだけなら、レジャーのような運動で十分なんじゃないか。 そして実は、レジャーのような運動が、ケアだけでなく、上記のような人に対するセラピー的な踏み込み方が一番学べるんじゃないかなと感じた。レジャーのような運動には気づきと踏み込みが一番必要。野球の球を受けるのも、バトミントンの羽根を打ち返すのも、気づきと踏み込みが必要。コミュニケーションというのは、理屈をこねくりまわすより、まず観察と身体動作なんですよ。
Posted by
タイトルで本を選び、宅配で届いて手に取った時に初めて、医学書院から出版された書籍と気がついた。そうか、学術書でもあるのか。 読み始めると、沖縄ならではの強い日差しと海の景色が映像で見えそうな描写と、デイケアでの日常が一見軽妙なエッセイとして描かれている。でも、これは学術書だ。 ...
タイトルで本を選び、宅配で届いて手に取った時に初めて、医学書院から出版された書籍と気がついた。そうか、学術書でもあるのか。 読み始めると、沖縄ならではの強い日差しと海の景色が映像で見えそうな描写と、デイケアでの日常が一見軽妙なエッセイとして描かれている。でも、これは学術書だ。 そして著者の経験を共有するうちに、多様性を認めようとかなんとか言いながらも、白黒はっきりと二分されてしまう今の世の中の生きづらさに思いをはせてしまう。 白と黒のあわいでどう自由に生きるか、流されずにちゃんと考え続けようと思わされた。 良書です。
Posted by
ケアとセラピーの協奏。または弁証法。 ゲラゲラ笑いながら読めるが、ケアの意味がよくわかる。 「会計」によって変化と成長を強いられる社会の厳しさよ。
Posted by
小難しい専門用語はほぼなく、出てきたとしても分かりやすい言葉で書かれている。 何より筆者が体当たりで感じたことを言葉にしているから、単に読み物として面白い。この本に出ている登場人物が架空であることを後から知り驚いた。言動に体温を感じたからだ。ケアやセラピーに携わらない人に対しても...
小難しい専門用語はほぼなく、出てきたとしても分かりやすい言葉で書かれている。 何より筆者が体当たりで感じたことを言葉にしているから、単に読み物として面白い。この本に出ている登場人物が架空であることを後から知り驚いた。言動に体温を感じたからだ。ケアやセラピーに携わらない人に対しても自信を持って勧められる一冊です。
Posted by