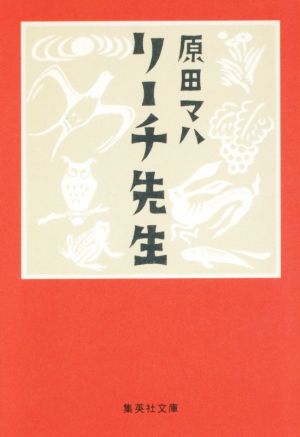リーチ先生 の商品レビュー
バーナード・リーチという実在の人物と創作の登場人物たちをこんなにもリアリティをもって描けるのはほんとうにすごい。 いつのまにか亀ちゃんの立場になってリーチ先生や柳さんのあたたかさに触れていた。 みんな、ただただ美しいものが好きで、ものをつくることが好きで。互いの、その純真さを信じ...
バーナード・リーチという実在の人物と創作の登場人物たちをこんなにもリアリティをもって描けるのはほんとうにすごい。 いつのまにか亀ちゃんの立場になってリーチ先生や柳さんのあたたかさに触れていた。 みんな、ただただ美しいものが好きで、ものをつくることが好きで。互いの、その純真さを信じているからこそ、通じあっているからこその信頼と尊敬がある。 楽園のカンバスや暗幕のゲルニカも大好きだが、あれらの鋭く切れのあるどこか冷徹な文章とはちがい、あたたかい気持ちで読める一冊でした。
Posted by
陶芸の知識がなくても芸術に没頭し 色々な苦労を重ねてるカメちゃん! リーチ先生との出会い!別れ! 素敵でした。映像化してほしい。
Posted by
原田マハ 「 リーチ先生 」 陶芸家バーナードリーチと弟子(亀乃介)の芸術活動を綴った小説 著者は 芸術と生活(社会)の接点を探すのがうまい。日常使いの雑器の芸術性を取り上げ、無名の陶工を主人公にして、芸術家としての個性より 窯や土との関係性(自然と人間の共生)から 芸術を...
原田マハ 「 リーチ先生 」 陶芸家バーナードリーチと弟子(亀乃介)の芸術活動を綴った小説 著者は 芸術と生活(社会)の接点を探すのがうまい。日常使いの雑器の芸術性を取り上げ、無名の陶工を主人公にして、芸術家としての個性より 窯や土との関係性(自然と人間の共生)から 芸術を伝えようとした? 亀乃介の生き方は 雑器の素朴さ、謙虚さとリンクしており、リーチや柳宗悦 より「名もなき花」 亀乃介の方が 輝いている。亀乃介は 「リーチ 日本絵日記」に出ていた 森亀之助がモデル? であれば フィクションでも会えて嬉しい。 濱田庄司 も魅力的。濱田庄司の作品や 大分県日田の おんた焼 (小鹿田焼)を見てみたい。 「新しい何かを創り出そうと思ったら、誰かがやってきたことを全部 越える気持ちが必要」
Posted by
原田マハさん。私はあなたのファンになりました。 芸術に関する史実と感性を学び感じたければ、あなたの本を読むことにします。 物語は小鹿田にて陶芸家の養子として暮らす沖高市を主人公に、同地区を訪れる高名なイギリス人陶芸家エドワード・リーチをもてなす場面から始まる。リーチとの会話で高...
原田マハさん。私はあなたのファンになりました。 芸術に関する史実と感性を学び感じたければ、あなたの本を読むことにします。 物語は小鹿田にて陶芸家の養子として暮らす沖高市を主人公に、同地区を訪れる高名なイギリス人陶芸家エドワード・リーチをもてなす場面から始まる。リーチとの会話で高市は、亡くなった父 亀之助が若き日にリーチ先生を師事し半生をかけて献身的に先生の夢の追求をサポートし、自らも陶芸を極めようと生きていたことを知る。 そして物語は主を亀之助に代え、リーチとの出会いや彼を師事して自らも芸術を志すことになる亀之助の純粋で真っ直ぐな心の動きを生き生きと描き出す。リーチを通じて親交を深める柳先生を始めとする白樺派の評論家たちやのちに陶芸の道を進む同士となる濱田を始めとする芸術家たちの面々は揃って志が高く、友人想いで誇りに満ちている。それぞれに魅力的で物語を骨太なものにしている。 一本気に自身が生涯をかけて追い求めるもの(芸術、陶芸)を見つけ、他のことには目もくれずに技術や感性の習得に取り組む亀之助たちの姿には胸が何度も熱くなったし、なにより、リーチ先生という大きく強い憧れの対象を若いうちに見つけることができた亀之助の幸運とそれを感じ取る素直さに羨ましさを感じた。 リーチ先生は圧倒的な芸術的感性をもち、さらには単身で日本に渡り、東西の芸術的架け橋になるべく奔走する情熱や気概、バイタリティをも持ち合わせているのだが、亀之助がこれほどまでにリーチを慕ったのは、このイギリス人が類稀なる大らかさと優しさの持ち主で、亀之助を始めとする弟子や友人達への思いやりと気遣いに満ちた、人格者だったからなのではないかと思う。 日本で陶芸に出会い、日本的な美意識や技術を存分に体得したリーチは、濱田と亀之助を連れて故郷のイギリスで芸術家と職人を育てる工房を開く。確かな手腕と根気強さをもって地元に新しい陶芸の文化を根付かせた頃、関東大震災を機に濱田と亀之助は東京に帰ることになる。 15年リーチとともに芸術を追いかけてサポートを続けてきた亀之助もこの時、自信を持って「自らの陶芸」を見つけようとリーチと離れる決意をする。 東京に戻り紆余曲折を経て、有名ではないが自らの陶芸を続けていた亀之助も、幼い子どもを残してその生涯を終える。我が子に、陶芸家に養子に行くようにと遺して。 巡り巡って父親の恩師であり同志であったリーチ先生との出会いを果たした高市の目線にまた戻り、物語は暖かな繋がりを感じさせながら終わりに近づく。 あとがきで知ったのだが、 リーチや柳、濱田らは実在の人物であるが、主人公の亀之助やその子・高市は完全なフィクションらしい。 心にとめたい場面をいくつか。 芸術に携わりたいといあ想いを抱えながら、元来の謙虚さで一歩を踏み出せない亀之助にリーチが伝えた言葉。 「画家で詩人のウィリアムブレイクがとても興味深いことを言っているよ。それはね、こういう言葉だ。『欲望が、創造を生む』」 「この世界じゅうの美しい風景を描いてみたい、愛する人の姿を手に残したい、新しい表現を見つけたい。そんなふうに『やってみたい』と欲する心こそが、私たちを創造に向かわせるんだ」 個性こそ芸術家に最も必要なものだと説くリーチが言った言葉。 「トミ(富本)と私は偶然、同じ日、同じ時、同じ場所で陶芸に目覚めた。同じように創作し、同じ道を、同じ方向に向かって歩み始めた。けれど、自分たちは、同じ人間ではない。同じ芸術家ではない。それは自分にしか創れないものを創り続けていくしかない、ということなんだ。そうすることによってしか、ほんものの芸術家になることはできないんだ」 イギリスのリーチ・ポタリーでの初めての火入れ。焼成。ことごとくひび割れや色むらが発生する中、ただ一つ、亀之助が作ったジャグだけが素晴らしい出来だったとき。リーチから掛けられた言葉。 「これを創ったのは、君だね?カメちゃん」 「どうしてわかるのですか?」 「わかるよ。だって私は、君が創るものを、もうずっとみつめてきたのだから」 「どうだいカメちゃん。私の言った通りだろう?全部の器を見てみない限り、焼成の結果はわからない、って」 「だからこそ、陶芸は、面白いんだ」
Posted by
今回は実在の陶芸家のお話で、高村光太郎や志賀直哉なんかの名前も出てきて興味深かったんですが、亀之介と高市のところがうーん。この二人はフィクションだったとのことなのでちょっと微妙でしたかねぇ。
Posted by
* 陶芸という芸術、用の美について 今回のお話は、「陶芸」という道を極めたバーナード・リーチの半生と共に、陶芸について考えさせられる作品。 私自身、母が陶磁器好きのため、百貨店の最上階ではよく高価な食器を見るし、都内の百貨店の食器売場がまるで美術館のように個性的で美しい陶磁器を置...
* 陶芸という芸術、用の美について 今回のお話は、「陶芸」という道を極めたバーナード・リーチの半生と共に、陶芸について考えさせられる作品。 私自身、母が陶磁器好きのため、百貨店の最上階ではよく高価な食器を見るし、都内の百貨店の食器売場がまるで美術館のように個性的で美しい陶磁器を置いているのを、興味深く見ていた。 また、昨年秋に行ったウィーン旅行では、貴族が収集・使用していた食器類の美術館を訪れたり、アウガルデンのショップにも行ったこともあり、作中で語られる「用の美」や陶芸の魅力には非常に共感した。 * 「芸術家」というコンテンツを使って見せる、多様性 最近よく聞く「多様性」という言葉。でも多様であることや自分らしさを大切にするという価値観は、決して最近出てきたものではないということがわかった。何年も何十年も前から芸術家たちは「自分らしさ」と「多様性」を求めて、はるか昔から「自分らしくあること」や多様な価値観を世間に示せるように努力してきた。芸術家という目線を通して、多様な価値観について言及されているのが、小説の題材となっている時代は昭和初期〜戦後でありながら、現代的なテーマも扱われており、めちゃめちゃ素晴らしいなと思った。 * 「ユニークネス」こそが芸術、を体現する原田マハの美術史フィクション小説 作中で後半、何度も語られる「ユニークネスこそが芸術」であるということ。自分にしかできない、自分らしい表現を探せと… それを読んで思ったのが、この小説こそが原田マハの芸術品だということ。 美術史の実在の人物を、史実にそりながらも、オリジナルキャラクター「沖亀之助」や「沖高市」と強く関わらせることでそのキャラクターをワトソン役に、恐らくある程度の演出・脚色を施しながらストーリーとして非常に魅力的なものにしている原田マハの手法は他に類を見ない。 オマケにそこで扱う芸術や芸術家の魅力も余すことなく伝えられるところも素晴らしい! この小説をどこかにジャンル分けしたくとも、ぴったりくるジャンルがないように感じる。 これこそ、原田マハにしかできない表現。新しいジャンルの芸術なのだと感じた。 原田マハの小説で「たゆたえども沈まず」も同じジャンルに属するな、とは思うものの、 「たゆたえども沈まず」の時よりも強くリーチと亀之助が関わっていて、その二人の友情、師弟愛が本当に素晴らしくて、めちゃめちゃパワーアップしてるなと感じた。
Posted by
リーチ先生や周りを取り巻く日本の友人達、日本とイギリスの民芸と『用の美』の素晴らしさについて、淡々と伝わってくる作品。 主人公である沖亀之助が控えめながら芯を持った人物で、それが民芸の話を一層際立たせていた気がする。マハさんの描く主人公は才色兼備な女性のイメージが強いが、こうい...
リーチ先生や周りを取り巻く日本の友人達、日本とイギリスの民芸と『用の美』の素晴らしさについて、淡々と伝わってくる作品。 主人公である沖亀之助が控えめながら芯を持った人物で、それが民芸の話を一層際立たせていた気がする。マハさんの描く主人公は才色兼備な女性のイメージが強いが、こういった作品もまた良い。
Posted by
一万円選書4冊目。題材が良い。イギリス人陶工家として有名なバーナードリーチを扱った物語。清々しく意識の高い登場人物達に心洗われた。日本民芸館にてリーチや濱田の作品を見たことがある。リーチの作品はエレガントで、濱田のはワイルドな印象を受けた覚えがある。この本を読んでまた興味が湧いた...
一万円選書4冊目。題材が良い。イギリス人陶工家として有名なバーナードリーチを扱った物語。清々しく意識の高い登場人物達に心洗われた。日本民芸館にてリーチや濱田の作品を見たことがある。リーチの作品はエレガントで、濱田のはワイルドな印象を受けた覚えがある。この本を読んでまた興味が湧いた。美的感覚が触発される。⭐︎3。
Posted by
最高。民藝についてもっと知りたくなった。 器が好きになった。 好きなものは、そしてアートは、国境を越える。 用の美。絵画などの美術品も素敵だけど、日常の中に美を取り入れるって、なんて素敵なんだろう。
Posted by
それはまるで、大河ドラマを観ているような感覚。文章を読みながら、目の前にその情景がありありと浮かび上がってくるようだ。 一人のイギリス人陶芸家の半生を、ある日本人の親子に渡って語り継がれて行く、史実を元にしたフィクションなんだけど、これがまたなんともドラマティックで感動的だ。 ...
それはまるで、大河ドラマを観ているような感覚。文章を読みながら、目の前にその情景がありありと浮かび上がってくるようだ。 一人のイギリス人陶芸家の半生を、ある日本人の親子に渡って語り継がれて行く、史実を元にしたフィクションなんだけど、これがまたなんともドラマティックで感動的だ。 その日本人男性は実際には存在しないのだが、実在した人物との密接な繋がりの描きようは素晴らしく、さすが原田マハ、という感じだ。 やはり、原田マハは最高だ。
Posted by