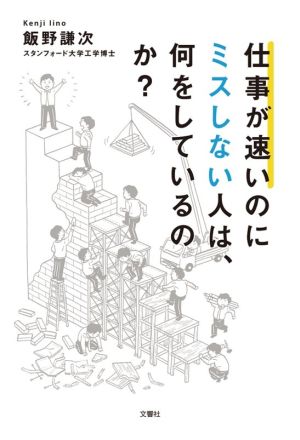仕事が速いのにミスしない人は、何をしているのか? の商品レビュー
スピードを上げつつミスをなくす仕事術の紹介と、失敗の原因を学習不足、注意不足、伝達不良、計画不良の四つに分類し、それぞれについての効果的な対策について解説しています。また、ミスとの向き合い方、ミスをいかに学びに繋げるかという考え方についても触れられているため、ミスに対する振り返り...
スピードを上げつつミスをなくす仕事術の紹介と、失敗の原因を学習不足、注意不足、伝達不良、計画不良の四つに分類し、それぞれについての効果的な対策について解説しています。また、ミスとの向き合い方、ミスをいかに学びに繋げるかという考え方についても触れられているため、ミスに対する振り返りが知見の蓄積が上手く出来てない方にも学びがあります。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
やはりYoutubeやネットの記事等でも見たことはありますが、ミスを減らすためにはミスをしない「しくみ」作りが大切なのだということがわかりました。 また、ミスを「失敗」とせず、「成功の過程にすぎない」という考え方は、是非僕も取り入れたいなと思いました。
Posted by
2022/3/4読了 ビブリアから移行 ちょっとした仕事テクが学べてよかった。 すぐ返信できるメールはすぐに返すとか、ファイルは一箇所で共有とか、ちょっとした工夫って自分じゃ思いつかないからなあ あと、この本の言葉で少し元気づけられた!ずっとクヨクヨしてることが失敗する一番の...
2022/3/4読了 ビブリアから移行 ちょっとした仕事テクが学べてよかった。 すぐ返信できるメールはすぐに返すとか、ファイルは一箇所で共有とか、ちょっとした工夫って自分じゃ思いつかないからなあ あと、この本の言葉で少し元気づけられた!ずっとクヨクヨしてることが失敗する一番の原因になるから、すぐ立ち直って何がいけなかったかの検証を行なって、二度と失敗しない具体的な工夫を行うことが信頼回復に繋がると信じて、今後積み重ねてゆこう。
Posted by
失敗に対して前向きに捉え方を学べる印象。失敗を起こさないための仕組み作りは製造業で重要視されていますね。精神論で以後気を付けます等は信用に値せず、その場しのぎなので気を付けます。しっかり二度同じ過ちを繰り返さない対策をしっかり自分の中で腹落ちさせたいですね。知らないことによる失敗...
失敗に対して前向きに捉え方を学べる印象。失敗を起こさないための仕組み作りは製造業で重要視されていますね。精神論で以後気を付けます等は信用に値せず、その場しのぎなので気を付けます。しっかり二度同じ過ちを繰り返さない対策をしっかり自分の中で腹落ちさせたいですね。知らないことによる失敗対策p152~は何度も読み返したいです。
Posted by
『仕事が速いのにミスしない』感想 『仕事が速いのにミスしない』を読んで、仕事の効率化とミス防止について多くの示唆を得ることができた。本書では、「ヒヤリハットの裏には10のミスがある」という法則が紹介されており、自分のヒヤリハットを放置するとミスの発生率が高まることを痛感した。こ...
『仕事が速いのにミスしない』感想 『仕事が速いのにミスしない』を読んで、仕事の効率化とミス防止について多くの示唆を得ることができた。本書では、「ヒヤリハットの裏には10のミスがある」という法則が紹介されており、自分のヒヤリハットを放置するとミスの発生率が高まることを痛感した。この考え方は、日々の業務で注意すべきポイントを再認識させてくれる。 タスク管理においては、付箋を使ったToDoリストの達成感が最も高いと述べられている。付箋を活用することで、目に見える形で進捗を確認でき、モチベーションの維持につながると感じた。また、ダブルチェックを行う際に、それぞれ別の順序で確認することがミスを防ぐ効果的な方法であることも印象的だった。 情報整理の面では、メールを年代や分類ごとにフォルダ分けすることで、必要な情報を迅速に取り出せる環境を整える提案がなされている。さらに、伝えたいことを3行でまとめることで、相手に明確に意図を伝えることができる点も共感した。 知らないことへの対処法として、その場で調べる習慣を持つことが推奨されている。これをシステム化することで、組織全体の知識向上にも貢献できるのではないかと考えた。 自分の工数を予測し、結果を記録しておくことも重要なポイントである。これにより、業務の見通しが立てやすくなり、無理のないスケジュール管理が可能になる。また、単に依頼を断るのではなく、代案を提示する姿勢も信頼関係を築く上で大切だと感じた。 マルチタスクを避け、一つのタスクに集中することの重要性も強調されている。複数の作業を同時に行うと注意が散漫になり、ミスの原因となるため、シングルタスクを心がけたい。 便利な機能に慣れすぎると考える力が衰えるという指摘も興味深い。意識的に機能を使わずに問いかけを行い、直感を鍛えるトレーニングを取り入れることも有益だと思った。 さらに、「フォルトツリーアナリシス」を活用して失敗の可能性を事前に考える逆転の発想も新鮮だった。仕事で起こる失敗を「注意不足」「伝達不足」「計画不良」「学習不良」の4つに分類し、それぞれを取り除くことでミスを防げるという考え方は、実践的で役立つと感じた。 最後に、暗黙知を形式知に変えることの重要性が述べられている。言葉にならない共通認識を明文化することで、チーム全体の生産性向上につながるだろう。 本書を通じて、仕事の質を高めるための具体的な方法と心構えを学ぶことができた。これらの教えを日々の業務に取り入れ、ミスのない効率的な仕事を実現していきたい。
Posted by
ミスをしないというだけでブランドになる。普段からミスが少ないと、仮に何かミスがあった時に、周りも受け入れてくれやすく、挽回するチャンスも与えられやすい。しかし、普段からミスが多いと、心証が悪くなり大きく損をしてしまうため。これだけは避けなければいけない。失敗を回避するためのコツを...
ミスをしないというだけでブランドになる。普段からミスが少ないと、仮に何かミスがあった時に、周りも受け入れてくれやすく、挽回するチャンスも与えられやすい。しかし、普段からミスが多いと、心証が悪くなり大きく損をしてしまうため。これだけは避けなければいけない。失敗を回避するためのコツをいくつか押さえて実践してみる。「共有するデータは一箇所で保存」「何か物を頼まれたときは、納品先と期限、方法を確実に明確にしておく」「チェックリストを作り、上からと下からで2周する」「To Doリストで管理する」「失敗を絶対に誤魔化さない」「ヒヤリとすることがあったら、絶対に振り返り、予防する」「持ち物は最低限ないと困るものだけ」「仕事仲間とスケジュールを共有する」「記憶に頼るのを止める」「メールは読みっぱなしにしない」「知らないことはその場でGoogleで調べる」「マルチタスキングはしない」「行き詰まったときは他人に頼る」「話し始める前に相手の聞きたいことを想像する」「どうしたら失敗できるかも考えてみる」「ミスに向き合い、しっかりと認める」
Posted by
具体的な解決法、というよりは考え方を抽象的に記載しているため タイトルとのミスマッチで自分が求めている内容の記載は少なかった。 1章 なぜあの人は、仕事が早いのにミスしないのか? ミスが起こらない仕組みに切り替えていく 2章 仕事の質とスピードを同時に上げる方法 入門編 ...
具体的な解決法、というよりは考え方を抽象的に記載しているため タイトルとのミスマッチで自分が求めている内容の記載は少なかった。 1章 なぜあの人は、仕事が早いのにミスしないのか? ミスが起こらない仕組みに切り替えていく 2章 仕事の質とスピードを同時に上げる方法 入門編 データは1か所、バックアップ2か所以上 付箋×TODOリスト 自分の仕事をマニュアルにしてみる →コストや手間をMINに、無駄もミスもない仕事が実現 3章 うっかりを防ぐ「最小・最短・効率」仕事術 毎日必ずする習慣に組み込む コストと時間を最小限に抑えることができることを考える ダブルブッキングを防ぐ →データ一元管理:プライベートと仕事も共有して管理が良い? 4章 メールを制するものが、ビジネスを制する (Teamsなどのツールに置き換わっているところもあり、割愛) 5章 自分のパフォーマンスを最大まで高める仕事術 知らないことはまず調べる 仕事量は「時間」でとらえる マルチタスクは生み出す仕事と単純作業を1つずつ組み合わせ。 6章 ずば抜けた仕事の決め手となる人間関係とコミュニケーションのコツ 完璧を求めない 時間とともに変わっていくことを許容する →視覚化(図、絵、文字)でコミュニケーションする 大きなタスクは小さなタスクの分解する 他人の意見を積極的に取り入れる柔軟さを持つ 自分の話は短めに。言い訳はしない。 7章 仕事の質とスピードが同時に上がる逆転の発想法 どうやったら失敗するか(FTA)を書く ミスに、思い切ってポジティブな視線を向ける どうしてもうまくいかないときは小ゴールを再設定する 8章 自己流・万能仕事術の作り方 失敗の原因:学習不足、注意不足、計画不良、伝達不良の4つ 注意不足:注意タイミングとダブルチェックの質 伝達不良:相手に何を伝えたいのか。 学習不足:勉強する動機付け 計画不良:PDCAも的確な計画を立てることがすべて。 計画の何が悪かったのかを振り返れるようにする 9章 自己実現を最短で叶える仕事の取り組み方 言い訳をしないで、自分の失敗を認める 迷惑をかけた相手中心に考え、謝罪する
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
「失敗学会」の取り組みから高度な内容を期待したが、ミスに限らず仕事の進め方についてのアドバイスが書かれている。ミスをしないために、体系化されたものや、どう仕組化すれば良いかを知りたかったが、経験に基づく内容が多く、わかっていたことの再確認が中心となった。社会人2~3年目くらいに読むとためになるかも。 以下、気になったところ ・先人のいるエリアで失敗している場合ではない ・失敗を防ぐヒントは過去にある ・集中力を温存する ・注意力を求められるときは、そうしなくていい方法を考える ・2種類以上のバックアップをとる ・1つの項目に1つの細かい内容(□水温は10度より低くない □水温は20度より高くない)のアメリカ式チェックリストのほうが、1つの項目にざっくりとした確認の日本式チェックリスト(□水温が適温かどうか確認する)よりも良い。 ・見るものの状態を変えてダブルチェックする ・仕事において、「正しいけどわかりにくい」のは失敗しやすい → どちらでもいい手順は、どちらかに決めてマニュアル化する。(順番はどちらでもいいとか書かないでシンプルにする) ・最小、最短を意識する ・「どのようなやり方に変えれば、そのミスを繰り返さなくて済むのか?」を考える ・「自分も相手も完全ではない」 ・具体的な事柄を一つひとつ達成していけば、当初の目標が達成できる。 ・素直に専門化に相談する ・「どうすれば失敗できるか」をあえて考えてみる ・「どうすれば作業が惰性にならないか」を考える ・「いつまでに、自分の持てる力のどのくらいをかけて実行するか」を考える ・赤福は不正を繰り返さない仕組みを作った
Posted by
ミスをした時は、そもそも仕組みを見直せっていうのはわかってるようでできてなかったな。 あとは「データ共有は1箇所に」も確かになぁと。上司が残していった負の遺産フォルダをみると「どれが最新データやねん!」てキレそうになる同じようなデータの山。今後の管理に役立てたい。 あと、「現...
ミスをした時は、そもそも仕組みを見直せっていうのはわかってるようでできてなかったな。 あとは「データ共有は1箇所に」も確かになぁと。上司が残していった負の遺産フォルダをみると「どれが最新データやねん!」てキレそうになる同じようなデータの山。今後の管理に役立てたい。 あと、「現地・現物・現人を大切にせよ」ていうのは営業でもかなり大切。改めて仕事で大切なことを見直せました。 (言い訳ばっかりする今年の新人くんに読んでほしい笑)
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
仕事に対する姿勢も学んだ ミスした時に反省だけするのは三流。 原因を突き止め、改善方法を考えるのが二流。 脳死でもミスをしない仕組みを作るのが一流。
Posted by