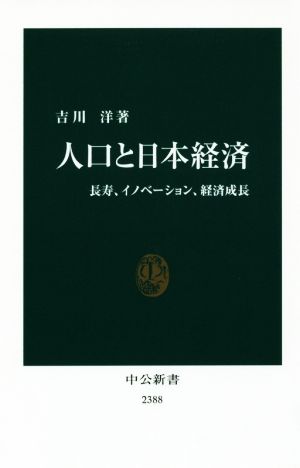人口と日本経済 の商品レビュー
この本は学者が書いたのに詩のよう!!とてもスッキリまとめられてるのに文の一つ一つに思いが込められてる。たくさんの参考文献は、どれも著者の心のなかで輝きを放って存在し、ここに引用されているのだとわかる。(しかも洋書も多く、著者が訳している)なかなか核心をつかないまま残りページが少な...
この本は学者が書いたのに詩のよう!!とてもスッキリまとめられてるのに文の一つ一つに思いが込められてる。たくさんの参考文献は、どれも著者の心のなかで輝きを放って存在し、ここに引用されているのだとわかる。(しかも洋書も多く、著者が訳している)なかなか核心をつかないまま残りページが少なくなるが、最終章、よい世の中とは何か?まで考えさせられる展開に大満足!!
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
イノベーションのほうが大事、人口はそれほど大きな要因じゃない説。経済学の本流ってこんな感じなんだろうか。都留重人の書き方をなんとなく思い出すのが妙。でもねえ、年金は確実にやってくるんだよね。
Posted by
人口が減るということは働き手の数が減っていくということ・・・ これからの日本経済は良くてゼロ成長、おそらくマイナス成長も覚悟しないといけない… いやいや、ちょっと待って… 確かに、人口減は大きな問題だけど、ちょっと人口減少ペシミズムが行き過ぎてますよ、と… 悲観しすぎ、と著者は言...
人口が減るということは働き手の数が減っていくということ・・・ これからの日本経済は良くてゼロ成長、おそらくマイナス成長も覚悟しないといけない… いやいや、ちょっと待って… 確かに、人口減は大きな問題だけど、ちょっと人口減少ペシミズムが行き過ぎてますよ、と… 悲観しすぎ、と著者は言う・・・ そもそも先進国の経済成長は、基本的に労働力人口ではなく、イノベーションによって生み出される・・・ 例えば、本書にある明治3年から100年余りの日本の人口と実質GDPの推移を見れば分かる・・・ 経済成長率と人口の伸び率の差がハンパない・・・ そのハンパない差は何によってもたらされるか? それは労働生産性の成長である・・・ 労働生産性の伸びは、概ね『1人当たりの所得』の成長に相当する・・・ つまり・・・ 労働力人口が変わらなくても(あるいは少し減っても)1人当たりの労働者が作り出すモノが増えれば・・・ 労働生産性が上昇すれば・・・ 経済成長率はプラスになる、と・・・ では・・・ 労働生産性の上昇をもたらす最大の要因は? それは新しい設備や機械を投入する『資本蓄積』と、『イノベーション』による・・・ 例えば、それまで1000人でやっていた工事が、ブルドーザーが発明され(イノベーション)、それを建設会社が導入し工事現場に投入され(資本蓄積)、5人で出来るようになる・・・ 労働生産性上昇! といった感じ・・・ またこういったハード面だけでなく、ソフト面のイノベーションにも当てはまる・・・ 例えばスターバックス・・・ あまり良くない豆のただのコーヒーなのに、あんなに高い値段でも売れる・・・ それまでの喫茶店やカフェと違うコンセンプトやマニュアル、そしてブランド力といった、総合的なソフトパワー・・・ これらもまたイノベーションである・・・ さらに産業構造の変化によっても労働生産性は上がる・・・ 例えば高度成長期の日本の産業構造・・・ 主役は農業から工業、さらに第三次産業へ・・・ 生産性の低いセクターから高いセクターへ労働や資本がシフトすれば、経済全体で労働生産性は上昇する・・・ また・・・ 高度成長期の経済成長率の平均は10%であり、オイルショック後からバブル崩壊までの成長率は大体4%台であるのに・・・ 高度成長期とオイルショック以降の労働力人口の平均成長率は1.3%と1.2%でほとんど変化がない・・・ つまり高度成長が労働力人口の旺盛な伸びによって生み出されたものではないことが分かる・・・ では何でかって言うと、労働生産性の伸びが8.3%から3.4%へと大幅に低下したから、なんだそうな・・・ 経済成長は労働力の伸びで一義的に決まるものではない、と・・・ 経済が人口の増加率をはるかに超える率で成長するということは、経済成長の帰趨を決するのは、労働力人口というよりむしろ労働生産性の推移だということを意味している、と・・・ 労働生産性が伸びるかどうか鍵になるということですね・・・ ちなみに、労働生産性の伸びは『1人当たり』のGDPの成長と言い換えられるんだと・・・ で・・・ 既存のモノやサービスに対する需要は必ず飽和するわけで・・・ 先進国経済は特に慢性的に需要不足に悩まされるわけで・・・ 多くのモノやサービスが普及した成熟経済には、常に成長率低下の圧力がかかっている・・・ そんな先進国経済で成長を生み出す源泉は、高い需要の成長を享受する新しいモノやサービスの誕生、プロダクト・イノベーションである、と・・・ なもんで、問題は・・・ 日本企業が潜在的な需要に応えられるようなプロダクト・イノベーションを成しうるかによる、と・・・ 日本企業燃えろよ!人口減少してるからって過度に悲観して縮こまるなよ!って本・・・ うむ・・・ 日本経済の衰退は必然・・・ ではない・・・ 理屈は分かりやすく、読みやすいのでオススメであります・・・ さすが東大名誉教授・・・ そうは言っても今後の日本経済は厳しいけれども、悲観になり過ぎずに頑張りましょう・・・
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
われわれは等しく、ふるさとに生まれ祖国を築き上げた先人たちに対する敬意を、忘れているのではあるまいか。紙幣の肖像はただ偉人を顕彰するためのものではなく、彼らの努力の結果としてわれわれが生きる糧を購えるのだと、常に自覚するために描かれているのである さて、読者のご当地の二千円札には、誰がふさわしいであろう。(p.100) 私たちは生活習慣として、うしろ向きに履物を脱ぎ、リアから注射する。今さら物を考えず、いわばおざなりにそうしているのであるが、外国人の目には比例と映り、あるいは非合理的な一律性に見えるのである。 よくよく考えてみれば、こうした例は枚挙にいとまないのかもしれぬ。(p.186) ラーメンだけではきっと「替え玉」を要求してしまうであろうというたしかな懸念から、「ラーメン餃子セット」を注文した。まあ、どっちもどっちであろうけれど、根拠なき良心がそう命じたのであった。 ところが、アッという間に運ばれてきた盆に、私は瞠目した。ラーメンと餃子のほかに、白いご飯まで付いていたのである。「でんぷん+でんぷん」どころか、「でんぷんの三乗」という壮挙であった。 良心に従って提示された運命に抗うほど、私はへそまがりではない。禁忌のでんぷんをあますことなく平らげながら、米と麦を食い続けてきた日本人であることを、今さら自覚した。肉や野菜をいくら腹いっぱい食おうと、この充実感は決して得られぬのである。(pp.232-233) 吉川洋『人口と日本経済:長寿、イノベーション、経済成長』(中央公論新社、2016年(2017/02/02読了) 最適な人口とは、それ以上に人口が増えると平均的な福祉の水準が、もはや上がるのではなく、逆に下がってしまうような人口の水準である。つまり、最適な人口とは、1人当たりの平均的な福祉の水準を最大にするような人口である。(p.46) (上田)一昨年になりますが、人口・世帯概数が発表になっておどろいたことは、人口が減った県は25件もあるのに、世帯数が減った県は一つもないということですね。これだけでも大変な変化だと思ったのですが、1%抽出集計の結果をみてそれがはっきりわかりました。(p.84) 先進国の経済成長は、人の数で決まるものではなく、イノベーションによって引き起こされる、ということである。(p.91) いつの時代も高齢者は若い人に比べて有病率が高いが、1955年には医療機関での受療率は高齢者の方が低かったのである。その後、1961年に皆保険制度が成立すると、高齢者の受療率は若い人たちより高くなった。皆保険が成立する以前には、多くの高齢者が病気になっても経済的な理由によって受療を抑制していたと推察される。今日では課題な受療が医療費膨張の一因として問題にされることもあるが、戦後の歴史を長期的な視点から概観すれば、皆保険が平均寿命の延びに重要な貢献をしたことは明らかであろう。(p.116) 開化と云うものが如何に進歩しても、案外其開化の賜として吾々の受くる安心の度は微弱なもので、競争其他からいらいらしなければならない心配を感情に入れると、吾人の幸福は野蛮時代とそう変りはなさそうである。(『漱石全集』第11巻)(p.168) 戦後復興とそれに続く高度経済成長が終焉し、1970年代に入ると、がむしゃらな成長市場主義は姿を消した。これは、先進国においては歴史の必然である。しかしそのことと、文字どおりのゼロ成長論は別だ。あたかも人にとっていってんでいつまでもじっと静止しているよりも、それぞれ自分にあったベースで歩行しているほうが心地よいのと同じように、成熟した先進国においても、それぞれの経済に合った経済成長のほうが、ゼロ成長よりもはるかに自然だ。(pp.184-185)
Posted by
人口減少による結末は、地方消滅などの悲惨な結末には、ならない、と論じた本。 人口と経済の関連性について、学説が良くまとめられているので、その変遷を知りたい人にとっては良いと思う。 しかし、イノベーションが大事!という主張は、なかなか厳しいような…
Posted by
人口減社会での成長のカギは「生産性の向上」であり、2017年の大きなテーマになっている「働き方改革」に繋がってくるんだと感じた。 そもそも成長が幸福なのか、という問題提起も響いた。
Posted by
ペシミズムカオプティミズムかという視点の差異にそれほど大きな影響力はないと考える。それよりも、論理的構成で将来の人口推計と経済成長予測の関連性を見出すことができればそれでよい。 何がどう関連し、因果関係を持っているのか、あくまでもその追求を学者・科学者としてめざしてもらいたい。 ...
ペシミズムカオプティミズムかという視点の差異にそれほど大きな影響力はないと考える。それよりも、論理的構成で将来の人口推計と経済成長予測の関連性を見出すことができればそれでよい。 何がどう関連し、因果関係を持っているのか、あくまでもその追求を学者・科学者としてめざしてもらいたい。 宗教的に賛同者や心酔者を求める活動は、研究活動の妨げにもなりうることを昨今の学者には自覚してもらいたい。 生物学的限界が近付いているかどうかはさておき、寿命の伸長に関する経済学的考察は大変有意義なものだと思う。
Posted by
人口減が我々の幸せにとって悪いことなのか疑問だった。 北欧など人口は少なくても豊かな生活をしている国はある。大事な尺度の一つは1人あたりGDPだ。 過去の経済学者の疑問を見ていると、人口減はプラスにもマイナスにも語られていることに気づく。 やはり1人あたりの豊かさを図る指標を...
人口減が我々の幸せにとって悪いことなのか疑問だった。 北欧など人口は少なくても豊かな生活をしている国はある。大事な尺度の一つは1人あたりGDPだ。 過去の経済学者の疑問を見ていると、人口減はプラスにもマイナスにも語られていることに気づく。 やはり1人あたりの豊かさを図る指標を気にするべきと考える。 1人あたりGDPであり、労働生産性であり、所得のような。
Posted by
人口減少は経済の衰退は必然ではない。 経済成長に必要なのは人の数ではなく、イノベーションである。 一人当たりの労働生産性を上げることで経済成長を成せる。 高度経済成長は世帯数の増加によってもたらされた。 需要は必ず飽和する。 ブルドーザーは人間の「筋力」、AI・ITは人間の...
人口減少は経済の衰退は必然ではない。 経済成長に必要なのは人の数ではなく、イノベーションである。 一人当たりの労働生産性を上げることで経済成長を成せる。 高度経済成長は世帯数の増加によってもたらされた。 需要は必ず飽和する。 ブルドーザーは人間の「筋力」、AI・ITは人間の「頭脳」これらは本質的にどう違うのか。
Posted by
イノベーションによる生産性の向上で、経済は成長する。 GDPが増えているのは、製品やサービスの付加価値が大きくなっているから。
Posted by