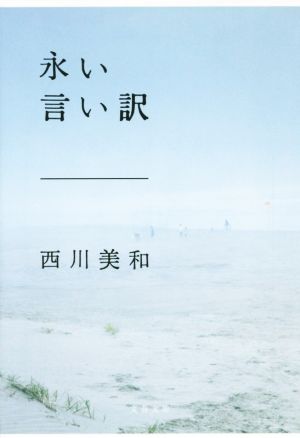永い言い訳 の商品レビュー
わたしには難しかった。進まず最後まで読みきれない…またチャレンジします… 永い言い訳だけあって長い…
Posted by
前半は、妻を失くしてもあっさりな主人公にあまり没入出来なかったのですが、ページを追うごとに自分の身の置きどころや想いに葛藤する部分が出てきて、とても面白かった。 バーで会った人に気持ちを吐露するシーンはもらい泣きしました。
Posted by
不慮の事故で妻を亡くした二人の話。妻が事故に遭った時、不倫をしていた「幸夫」。妻を愛し、二人の子供に囲まれている「陽一」。対照的な二人と思いきや、汚い感情や不完全な部分が描かれることで、妻の死に向き合うことができない同じ人間なのだと考えさせられる。 出会いを通して、失った人や残さ...
不慮の事故で妻を亡くした二人の話。妻が事故に遭った時、不倫をしていた「幸夫」。妻を愛し、二人の子供に囲まれている「陽一」。対照的な二人と思いきや、汚い感情や不完全な部分が描かれることで、妻の死に向き合うことができない同じ人間なのだと考えさせられる。 出会いを通して、失った人や残された時間と向き合っていこうとする様には感動した。綺麗事だけでは語れない様々な感情が、それぞれの視点で表現される面白さ、素晴らしかったと思います。
Posted by
淡々とゆっくりと主人公?の心情が書かれているのが良かった。 最後の方はぐっとくるものがあった。章ごとに語り手が変わりそれぞれの目線があるのも良かった。
Posted by
愛するべき日々に愛することを怠ったことの、代償は小さくはない。 突然の事故で妻を亡くした衣笠幸夫の、愛することを知るまでの物語。 幸夫は事故当初愛人と最中だった。事故前の幸夫と妻夏子の関係はとっくに冷え切ってた。そんな幸夫は妻の死を悲しむことなんかできなかった。 そんなとき、...
愛するべき日々に愛することを怠ったことの、代償は小さくはない。 突然の事故で妻を亡くした衣笠幸夫の、愛することを知るまでの物語。 幸夫は事故当初愛人と最中だった。事故前の幸夫と妻夏子の関係はとっくに冷え切ってた。そんな幸夫は妻の死を悲しむことなんかできなかった。 そんなとき、同じ事故で妻を亡くした大宮陽一一家での生活が始まる。 ふたりの子供と陽一と触れ合ううちに、人を大切に思う気持ちが芽生え始める。 愛するべき人を愛せない、って不幸なんだよなぁ。 わたしは人への愛が浅いから、読んでて少し苦しかった。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
サチオ君の屁理屈こねくり回したような癖のある物言いが 気にいるかどうか。その部分でこの本の好き嫌いが分かれるだろうなぁと思う。 私は 嫌いではない。 映画を監督した作者が書いてるのだから至極当たり前かもしれないが、描写が、景色が、映画のようで、読みながら容易に、と言うか自動でそのシーンが頭に思い描かれる。私はまだ映画版を見ていないのだけれど、一コマ一コマ、まるでスクリーンで見ているような感覚に陥った。本木さんがサチオ君ということは知っているので、余計に。 私には子供が三人いる。だからこそか、泣けるほど入り込んでしまう。娘の小さい頃、息子の小さい頃、うちの子もきっとこう言う態度をとるだろうな。それくらい子供達の描写が素晴らしい。ただ愛らしいだけではない子供のリアルが感じられて入り込んでしまう。サチオ君の反応も凄くイイ。捻くれた感情の中にもサチオ君の本当は悪くない「人柄」が滲み出て、笑いながら涙がこぼれてしまった。サチオ君と陽一家族の段々と暖かくなる交流にサチオ君と共に本当に入り込んでいたから鏑木先生に嫉妬して本性が現れてしまうサチオ君にはあちゃぁ〜と思いつつも、何だかとても愛おしかった。 とても面白かった。バカで不器用で愛すべき登場人物たち。決して良い人たちばかりではないのに、人間臭くて嫌いになれない。終わり方も素晴らしかった。サチオ君の最後の涙が陳腐じゃない、本当に感動的だった。こんなにスッキリとした気分で読み終えることの出来る小説はなかなかない。素晴らしかったです。
Posted by
私はまだ小説というものの読み方がイマイチわかってないのかな? 人それぞれなのかもしれませんが、スムーズしっくりと表現を受け入れられる時もあるけれど、それが出来ない時が、辛い。 読み始めたら、最後まで読まなくちゃと自分を奮い立たせるのだけど、、 この小説はちょっと時間がかかった...
私はまだ小説というものの読み方がイマイチわかってないのかな? 人それぞれなのかもしれませんが、スムーズしっくりと表現を受け入れられる時もあるけれど、それが出来ない時が、辛い。 読み始めたら、最後まで読まなくちゃと自分を奮い立たせるのだけど、、 この小説はちょっと時間がかかった。 主人公の男が最悪だから。 (すでにここでこの小説から出られなくなってるんでしょうけどね。) しかもその男は小説家。 不慮の事故で親族を亡くすのって辛い。 でも、それを表現するには生きているときの関係が浮き彫りになる。 悲しんでないわけじゃない、 色々理由(言い訳)があって苦しいんだよね。 私は真平くんと灯ちゃんと幸夫がメチャクチャに遊ぶシーンが好きだな。 構成が面白くて、どんどんストーリーに飲み込まれるのもあった。 結局、オススメの一冊。
Posted by
映画がとても良かったので読んでみる事に うん、やはり良かった 僕も面倒くさい人間、特に呑んだ時がヤバいく幸夫くんがダークサイドに落ちた時の心境が凄くわかる笑 原作を読み終えて尚更 映画のキャスティング、演技が良かったんだなと再認識
Posted by
『永い言い訳』読了。 すごくよかった。この一言に尽きる作品でした。主人公の気持ちがイマイチよく分からなかったけど、最後の方でグッとくるものがきた。 最初はすごく重かったけど、成り行きで始まった子どもたちの触れ合いが絶妙に面白かった。ちょっと笑った。 人ってひとりで生きていけんよね...
『永い言い訳』読了。 すごくよかった。この一言に尽きる作品でした。主人公の気持ちがイマイチよく分からなかったけど、最後の方でグッとくるものがきた。 最初はすごく重かったけど、成り行きで始まった子どもたちの触れ合いが絶妙に面白かった。ちょっと笑った。 人ってひとりで生きていけんよねって思った。本当に辛い時は誰かに頼ることも必要だなと。私も人に頼ったり甘えたりするの苦手だから、なんとなくその辺は主人公の気持ちは分かるような気がする。極端にぶった斬るところあるから、、、 でも、その辺の器用そうで不器用なところが面白かった。 一見、冷徹そうに見える人って実はどう感情を表に出せばいいのか分からないだけなのかもしれないな… だんだん途中で人間味が出てきてそれで面白かったのかもしれんです。はい。 2021.7.9(1回目)
Posted by
深夜バスの事故によって妻を失くした小説家と、その妻とと共に亡くなった妻の友人の残された夫と二人の小さな子ども。ふとしたことから、小説家と彼の友人の家族との交流が生まれます。 小説家の衣笠幸夫を主人公としながらも、章ごとに視点や人称が入れ替わる体裁で書かれているので、群像劇のよう...
深夜バスの事故によって妻を失くした小説家と、その妻とと共に亡くなった妻の友人の残された夫と二人の小さな子ども。ふとしたことから、小説家と彼の友人の家族との交流が生まれます。 小説家の衣笠幸夫を主人公としながらも、章ごとに視点や人称が入れ替わる体裁で書かれているので、群像劇のような印象も受けます。また、一人称で語れる章は、ぐっと人物にズームアップするように感じられるので、そうじゃないところとの関係に緩急が生じていて、作品がより柔軟なつくりになっていました。くわえて、それぞれの人物の向いている方向が微妙にずれているし、角度も違いますし、同じ人物のなかでも気分によって素直だったり憎たらしくなったりして、デコボコがある感じがします。総合的なイメージでは、いろいろな柄の布(大柄の文様や細かい文様、キャラクターものや縞模様などさまざまな種類)で縫われたキルトが多角形の箱の表面に張られている、というような作品というように、僕には感じられました。 この小説の意識の底にあたるような部分に流れているのは、たぶん愛情に関するものでしょう。冷え切った関係になってしまった夫婦の、その残された夫のなかにはどんな愛情があるのか、というように。また、お互いが正面からつきあいあう家族、つまりぶつかり合いであってもそれぞれが甘んじて受けることを当たり前とする家族に相当する、小説家と交流するようになる家族のなかの愛情もそうです。 が、読んでいて引っかかってくるのは、いろいろな人物たちの本音ばかりではなく、その本音に結ばれた行為のひとつである「卑怯さ」なのでした。卑怯さを許さないだとか許すだとかの考え方もあると思うんです。前者は真摯さの大切を問うようなものでもあるし、後者は寛容さでおおきく包み込みつつ人間への諦念を持ちながらもその後の少しだけだとしたとしても「改善」を約束させるものだったりします。 卑怯さというのは不誠実さを土台としていたりします。そして本書のタイトル『永い言い訳』とは、そんな不誠実さへの永いながい言い訳、終わらないような言い訳なのではないかと僕は読みました。ここでは主人公の衣笠幸夫の言い訳が芯になっていますが、これについては、誠実であるほうが好いのだと考える人であればだれもが言い訳をするものだと思うのです。原罪のように、人はその土台に、本能的な利己ゆえの不誠実を備えているだろうからです。それを超えたいがために、言い訳をするのです。その言い訳は、ただ逃げるだけではなく、ただ逸らすだけでもなく、乗り越えるためのじたばたする態度なのです。 本書で著者はそういったところに挑戦しているし、結果、なかなかに真に迫ったのではないかと思いました。また、だからこそ、よく執筆関係の文章で「ちゃんと人間が書けているかどうかを小説で問われる」なんて見かけたりしますけれども、その点でいえば、むせかえるくらい多様な人間臭さが詰まっている作品として書けていると言えるでしょう。 作品自体、枠から暴れ出たそうにしているところを感じますし、著者は作品がそうしたいのならそうさせる、というように書いたのではないかなと想像するところです。そういう作品だけに、作品自体にまだ空想の余地もあり、「自分だったらどう編むか」みたいに考えたくなったりもします。刺激になりますね。 人をまるごとみようとするときに、そして、それを自分で表現したいときに、何を見ていて何を見ていないか、そして何を意識の外に無意識的にうっちゃってしまいがちか、というようなことに向かいあってみたい人にはつよくおすすめした小説作品でした。そうじゃなくても、ぞんぶんに楽しめると思います。読み手に敷居が高くない文体で、それでいてだらしない表現はなく、手に取ってみればよい読書になると思います。おもしろかった。
Posted by