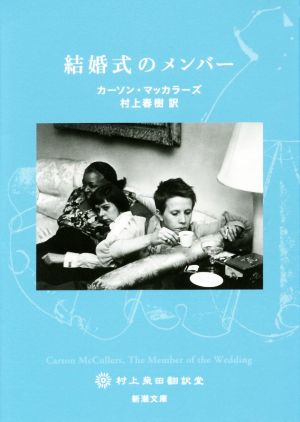結婚式のメンバー の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
この作家の名前を初めて知ったのは、たぶん町山智浩のポッドキャスト「アメリカ映画特電」の、「心は孤独な狩人」(1940)を原作にした映画「愛すれど心さびしく」(1968)の回において(2007)。 後に「トラウマ映画館」としてまとめられた。 その「心は孤独な狩人」を、後に皆川博子が「辺境図書館」(2017)で取り上げていて、うおーっと驚いていたら、なんとその後、村上春樹による「心は孤独な狩人」邦訳が出た(2020)。 とはいえ本作(1946)はそれ以前に「村上柴田翻訳堂」開幕作品として選ばれていた(2016)ので、春樹は本作をジャンプ台にして「心は孤独な狩人」に立ち向かわんとしていたんだろうな。 ちなみに本作、「夏の黄昏」という邦題で加島祥造の訳(1990)、「結婚式のメンバー」という邦題で渥美昭夫の訳(1972)、竹内道之助の訳(1958)がある。 ざっくりいえば、十数年だか二十数年だかの単位で新訳が生まれているわけだ。 なぜか。 どの時代、年代、世代にとっても普遍的な、ある時期=プレ思春期を描いているから、翻訳者の欲を呼び込むのではないか。 また本作は、原作発表後に舞台化し、その舞台をほぼ忠実に、フレッド・ジンネマンが映画化している(1952)。 英語字幕版しか見つけられなかったので流し見した程度だが、なかなかよさそう。 (泣く→歌う、新しい友人が女性→男性、とか変更点があるみたいだけど。) 長々とアダプテーションの歴史を書いてみたが、この話の影響下に編まれたクロード・ミレール「なまいきシャルロット」(1989)との出会いが、私にとっては実質的に「結婚式のメンバー」との出会いであった、と、今回初めて知った。 なんでも映画化権が得られなかったので異曲を作ったらしいが、ほぼ同工異曲といっていいくらい人物配置が似通っている。 さらにいえば、グレタ・ガーウィグ「レディバード」も本作の影響下にあると思った。 というか、あれがこれに影響していると線を引くよりは、どの国どの年代どの世代にも通用すると思うべきか。 で、作品の感想だが、ちょっとまとめるのが難しい……自分にとってあまりにも切実に感じられたので。箇条書きで。 ・12歳という年齢設定が絶妙。根拠の無い自信。いや、自信がないからこそ現実逃避的なファンタジーに縋らなければならないのか。その狭間。子供にとってはこの夢想に賭けるしかない、ということがあるのだ。 ・ここではないどこかへ、という生涯続きかねない夢想の、最も生まれたての姿が、描かれているのかもしれない。 ・苛々と、反面、人恋しさを、ここまで描き込めるとは。 ・「なまいきシャルロット」は13歳(同じシャルロット・ゲンズブール主演「小さな泥棒」は16歳)。「レディバード」は17歳。はっきりいってセックスとの距離感が異なる。身を任せたいと焦がれる対象が、人であるなら話は早いが、結婚式という「イベントへの恋」(ベレニスが変だよと言っている。同年代の男の子に恋しな、と)への恋慕だから、話も気持ちもこじれてしまう。 ・さらに作中の兵隊について。12歳でも、性の舞台に引き上げられんとする外圧がかかるということを、書いている。少なからぬティーンエイジャーは、なし崩しにそうなるわけだが、本作では拒否し(ガラスの水差しで殴打→逮捕されるかもという怯えが、子供っぽい想像で、なお痛ましい)、逃亡。 ・作者は後にバイセクシャルになり、同じくバイセクシャルの男性と結婚、離婚、再婚、自殺目撃、自分も早逝を迎えるわけだが、本作に描き込まれた性への違和感が、あったのだろう。 ・で、最近ちくま文庫から短篇集が刊行され、帯に角野栄子、藤野可織がコメントを寄せているのも、クィア小説として再注目されているからなんだろう。もちろん読む。 ・が、もうちょっとふてぶてしい異性愛者のアラフォー男性でも切実に感じたということを、書いておきたい。「わたしがわたし以外の人間であればいいのにな」は、何度思ったことか。 ・また自分の娘が数年後にこの年齢になってどんな精神の遍歴を送るのかと想像するだに、辛いんだか甘美なんだかわからない気持ちになる。 ・とはいえ、三人で抱き合って泣く場面の、失われた永遠を、ときどき額に入れて思い返したい。支えになってくれるはずだ。 ・ちなみに南部ゴシックという名称でウィリアム・フォークナーと同じ括りに入れられることもあるらしいが、ベレニスという黒人の料理女が、確かにフォークナー作品にもいそうだと感じた。日本でいえば忌憚ない近所のおばちゃんか。
Posted by
舞台や環境、取り巻く状況は何も変わっていないのに心境だけが「すっかり新しく」なり、見えるものの姿が変わり、自分の名前も変わり、フランキー時代の亡霊が後ろをついてくる。どこかに閉まってあった「12才」の心境がありありと描かれる。文学じゃないと描けない「何か」が満載で最高。 登場人物...
舞台や環境、取り巻く状況は何も変わっていないのに心境だけが「すっかり新しく」なり、見えるものの姿が変わり、自分の名前も変わり、フランキー時代の亡霊が後ろをついてくる。どこかに閉まってあった「12才」の心境がありありと描かれる。文学じゃないと描けない「何か」が満載で最高。 登場人物の死をはじめとして所々にドラマチックなことは起きるが、それを圧倒して印象深いのはFジャスミンとして生まれ変わって街に出た景色と、そこから家に帰りベレネス、ジョンヘンリーと過ごす一夏の夕方である。アーカンソー州という多分人生で初めて聞いた州から来た兵隊との出会い。 戦時中、黒人専用席、日本人をはっきり「敵」と認識した描写等がところどころに痛々しく、ただオシャレなだけじゃないアメリカ南部の土臭さがツンと鼻につく素敵な小説だった。タイトルもいい。久々に1冊小説を読み切ったと思う。
Posted by
カーソン・マッカラーズを読むのはこれで二作目だが、ものすごい描写力に圧倒されます。 主人公は12歳の女の子で、その心理は経験したことがなくても共感できるような部分が多くて、一般的にいう「筆力」というものを感じます。 引き込まれる一冊です。
Posted by
1940年代のアメリカ南部。結婚式のために従軍先のアラスカから帰ってきた兄とその婚約者を見た瞬間、12歳のフランキーの人生は激変した。二人の新婚旅行にくっついて生まれ育った町から出て行くと決めたフランキーには、突如すべての人びととの繋がりが感じられるようになる。6歳の男の子と料理...
1940年代のアメリカ南部。結婚式のために従軍先のアラスカから帰ってきた兄とその婚約者を見た瞬間、12歳のフランキーの人生は激変した。二人の新婚旅行にくっついて生まれ育った町から出て行くと決めたフランキーには、突如すべての人びととの繋がりが感じられるようになる。6歳の男の子と料理人だけを話し相手にしてきた少女が、世界と一瞬だけ繋がったある夏の物語。 これは自分が所属するコミュニティをどう決めたら良いのかをめぐる小説だ。父子家庭で暮らすフランキーは地元の少女たちからハブられ、ジョン・ヘンリーとベレニスしか話し相手がいない。6歳の白人の男の子、12歳の白人の少女、40手前の黒人女性が白人男性中心の社会から疎外された存在として等価に配置され、奇妙に同じレベルで語り合う。三人に共通するのは自分で自分のコミュニティを選択できないもどかしさ。フランキーは嫌がっているが、たしかに彼女はこの小さな共同体のメンバーだったのであり、三人が交わるのはこの夏の一瞬だけだった。 フランキーにとってアラスカに行った兄は〈ここではないどこか〉の象徴であり、町にやってくる軍人全員に新天地への幻想をおっかぶせている。背の高いフランキーは年齢を知らないとハイティーンに見えるらしく、若い軍人からデートに誘われてしまう。ここで彼女は〈大人〉というコミュニティに参加できたつもりになるのだが、その実態はわかっていなかった。素敵だと思っていたものがそうでもないのではないかという違和感を抱きながらも認められない感じ、その後の静かな失望の描き方にリアルな質感があってヒリヒリする。新婚旅行同行計画の顛末は回想でダイジェスト的に語るのもスマート。 南部の田舎町を舞台に、ローティーンの焦燥感を描いた小説としてはやはりカポーティの『遠い声 遠い部屋』を連想したけれど、カポーティのムッと匂い立つような自意識過剰さは、本書には希薄だと思う。フランキーは自意識過剰さで『遠い声〜』のジョエルに劣らない主人公ではあり、風景描写のすべてが主人公の心象と呼応しているような濃密な文体も共通するけれど、語り手がフランキーから一歩引いている気がする。ミルハウザーやアニー・ディラードとも近い、顕微鏡的な目で幼い記憶を精査できる人という感じがした。 うだるような夏が一瞬だけ輝いた一日と、残暑の苦い後味。八月の最後の夜にぴったりな小説だった。
Posted by
なんとも形容し難い、表現しづらい気持ちっていくつになってもあるものだなぁと思う。 知識のあるなし、経験のあるなしとは関係なく、言葉では表せない何か。 なんというもどかしさ、なんて気持ちの置き場のないことだろう。
Posted by
お兄さんの結婚式をきっかけに、人生を変える、と決心する12歳の少女フランキーの物語。 名前を変えたくて、田舎町から出たくて、自分はこんなんじゃない、と悶々とする日々。裏返せば、私はなんでここにいるんだろう、と自我とか生死について(直接そんな言葉は出てこないんだけど)あれこれモヤ...
お兄さんの結婚式をきっかけに、人生を変える、と決心する12歳の少女フランキーの物語。 名前を変えたくて、田舎町から出たくて、自分はこんなんじゃない、と悶々とする日々。裏返せば、私はなんでここにいるんだろう、と自我とか生死について(直接そんな言葉は出てこないんだけど)あれこれモヤモヤと考えはじめる時期でもあったような、12歳という年齢。 ねっとりと湿気を帯び、何にも満足できないイライラを、ずっと訴えていて、なかなか読み進められないところもあったのだけど、でもなぜか、とても純粋で、繊細だったな、と読後は思うのだった。
Posted by
『「世界って間違いなくちっぽけなところなのね」と彼女は言った。「なんだって急にそんなことを言い出すんだい?」「つまり、突然だっていうことよ」とフランキーは言った。「世界って間違いなく突然なところだわ」「さあ、どうだろうね」とベレニスは言った。「ときには突然なこともあるし、ときには...
『「世界って間違いなくちっぽけなところなのね」と彼女は言った。「なんだって急にそんなことを言い出すんだい?」「つまり、突然だっていうことよ」とフランキーは言った。「世界って間違いなく突然なところだわ」「さあ、どうだろうね」とベレニスは言った。「ときには突然なこともあるし、ときにはのろのろしていることもある」』 パート1のフランキーは、パート2ではF・ジャスミンとなり、パート3でフランセスになる。それを、13歳のフランキーは自分はもう子供ではないと自覚して自らをF・ジャスミンと呼称するが、最後には年相応の少女フランセスとなる、と書き下してしまうと判ったような訳の分からない要約となってしまうのだけれど、要はその変化こそが描かれていることの全てだとも言える。ただ、その時々に頼りとするものも変わっていくので目が回る感覚にも囚われてしまう。 世の物書き全てが何かしらの警句や倫理観をその作品に落とし込んでいるとは思わないけれど、読んでいる内に何かそんな道徳的なメッセージが聞こえてくる作品は多い。逆にそんな倫理観を嘲笑するかのような物語を敢えて書く作家もいるけれど、それは一つの価値判断の基準線の上にあるという意味では同じ分類の価値観の内にあるとも言える。ところがカーソン・マッカラーズの書くものはそんなある意味陳腐な価値観を軽々と超えているように思う。「心は孤独な狩人」を読んだ時にも、その押し付けられた価値観を拒むような物語が印象的だったし、この同じ街並みが描かれているのかと思ってしまう作品の印象も全く同じ。 それを言い当てるのに、多様性、と最近使われ過ぎて意味がゲシュタルト崩壊しかけている言葉で言い表すのが精一杯なのだけれど、それさえもマッカラーズが描こうとしている世界の表層をかすめただけの、偽善的とさえ言える価値基準の押し付けであるようにも感じる。主人公の抱く何かを探し当てたいとする衝動のようなものも読んでいると感じるのだがそれがはっきりと提示されることはなく、訳者解説から浮かび上がる作家の幼少期を踏まえればこの小説は多分に自叙伝的要素の濃い作品(文庫のカバー写真を参照)であると読むことも出来るし、自らの体験・心情をそのまま反映したであろうと思われる描写も多いけれど、南部の街、大恐慌前夜という雰囲気、思春期に入り掛けた少女の心情などを束ねるものは「混沌」という言葉だけ。 ところが自らの真実を見極める能力に露ほどの疑いも持たない主人公はそんな混沌を前にしながらも、常に何かを危なっかしくも選び取っていく。その選択の瞬間に世の中の矛盾が凝縮されているように思えるのは、マッカラーズの筆致の素晴らしさの故なのだろう。マッカラーズは、物事の多面性を外側からではなく内側から知るものとして響く声を聞かさせる作家だと思う。そんな作家の言葉は(新潮社のウェブサイトに掲載[https://www.shinchosha.co.jp/book/507181/]されている)、この作品の主人公フランキーの葛藤と響き合うように思う。
Posted by
夢みがちな少女が小さな自分の世界から抜け出すことを夢想する。しかし現実は彼女にはお構いなしに進んでいく。彼女に幸せはやってくるのか? 村上春樹訳で後半からは引き込まれた小説でした。
Posted by
またひとりセンスある芸術家に出会ってしまったーー。 読後の今、静寂の中の興奮に浸っている。 兄弟愛の眩しさと、 幼少期の怖いもの知らずさ これらの表現の仕方にセンスを感じずにはいられない。 男の子とことを成そうとするわ、 家出未遂を起こすわ、 自分の名前改名するわ、 まったく...
またひとりセンスある芸術家に出会ってしまったーー。 読後の今、静寂の中の興奮に浸っている。 兄弟愛の眩しさと、 幼少期の怖いもの知らずさ これらの表現の仕方にセンスを感じずにはいられない。 男の子とことを成そうとするわ、 家出未遂を起こすわ、 自分の名前改名するわ、 まったく、ハイセンスな12歳。。。 そしてこれを描く作者のハイセンスさ。。。 結婚式という幸せの場と 嫉妬で狂う12歳の少女 コントラストが美しい。
Posted by
世界とのズレ感をぼんやりと描く小説はなかなか読んでいて乗れないことが多かったのだけれど、ここまで鮮やかかつ徹底的だと大変心揺さぶられる。このくらいの密度で読みたいと自分が思っているのだということに気付かされた。特に2部の午後の台所、日が暮れながらの3人の会話が白眉。息を呑むような...
世界とのズレ感をぼんやりと描く小説はなかなか読んでいて乗れないことが多かったのだけれど、ここまで鮮やかかつ徹底的だと大変心揺さぶられる。このくらいの密度で読みたいと自分が思っているのだということに気付かされた。特に2部の午後の台所、日が暮れながらの3人の会話が白眉。息を呑むような鮮やかなセリフの応酬。
Posted by