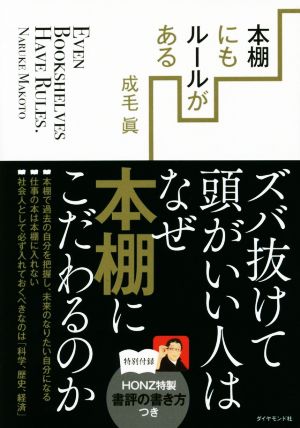本棚にもルールがある の商品レビュー
本棚と本のこだわりについて語った本。本棚について一冊の本を執筆してしまえる本への情熱は尋常ではない。 著者の思う理想の本棚の条件には ・見やすいこと ・2割の余白があること の二つを挙げている。これは本棚を可視化された「外部脳」として捉えているからである。どのような本を面白いと...
本棚と本のこだわりについて語った本。本棚について一冊の本を執筆してしまえる本への情熱は尋常ではない。 著者の思う理想の本棚の条件には ・見やすいこと ・2割の余白があること の二つを挙げている。これは本棚を可視化された「外部脳」として捉えているからである。どのような本を面白いと感じるのか、また、入れ替わる本棚を観察することでどれくらい自分は成長したのか。それらを反映する機能を持つのが「本棚」なのだと言う。 だから、本棚に入れる本は意図をもって選ぶべきである。ただの本の収納場所にしてはいけないのだ。 また、本棚以外には本の買い方について紹介されているページがあり、「著者のメガストアの歩き方」は新しい発見となった。大型書店を回る際には重い荷物に耐えられるリュックやカバンを背負い、口の閉じる手提げ袋を持っていき(万引きだと勘違いされないため)そして、長時間店内を歩いても足が疲れないように、底がほどよく柔らかい靴を履いて書店に行くのだそうだ。本を入れるモノに注意を払うのはすぐに思いつくが、靴にまで意識を飛ばせる人はなかなかいないと思う。本に対しての本気度がよく表れているエピソードであると感じた。
Posted by
著者流の本棚づくりのルールを開陳した一冊。「本棚に並べるべき本とは、面接で答える愛読書だ。自分がどう見られたいかを物語る本」とは、コンサルの本棚がまさにそんな印象だった。 代官山の蔦屋書店「Anjin」(アンジン)の本棚もあまり関心しないので(インテリアとしてはOKだ)、お...
著者流の本棚づくりのルールを開陳した一冊。「本棚に並べるべき本とは、面接で答える愛読書だ。自分がどう見られたいかを物語る本」とは、コンサルの本棚がまさにそんな印象だった。 代官山の蔦屋書店「Anjin」(アンジン)の本棚もあまり関心しないので(インテリアとしてはOKだ)、おそらく著者と私とでは本棚に求めるものが少し違うのだろう。 ただ、「①『サイエンス』②『歴史』③『経済』のセルのない本棚は、社会人として作ってはならない」とか、「会社の本棚には、必ず簿記の基本書を入れておく」あたりは納得感が高い。 加えて、本書に登場するオススメ本は、どれも読んでみたいものばかり(いくつか買ってしまった)。ブックガイドとして秀逸なのだが、本棚がもう一杯だ。「2割の余白」「勝負本のみ」……といった本書のノウハウに従って、少し本をリストラしないと。。。
Posted by
「本棚の意義を再認識」 場所を取らずに本を所有することのできる電子書籍の便利さによって、紙の本を購入し本棚で管理するということをしなくなっていたが、 この本を読む事で「本棚は単なる本置きではない」と本棚の意義を再認識することができた。 本書によると本棚の意義とは、自分の興...
「本棚の意義を再認識」 場所を取らずに本を所有することのできる電子書籍の便利さによって、紙の本を購入し本棚で管理するということをしなくなっていたが、 この本を読む事で「本棚は単なる本置きではない」と本棚の意義を再認識することができた。 本書によると本棚の意義とは、自分の興味を可視化できることで、本棚を眺めるだけで今現在自分が何に興味を持っているのか、知識はどれくらいかが一目でわかるということにある。 ただし、読んだ本全てを本棚にコレクションすれば良いというわけではなく、 何を並べて何を並べないか、限りある本棚のスペースの中で自分が特に残したいと思う本をセレクトする過程により本を選ぶ感性が育つとのこと。 自分はこれまで、購入した本は全て手元に残しておきたいと思うあまり、家の本棚が全て埋まってしまった後も、もう読まないような本まで収納箱に入れて手元に残しておくということをしていた。 物を置くスペースがなくなるにつれ、これからは全て電子書籍で購入すれば手元に全て残せるじゃないかという考えから紙の本は買わなくなってしまっていた。 しかし本によっては電子書籍よりも紙の本の方が読みやすかったりパラパラと紙をめくる動作が好きだったり、本による製本の違いを楽しんだりと紙の本ならではのメリットも感じていたので、これをきっかけに「自分好みの本棚を作る」という目的で再び紙の本を購入することにした。 著者が紹介するルールとは多少違いはあるが、「100冊程度が収納できる本棚に自分なりのルールを決め本をセレクトする」という決まりを作ったおかげで、自分の好みを集めた厳選された本棚が出来上がっていく様子や、後から本棚を眺めることが楽しくなった。 本が溢れて仕方がないからどうにかしたい、でも電子書籍よりも紙の本が好きという方には特に読んでもらいたい本。
Posted by
本書を読むと、急激に本棚を整理したくなります。 これまで本棚はクローゼットの中に閉まっていましたが、本棚から刺激をもらうためにも、部屋の中に置くことを決心。また、本棚を整理するために保管していた本を読み返すきっかけに。 その他、「おもしろそうなところから読む」、「1冊を一気に読み...
本書を読むと、急激に本棚を整理したくなります。 これまで本棚はクローゼットの中に閉まっていましたが、本棚から刺激をもらうためにも、部屋の中に置くことを決心。また、本棚を整理するために保管していた本を読み返すきっかけに。 その他、「おもしろそうなところから読む」、「1冊を一気に読み通そうとしない」など読書家である著者の読み方やおすすめ書籍の紹介もあり、本好きには満足の1冊です。
Posted by
本を読んだり、勉強したりするうえで、こういうふうにしたらいいよという話を読みながら、なんか自分もできる人になったように感じる。こういうの、教養エンタメだよなぁと感じる。本棚とか俺もけっこうたいへんなことになっているし、やってみたいと思うところはけっこうあった。つっこんだままになっ...
本を読んだり、勉強したりするうえで、こういうふうにしたらいいよという話を読みながら、なんか自分もできる人になったように感じる。こういうの、教養エンタメだよなぁと感じる。本棚とか俺もけっこうたいへんなことになっているし、やってみたいと思うところはけっこうあった。つっこんだままになっている本とか、ながめて整理して、並べ替えるって、楽しいよね。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
本棚は本置き場ではない。それ自体が強力な武器である。 本棚以前の基本として、まず、同時に10ジャンルの本を読もう。 ジャンルの化学反応は、他の人には生み出せない独創的なアイデアの種になる。 3種類。それらの本を収容するための本棚は3種類だ。 (1) 新しい(今読んでいる、これから読む)本棚 (2) 厳選のレギュラー(読み終えた、また読む)本棚 (3) 参照(辞書、ハンドブック)本棚 特に (1) と (2) について。 (1) 新しい本棚について 自分の好奇心が本棚という形で視覚化されたもの。 出会いを貪欲に。どんな新しい本でも即座に受け入れる。 そのために、収容本の新陳代謝を保つ (一定期間以内に読み、これぞという本は「厳選のレギュラー本棚」へ。それ以外はサヨウナラ)。 (2) 厳選のレギュラー本棚について これぞという本を、ジャンルごとに収容する。 本を置いてよいのは本棚の8割まで。大体、週一でメンテナンスする。 8割を超えてきたら(面白い、新しい、情報量などで)厳選し、選外は処分する。 ここで、本棚は強力な武器になる使い方の紹介。 本棚でも、博物館や美術館の「常設展示」と「特別展示」をイメージするのだ。 すなわち、本棚の一角に、他人に見せることを意識した特別展示枠を設けるとよい。 ラインナップ、並び順、小物をあしらうなど、それらを考えることで化学反応が生じる。 これを毎月行えば、毎年12のテーマについて教養が深まる。 テーマは、手薄な(あるいは、これまで全く興味のなかった)ジャンル、 本の内容ではなく装丁、たった1つの興味から広がる一連の資料など、 在り来たりなものからユニークなアイデアまで、制約はない。 せっかく読書、本棚に手間を掛けているのだから、できるだけ血肉にしたいところ。 他人に話すほど血肉になる。本好きとの付き合いも広がって一石二鳥。 1人より2人。2人より10人に、どんなことが書いてあるか、何が面白いかを話すのだ。 読書の話ができる人がいなければ、書評するのもよい。 1200〜2000字で、他人にその本を読もうと決断させるのが書評。 何冊も読み、面白かった本のなかでも、特に面白かった本について書評を書こう。 具体的には、面白い(=誰も知らない「驚くような事実」「新しい情報」)が 鮮烈に伝わるエピソードやキーワードを核にするとよい。 なお、書評はおおむね形式があるので、書評のオリジナリティは選書の方で発揮すること。 「特別展示」は上手い表現だと思う。 考えてみると、無意識に雑な「特別展示」をしてきた気がする。 直近で読む本(新しいもの、再読したいものなど)どんな組合せにしようか考えて、 数十冊程度を手近に並べているけれど、着想(というほど大げさではないけれど)は 確かに影響を受けているように思う。 スペースがなくても、例えば、机上が「新しい本」+「特設展示」で、 本棚が「厳選のレギュラー」+「常設展示」など、何とでもなる。 意識的に試してみることにした。
Posted by
著者成毛氏の本棚のこだわりのみならず選書方法、ジャンル、書評の書き方など、興味深い視点が随所に散りばめられている。
Posted by
読後、本棚を整理せずにはいられない本。「漫画や小説を入れない」「ベストセラーは置かない」など人によっては反感を買いそうなことも多々あったけれど、それ以上に参考になる部分があった。「本棚は余白を残して新陳代謝を上げることが大切」という点を特に意識していきたい。
Posted by
積読が多くなってきたので、それを消化するのもあって本書を購入。「経済」「歴史」「サイエンス」などのジャンルを分けて本を並べる必要性や、メガストアの歩き方などたいへん参考になった。 読んでいて、恩師の本棚を拝見させて貰った時のことを思い出した。そこには100数冊の本が秩序だてて並...
積読が多くなってきたので、それを消化するのもあって本書を購入。「経済」「歴史」「サイエンス」などのジャンルを分けて本を並べる必要性や、メガストアの歩き方などたいへん参考になった。 読んでいて、恩師の本棚を拝見させて貰った時のことを思い出した。そこには100数冊の本が秩序だてて並んでいて、圧のようなものを感じたのをよく覚えている。 そういう意味では本棚も生き物であり、そこには読み手の思想・考え方が浮かび上がるというもの。かつて見た恩師の本棚に負けずとも劣らないものを用意できるよう、日々、本棚のアップデートに努めたい。
Posted by
まんまと本棚を新しく作ったし、今まで図書館で本借りるをメインにしていたが、買う事を優先する気持ちになった。 ポイントで本の紹介もあり気になる本がたくさんあった。特に建築、サイエンスには興味が湧いた。
Posted by