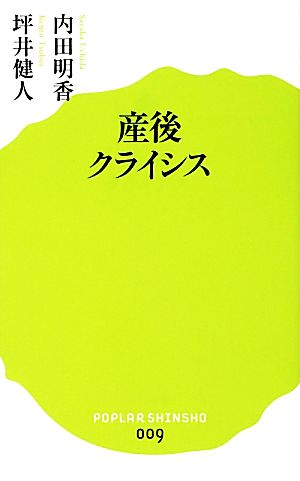産後クライシス の商品レビュー
妊娠中に産後の心構えができたので、読んでよかった。里帰りで夫婦に、育児スキルの差ができ、夫の育児参加の機会が途切れるというのは納得。夫婦でお互いにこういうことがあると、出産前に知っておくべきだと感じた。
Posted by
Yahooニュースで、産後クライシスの記事を見て、自分が妊娠中ということもあり、産後クライシスや興味を持った。たまたま、書店でこの本を見かけ購入。出産を経験するカップルに必ず訪れるクライシスの心構えや対処方を、事前に知ることができた。出産を控えるカップルは、絶対に読むべき。
Posted by
これから職場復帰するにあたって、漠然と感じていた不安が言語化された感じ。 共働き夫婦は読んでおいた方がいいかも。
Posted by
・ 育児に追い詰められた彼女は、とうとう夫に一つ頼み事をしました。「今日は早く帰ってきて」ごくシンプルですが、これまで口に出したことはありませんでした。それだけ切実だったのです。しかし、夫から返ってきたのは、「そんなこと、できるわけないだろ。わかっているだろう」彼女は、「私がこれ...
・ 育児に追い詰められた彼女は、とうとう夫に一つ頼み事をしました。「今日は早く帰ってきて」ごくシンプルですが、これまで口に出したことはありませんでした。それだけ切実だったのです。しかし、夫から返ってきたのは、「そんなこと、できるわけないだろ。わかっているだろう」彼女は、「私がこれだけ大変なのに夫は助けてくれない。夫はもともと私も子どもも愛していないし、必要としていないのではないか」 ・ 夜泣きが何日か続いたある晩のこと。昼間も頻繁に授乳していますから、彼女はまとめて眠る時間がとれずくたくたです。普段は子どもが泣いても起きない夫が珍しく目を覚ましたので、「寝かしつけてくれるかな?」と思ったその瞬間、夫の口から出たのは、「俺、明日早いんだけど」の一言でした。夫はそのまま布団にもぐりこみ、背中を向けたといいます。 ・ 男性陣に取り囲まれて、女一人で「違う違う。ひどい夫なんだ!」と議論しているうちに気づきました。男性陣は「言い訳」をしているのではなく、「本気」なんだと。本当に気づいていないのだと。「自分が妻の愛情を失っていること」そして「その原因を自分の行動が作っていること」にです。 ・ 夫たちは妻の変化になぜ気づくことができないのでしょうか。それは「稼げるかどうかで男の価値は決まる」という教育をされてきたために、結婚後も「稼げさえすればよい夫だ」と勘違いしているケースが多い。 ・ 収入は結婚の条件にはなるけれど、必ずしも夫婦関係の満足度をアップさせることにはつながらないということです。 ・ 真のゴミ出しとは、家中のゴミ箱からゴミを集めて、代わりのゴミ袋をセット。生ごみをさらった上で、ぬるぬるをお掃除するなども含める。 ・ 「〜をやっとくね」といった主体性のある言葉がよい。この言い方はとても前向き。しかも、しっかり引き受けてくれる感じもあって、妻に絶大な安心感を与えることができるでしょう。 ・ 妻が上司だと思ってください。職場で部下が言ったら、「イラッとする」言い回しはしない。部下がこういったら「お、やる気があるな」と思える言い方をする。 ・ 産後は夫婦にとってクライシスであると同時に、夫婦の絆を深めるチャンスでもある。産後とはカップルを破綻させもするが、それを乗り越えられれば、より深い関係を作るチャンスでもある。 まとめ 「〜をやっとくね」を使う。妻を上司と思え。
Posted by
漠然と感じていた産後の夫婦の状態を危機として描くことにある程度成功していると思う。いかにもテレビ的な手法ではあるが。完全なデータや緻密な研究に基づかずとも、印象に残す、というやり方だ。ケースもサンプルも偏りがあるのではないかとうがってしまう。井戸端会議レベル、居酒屋で話すレベルと...
漠然と感じていた産後の夫婦の状態を危機として描くことにある程度成功していると思う。いかにもテレビ的な手法ではあるが。完全なデータや緻密な研究に基づかずとも、印象に残す、というやり方だ。ケースもサンプルも偏りがあるのではないかとうがってしまう。井戸端会議レベル、居酒屋で話すレベルとしては申し分ない。著者たちの狙いもそこにあるのだろう。まずは動機づけ。私は男性ですが、妻編のアドバイスが身に沁みました。
Posted by
NHKの特集から話題になった産後クライシス、言葉の定義は「出産から子どもが2歳ぐらいまでの間に、夫婦の愛情が急速に冷えこむ現象」、とのこと。 すごく簡単にまとめると、「非言語のアプローチじゃ伝わらないよ」、「とことん会話をしようよ」といったところです、男性目線から。 様々なデ...
NHKの特集から話題になった産後クライシス、言葉の定義は「出産から子どもが2歳ぐらいまでの間に、夫婦の愛情が急速に冷えこむ現象」、とのこと。 すごく簡単にまとめると、「非言語のアプローチじゃ伝わらないよ」、「とことん会話をしようよ」といったところです、男性目線から。 様々なデータを用いて理路整然と語られています。 相関関係と因果関係とをしっかり分けて論じているところに好感が持てます。 誰が読むとよい本なのか、人に勧められるのか、判断に迷います。 もちろんどのライフステージにいる人でも何かしら得るもののある本ですが、クライシスの期間を過ぎて離婚をしていないパパは読まない方がよいかもしれません。 自分がその立場なら、読んでいてつらくなります。 自分の仕事の内容に近いこと、話題になっているから、という動機で読んでみましたが、意外にも自分の仕事観やら人生設計やらについて考えさせられました。 >会社に尽くしても幸せになれるわけではない。 >家族か仕事かの選択のときには家族を選ぶべきだ。 1ヶ月の育休を取った結果、会社で干された男性の発言です。 この発言に何一つ違和感を覚えない私はきっと、かわいくない部下なんでしょう。 >一人目が生まれないのは社会制度の問題 >二人目が生まれないのは夫の育児態度の問題 >三人目が生まれないのは経済の問題 とあるNPO代表の言葉です。 「一人目から経済の問題だろう」と思う、そこそこ稼がせてもらっている20代後半、気ままな独身男です。
Posted by
お互いにわかってそうで、わかってない。ちょっとの積み重ねが良い方に転ぶか悪い方に転ぶかなんだなと。出産間近のこの時期に読んでよかった。
Posted by
話し合う以外にこれと言った解決策はないということ。世の中の男女でここまで認識が違うとは思わなかった。自分の子供なのに男性が「育児を手伝う」って意識が大半なのは驚く。
Posted by
かなり読みやすく、一日で読めちゃいますが内容はとてもしっかり書かれており読んでよかったなと思います。うちはかなり良好な関係だと思いますがそれでも産後直ぐは夫や周りへのイライラが産前より倍増しました。是非たくさんの人に読んで貰いたいなと思いました。夫にも読んでもらおう!
Posted by
薄くてサクサク読めるが、衝撃的。内容もしっかりしている。NHKのドキュメンタリーが元ネタで、それを本にしているからか、コンパクトだけど深い。 産後の夫婦のすれ違いがどんな風に生まれていくか、実例が豊富でよくわかるし、想像しやすい。身の回りの人が結構読んでたり、知っていたりした。 ...
薄くてサクサク読めるが、衝撃的。内容もしっかりしている。NHKのドキュメンタリーが元ネタで、それを本にしているからか、コンパクトだけど深い。 産後の夫婦のすれ違いがどんな風に生まれていくか、実例が豊富でよくわかるし、想像しやすい。身の回りの人が結構読んでたり、知っていたりした。 読んでおいてよかった。
Posted by