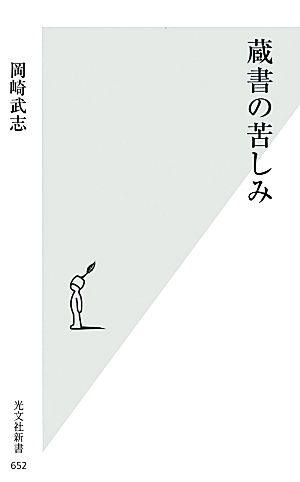蔵書の苦しみ の商品レビュー
本ってあっという間に増えちゃうんですよね。実家に置いていた本なんて親から捨てられちゃったよ。アナログレコードも、CDも。音楽メディアも同じ悩みがあります。本書にも書かれていますが、結局一番良いのは中古で売ることなのかな。たぶん、そうなんだしょう...。
Posted by
タイトルが素晴らしい. 私も以前引っ越しで本を所有することの苦しみをかなり強く味わったので, 思わず手にとってしまった. 本を読み進めるうち,著者の苦しみは私なんぞの比ではないことがひしひしと伝わってくる. けれども冷静に考えれば,この苦しみは,読めない量の本を所有欲にまかせ...
タイトルが素晴らしい. 私も以前引っ越しで本を所有することの苦しみをかなり強く味わったので, 思わず手にとってしまった. 本を読み進めるうち,著者の苦しみは私なんぞの比ではないことがひしひしと伝わってくる. けれども冷静に考えれば,この苦しみは,読めない量の本を所有欲にまかせて買い込めば当然の帰結とも思われる.土地の高い東京でものを集めだすとこれは地獄である. 私自身はそういう状態にいたる前に,本に対する所有欲をなくさざるを得なかったというのは逆に幸せかもしれないとも思ったりした.逆説的だけど.
Posted by
自分の過剰な蔵書の苦しみをどこか嬉しそうに語り、同病者の様子もレポートし、結局処分するしかないとの当たり前の結論に至っている。この病につける薬は、無いようで、困ったもんだ。
Posted by
大量の蔵書に圧迫され、持つ苦しみもあれば、手放す苦しみもある。そんな蔵書にまつわる苦しみと、その逃れ方、の本。強がりも含めながら、手放して、新陳代謝をよくするのだ、という話。 人は、自ら発する熱が放熱が遅ければ暑さを感じる。放熱が速すぎれば寒さを感じる。本の出入りも、同じようなも...
大量の蔵書に圧迫され、持つ苦しみもあれば、手放す苦しみもある。そんな蔵書にまつわる苦しみと、その逃れ方、の本。強がりも含めながら、手放して、新陳代謝をよくするのだ、という話。 人は、自ら発する熱が放熱が遅ければ暑さを感じる。放熱が速すぎれば寒さを感じる。本の出入りも、同じようなもんだ。 蔵書の絶対量は問題ではなくて、本人にとってそれが適切かどうか、というのが重要で、読み返せる本が適度かあればいい、と。そりゃそうだ。 自炊電子書籍は、紙本好きの蔵書の苦しみには、何の解決にもならないという。同感である。気に入った本は紙で残しておきたい。そう思った時点で蔵書の苦しみは再開する。そもそも僕は自炊本のもとを手放していない。死ねば持っていけなくなる、ぐらいの無常観を持つしかない。死ねば関係ないから持っておこう、ともなるのだけど…。 僕には苦しむほどの蔵書はないから、そんなふうに思えるのかもしれない。だから蔵書の苦しみを持つ人たちには、苦しくてよかったね、と声をかけてあげるのが一番いいのだろう、と思った。
Posted by
2万冊超の本に苦しみ続けている著者が、格闘の果てに 至った蔵書の理想とは? ・蔵書は健全で賢明でなければならない ・多すぎる本は知的生産の妨げ ・本棚は書斎を堕落させる ・自分の血肉と化した500冊があればいい ・机のまわりに積んだ本こそ活きる など14個の教訓。 ...
2万冊超の本に苦しみ続けている著者が、格闘の果てに 至った蔵書の理想とは? ・蔵書は健全で賢明でなければならない ・多すぎる本は知的生産の妨げ ・本棚は書斎を堕落させる ・自分の血肉と化した500冊があればいい ・机のまわりに積んだ本こそ活きる など14個の教訓。 面白い。嗜好は異なるもの相通じるものがある。 蔵書の苦しみは、のろけでもある。同病相哀れむ、愛書家 にはのろけ話を聞きながらあるあると楽しめる本である。
Posted by
岡崎さんという名前と、タイトルにつられてすぐに買ってしまったが、本書はもちろん、日々増え続ける岡崎さんの苦しみを訴える書でもあるが、同病の人たちの苦しみを調べて書いたもので、蔵書で家が壊れた話からはじまり、蔵書が燃えた人々、蔵書のために家を建て直した人、トランクルームを利用した人...
岡崎さんという名前と、タイトルにつられてすぐに買ってしまったが、本書はもちろん、日々増え続ける岡崎さんの苦しみを訴える書でもあるが、同病の人たちの苦しみを調べて書いたもので、蔵書で家が壊れた話からはじまり、蔵書が燃えた人々、蔵書のために家を建て直した人、トランクルームを利用した人の紹介を経て、「自炊」があれば蔵書はいらないか、図書館があればどうか等々の話題のあとに、蔵書処分の最終手段として「一人古本市」を提唱している。本に囲まれることに最上の喜びを感じる人もいれば、一冊も蔵書をもたず安閑と暮らす人と、蔵書にまつわる話題は事欠かない。そういうぼくは院生のころから、際限なく増え続ける蔵書を定期的に処分してきたが、最近所属が変わり、研究室を引っ越ししたのを機に(定年まで10年をきったこともあったし)、もとの蔵書の3分の1を処分した。およそ8段30本あった蔵書を20本に減らす必要があった。そこで、ぼくは新しい研究室にいくら入るか、分野別に書架を割り振りし、そこへ入る分を、一度に4箱約100キロずつ運んで入れた。そして、残ったのが3分の1で、これは捨てたものもあるが、大方は専門別に数件の古書店に売った。処分してあとで後悔している本もあるが、こんな機会がなければ、また思い切りがなくては手放せないものだと思った。本書のあとがきに、「『本が増えすぎて困る』というぼやきは、しょせん色事における『惚気のろけ』のようなもの、…これを本気で悩みとして聞く者はいない」まさに言い得て妙である。
Posted by