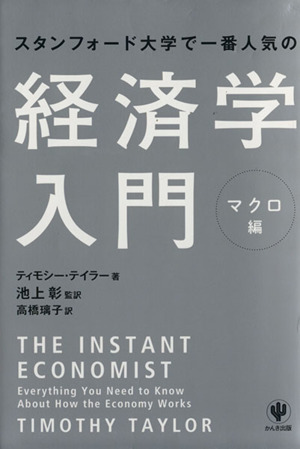スタンフォード大学で一番人気の経済学入門 マクロ編 の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
ミクロ編よりは難解だったが読み終えた。マクロの視点を学ぶと、個々の事象にどのような政策が効いてるのかを考える土台を培うことができると思う。今後は日本銀行や政府の政策のニュースを見て、自分の頭でどのようなことが行われているのか考えてみたい。
Posted by
先日レビューを上げさせて頂きました”スタンフォード大学で一番人気の経済学入門”のマクロ編です。GDP, インフレ・デフレ, 為替, 需要と供給等, 普段よく耳にするキーワードの多くが解説されています。とても判り易く、おすすめの一冊です。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
なかなか面白かった。最初はGDPの話、経済成長、失業率、インフレ、国際収支(経常収支のこと)、総需要と総供給(需要が供給を生むと考えるケインズ理論と、供給が需要を生むと考える新古典派の考えがあり、供給は概ね計画的だが需要は流行などのアニマルスピリットで変動し、この間をつなぐ理論はまだないとのこと、短期的にはケインズ理論で長期的には新古典派の理論が有効)、財政、景気対策、財政赤字で政府の介入の問題点をのべ、つぎに中央銀行の金融政策をのべている(公開買付や量的緩和)。以下は自由貿易のメリット・保護貿易の問題点、為替相場と金融危機、さいごに世界経済を地域ごとにまとめている。
Posted by
マクロ経済学の目標を示し、インフレを避ける理由、お金と銀行の仕組み、貿易の必要性など経済の基礎を例えを交えつつ、わかりやすく解説。アメリカ視点ながらもそれに捉われることなく、世界的な視野で解説しているので読みやすい。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
「長引く不況、さらにはグローバル化や高齢化への対応など、日本は世界の先頭に立っている(p1)」とのこと。 そんな中で「経済学を知れば、この先の経済を待ち受けている希望や、それに伴う代償を正しく理解することができる(p261)」のであれば、学ぶに越したことはない。 マクロ経済の基本を学べるこの本はとってもわかりやすかった(ただページ下の用語解説は本文とダブルので少し邪魔だ)。
Posted by
金融資本の需要料と供給量は必ず一致する。 国民貯蓄+国外からの資金流入=民間の設備投資+政府の借入 国際収支が赤字ということは、国外からの資金の流入が多いといいうことだから、他の三つのいずれかが変化しているはず。経済成長で経常赤字を減らすには国民貯蓄率を上げればいい。貿易が増え...
金融資本の需要料と供給量は必ず一致する。 国民貯蓄+国外からの資金流入=民間の設備投資+政府の借入 国際収支が赤字ということは、国外からの資金の流入が多いといいうことだから、他の三つのいずれかが変化しているはず。経済成長で経常赤字を減らすには国民貯蓄率を上げればいい。貿易が増えるから形状赤字が生まれるわけではない。外国の貿易政策を経常赤字の理由とするのは間違い。
Posted by
学生時代、政治経済学部だったが、ミクロとマクロの違いについて、葉と木全体に例えて俺「分かっているぜ!」と言う感じでいきっていたクラスメイトを冷めた目で見ていたので、経済をミクロとマクロで語る人を見ると、こいつ本当に分かっていっているのか?と斜に構えてしまう事が多かった。 しかし...
学生時代、政治経済学部だったが、ミクロとマクロの違いについて、葉と木全体に例えて俺「分かっているぜ!」と言う感じでいきっていたクラスメイトを冷めた目で見ていたので、経済をミクロとマクロで語る人を見ると、こいつ本当に分かっていっているのか?と斜に構えてしまう事が多かった。 しかし、この経済学入門は実際自分たちが行う経済活動や、ニュースで放送されるFRBの連邦準備制度理事会や、貿易赤字の原因、そしてそれが続くと将来的にどのような影響があるのか?と言う事を分かりやすく説明していて自分でもわかるし面白い。 また、自分が履修した経済学原論の内容を思い出す事も出来た。 そして自分はなんとなくわかった気持ちになっていたが、実際は正面しか理解していなかった事も改めてよくわかった。
Posted by
気づいたときに読むように心がけている、経済関係の本。 この本は、スタンフォード大学の講義を書籍化したもの。 先に発売されたミクロ編に続き、この本ではマクロ経済学が解説されています。 まず、マクロ経済政策の4つの目標が掲げられています。 そしてその項目である、①経済成長、②失業率、...
気づいたときに読むように心がけている、経済関係の本。 この本は、スタンフォード大学の講義を書籍化したもの。 先に発売されたミクロ編に続き、この本ではマクロ経済学が解説されています。 まず、マクロ経済政策の4つの目標が掲げられています。 そしてその項目である、①経済成長、②失業率、③インフレ率、④国際収支、について、以降の章で解説されています。 その上で、財政政策、中央銀行の役割と金融政策、自由貿易と保護貿易、為替といった、世界経済の変動要素について、著者の意見を交えて説明されています。 話題が多岐にわたり、かつそれらが相互にからみあっているので、一度読んだだけで理解できたとは言い難いのですが、マクロ経済が語られる際に、どのようなテーマが議論されるのかは、認識出来たかなと思います。 著者の主張として、財政/金融の政策にしても、貿易の保護にしても、人為的にコントロールするのは限りがあり、また副作用に注意が必要であるということが、伝わってきました。 また、経済成長のベースとなるのが、「生産性の向上」であり、その方法として、技術とそれを活用する人・設備のレベルアップである、ということが繰り返し書かれていたのも、印象に残りました。 この本に書かれている各要素について、さらに知識を深堀りする必要はありますが、世界の経済の動きを理解する入口として、自分にとっては有用な一冊でした。
Posted by
アメリカ視点だが、ある程度読みやすい。用語補足も随所にあるのは好感。ただ、内容が頭に残り辛い。保護貿易には否定的。前半は、歴史とツールの説明。後半は、現状と解説。将来の見通しは、最終18章。時間が無い時に読み直すなら、この章だけでも良い。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
新聞の解説でなんとなくわかっていたことが、本書で明確になったので読んだ価値がありました。貿易に関する比較優位論は本書が今まで読んだ中でもっともわかりやすかったです。
Posted by