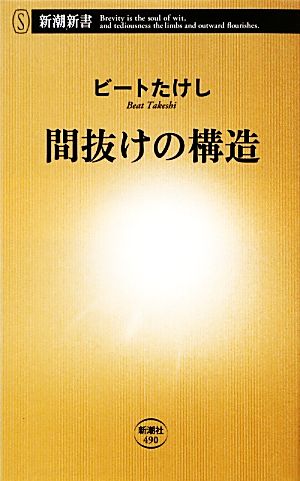間抜けの構造 の商品レビュー
普段あまり深く考えたことがない間について、漫才師や映画監督の視点から説明しており、妙に説得力があった。 印象的だったのは、人間は一部の天才がいたから進化しているように錯覚している、人生は生まれたときと死の間であり、その間しかわからないと。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
・映画の中で説明⇨意味が限定されてしまう もっと考えてほしい ・考えさせるためには余韻や映像の美しさが必要で、そうすると自然に「間」も決まってくる ・この本では「はなから相手にしていない」というフレーズが使われている
Posted by
本書の内容は大きくわけて次の2つです。 ・間抜けな人、すなわち"間(ま)"の悪い人たちの特徴やそれについて思うこと ・お笑い、スポーツ、映画、日常、人生などの、さまざまな場面における"間"のとらえ方 冒頭では、昨今の日本で話題になった...
本書の内容は大きくわけて次の2つです。 ・間抜けな人、すなわち"間(ま)"の悪い人たちの特徴やそれについて思うこと ・お笑い、スポーツ、映画、日常、人生などの、さまざまな場面における"間"のとらえ方 冒頭では、昨今の日本で話題になった"間"の抜けた人たちへ、たけしさんが独特のつっこみを入れています。 間抜けな人に共通しているのは、本人はそのつもりはないけど「間が悪い」とか「間を外してしまう」ことが多く、つまり自分がどういう立場・状況にいるのかを客観的に見ることができないこと、と述べています。 ご自身や周りの方の破天荒なエピソードと、その時の心境がオープンに語られていて、読み進めていて思わず何度も笑ってしまいました。 しかし、間抜けが必ずしも悪いわけではありません。 とりわけお笑いの世界においては、間抜けであることや恥ずかしいエピソードをどうにかして笑い話に変えることで、間抜けさが芸人としての勲章になるからだといいます。 それだけ、"間"というものは、あらゆる場面で大きな要素を占めています。 「お笑いを制するには"間"を制すること。」 たけしさんが話されるからこそ納得する言葉ですね。 そしてお笑いに限らず、私たちの周りにはさまざまな"間"があります。 ・野球でピッチャーが投球するときの"間" ・議論や討論などで、会話に割り込むときの"間" ・映画やドラマの、役者の演技や台詞の"間" 特に映画では、カメラに映る映像の空間的な"間"や、編集時のコマ割りの時間的な"間"など、いろいろな"間"が作品の出来を左右するといいます。 映画監督として海外の映画祭に行くことで、"間"という感覚が、海外にはない日本独特の概念だということも感じたそうです。 面白おかしく読み進めながらも、いろいろな"間"の取り方について深く追求されているたけしさんの仕事に対する姿勢に、とても魅力を感じました。 さまざまな視点から物事を見ることが大切なのだなと感じましたし、私は仕事として多くの人の前で話す機会が多いので、"間"をあらためて意識して話してみようと思います。 肩の力を抜きながら読める、たいへん興味深い一冊です。
Posted by
ハッとさせられる視点の鋭さは健在です。 それにしても、月1億円を稼いでいたとは・・やはりすごい人です。
Posted by
ビートたけしがとことん"間"について語る。口述筆記のような文体なんで(ダウトだろうけど)たけしさんの声を脳内再生させればすらすら読めるものになってる。 日本人独特の"間"を考えても感覚的で、とにかく理論を展開させてはっきりするものではない...
ビートたけしがとことん"間"について語る。口述筆記のような文体なんで(ダウトだろうけど)たけしさんの声を脳内再生させればすらすら読めるものになってる。 日本人独特の"間"を考えても感覚的で、とにかく理論を展開させてはっきりするものではないと分かる。芸人も観てる側からしたら「面白い」「つまらない」の2択だろうけど、実際はとんでもなく頭を使って場の空気をコントロールしている、と。そこにあるのが"間"になるわけですが。 p155〜の、常識に囚われがちな国民性の件も、頷くような内容。俺も「前例がないから出来ない」ってのが嫌いで、前例を作らなかったら何も起こらないままだよと言いたくなる。それは過去の失敗例や成功例にみるリスクを鑑みた上での現状維持なのだろうけど、クリエイティブな立場だとイノベーションを妨げることに繋がってしまうのだと思う。 映画の足し引きの話は、数学の得意なたけしさんらしい考え方。足して詰め込むのがハリウッドの映画だとしたら、引いていくのが北野映画だと。因数分解の例えが凄く分かりやすい。見せずして分からせる。言わずして分からせる。侘び寂びの感覚。それが日本の良いところであるのに、想像力の足りなくなっている人が増えている。想像力の欠如がよく分かる例としてバラエティ番組の過剰なテロップが挙げられているが、自分の頭で考えなくなるとマジでやばいと思う。空気を読む、人の顔を伺う、楽しいと思えるものを我慢する、周りに合わせる、全部クソです。何の意味もない。そうした右に倣え精神は自分を見失うし、自分で考えて判断が出来なくなる。"空気"を読むより、"行間"を読め、これこそ本著でたけしさんが言う"間"を読むことの大切さではないか。 【読了時間:2時間30分】
Posted by
vol.189 “間”を制するものはすべてを制す。間の悪い人と良い人との違いとは? http://www.shirayu.com/letter/2013/000380.html
Posted by
様々な「間」に対する考察 日常生活、漫才、スポーツ、映画 ・たけしの映画ではなるべく間を大きくとるようにしている(空間的、時間的) →映画を見る人の想像力、思考力を使ってほしいから ・日本人は特に間を気にする…空気を読む →既存のものを壊し全く新しいものを作るのが苦手 たけ...
様々な「間」に対する考察 日常生活、漫才、スポーツ、映画 ・たけしの映画ではなるべく間を大きくとるようにしている(空間的、時間的) →映画を見る人の想像力、思考力を使ってほしいから ・日本人は特に間を気にする…空気を読む →既存のものを壊し全く新しいものを作るのが苦手 たけしの人生にも大学を中退してからの間があった。 履歴書に空白を許さない社会は生きづらい。
Posted by
“間”の取り方で世界は変わるー。 確かに“間”って日本独特の感性であり、日本以外の言語で表現するには非常に難しい、微妙なニュアンスですね。この本は、“間”をどうやったらコントロールできるのか、人生において、どう活かすのかを、たけしさん自身の体験談や周りにいる“間抜け”な人びとを紹...
“間”の取り方で世界は変わるー。 確かに“間”って日本独特の感性であり、日本以外の言語で表現するには非常に難しい、微妙なニュアンスですね。この本は、“間”をどうやったらコントロールできるのか、人生において、どう活かすのかを、たけしさん自身の体験談や周りにいる“間抜け”な人びとを紹介しながら、飽きさせない章立てで構成された実に読みやすい本でした。あの日の事故はさらりと流してますが(^^;)
Posted by
豊富なエピソードを交えて、氏の考える「間」が語られる。 まるでどこかのテレビで話しているかのような錯覚を覚えるぐらいいつもの北野節という感じ。 本書を読んでも、間のつかみ方が上手くなることはないが、お笑い、野球、映画と、氏の得意?分野や、これまでの半生が振り返っての話など、とても...
豊富なエピソードを交えて、氏の考える「間」が語られる。 まるでどこかのテレビで話しているかのような錯覚を覚えるぐらいいつもの北野節という感じ。 本書を読んでも、間のつかみ方が上手くなることはないが、お笑い、野球、映画と、氏の得意?分野や、これまでの半生が振り返っての話など、とても興味深く読めた。 [more] (目次) はじめに 第一章 間抜けなやつら バカと間抜け 間抜けな政治家 間抜けな客 風俗の間抜けな待合室 間抜けな選挙演説 間抜けな芸能レポーター 間抜けなテレビ 間抜けな男と女 間抜けな運転手 間抜けな弟子たち お笑いにとって“間抜けさ”は時として勲章となる 第二章 “間”を制すもの、笑いを制す――漫才の“間” “間”を無視して笑いはできない 「ツービート」の由来 最初おいらはツッコミだった 漫才の例/ツッコミが“間”を操作する 笑いに「正解」はない 同じ相方と最低十年 漫才の高速化 スリムクラブは“間”が悪いのか 「お見立て」のセンス/漫才のリズム 第三章 お辞儀がきれいな人に落語の下手な人はいない――落語の“間” 絶品の「野ざらし」 談志への恩 落語の“間”を決めるもの 「笑い待ち」という“間” 舞台と客席の関係性 高座の意味 第四章 司会者の“間”を盗め――テレビの“間” 間抜けなテロップ 息継ぎの“間” 討論の“間”を制するための技術 「ひな壇芸人」はつらいよ テレビの集団芸に必要なこと 差別用語とあそぶ 水商売の“間” ラジオの“間” 第五章 いかに相手の“間”を外すか――スポーツ・芸術の“間” 間抜けな日本野球 バッターの“間”を外せ サッカーの“間” おかしな相撲の“間” 力の入れ方より抜き方 時代が先か、スターが先か アートと職人芸の差 一握りの天才が人類を進化させる 第六章 映画は“間”の芸術である――映画の“間” 映画の“間”はコマで決まる 映画の空間/殺陣の“間” 映画の因数分解/演技の“間” 役者同士の“間” 映画は“間”の芸術 間抜けな映画 間”を埋めようとする病 第七章 “間”の功罪――日本人の“間” ふしぎな日本語 日本語の“間” 茶と能の“間” やっぱり日本は変な国 “間”がイノベーションを妨げる 第八章 死んで永遠の“間”を生きる――人生の“間” 山あり谷ありだからこそ 大学中退を決めたときの空の色 死ぬ理由をつくる 漫才師になる 漫才ブームからオールナイトニッポンへ フライデー事件とバイク事故 芸人の引退 生き様が最高のエンタテインメント 芸人の損得勘定 過去を振り返らない理由 生まれた時代の“間” 芸人は結果論の世界 なぜ芸能人は占い師にコロッと騙されるのか 人生は、生と死の“間”である
Posted by
・間に対する感覚は日本人独特のもの.しかし間を大事にするということは過剰に空気を読む文化でありイノベーションを妨げる. ・力の入れ方より,抜き方が大事. ・今の時代は“間”がなくなちゃってギスギスしている.“間”があった方が豊かになる. ちなみに私の苗字のも“間”がある.間を大...
・間に対する感覚は日本人独特のもの.しかし間を大事にするということは過剰に空気を読む文化でありイノベーションを妨げる. ・力の入れ方より,抜き方が大事. ・今の時代は“間”がなくなちゃってギスギスしている.“間”があった方が豊かになる. ちなみに私の苗字のも“間”がある.間を大切に生きたいね.
Posted by