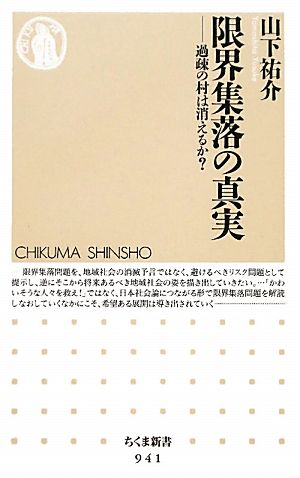限界集落の真実 の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
新書あるあるだけれど、データや情報の羅列ではあるので、読むスピードは落ちるかも。 メディアの誇張された報道であったという主張はわからないでもないが、そのことを幾度も記すクドサは若干ある。でもこれは新書というジャンルではあるあるな気はする。やはり読み物は強烈だったり、斬新さがないと読み応えはないのかもしれない。ドキュメントではなく、フィクションを通じて訴える方が刺さるし、好みではある。 地形や交通によって追い込まれる集落。 若い村の方が消滅しがちな現実。 当事者の問題意識、諦めの気持ち
Posted by
1980年代末に、当時高知大学にいらした大野晃氏が提唱したのが「限界集落論」。 これによると「限界集落」とは、「65歳以上の高齢者が集落人口の半分を超え、独居老人世帯が増加し、このため、集落の共同活動の機能が低下し、社会的共同生活の維持が困難な状態に置かれている集落」と定義される...
1980年代末に、当時高知大学にいらした大野晃氏が提唱したのが「限界集落論」。 これによると「限界集落」とは、「65歳以上の高齢者が集落人口の半分を超え、独居老人世帯が増加し、このため、集落の共同活動の機能が低下し、社会的共同生活の維持が困難な状態に置かれている集落」と定義される。 発表当時はそれほど注目されず、2000年代に入って突如メディアや政府から注目されるようになったという。 著者は、そもそも大野氏が「限界集落論」を提唱したことの意味を整理し、自身の全国の「過疎地域」でのフィールドワークに照らして、本当に限界集落は消滅しているのか、するのか、と検証していく。 2012年初版、2014年7刷なので、現在はどうなのかが非常に気になる。が、山下さんの直近の著作はあの『地域学をはじめよう』などであった。そうかー。 藤里町の事例が出ていて、以前、訪ねて行って、菊池まゆみさんの著作を数冊もらったことがあったことを思い出した。 菊池さんは福祉職として、「お金のない不幸、病気に苦しむ不幸、年を取って体力も気力も記憶力も衰えていく不幸、障害を抱える不幸」などさまざまな不幸を目にしてきた…との過去の自分の発言を、「不幸ではなく不便だった」と言い換えておられる。 限界集落と呼ばれる地域での暮らしも、不幸ではなくて不便である、と言われているような気がした。
Posted by
日本の限界集落に置ける現状とその解決策を知る事が出来た。 自分も田舎から都会の大学に出てきてるけど、定年後は実家に帰るつもり。祖母もまだ生きてるし、あと8年くらいは農作物育ててそう。 限界集落における見方が少し変わった。一方で、これから50年後の日本の集落がどうなってるかはやっぱ...
日本の限界集落に置ける現状とその解決策を知る事が出来た。 自分も田舎から都会の大学に出てきてるけど、定年後は実家に帰るつもり。祖母もまだ生きてるし、あと8年くらいは農作物育ててそう。 限界集落における見方が少し変わった。一方で、これから50年後の日本の集落がどうなってるかはやっぱり心配。 作者のフィールドワークに関して、その村の情報だけじゃなくてもうちょい具体的なエピソードが欲しかったな。新書だから情報量を入れないといけないのは分かるけど、少し眠くなった。
Posted by
過疎を単なる人口減少としてでなく,世代間の住み分けとして捉えるという発想は面白いし,その結果としての限界集落という認識の提議には意味があると思う。 ただその議論がどうにもぼやっとするのは,結局,親と一緒に農業をやるより,都会に出て労働者になった方が稼げたから,団塊以下は長子も含...
過疎を単なる人口減少としてでなく,世代間の住み分けとして捉えるという発想は面白いし,その結果としての限界集落という認識の提議には意味があると思う。 ただその議論がどうにもぼやっとするのは,結局,親と一緒に農業をやるより,都会に出て労働者になった方が稼げたから,団塊以下は長子も含めてみんな都会に出て行ってしまいました、というごくごく当たり前の前提をどこかで糊塗しようとしているように見えるからではないかと思う。 大正~昭和一桁世代(戦前の多産少子・初めの人口増大世代)の兄弟間で「住み分け」が生じていたことはとてもイメージできる。(祖父母兄弟関係の実感として) しかし兄弟間の「住み分け」と,子の流出を同じ文脈で語るのはおかしい。
Posted by
限界集落と言われているところでも今の時点では、外部からの関与がない限り、健全に運営されており、直ちに消滅することはない。 しかし、集落の住民が高齢化しており、若い世代の補充がなければ、このままでは問題が出てくる。近郊に居住している親族の帰還を可能にするような施策を取るべきだ、とい...
限界集落と言われているところでも今の時点では、外部からの関与がない限り、健全に運営されており、直ちに消滅することはない。 しかし、集落の住民が高齢化しており、若い世代の補充がなければ、このままでは問題が出てくる。近郊に居住している親族の帰還を可能にするような施策を取るべきだ、という主張。 帰還を促すのは無理ではないか、という気がします。
Posted by
青森に長年暮らした著者の丹念なフィールド調査の成果が凝縮された、読み応えのある本。 人々の生活の知恵、たくましさが伝わってくる。 著者の地域社会への愛情と「過疎」に対する偏見への怒り も表れている。
Posted by
なかなか読みごたえあり。今からV字回復とはいかないまでも、なにか存続のきっかけはできそうな気もしてきた。
Posted by
<目次> 序 むらは消えるか~東日本大震災を経て 第1章 つくられた限界集落問題 第2章 全国の過疎地域を歩く 第3章 世代間の地域住み分け~効率性か、安定性か 第4章 集落発の取り組み 第5章 変動する社会、適応する家族 第6章 集落再生プログラム <内容>...
<目次> 序 むらは消えるか~東日本大震災を経て 第1章 つくられた限界集落問題 第2章 全国の過疎地域を歩く 第3章 世代間の地域住み分け~効率性か、安定性か 第4章 集落発の取り組み 第5章 変動する社会、適応する家族 第6章 集落再生プログラム <内容> 藻谷さんの本で紹介されていた本。ようやく読めました。簡単に言うと、「限界集落」は作られた問題で、2014年現在で言えば、問題ではない。ただし、それから3年たった現在では、いわゆる「限界集落問題」ではなく、単純にそこをけん引していった世代が高齢化し、消えていくことが問題。ただ、地方ではそこは織り込み済みで考えている。跡継ぎは「限界集落」に近いところに世帯を持ち、前の世代が死んだあとに、入らなくても家や田畑の管理をし、むらのコミュニティに参加している。「限界集落」はない。問題なのは、そうしたコミュニティのない、都会やその周辺の地域である。 近年読んでいる本を総合しても、そういう話のようだ。地方再生ではなく、問題なのは都会の人間らしさの再生であり、地方から学ばないといけない。そのためには、グローバル化とか言って、無駄な成長神話を吹聴する必要はない。身の丈で生きていけばいい、ということだ。 逗子市立図書館
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
限界集落の側から中心は見えるが中心から周辺は見えにくい。真実だ。さて中心に近いところに置いてきぼりにされたものはどうするのか。その場所を周辺とみなしてその場所の真実を見ていくのか?5世代目としてはさてさて。
Posted by
高齢化率が上昇することにより、すでに100以上の集落が消滅し、今後、多くの集落が消滅する。このようなショッキングな報道があったが、本当なのか?を検証しつつ、進むべき道を考える視点を、本書では提供している。 ネタバレながら書くと、現状では高齢化を理由に消滅した集落はなく、因果律が合...
高齢化率が上昇することにより、すでに100以上の集落が消滅し、今後、多くの集落が消滅する。このようなショッキングな報道があったが、本当なのか?を検証しつつ、進むべき道を考える視点を、本書では提供している。 ネタバレながら書くと、現状では高齢化を理由に消滅した集落はなく、因果律が合わない。また、個々の集落で事情は異なり、元気な地域もある。これらから、マスコミに踊らされた感がある。ただ、高齢化の進行は、今後、発生しうるリスク問題としては存在しており、対応を考えていかねばならない。
Posted by