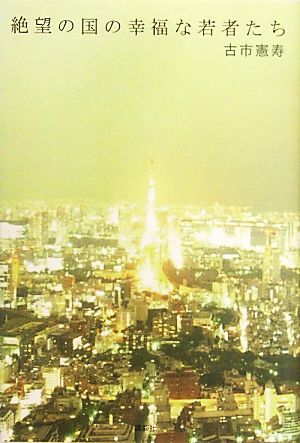絶望の国の幸福な若者たち の商品レビュー
図書館より 『だから日本はズレている』の古市さんの著作で『だから日本はズレている』内で言われていたキーワードもいくつか見られます。 面白かったのは第一章の「若者」がいつのころから社会的な概念として誕生し、そしてどのようにその立ち位置を変えてきたか、ということ。ビックリする...
図書館より 『だから日本はズレている』の古市さんの著作で『だから日本はズレている』内で言われていたキーワードもいくつか見られます。 面白かったのは第一章の「若者」がいつのころから社会的な概念として誕生し、そしてどのようにその立ち位置を変えてきたか、ということ。ビックリするほど昔の大人たちと今の若者批判が似通っていて思わず笑ってしまいそうでした。今も昔も大人たちは若者に対し、ある種の似たような期待をし続け、そして裏切られ続けているのですね。 そうした若者論といっしょにこの本内で語られるのは、日本という国家のことです。成熟し先進国の一員となった日本の限界もこの本では語られているように思います。共通の倒すべき敵を失い、叶えるべき大きな目標がなくてもインフラの充実で生きていける、そうなると自分の身の回りのことを充実させ満足するしかない。国家としては完成形の様な気もしますが、それが絶望の国の正体だと言われるとなんだか複雑な気持ちになります。 著者は最後に一人一人が生きられるなら日本が終わってしまってもいい、と書いています。ただそれは日本というインフラを過小評価しているような、また日本というインフラなんかなくても生きていける、と自分たちを過剰評価しているような気もします。 ただ自分が臆病なだけかもしれませんが、自分も含めた1億人以上の人が日本というインフラを頼って生きている以上、絶望の国に簡単に絶望できない気がします。かといって何か行動ができるかと言うと、その手段は非常に限られているわけで結局は徐々に沈んでいく日本を見ていることしかできないような気もしますが…
Posted by
数年前に話題になった本。著者が現役の東大院生という若さ故に話題になった、ともいえる。 この本の主題ではないが、マスメディアやSNSから受けとる情報を「印象」や「感覚」で理解していくことの危うさを考えさせられる。様々な機関、政府や民間の、が行う調査などをきちんと読み込んで正しく理...
数年前に話題になった本。著者が現役の東大院生という若さ故に話題になった、ともいえる。 この本の主題ではないが、マスメディアやSNSから受けとる情報を「印象」や「感覚」で理解していくことの危うさを考えさせられる。様々な機関、政府や民間の、が行う調査などをきちんと読み込んで正しく理解していくこと、その「時事」をもとに議論を展開していくリテラシーが、玉石混交の情報が溢れ還っている現代においては重要だということを改めて認識させられた。そういう意味で、この本が若い読者にたくさん読まれたということはよかったということが言える。 この認識、事実から発しない議論や政策は見当違いの結論を持ってしまうということであろう。
Posted by
書かれていることが特に目新しいとは思わないけれど、いわゆる「世代論」自体が現在の日本にあってはほとんど無価値であること、特に「ワカモノ」というくくりが非常に曖昧であり、増してやその動向が社会に対して与える影響云々を心配する上位世代の言動がいかにも空虚であること、などをわかるために...
書かれていることが特に目新しいとは思わないけれど、いわゆる「世代論」自体が現在の日本にあってはほとんど無価値であること、特に「ワカモノ」というくくりが非常に曖昧であり、増してやその動向が社会に対して与える影響云々を心配する上位世代の言動がいかにも空虚であること、などをわかるためにはとてもよくまとまったものだと思う。ポスト団塊でプレ2ndベビーブーマーというハンパな世代に属する身分としては、どれも「外から」の視線で見ることができるので、親近感を持てる内容だった。
Posted by
どこのなく冷めた感じで社会を俯瞰しているような文で個人的にはすごく読みやすかった。 若者の幸福度が高いという事実は新しい発見であったし、その理由も腑に落ちるものでありそこそこ満足。 日本が絶望の国であることは、いろいろな人が言っていることであり、ほぼ確定。現在そこそこ幸せである...
どこのなく冷めた感じで社会を俯瞰しているような文で個人的にはすごく読みやすかった。 若者の幸福度が高いという事実は新しい発見であったし、その理由も腑に落ちるものでありそこそこ満足。 日本が絶望の国であることは、いろいろな人が言っていることであり、ほぼ確定。現在そこそこ幸せである若者がもっと具体的な形で絶望の当事者になった時どうなるんだろう・・・と考えてみたり。 #例えば、被災地へボランティアに行く様な慈愛あふれる?人が、災害の当事者になったらどんな行動をとるんだろうとか。
Posted by
年取ってくると、ステレオタイプでものを見ちゃうので、こういう目線て、とても大事だと思う。 新鮮味はさほどなかったけれど、府に落ちることが多く、大変おもしろかったです。
Posted by
若い世代の著者が書いている本で、著者が時代に対する感覚が自分が思っているところと近く共感できた。確かに、将来のことを思うと気が重くなるのだが、今の暮らしが不幸かというと必ずしもそうとは言えない。結局、その時代で生きるためのものさしが変わるのだから、画一的な思考に縛られない方がしな...
若い世代の著者が書いている本で、著者が時代に対する感覚が自分が思っているところと近く共感できた。確かに、将来のことを思うと気が重くなるのだが、今の暮らしが不幸かというと必ずしもそうとは言えない。結局、その時代で生きるためのものさしが変わるのだから、画一的な思考に縛られない方がしなやかに生きていけると思った。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
若者の立場から、若者論を総括するような本。「若者」論の原型は90年代には、ほぼ出尽くしたという指摘はなるほどなと感じます。 現況として、世代間の断絶が無くなり「総若者化」しているという指摘は示唆的な気がします。 まじめな本ではあるのですが、著者の注釈が、ブラックユーモアたっぷりで面白い。ここが低評価な人は全体の評価も低いかな、という気がします。
Posted by
内容紹介 「今、ここ」が幸せであればいい――。 W杯の深夜、渋谷で騒ぐ若者たち。ネット右翼の主催するデモに集まる若者たち。そして震災を前に、ボランティアや募金に立ち上がる若者たち。 すべての現場に入り調査を重ねた末に見えてくるものは? 最注目の若き社会学者が満を持して立ち上げる、...
内容紹介 「今、ここ」が幸せであればいい――。 W杯の深夜、渋谷で騒ぐ若者たち。ネット右翼の主催するデモに集まる若者たち。そして震災を前に、ボランティアや募金に立ち上がる若者たち。 すべての現場に入り調査を重ねた末に見えてくるものは? 最注目の若き社会学者が満を持して立ち上げる、まったく新しい「若者論」! 三年前ほどに刊行された本書も、いま読み直してもまったく違和感がないということは総じてきっと世間に劇的な変化というものはないことの証明なんだろう。 統計学的な観点で「若者論」真相にせまっている。普段、何となしに社会に感じている疑問や不満や不安や不信。それをまるで代弁してくれているのが本書だ。 東京の夜景に、ひっそりと浮かび上がった東京タワーがなんだかさびしい。 浅野いにお「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」
Posted by
おもしろかったー。古市さんの真髄はこのおちょくってる感にあるよね。ばかにしとんのか、と。この距離感というか、自分すら嘲笑の対象にする感じ、すごい今の若者っぽくてツボ。でも、古市さんてすんげー本読んでて頭いんだなーって遠い存在に思う一方、こんなエッセイみたいな、卒論みたいな本で食え...
おもしろかったー。古市さんの真髄はこのおちょくってる感にあるよね。ばかにしとんのか、と。この距離感というか、自分すら嘲笑の対象にする感じ、すごい今の若者っぽくてツボ。でも、古市さんてすんげー本読んでて頭いんだなーって遠い存在に思う一方、こんなエッセイみたいな、卒論みたいな本で食えるってだいぶ身近に思えて羨ましくなる。 めも 「世代」で人を分類することが近代。それまでは「位」だった。 戦争になったらお国のために死ねる日本人は諸外国にくらべ少ない。
Posted by
「最近の若者はけしからん!」「じじいうるせー!」を統計データと『若者』という定義の曖昧さからの考察で、明快に説明されている。物知り顔に話す専門家をたっぷりの皮肉を込めて批判しているのも痛快。でも、テレビで物知り顔に話す評論家は、この程度にしか認識されていないことを知った方がいいと...
「最近の若者はけしからん!」「じじいうるせー!」を統計データと『若者』という定義の曖昧さからの考察で、明快に説明されている。物知り顔に話す専門家をたっぷりの皮肉を込めて批判しているのも痛快。でも、テレビで物知り顔に話す評論家は、この程度にしか認識されていないことを知った方がいいと思う。そしてそれが実際の未来のための政治につながっていかないのがすごく残念だけども。
Posted by