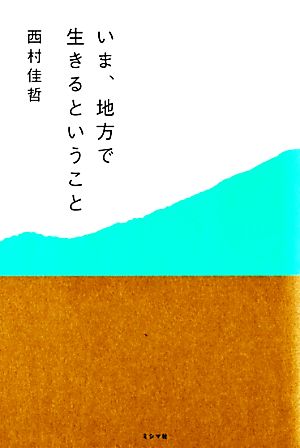いま、地方で生きるということ の商品レビュー
ある意味で非常に正直なタイトル。「地方で生きるとはどういうことか」について、著者が東北と九州で出会った人にインタビューをし、その内容をまとめた「だけ」の、シンプルな作りです。 著者自身が断わりを入れているとおり、この本を通じて著者なりの「地方で生きる」ことへの見解を提示しようと...
ある意味で非常に正直なタイトル。「地方で生きるとはどういうことか」について、著者が東北と九州で出会った人にインタビューをし、その内容をまとめた「だけ」の、シンプルな作りです。 著者自身が断わりを入れているとおり、この本を通じて著者なりの「地方で生きる」ことへの見解を提示しようとか、何かしらの動きを起こすような議論を展開しようとか、そういう試みがなされているわけではありません。あくまで、インタビューを受けたそれぞれの人が考える「地方で生きること」をありのままに示し、その上で、さあこれを読んだあなたにとって「地方で生きる」こととはどういうことですか?という問いかけをするに留まっています。 その点で、何かしらのクリアな「解」を求める人には不向きかも知れません。一方で、自分なりに「解」を考えるためのヒントが欲しいという方には適しているかも。 読み手の本への態度と求めるレベル・内容によって、評価が大きく分かれるのではないでしょうか。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
住む場所について、自分の仕事や役割について、 つまり、生き方について。 この本に登場するたくさんの若い方が、 それぞれの領域で、様々な活動を通じて、自分の生き方について感じていることを語っていらっしゃいます。 話者の皆さんが「都市部より地方じゃなきゃだめだ」ではなく、 むしろ「都市も地方も関係ない」と考えていらっしゃるのだということが、 力強い言葉を通じて、感じられました。 わたしが地方/都市という議論をするとき、聞くときに感じる もやもやを、うまく切り出してくれる本だった思います。 人口面や財政面で両者の区分が定義されるからなんでしょうか、 これまで、地方だ都市だというときに、変な卑屈さ?コンプレックス?をそれぞれに感じてしまっておりました。 都市部について語られる時、画一的な面ばかり強調されるけれど、 そもそも都市部にも、その地域性や独自性が多分に備えられているし、 そこに住む人同士の交わりだって、地方のそれと性質が違っているだけで、確実に存在すると思います。 また地方部は、果たして都市部と比べたときに「劣っている」のか。 なにを比べるべきか。どういう状態を目指すべきか。目標とするパラメータや値の大きさは都市のそれでよいのか。 わからないことではありますが、 性質が違うもの同士を、 同じ物差しですべて測ろうとするから、違和感があったのでしょうか。 物差しを一つにするのは、学問の一手段でしかないわけですが。 新しい動きと考え方に期待を感じます。とともに、自分の生き方も改めて見直したい。 読んでいるうちに、背筋が伸び、呼吸が楽になり、頭が柔らかくなる本。
Posted by
「仕方がないな」というかんじで作り始めている、この本にたいするスタンスがやや興ざめ。だけど、京都のカフェのこととか、震災のあとのことがわかって、いろいろとすごい。もっと聞き出せるような気もする。彼らの今後に期待。
Posted by
地方ならでは良さがあります。都会にこだわらなくても地方だからこそ、活かせる自分の働き方あります。本のタイトルはインパクトがあり好きです。内容も地方で活躍する方々にスポットライトをあて話を伺えるのでいいです。地方で働いている人やこれから働きたいと思っている人にはオススメです。
Posted by
タイトルのインパクトはあるけれど、何かパシっと答えが出てるような内容ではなかった。(し、そんなものを求めること自体が違いますね) 西村さんの本はいつも勇気とか活力みたいなものを与えてもらっていて、「働く為の本」とか読まない不勉強な私が唯一読む本です。 今も中堅都市で働いてはいる...
タイトルのインパクトはあるけれど、何かパシっと答えが出てるような内容ではなかった。(し、そんなものを求めること自体が違いますね) 西村さんの本はいつも勇気とか活力みたいなものを与えてもらっていて、「働く為の本」とか読まない不勉強な私が唯一読む本です。 今も中堅都市で働いてはいるけれど、なんとなく地方で生活することに後ろ暗さやコンプレックスみたいなものをずっと抱いていたんだな、とこの本を通じで感じました。 どこに軸足を持って何をするかを考えるきっかけになりました。
Posted by
仕事とは、住むとは何かを考えさせられた。地方だから遅れてるとか、何もないという旧態依然の考えから脱却し、自ら考えて地方で生きる人たちを本書を通じて垣間見ることが出来た。今後の人生の歩みを考える上で、非常に参考になったし、参考にしたいと強く思った。
Posted by
地方に生きる、というテーマの本書は、震災直後の東北を巡るというかなり極端な状況の土地からインタビューがスタートする。 ”「いつここを去ってもだいじょうぶ」という状態にならなきゃいけない” "「幸せになりたい」というアイデアを手放しさえすれば、どこでも十分に生きてゆける...
地方に生きる、というテーマの本書は、震災直後の東北を巡るというかなり極端な状況の土地からインタビューがスタートする。 ”「いつここを去ってもだいじょうぶ」という状態にならなきゃいけない” "「幸せになりたい」というアイデアを手放しさえすれば、どこでも十分に生きてゆけるんじゃないか。むしろそのアイデアによってがんじがらめに不自由になっているんじゃないかな。" ”「なにもなくても生きていけるぜ」っていう、生きる力っていうのかな、それをすごく持っている人がたくさんいて。” ハッとする言葉が並ぶ。 とても良い本だ。 しかし、前半のインタビューは、震災のボランティアでの視点というので偏りを生んでいるような気がする。 中には震災の支援をしている自分の行動に満足している、危機的状況の身を置く事で日常での満たされない感じを補填していはしないか、という感じの人もいるような気がする。 なので星3つ。 特殊な状況ではなく、もっと普段の地方の生活に根ざした人の生活感がわかるような内容を期待していたら、後半は秋田に移って地域コミュニティにデザインでもって丁寧に暮らす人達のインタビュー。 "何もないからつまらないんじゃなくて、(都会と)同じようになろうとしていたことがつまらなかったっていうことですか" もズバリとした言葉だ。 百杯会のエピソードは面白い。すごく身近なムーブメント。 その身近さは九州の田北氏のインタビューにもある。将来こうなりたいというものがなく、すっと入って仕事をしていく田北氏の姿勢。 鹿児島のしょうぶ学園の障害者の作るものを森に例えての描写は視点の転換をもたらす。 ”望ましさに応えるために頑張るのではなく、本人が本人と応答するようなあり方。生きている自分への責任を全うすること。” うん、面白くなってきた。 最後の星川氏へのインタビューは少しスピリチュアルなきらいが強い。 いい本だ。 星4つ。
Posted by
ちょっとここ最近気になっていたテーマのこと。外から溶け込むには専門性を持たない、地域の人が望むことを探すことの大事さ。あまりにもの自然礼賛が鼻につくかなと思ったものの、東京vs地方の構図ではなくなってきてることを改めて感じたりしますねと。 お金が要る重力の違いなだけかなと。
Posted by
被災地で活動をしている方々への震災直後のインタビューと、九州でその土地に生きている方々へのインタビューとをまとめた本。 タイトルは非常に魅力的です、タイトルは。 よい問いかけがたくさんあるんですが、思っていたのとはちょっと違う、残念。 東京にしがみつかなきゃいけない理由なんて...
被災地で活動をしている方々への震災直後のインタビューと、九州でその土地に生きている方々へのインタビューとをまとめた本。 タイトルは非常に魅力的です、タイトルは。 よい問いかけがたくさんあるんですが、思っていたのとはちょっと違う、残念。 東京にしがみつかなきゃいけない理由なんてひとつも無いんですけどね、3年後の姿を全くイメージできない私には重い一冊でした。
Posted by
仕事のこと、働くということを考え、ここでなければいけないのか?と思っていたときに、本屋で目があった本。さらにこれもって旅行行ったら、入ったお店にこの本と著者のセミナーのチラシがあって、なんかもうこれは呼ばれているとしか、とセミナーにまで行ってしまいました。 これは、著者が東北と...
仕事のこと、働くということを考え、ここでなければいけないのか?と思っていたときに、本屋で目があった本。さらにこれもって旅行行ったら、入ったお店にこの本と著者のセミナーのチラシがあって、なんかもうこれは呼ばれているとしか、とセミナーにまで行ってしまいました。 これは、著者が東北と九州を巡って、気になっている「その土地で生きる」人の話をきいた記録です。直接のきっかけは震災だけれど、その前から「働いて、生きてゆくこと」と「場所」の関係について考えていた(そして東京以外に拠点を持とうとしていた)著者が、「地方で生きるということ」と「どこで生きる?」という著者自身のわからなさを検証しようとして出た旅。 1日の大半を費やす仕事、残りの時間を過ごす部屋、それをとりまく環境。なにをして働き、どこで暮らすか、ってものすごく自分の生活に(あたりまえだけど)影響するよなぁ…と考えていた私にとっては、ぴったりすぎる本でした。いちばん始めが、RQ(市民災害救援センター)だったというのも読みたかった理由のひとつ。あとは、版元がミシマ社だったというのも。(ミシマ社も、震災後は東京と京都と2拠点にしていたそう。) 「生きてゆくためにお金が要る度合い」を示す重力分布図の話はなるほどそうだよなと思い、なんだろう?と思っていたパーマカルチャーのこともさらりと触れられていて、色々繋がった感のある1冊でした。「『四国らしさ』ってなんだろう?ノート」、読まなくちゃ。「地方」って、「東京」のローカライズじゃない、たしかに。
Posted by