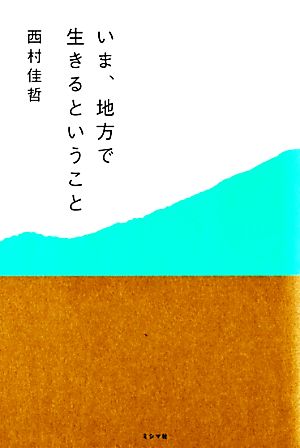いま、地方で生きるということ の商品レビュー
http://tacbook.hatenablog.com/entry/2016/05/03/222711
Posted by
20160417 今、何処で生きるか。これまでとは違う価値観で決めてよいのだという事。年寄りは年寄りの考えで決めればよいのだと思うが若い人に関しては他人を気にしないで自分の価値観を大事に出来るかがポイントかも。
Posted by
地方で生きることを選択した人の生活が、たんたんと綴られている。たんたんとしすぎて、ぼんやり読んでいるとスルリと通り過ぎてしまうぐらい。でも、生きるってそういうことなのかもなあとも思う。自分なりの思いは根底にありながら、日々は日常として過ぎ行く。 鹿児島県にあるしょうぶ学園の取り...
地方で生きることを選択した人の生活が、たんたんと綴られている。たんたんとしすぎて、ぼんやり読んでいるとスルリと通り過ぎてしまうぐらい。でも、生きるってそういうことなのかもなあとも思う。自分なりの思いは根底にありながら、日々は日常として過ぎ行く。 鹿児島県にあるしょうぶ学園の取り組みが面白かった。 鹿児島市の住宅地にある障碍者支援センター 「nuiプロジェクト」の一環。 以下引用抜粋。 従来の授産施設の在り方だと、たとえ作業内容は簡単でも、障害者はいわばファクトリーの工員として機能することを求められる。スタッフには管理者の働きが求められる。 でも、しょうぶ学園では、障害者は“森”や“山”のような自然界で、スタッフはそこに入ってきのこや山菜を採るような関係。 望ましさに応えるために頑張るのではなく、本人が本人と応答するようなあり方。生きている自分への責任を全うすること。 p.227
Posted by
何かを強硬に主張しようとするような構成でも文体でもないのが良い。それでいて、地域とかまちづくりとかについて、深いんだけど広い、色々な「ピンとくる」エッセンスがある。 まちに「誇り」をもつようにするのが良い。――使い古されたようなスローガンでもあるけれど、それでも、力を込めて改め...
何かを強硬に主張しようとするような構成でも文体でもないのが良い。それでいて、地域とかまちづくりとかについて、深いんだけど広い、色々な「ピンとくる」エッセンスがある。 まちに「誇り」をもつようにするのが良い。――使い古されたようなスローガンでもあるけれど、それでも、力を込めて改めて語っていると良いものだ。 また、地域開発のコンサルとかみたいに「仕事で」仕事をするのでなく、まず「住む」ということが何よりもまちづくりの一歩だと共感。住む(なり、通うなりする)ことで、そこの地域で段々、見えなかったものが見えるようになるということ(例えば、人とのつながりができ、ギブ&テイクができるといったこと)こそが、いかに力強く、大切で、本質的かと思う。再認識することが多かった一冊。
Posted by
インタビュー書下ろし形式。答えや結論は用意されておらず、それぞれの人が語ったことがつづられている。 全体を通して震災後の生き方。 被災地支援、ではない関わり方がたくさん。 これからの暮らし方のヒントになりそうな言葉があちこちに。どこにいても。
Posted by
何人かの田舎で生活している人を紹介。インタビュー形式も多い。 皆、自分をしっかりもっていて熱い人が多く、参考になった。 仕事は作るもの…かぁ。田舎は就職先が無いとグチってしまいがちですが、考え方を変えなくてはいけませんね(^^;;
Posted by
http://www.mishimasha.com/books/chihou.htm , http://www.livingworld.net/
Posted by
帰りの電車のなかで、西村佳哲『いま、地方で生きるということ』ミシマ社、読了。『自分の仕事をつくる』(ちくま文庫)で、働くことや生きることを考察してきた著者が東日本大震災後の東北や九州を巡り、地方で生(働)きることを考えた本。酷評が多いけれど、僕自身は面白く読んだ。初のミシマ本。 ...
帰りの電車のなかで、西村佳哲『いま、地方で生きるということ』ミシマ社、読了。『自分の仕事をつくる』(ちくま文庫)で、働くことや生きることを考察してきた著者が東日本大震災後の東北や九州を巡り、地方で生(働)きることを考えた本。酷評が多いけれど、僕自身は面白く読んだ。初のミシマ本。 内容はインタビューが中心。そしてこの本にその答えはない。(言い方は悪いけれども)「田舎の実像はそんなんじゃねえよ」と迷羅馬風イチャンを付けようとすればきりがない。しかし、筆者の聞き書きは、日本の田舎の挑戦の〝今〟をレポートしている。 自然学校の広瀬さんの言葉が印象的。「多くの人が『田舎には仕事がない』と言うけれどそんなことはないんだ、と話していた。それは勤め先がない、つまりいわゆる会社のような求人口がないだけの話で、人手が足りなくてできずにいる仕事は山ほどあるんだと」。 僕も18まで田舎で生活していたから理解できるけれども、まさに田舎には〝勤め先〟としての〝仕事〟は少ないし、勤め先の「肩書き」がないと都会以上にとやかくいわれる社会(日本的精神風土含めて)。しかしながら、人手が足りないのも実情。そこにどう挑戦するか。 権力や手抜きの就業行政に〝ていよく〟利用されることや、すり替えられた自己責任を金科玉条の如く奉ることは毛頭不要だけれども、日本の田舎での挑戦ははじまっていると思う。だからこそ、東京への一極集中へシフトがもう一度きられたことは、ものすごく逆風になってしまう。そこがねえ……、。 ムック本的な「いまこそ、地方で農業☆」には、記事自体が、都市で生成された勝ち組-負け組の枠組みに準拠しているから、正直、反吐が出る。しかし、東京に20年近くすんで理解できるものでもあるけど「生きてゆくためにお金が要る度合い」は、都市に近づくほど強く、遠ざかるほど弱いのは事実。 田舎の「しがらみ」自体は爆発しろなんだけど、脱サラしたらどうにかるなるべみたいな甘っちょろい幻想でもなく、「働く」ということが「生きる」ということとどう連動しているのかをもう一度、省察しながら、自身が働いていることや、その土地で生きていることを検討するきっかけにはなった感。
Posted by
東日本大震災後の日本を巡り、 震災後の日本で生きる事について述べています。印象的な文章が多数あります。
Posted by
地元で生きてゆこうと決めて、東京から帰ってきたその春に出会った本。故郷て生きていくうえで、なんとなくだけどヒントをもらえた気がする。
Posted by