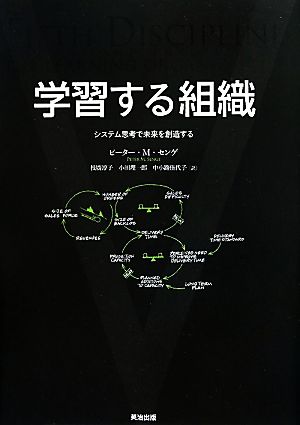学習する組織 の商品レビュー
今までの人生で五本指に入るほど読了まで時間かかった。しかも理解しきれてない。 時間あるときにじっくり読み直します。
Posted by
これまためちゃめちゃ名著。自分の中では7つの習慣超えたかもというくらいのインパクト。何度も繰り返し読んで実践、試行錯誤するのみ。
Posted by
世間に溢れているビジネス書とは一線を画す本 経営ノウハウというよりは、システム思考という新しい思考法を重心として、経営課題のみならず世界中のありとあらゆる課題へ対処するための根源的な思考法を提供してくれる。 実戦には時間がかかるし、会社でトライした時にも難しさを痛感したものではあ...
世間に溢れているビジネス書とは一線を画す本 経営ノウハウというよりは、システム思考という新しい思考法を重心として、経営課題のみならず世界中のありとあらゆる課題へ対処するための根源的な思考法を提供してくれる。 実戦には時間がかかるし、会社でトライした時にも難しさを痛感したものではあるが、今求められるスキルの一つであると確信
Posted by
長い!やっと読み切った! システム思考、自己マスタリー、メンタル・ モデル、共有ビジョン、チーム学習の5つの原則・ディシプリンについて丁寧に解説される。システム思考が本社の核のため、全く知らない人は先に予習しておくと読みやすいかもしれない。簡潔に書かれている「実践 システム・シ...
長い!やっと読み切った! システム思考、自己マスタリー、メンタル・ モデル、共有ビジョン、チーム学習の5つの原則・ディシプリンについて丁寧に解説される。システム思考が本社の核のため、全く知らない人は先に予習しておくと読みやすいかもしれない。簡潔に書かれている「実践 システム・シンキング」を先に読んでおくのが個人的にはオススメ。 後半にあたる12章以降は実践編であり、前半に比べれば多少流し読みできるだろう。前半の考え方についての世の中での適用例と言って良い。旧版を発行して以降の取り組みが書かれていて参考になる。特に2011年の段階で持続可能性についてここまで取り上げていることには尊敬するように思う。 しかし長いな…もう少し簡潔になる気はするが…
Posted by
経営においてディシプリンがどう繋がっているかよく整理されている。 以下、印象的なフレーズ ・学習する組織は「いかに私たちの行動が私たちの現実を生み出すか、そして私たちはいかにそれを変えられるか」ということを人々が継続的に発見し続ける場である。 ・ビジョンは具体的な目的地、望まし...
経営においてディシプリンがどう繋がっているかよく整理されている。 以下、印象的なフレーズ ・学習する組織は「いかに私たちの行動が私たちの現実を生み出すか、そして私たちはいかにそれを変えられるか」ということを人々が継続的に発見し続ける場である。 ・ビジョンは具体的な目的地、望ましい未来像である。目的は抽象的で、ビジョンは具体的なものだ。 ・失敗とは、単なる不足、ビジョンと今の現実の間に乖離があることを示すものにすぎない。失敗は学びのチャンスでもある。 ・否定的ビジョンの根底にあるのは恐怖の力である。肯定的ビジョンを動かすのは大志の力である。恐怖は短期的に驚くべき変化を生み出すこともあるが、大志は学習と成長の絶えざる源泉として持続する。
Posted by
心理的安全性、パーパスなど、2022年で注目されている言葉は、1990年に書かれたこの本に体系的に書かれている。 この本が、最も整理された現代の組織論のようにも思う。
Posted by
課題を目先のことと捉えず、システム全体から解決しようとするアプローチが実に示唆に富む。「最強組織の法則」とは全く違う本を読んだ印象を持った。(本間)
Posted by
本書の前提となる5つのディシプリンのうち、志の育成とされる自己マスタリーと共有ビジョンは今日的にはキャリア自律として扱われる領域で、パーパスマネジメントの考えと概念が近い。日本の組織、働く人にジワジワと浸透している。 内省的会話の展開とされるメンタル・モデルとダイアログも1on...
本書の前提となる5つのディシプリンのうち、志の育成とされる自己マスタリーと共有ビジョンは今日的にはキャリア自律として扱われる領域で、パーパスマネジメントの考えと概念が近い。日本の組織、働く人にジワジワと浸透している。 内省的会話の展開とされるメンタル・モデルとダイアログも1on1やキャリアコンサルティングとして試みが導入されている。 以上の四つは、個人への働きかけによってある程度達成可能な課題に見受けられる。 問題は最後のシステム思考、複雑性の理解であろう。組織的課題は遅行軸であることがこのディシプリンが抱える最大の難しさで、より上位の経営者やリーダーが理解し戦術的に組織や業務に組み込むことができなければ、その浸透は達成し得ない。日本人が苦手な領域でもあり、身近で聞かれるような事業の失敗の典型例のようなケースが本書でも説明される。組織はどのようなアプローチでこの問題を解決し得るだろうか。
Posted by
組織が学ぶ為の必要な要素を展開している。自身もシステムの一部である事を認識することで、働きかけができる。その為に組織もまた個人も必要な考え方を持つ必要がある。 内容が濃く、一読での消化は難しい。途中挫折をするも読み終えた。また時を見て学習したい。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
「学習する組織」とは、持続可能性を導く、まさにイノベーションそのもののことである。この組織を創るには、共有ビジョンの構築とチーム学習が必要と説く。 これについては、以下少し説明を追記する。 持続可能性のある組織について、「目的を達成する能力を効率的に伸ばし続ける組織」とも言い換えられる。 共有ビジョンとは、外発的なものでも内発的なものでもいいのだが、外発的なものの場合、競合と比較したときに、何かを達成することに主眼をおいたほうがいい。 チーム学習について、個々の学習の総和であり、チーム学習が組織の学習につながるということである。 タメになったのはビジョン。 「人類の宇宙探索の能力を進歩させる」は目的で、目的は方角や進行方向を示すもの。「1960年代末までに、人類を月面に立たせる」はビジョンで、目的地や望ましい未来像を示したもの。 多くの企業が、ビジョンを正しく定義出ていないような気がする。できれば、ビジョンを聞いて、光景が見えるといいんだろうな。 次に面白かったのは、環境。 より有意義でやりがいのある職場環境を作ることで、業績は改善するそう。この有意義さは、共通のビジョンが必要なのだが、やる気にさせる唯一のビジョンはあなた自身のビジョンであるという点から、個々のビジョンのすり合わせの結果、共通のビジョンを作るというプロセスがよさそう。ま、協力してできると、単独でやるよりはるかに大きな成果ができるので、こうしたプロセスを経て、協力する関係が作れるといいなと思う。稲盛さんの言葉も出てくるけど、まず組織は物心両面の幸福を従業員に与えられるようにし、本当にしたいことに全力をそそげるようにすることが大切なのかなと思う。これが会社の責任だとして、個々の責任はというと学習をし続けること。学習がリーダーシップの源泉であり、持続可能性の源泉であるので、学習こそが義務であり、チームや組織とすり合わせをすることが求められているのだと思う。
Posted by