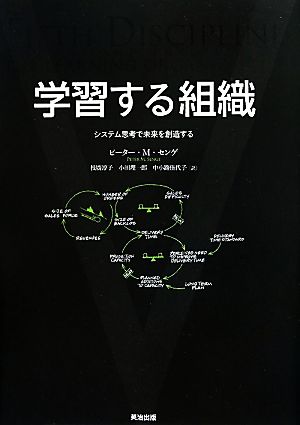学習する組織 の商品レビュー
課題を目先のことと捉えず、システム全体から解決しようとするアプローチが実に示唆に富む。「最強組織の法則」とは全く違う本を読んだ印象を持った。
Posted by
申し訳ありません。あまり新しさを感じませんでした。本書でいう共有ビジョンはドラッカーが、自己マスタリー、ダイアログ、メンタルモデルはコビィ(『7つの習慣』)が主張していたと感じました。あとはシステム思考ですが、これは「木も見て森をみよう」という言葉で凝縮されており、「うん、そうだ...
申し訳ありません。あまり新しさを感じませんでした。本書でいう共有ビジョンはドラッカーが、自己マスタリー、ダイアログ、メンタルモデルはコビィ(『7つの習慣』)が主張していたと感じました。あとはシステム思考ですが、これは「木も見て森をみよう」という言葉で凝縮されており、「うん、そうだよね」と感じてしまいました。ですが、個々の事例などはとても面白かったです。
Posted by
トップダウン型の組織、業務が完全に分担され人間が機械の歯車のようになっている組織、、 AIが発達し、人間にクリエイティブさが求められる社会で、組織の新しい在り方が書かれた本。 学習する組織に重要な5つのディシプリンとして、 メンタルモデル チーム学習 自己マスタリー 共有ビジョ...
トップダウン型の組織、業務が完全に分担され人間が機械の歯車のようになっている組織、、 AIが発達し、人間にクリエイティブさが求められる社会で、組織の新しい在り方が書かれた本。 学習する組織に重要な5つのディシプリンとして、 メンタルモデル チーム学習 自己マスタリー 共有ビジョン システム思考 が挙げられる。 学習する組織としてあるためのプロセスであり、要素であり、行動目標とも言えるのではないだろうか。
Posted by
時間をかけて唸りながら読みました。良書。 いかに学習する組織の少ないことか。。。 そして自分の組織は学習する組織でありたいと思う。 以下、フレーズの抜粋。 ・問題はどんなビジョンかではない。ビジョンで何をするかだ ・人は変化に抵抗するのではない。変化させられることに抵抗する...
時間をかけて唸りながら読みました。良書。 いかに学習する組織の少ないことか。。。 そして自分の組織は学習する組織でありたいと思う。 以下、フレーズの抜粋。 ・問題はどんなビジョンかではない。ビジョンで何をするかだ ・人は変化に抵抗するのではない。変化させられることに抵抗するのだ ・組織を設計することは理性の力を超える ・私たちはより賢く働く代わりに、単にがむしゃらに働いていた ・私たちは昔から上司への報告を書くのはお手の物だが 自分の経験から学ぶことは必ずしも得意ではない ・上司を相手にするときは「約束は控えめに結果は期待以上に」 ・過去の戦略や経営上の変更、リーダーシップのアプローチにおいて 何が成功し、何が失敗したかを調査することに 自分たちの組織がほとんど資源を投資していないことは まさに職務怠慢と言ってよい
Posted by
本の題名にあるように企業の組織がより発展し持続した繁栄を維持するためには組織の成員その組織に所属する全ての人々がおのずから学べる体制、学び分析し検証でき、それを改善に繋げられるシステムになっていなければならないとする理論である。そのためにはどのような組織体系を作ることが良いのか...
本の題名にあるように企業の組織がより発展し持続した繁栄を維持するためには組織の成員その組織に所属する全ての人々がおのずから学べる体制、学び分析し検証でき、それを改善に繋げられるシステムになっていなければならないとする理論である。そのためにはどのような組織体系を作ることが良いのかと言うことをいろいろな例題を下に記載しているが非常に読み応えがあり何回か読まなければなかなか理解しづらい本でもある。 自ずから努力して学ぶ組織ではなく、組織のシステムとして、進化、変容、改善を遂げていけるシステムとは、どのようなものかと言うことであり、非常に参考になる。
Posted by
5つのディシプリン 1. システム思考 2. 自己マスタリー 3. メンタル・モデル 4. 共有ビジョン 5. チーム学習 戦略 ・学習と仕事を一体化させる ・そこにいる人たちとともに,自分のいる場所から始める ・2つの文化を併せ持つ ・練習の場を創る ・ビジネスの中核とつなげ...
5つのディシプリン 1. システム思考 2. 自己マスタリー 3. メンタル・モデル 4. 共有ビジョン 5. チーム学習 戦略 ・学習と仕事を一体化させる ・そこにいる人たちとともに,自分のいる場所から始める ・2つの文化を併せ持つ ・練習の場を創る ・ビジネスの中核とつなげる ・学習するコミュニティを構築する ・他者と協働する ・学習インフラを構築する
Posted by
経営の名著ということで購入。 複雑に構成される主張を一方向に流れる「文章」という体裁で解説しているため、論理と論旨を追うには行ったり来たりする必要があった。それはまるで本書で紹介されるシステム思考を彷彿とさせる。 内容は一言でいうと、「いかに自立した組織を創造するか」で...
経営の名著ということで購入。 複雑に構成される主張を一方向に流れる「文章」という体裁で解説しているため、論理と論旨を追うには行ったり来たりする必要があった。それはまるで本書で紹介されるシステム思考を彷彿とさせる。 内容は一言でいうと、「いかに自立した組織を創造するか」である。主張はすばらしく、途中で紹介されているように京セラのアメーバ経営のような組織をワークさせるのは本書のディシプリンを身に着けたメンバーのなせるわざなのだろう。 ここまで壮大になると「会社文化」の世界なので、大きな会社が後段適用することを考えるのは非現実的なように思えてしまう。中小の組織のうちに文化として根付かせることが肝要である。ベンチャー企業に関わりがある方、もしくはそれに匹敵するぐらい柔軟な組織構造をもつ会社の経営者なら活かせるかも。
Posted by
図書館から借りてきたが2週間で半分くらいしか読めず、タイムアップで返した本。 なにしろ580ページもある。内容的にも重厚な本で、読みながらいろいろ考えてしまうので、なかなか進まない。それだけ読み応えがあるのだが、逆に言えば盛りだくさんで消化不良になる。要約を書こうと思っても、全...
図書館から借りてきたが2週間で半分くらいしか読めず、タイムアップで返した本。 なにしろ580ページもある。内容的にも重厚な本で、読みながらいろいろ考えてしまうので、なかなか進まない。それだけ読み応えがあるのだが、逆に言えば盛りだくさんで消化不良になる。要約を書こうと思っても、全体像が見通せない感じだ。 というわけで、以下は中途半端なメモ。 学習する組織には5つの要素技術がある。 1. システム思考 相互に依存する複雑なシステムの中にパターンを見出し、そのシステムを効果的に変えるための方法を見つけるための概念的枠組み。 2. 自己マスタリー 学習する組織の要。芸術家が作品に取り組むがごとく生涯を通じた学習に身を投じられるような心のあり方のこと。 3. メンタル・モデル メンタル・モデルとは私たちがどのように世界を理解し、どのように行動するかに影響を及ぼす深く染み込んだ前提や一般概念。メンタル・モデルに働きかけ、固定観念にとらわれずに新たな考えを受け入れられるようにすることが必要。 4. 共有ビジョン 人々が自らすすんでコミットするような共通の力強い未来像。 5. チーム学習 個人では得られない洞察をグループとして発見することができるような対話と思考。 こうして書き出してみると、ただのよくあるお題目のようだ。この本の厚さはこれがお題目ではなく中身を持ったものだということを納得させるための数多くの事例や、さまざまな角度からの洞察、方法論の説明に費やされている。 中でも出色なのはビールゲーム。最後には誰もが大量のビールの在庫を抱えてしまうこのゲームは、システムそのものが往々にして危機を引き起こすこと、その中では個人がどう考えどう動こうとも、結局は同じ結果を生み出してしまう傾向があることをくっきりと浮かび上がらせている。そして個人は構造の問題に気づくことはなく、限られた視野の中で他人に責任を転嫁する。
Posted by
年間で10冊まで読まないビジネス書。簡単にメモだけ。 ・「システム思考」がベース。 ・「1個人は全体に影響を及ぼすことはない」と考えない。 ・行動の結果は、ロールのビューから見えない、時間軸上でずれた所で意外な形で出ることが多い。 ・ボトム(全社員)の個々人のビジョンが企業のビジ...
年間で10冊まで読まないビジネス書。簡単にメモだけ。 ・「システム思考」がベース。 ・「1個人は全体に影響を及ぼすことはない」と考えない。 ・行動の結果は、ロールのビューから見えない、時間軸上でずれた所で意外な形で出ることが多い。 ・ボトム(全社員)の個々人のビジョンが企業のビジョンに結び付くと強い組織になる。 ・トップダウンのビジョンが共有(共感・同意)されることなど有り得ない! ・ビジョンを描くのには練習が必要。間違いを許容できる心理的安全の確保が必須前提。 ・全員が個人のビジョンを持つとは限らない。他人のビジョンへの相乗りも有り得る。 ・改善のつもりでも、負のループが作用している場合も。自身を分析し、思考に影響しているループ構成を描き出すと良い。
Posted by
【由来】 ・レジリエンス本かと思ったが、「読書ための全技術」だった(P249)。 【期待したもの】 ・ ※「それは何か」を意識する、つまり、とりあえずの速読用か、テーマに関連していて、何を掴みたいのか、などを明確にする習慣を身につける訓練。 【要約】 ・ 【ノート】 ・ ...
【由来】 ・レジリエンス本かと思ったが、「読書ための全技術」だった(P249)。 【期待したもの】 ・ ※「それは何か」を意識する、つまり、とりあえずの速読用か、テーマに関連していて、何を掴みたいのか、などを明確にする習慣を身につける訓練。 【要約】 ・ 【ノート】 ・ 【目次】
Posted by