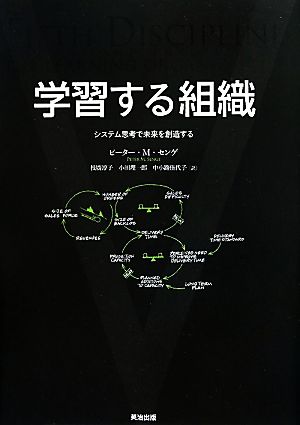学習する組織 の商品レビュー
「最強組織の法則」の改訂版。ということで当然ながら、ヘビー級かつ難解である。しかし、それでも本書を読む意味は、大きく、広く、深い。個の能力の総和より、はるかに大きな能力をもつチームを持ちたいと願うマネージャは多いだろう。しかし、こんな組織がその辺に転がっているわけでもなく、自分が...
「最強組織の法則」の改訂版。ということで当然ながら、ヘビー級かつ難解である。しかし、それでも本書を読む意味は、大きく、広く、深い。個の能力の総和より、はるかに大きな能力をもつチームを持ちたいと願うマネージャは多いだろう。しかし、こんな組織がその辺に転がっているわけでもなく、自分が今持っている組織を作りかえるしかない。だた、どうすればいいかわからない。やみくもに、ベスト・プラクティスを実行しても、しょせんそれはパッチワーク。チームの成長にはつながらない。本書は、このような状況(おそらく、ほとんどの組織はそうだと思う)から、いかに抜け出して、卓越した組織を作るかを、真正面から答えようとし、十分な成功を勝ち取っていると言える。真正面から、正論で臨むために、おそらくこれを実践する人間は、多くの軋轢になやみ、くじけることがあるかもしれないが、それでも、あなたがプロフェッショナルなら、やめてはならない。最強の組織を作ることが、あなたの使命なのだから。
Posted by
大企業のほとんどは、人間の寿命の半分も生きられない。なぜ組織運営は失敗するのか。その考察と対策。まず、フィードバックのプロセスを、自己強化型とバランス型に分けての説明。広告費を増やしていけば売上は増えていくが、対象顧客層にリーチしつくしたところで平衡する。研究開発費を増やしていけ...
大企業のほとんどは、人間の寿命の半分も生きられない。なぜ組織運営は失敗するのか。その考察と対策。まず、フィードバックのプロセスを、自己強化型とバランス型に分けての説明。広告費を増やしていけば売上は増えていくが、対象顧客層にリーチしつくしたところで平衡する。研究開発費を増やしていけば新商品の開発を進んでいくが、技術の限界、マネジメントの限界、設備の限界、すなわち組織の限界に到達したところで成長は止まり、平衡する。それならばと1人だけ現状維持を貫いたって、社会は進む。社会が進めば生活が変わる。生活が変われば、平衡は崩れる。それを破るのが、イノベーション。イノベーションは稀であり、さも"偉業"かのように語られるが、組織が存続し続けるには絶対に必要な条件なのだ。"偉業"がなければ存続できないというのであれば、会社の平均寿命が短いのも頷ける。よって、組織に必要とされるのは、限界が決定されている状況下での"成長"ではなく、限界の原因を見極め、対処し続けていく力を養う"学習"なのだ。 そして提示される5つのディシプリン。個人の成長、チームでの成長、既成概念の把握、共有ビジョン、全体指向。どれについても納得できるだけの構造が解説されているのだが、どうにも受け入れ難いところがある。どれも正論がすぎるのだ。確かに個人の成長には理想と現実の創造的緊張が必要だし、チームで成長するためには議論する"ディスカッション"でなく、協働するための"ダイアログ"が重要だろう。考えの妨げになっている既成概念を把握し、より広い視点で物事を捉える全体指向がなければ、その場しのぎでない根本解決は果たせない。…しかし、やる気がなければ何もできない。みんなが正論が正しいと分かっているのに従えないのは、やる気になれないのは何故だろうか。 『モチベーション』について勉強するやる気がでてきたので、次はこちらを勉強してみよう。
Posted by
内容が広く深く、一回読んだだけだと理解も覚束ない。再読しよう。でも、内容を理解すると間違いなく目の前で起きている事象について自身の捉え方が変わる。 端的には、目の前の事象を自身も含めた相互作用の構造として理解することの重要性を述べている。 その他にも色々と重要な気付きがある。が、...
内容が広く深く、一回読んだだけだと理解も覚束ない。再読しよう。でも、内容を理解すると間違いなく目の前で起きている事象について自身の捉え方が変わる。 端的には、目の前の事象を自身も含めた相互作用の構造として理解することの重要性を述べている。 その他にも色々と重要な気付きがある。が、実践で取り組まないと本当に理解できない部類の内容なので、まずはやってみよう。
Posted by
動的平衡文脈で、組織を構成要素ではなくシステムとしてとらえるという考え方に興味があって読んだ。 メモが大量になるほど面白かった。笑 ついつい、自分が中心とした世界をイメージしがちでそこにはバイアスが多く含まれる。自分の言動の結果が何にどう繋がるのか想像力が働く人、組織が理想。 ...
動的平衡文脈で、組織を構成要素ではなくシステムとしてとらえるという考え方に興味があって読んだ。 メモが大量になるほど面白かった。笑 ついつい、自分が中心とした世界をイメージしがちでそこにはバイアスが多く含まれる。自分の言動の結果が何にどう繋がるのか想像力が働く人、組織が理想。 • 個人の価値観や人生の方向性と組織のビジョンとを一つのシステムと捉えないといけない • ここでの学習は座学のことではなく、できなかったことができるようになるとかそれを通して世界の見方が変わるとかって類のもの • 最善の学習は経験を通じた学習だが、多くの場合大事な意思決定の結果は直接経験できないから「学習の視野」の範囲外になる • 構造が挙動に影響を与える →だから何をしてもむだなんじゃーじゃなくて自分の行動がシステムにどう影響を与えるのかをイメージすることが大事 • 影響のフィードバックを考えると、自分が中心ではなくなる • システムによって生み出される問題に対しては全員が責任を共有する • 個人というミクロから個人と組織、社会との繋がりのマクロまで想像力が働く人は頭いいと感じる • 論理的に正しい(ように見える)のに間違えるって状況があるのが面白いよね • 大企業の競争劣位の一つが指揮系統の長さによるシステムの影響の見えにくさ 成長の限界を招くのはバランス型ループの方にあると 意志力や否定的な感情に頼るのは長続きしないみたいな、現実的な考え方 望ましい結果そのものに焦点を当てるのは1つのスキル 世の中の見方(=メンタルモデル)に自覚的である必要がある 振り返りは基本的に、口で行ったことと行動との乖離からわかるメンタルモデルの自覚化 組織と自分のメンタルモデルの一致は大事よなあ 過度の一般化をしてしまっていることを自覚すると「こういうものだ」ではなく「自分はこう見てる」と言えるようになる 共有ビジョンは個人ビジョンと統合的である必要 追従とコミットメントはルールを変える力があるかという点で明確に違う 否定的なビジョンは短期的 人生の目的は息をすることではない 企業という集まりはなぜアマゾンの湿地のように振る舞えないのか 理念の言語化に時間をかける 「どんなビジョンかではなく、ビジョンが何を起こすかが問題」 知識がないことは、たくさんの疑問を持てるという意味で財産
Posted by
人はとかく、局所解に陥りがちである。 ある場面では是とされた行動であっても、視点を上げシステム全体から俯瞰してみると機能不全のボトルネックになっていることもある。 本書「学習する組織」では視野狭窄によるシステム破局事例を紹介しつつ、 「システム思考」で全体をあるべき姿にしていくた...
人はとかく、局所解に陥りがちである。 ある場面では是とされた行動であっても、視点を上げシステム全体から俯瞰してみると機能不全のボトルネックになっていることもある。 本書「学習する組織」では視野狭窄によるシステム破局事例を紹介しつつ、 「システム思考」で全体をあるべき姿にしていくためのディシプリンが語られる。 自己マスタリー、共有ビジョン、ふりかえり、リフレーミング… 後発のビジネス書で「断片」が語られるこれらの要素が一つのシステムとしての文脈で語られる。 ボリュームが大きく、決して平易な内容ではないため歯応えはあるが登る価値のある山脈。
Posted by
学習するする組織構築のための基本概念が書かれた本. 実行は容易ではなさそう. 一度読んだだけは租借しきれなかったので,再度読み直したい.
Posted by
重要な示唆の外縁を歩いている感覚。要再読。 抽象度が高く、前半の説明と後半の実践の対応がわかりにくい。 ◯システム思考:一見の改善策が次なる課題を生む可能性↔︎小さな変化が大きな改善を生む可能性も →システムの理解が必要 ◯構造の説明により、挙動パターンそのものが変えられる...
重要な示唆の外縁を歩いている感覚。要再読。 抽象度が高く、前半の説明と後半の実践の対応がわかりにくい。 ◯システム思考:一見の改善策が次なる課題を生む可能性↔︎小さな変化が大きな改善を生む可能性も →システムの理解が必要 ◯構造の説明により、挙動パターンそのものが変えられるレベルで、挙動の根底にある原因に対処する。 ・自らの行動により他者の挙動に影響を与えることを理解する。 ・行動による影響が現れるまで待つことを理解し、パニックを起こさない。 ◯相殺フィードバック:良かれと思って行った介入が、その介入の利点を相殺するような反応をシステムから引き出す 例)途上国の食料・農業支援による栄養失調の減少→出生率の上昇による人口過密で栄養失調が増加して相殺 ◯システム理解のポイント ・全体で捉える ・誰も悪くない→関係性に問題がある ◯複雑性 ・種類による複雑性(多様な変数) ・ダイナミックな複雑性(短期と長期で大きく異なる影響) ◯フィードバック・プロセスはループする→システムによって生み出される問題に対する責任は共有される ◯自己強化型ループとバランス型フィードバック バランス型プロセスが存在していることに気づかず、変化させたくてもできない ◯プロセスの遅れを改善することで一定程度の改善がある ◯システム原型の理解 ・成長の限界: 成長させる行動が減速させる行動を生み状況をつくる →制約要因を特定して取り除く ・問題のすり替わり: 対処療法的な解決策が根本解決をより遠ざける →根本的解決策を同時に示すとともに対処療法的対策の段階的削減を示す ◯自己マスタリー ・自分にとって何が重要かを絶えず明確にすること ・どうすれば今の現実をもっとはっきり見ることができるかを絶えず学ぶこと →はっきりとしたイメージを対置させることで創造的緊張が生まれる →行きたい所に行くには、今どこにいるかを知ることが先決 ◯学習する組織では、人の最大限の発達と財務的な成功とは同列 ◯人が心から目指したいもの、その具体性を持ったビジョンを持つ ↔︎逃避のための目的、手段に焦点を当てた目的 ◯構造的対立: 多くの人が「自分は無力である」「自分には価値がない」という根底にある信条を持っていて、目標に向かう分、強い力で作用する →まず構造的対立及びその影響の認識が必要。ただし構造的対立が作用していることに気づかないことが多い →自分の問題を何かや他人のせいにしていると自覚したとき警戒することが発見の助けになる 例)自分の手足を自分で動かせることを理解していない赤ちゃんは自分の手が自分の耳を引っ張ったときに驚いて余計状況を悪化させる ◯潜在意識の能力を発揮する →その訓練として、望ましい結果そのものに焦点を当て、具体的にイメージする ◯自己マスタリーの強化は強制できない →以下の組織環境は促進できる ・メンバーが安心してビジョンを描くことができる ・真実の探求や真実に忠実であることが当たり前になっている ・現状に対して、特に避けたいために覆い隠したくなるものに異議を唱えることが期待されている ◯メンタル・モデルを問い直す →相互探求のバランスが重要 ◯共有ビジョンを築く →個人のビジョンを奨励する。それは断片にはならないが、共有ビジョンへの目線を用意する。リーダーはトップダウンで示すものではないが、個人のビジョンを積極的に示す ◯ダイアログ(≠ディスカッション)によるチーム学習、その基本原則 ・前提の保留。一般に人はある立場を取り、それを弁護し、それに固執する。他の人たちが反対の立場をとると、分裂が起こる。方向や戦略の根底にある前提を検証する場合、その前提を弁護士ないようにする。 ・仲間として行動する。全参加者は肩書きを持ち込まず、序列は一切ないことを意識する。ただし、ファシリテーターは例外で、話し合いを順調に進めてくれるものとして期待する。ファシリテーターは言語化に努める。 ・探求の精神。自分の意見の背景にある考え方、その根底にあるかもしれない前提、裏付けとなる論拠を探求する。「どのようにしてその意見、考えになったのか?」「なぜそれについて質問するのか?」の問いを発することを奨励する。 ◯学習と仕事を一体化させる →事前のダイアログと振り返り ・何が起きたのか? ・何を予想していたのか? ・この乖離から学べることは何か? ◯設計者としてのリーダー
Posted by
組織に関する内容ですが、その前提として、既に完成度が高い個の集まりを立脚点として、述べている印象です。 もちろん、その完成度を高めた個として、”自己マスタリー” ”メンタル・モデル” が定義付けられています。 その点は西洋流ですね。 あと個人主義的なメンタリティーを持つ中国も含ま...
組織に関する内容ですが、その前提として、既に完成度が高い個の集まりを立脚点として、述べている印象です。 もちろん、その完成度を高めた個として、”自己マスタリー” ”メンタル・モデル” が定義付けられています。 その点は西洋流ですね。 あと個人主義的なメンタリティーを持つ中国も含まれるかな。 逆にいうと、農耕的集団志向のルーツを持つ日本人が特殊なだけだろうか。。 野中郁次郎さんの"知識創造企業"でも、その点が野中さんのSECIモデルとの相違点だとご自身で述べていたような…… "システム思考"には、共感します。 本書の最後は、"ガイア理論"→地球レベルまで、論じられております。 人間て、どんどん視野が狭くなっていく主観的な生き物。 問題解決が本業の自分は、真因究明という解にたどり着くために、深く掘り下げていかなければならないという宿命を持っています。 この"システム思考"を心に秘めながら、常に全体を振り返ることを忘れずに、部分と部分の関係に配慮して、ストーリー(ロジック)を作っていこう! そのためには、もっと先を見据えながら生きていかなきゃ! ・システムと自分の主観との両立。 ・Win-Winの探索。 ・実務と学習のリンク。 読み進めながら、かなり自己が啓発されました。 ハウツー的な内容ではありませんが、なにか自己変革できるきっかけをいただくことができた様な読後感でした。 自分が現在考えている組織観は、この学習する組織で述べられている、システム思考をフレームとして、その中のプロセスへの適用にSECIモデルといったところだろうか。 学んで頭に入っているだけではさびついちゃうので、早速 会社へ適合していこうと思います。
Posted by
「学習する組織」の原典ともいえる"the fifth discipline"の2nd editionの完訳版。 原書の2nd editionは、1st editionから100ページくらい増えていて、これまでの翻訳「最強組織の法則」は1st editionか...
「学習する組織」の原典ともいえる"the fifth discipline"の2nd editionの完訳版。 原書の2nd editionは、1st editionから100ページくらい増えていて、これまでの翻訳「最強組織の法則」は1st editionからの抄訳だった。 まずは、ざっと一読した感じは、「最強組織の法則」とは全然違う本になったな、というところかな。 580ページの厚めの本になったということもあるけど、なんだか、調子が大部違う感じだ。 「最強組織の法則」を読んだのが大分前なので、ちゃんとした比較はできないのだけど、そのときの印象は、「良い事言っているけど、なんだか大雑把で、一貫性ないな」という感じだった。 同時期にたまたま読んだ「ビジョナリー・カンパニー」が、かなりしっかりとした実証研究のうえになりたちつつ、そういう実証的な本が陥り勝ちな「そんなの当たり前じゃん」的な退屈さからはすごく遠い、スリリングで明快な主張を持つ本だったのとは対照的で、「最強組織の法則」は、「で、それがうまくいく証拠あるの?まだまだ頭で考えただけじゃん」という印象であった。 つまり、「最強組織の法則」は、なんだかピンと来ない本だった。 で、今回の翻訳だが、「そうそうそうなんだ!」と共感しまくり、付箋を貼り始めたら、付箋だらけになってしまった。 この数年間、「フィールドブック」を始め、「学習する組織」関係の本をいろいろ読んできたので、理解度が深まったということもあるが、初版から15年を経ての実践からの学びが本のなかに凝縮されている感じだ。つまり、フィールドブックや「出現する未来」など1st edition以降に出された本のエッセンスも織り込まれたまさに「学習する組織」の原典に相応しい本に仕上がっている。 あいかわらず、事例の部分は、インタビューを中心としていて、全く実証的ではないのだが、それをはるかに超える迫力と説得力をもった本だ。 不確実ななかで、これからの未来を作るのに、過去の成功事例とか、統計処理とかから、帰納的に考えてもしょうがないんだね。 それから、もともとシステム思考が最重要のディシプリンということだったはずなのだが、2nd editionでは、「自己マスタリー」のほうに重点が移った感じがした。結局、未来をつくっていくのは、なにかを始めようとするリーダーなんだよね。そして、それは役職としてのリーダーじゃなくて、一人一人のなかにあるリーダーシップ、自己マスタリーの問題なんだな。 内容も素晴らしいが、翻訳がとても信頼できる感じがして、そこがとても良い。 「最強組織の法則」が抄訳だったり、なんだか誤訳じゃないかと意味が分かりにくいところがあったので、原書と読み比べたりしていたのだが、今回の本は、原書の印象とかなり近い気がする。 前回が無理矢理ビジネス書の体裁にまとめました、という感じだったのに対して、今回の訳は、原文の内省的な感じがよくでていると思う。 ちなみに、原書の最初には、蛇が5匹とぐろを巻いていて、それを大きな蛇が囲む挿絵が入っているのだが、今回の翻訳では、これが省略されている。これを最初につけると「かなりスピリチュアルにいっちゃうな、ビジネス書っぽくない」という判断なのかな、と思ったが、個人的には、そのビジネス書らしからぬところが好きなので、ちょっと残念。 その点を除けば、素晴らしい出来だと思う。 何度でも読み返すに値する本
Posted by
一つ一つの問題や個別の事象に着目するのではなく、システム全体としての構造に注目する。木を見て森もみる視点を前提に持つこと。自己学習のサイクルを自覚すること。また、個人それぞれが自らの経験と知識によって形作られるメンタルモデル、つまり思い込みや認知バイアスがあることをわかった上で、...
一つ一つの問題や個別の事象に着目するのではなく、システム全体としての構造に注目する。木を見て森もみる視点を前提に持つこと。自己学習のサイクルを自覚すること。また、個人それぞれが自らの経験と知識によって形作られるメンタルモデル、つまり思い込みや認知バイアスがあることをわかった上で、全員が共有できるビジョンを組織として持つこと。組織全体で学習し、能力を開発していく。個人でなく、組織全体のシステムを改善していくことで最強組織ができるとピーターさんは言っている。 まず理論をわかっていることはとても重要。だけど、これを実践することはとても難しい。一人がわかっていてもダメだが、全員でこのことを理解することもまた難しい。 おそらくこの理論と実践を強力なリーダーシップのもと勧めていかなければとても現実に適用できるモデルとは言い難い。 なのでこの理論を抑えた上で、ドラッカーのマネジメントや、人と組織はなぜ変われないかでおなじみの免疫マップを活用するなどして掛け合わせで理想を追い求める継続した努力がないとなかなか実現はしないだろうと思う。 だからこそ、チャレンジのしがいがある課題だとも言える。
Posted by