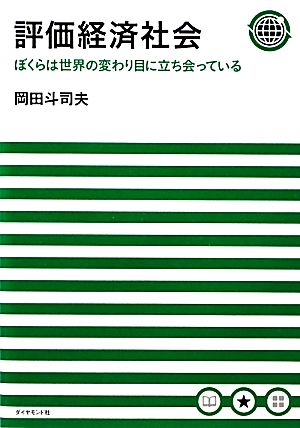評価経済社会 の商品レビュー
貨幣経済から評価経済へ。各論としては分からんではないのだが,全体として何故か腑に落ちない。旧パラダイムから抜け出せずにいるからなのか。 最終的に,働く人がお金を払うというシステムに繋がるところが特に分からない。その人達が払うお金はどこから生まれるのだろうか。もう少し贈与経済とか勉...
貨幣経済から評価経済へ。各論としては分からんではないのだが,全体として何故か腑に落ちない。旧パラダイムから抜け出せずにいるからなのか。 最終的に,働く人がお金を払うというシステムに繋がるところが特に分からない。その人達が払うお金はどこから生まれるのだろうか。もう少し贈与経済とか勉強すれば理解が進むのか?
Posted by
実証性のない思いつき議論。説得力はあるような無いような。 古代のパラダイム:資源は余っている。時間がない。個人の思索をしない。 中世のパラダイム:資源が不足。時間がある。個人の施策をする時間があるので、思想体系が発達する。秩序を壊す方向性はない。 近代のパラダイム:資源は無限にあ...
実証性のない思いつき議論。説得力はあるような無いような。 古代のパラダイム:資源は余っている。時間がない。個人の思索をしない。 中世のパラダイム:資源が不足。時間がある。個人の施策をする時間があるので、思想体系が発達する。秩序を壊す方向性はない。 近代のパラダイム:資源は無限にある。時間がない。資本主義=均一な価値観。個人の欲望が許される=自由主義。 今後の新パラダイム:資源が不足、有限。時間がある。個人の様々な価値観に支えられた思想の発達。上昇志向は制約される。 という感じで要約できるか。
Posted by
今起こっている変化について、なんとなくついて行っているようで行けてない身にありがたい解説本。それでモヤモヤがはっきりするわけではないけれど、病院をたらい回しにされてやっと病名が明らかになったような感じ、と言えばよいか。
Posted by
前著である「ぼくたちの洗脳社会」を呼んだことを前提とすると、わざわざ読む様な本ではない。 1998年に書かれたということの凄さを感じるための温度感が薄れ、また洗脳と評価を言い換えているが意味づけの整合性が取れておらず、むしろわかりにくくなっている。
Posted by
40代以上の人で、若い世代との違いを感じると思う人ほど読んでもらいたい本。 2011年初版の本と思えないほど、近未来をよく言い当てている。 YouTubeでその発言内容を知ることも出来る。話しに引き込むのがうまい著者。まったく同じトーンで本も書かれている。そのためか、文章も話...
40代以上の人で、若い世代との違いを感じると思う人ほど読んでもらいたい本。 2011年初版の本と思えないほど、近未来をよく言い当てている。 YouTubeでその発言内容を知ることも出来る。話しに引き込むのがうまい著者。まったく同じトーンで本も書かれている。そのためか、文章も話し口調で展開されており、軽く読みやすい分、やや展開に違和感を感じる人もいると思う。 ただ、骨子となるパラダイムシフトへの着眼点は素晴らしいし、Z世代の若者たちを理解しやすくなる手引きとなる。 また、後半に「自分が何をしたいか、すべきなのか分からない人」達に向けたメッセージがある。これは中途半端な心理学の本など読むより、圧倒的に納得感がいき、気持ちが楽になると思う。
Posted by
・今の私たちは「科学が私たちを幸せにしてくれる」とは思えなくなっている ・堺屋太一が「知価革命」で「優しい情知の法則=どんな時代でも人間は、豊かなものをたくさん使うことはかっこよく、不足しているものを大切にすることは美しい、と感じる」と述べている ・ネットが「信じたい情報」だけを...
・今の私たちは「科学が私たちを幸せにしてくれる」とは思えなくなっている ・堺屋太一が「知価革命」で「優しい情知の法則=どんな時代でも人間は、豊かなものをたくさん使うことはかっこよく、不足しているものを大切にすることは美しい、と感じる」と述べている ・ネットが「信じたい情報」だけを求める人たちの「気持ち」を加速する ・自分の気持ち以下の値打ちしかない「科学」が21世紀の科学像 ・「モノ不足、時間余り、情報余り」の「ネット中世」の時代がやってくる ・近代になって神様が「こう生きろ」と言ってくれなくなった。そのため自分で自我の確立をする必要が出てきた=「近代的自我の呪い」 ・現代においては、「自分の気持ちを大切にする」「自分らしさを大切にする」という形で”逃げ”た ・中世と現代の違いは「ネットによる情報余り現象」「唯一無二の自分という自己認識」「一生勉強という気持ち」 ・情報化社会の本質は、「大きな事件の解釈や感想が無限にあふれ出す社会」 ・「評価」を仲介として「モノ」「サービス」「カネ」が交換される社会が「評価経済社会」 ・価値観の提示、具体的要求、成果の報告の三つがそろって初めて評価資本は増大する ・これから重宝されるのは情報の「整理屋」 感想 本文中では貨幣経済と評価経済が対立するように書かれているが、本当にそうだろうか。評価がお金に変換できる以上、評価が貨幣の上位互換というだけではないのか。旧来の価値観が否定されるといっても、すべての人が1つの絶対的価値観を信じることがなくなるだけで、少数ながら旧来の価値観を信じ続ける人は存在するだろう。
Posted by
刊行が2011年。第二版を読んだが、この時点でオンラインサロンの存在を予見させるような記述もあり、著者の先見の明には驚かされる。 他方、アジテーションが目立ち、表現において粗暴さが目立つ。また、根拠とする文献・知見が明らかにされることも少なく、恣意的な論理構成が目立った。 自己啓...
刊行が2011年。第二版を読んだが、この時点でオンラインサロンの存在を予見させるような記述もあり、著者の先見の明には驚かされる。 他方、アジテーションが目立ち、表現において粗暴さが目立つ。また、根拠とする文献・知見が明らかにされることも少なく、恣意的な論理構成が目立った。 自己啓発本ではない、と思い購入したが自己啓発本。ビジネス本ではない、と思ったがビジネス本。自分の判断が浅かったことを悔いるばかりだ。
Posted by
これから社会の中心がどうなっていくのかを描いた本。 2011年時点(旧書は1995年)で「貨幣」よりも「評価」が重要視されるという予想は2021年現在で考えると当たっていると感じた。今は、YouTubeやInstagram等のツールを用いることで一般市民である個人がある程度の評...
これから社会の中心がどうなっていくのかを描いた本。 2011年時点(旧書は1995年)で「貨幣」よりも「評価」が重要視されるという予想は2021年現在で考えると当たっていると感じた。今は、YouTubeやInstagram等のツールを用いることで一般市民である個人がある程度の評価を受けて、youtuberなどの職業として存在できる。お金を持っている人は偉いという感覚は未だ残っているが、実際に評価を受けている人が偉いという感覚が台頭してきているように感じる。 また、本書で語られている、「モノ不足、情報(に対する解釈)過多」の時代であるという指摘も的を射ていると感じた。農業革命や産業革命によって起こったパラダイムシフト(人々の価値観などの変化)の真っ只中に私たちはいるのだろう。 本書は現代の社会、価値観に対する捉え方をはっきりとさせる手助けとなるだろう。個人的には面白かった。 ちなみに著者が未来の若者像として語っていた部分で今の自分の考え(価値観)をピタリと言い当てられたのはナイショである。読んでびっくりした。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
とにかくまずは、自分の事を「勝ち組だ」と思っている人に是非とも読んで欲しい本だと思います。これからの日本の大多数になりつつある弱者の論理がよく分かる本だと思います。 傍から見れば「ダメなやつだなあ」と思える人たちでも、その人たちはその人なりに、そういった行動を取る理由があるはずです。それを理解しようとせず、自分の価値観だけで「こうあるべきだ」と偉そうに主張するようなやり方は、これからの日本では通用しません。「昔と違って今の時代は価値観が多様化している」という事実をしっかりと認識した上で、そういった人たちの意見にまずは反論せず最後までその主張を聞き通す事が今後のビジネスにおいて重要なんだと思いました。・・・ビジネスとか言ってる時点でこの本の主張に反するかも知れませんが^^;。 蛇足ですが、この本が主張している「私たちはもう科学に多くは期待していない」という考えに対し、同意はしつつも、エンジニアとしてはその期待を良い意味で裏切ってやりたいと感じました^^;。 正直、確かに世界が一気に変わるドラスティックな商品を世に産み出す事は難しいと思います。ただ、例えそれが小さな一歩であっても、その積み重ねによってより良い世界になっていくと信じたいです。またその際には、市場を見ない作り手側の独りよがりなモノづくり(利益独占を狙った独自規格、過剰過ぎる機能、新たな儲け口を作ろうという意図が透けてみえる機能などなど)をするのでは無く、使う側の立場に立った視点でのモノづくりを行っていきたいと思います。
Posted by
堺屋太一 やさしい情知の法則 どんな時代でも人間は、豊かなものをたくさん使うことは格好よく、不足しているものを大切にすることは美しいと感じる ピクサーってジョブズだったんだ…知らんかったけど納得 これまでの価値観の変遷の考察を見るにはいい本。 自分の意見や価値観を全部自分で...
堺屋太一 やさしい情知の法則 どんな時代でも人間は、豊かなものをたくさん使うことは格好よく、不足しているものを大切にすることは美しいと感じる ピクサーってジョブズだったんだ…知らんかったけど納得 これまでの価値観の変遷の考察を見るにはいい本。 自分の意見や価値観を全部自分でつくり出すことがそもそも不可能だと思う。生まれたときから何かの意見や価値観に囲まれているから。 しかもこれだけ歴史や知見が溢れていれば、重複しない方がおかしい。 でもたくさんの知見、経験から咀嚼して、組み合わせて、オリジナルを出すことは可能。 考える=ネットで賛同できる意見を探す ではなく いろんな意見を見て自分なりの答えを出す だと思ってる。 その結果、同じ考えをする人もいるにすぎない。 そうやって考えられたものたちがぶつかって、新しい解を導き出して進化してきたのでは? 競争という概念から、協力とか互助的な方向に進むと思う。 本当の最終章はラストページな気がする。
Posted by