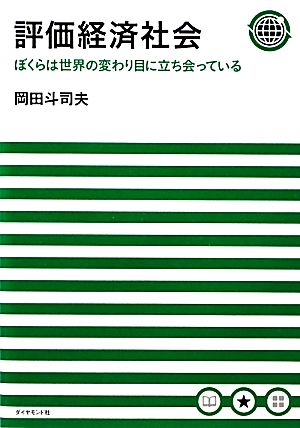評価経済社会 の商品レビュー
岡田斗司夫はサブカルの蘊蓄(とダイエット)を語る人という印象しかなかったが、全然違った。渡部昇一のような語り口。
Posted by
(前半部分のみ、暫定でレビュー 読後に加筆修正します) オタキングこと岡田斗司夫による著作。 ITなど技術の進歩により、農業革命・産業革命以来の第3の波が起きている現代。これからは社会システムが変わるだけでなく、我々の常識や価値観も同時に大きく変わっていく。端的にいうと、「科学」...
(前半部分のみ、暫定でレビュー 読後に加筆修正します) オタキングこと岡田斗司夫による著作。 ITなど技術の進歩により、農業革命・産業革命以来の第3の波が起きている現代。これからは社会システムが変わるだけでなく、我々の常識や価値観も同時に大きく変わっていく。端的にいうと、「科学」も「経済」も信じられなくなった人々は、「自分の気持ち」や「他者の評価」を重んじる「評価経済社会」へとパラダイムシフトしていくことを説いた一冊。 今後と同様に、パラダイムが精神性に傾いていた時代(≒人々が宗教に没頭していた時代)の原因をそれぞれ分析していたのが興味深かったです。 ごとう
Posted by
『お金』から『評価』へ。オタキングこと岡田斗司夫氏が説く大きな時代のパラダイムシフトを生き抜くための方法論が提示されている本書はとても示唆に富んだ内容で、将来こうなるかもなぁという説得力がありました。 本書は「オタキング」こと岡田斗司夫氏が 『3社から3冊同時刊行プロジェクト/...
『お金』から『評価』へ。オタキングこと岡田斗司夫氏が説く大きな時代のパラダイムシフトを生き抜くための方法論が提示されている本書はとても示唆に富んだ内容で、将来こうなるかもなぁという説得力がありました。 本書は「オタキング」こと岡田斗司夫氏が 『3社から3冊同時刊行プロジェクト/ジェットストリーム計画』 という企画で刊行された書籍のひとつで、『あなたを天才にするスマートノート』の後に読みました。 内容はというと、価値観のパラダイムが『貨幣』から『評価』に変わる時代がやってくるということで、岡田氏のトークイベント『ひとり夜話』でも語っているので、興味をもたれた方はニコニコ動画やYoutubeなどで確認されてみてはいかがでしょうか?本書の土台になったものは1995年に刊行された『僕たちの洗脳社会』という本だそうで、インターネット社会に対応したものとして改訂したものなのだそうです。 我々の社会は狩猟社会から始まって、農耕社会に変わり、そこから都市生活へと変わって行ったわけですがその過程で失われたものやそれとは変わって新しく得たものに関する論の展開はとても面白かったです。それが今度はネット社会によって『評価』というものが『貨幣』に変わり得る者になるであろうと筆者は説いていて、その過程で現在起こっているさまざまなことが変わりつつあるんだという結論部はなるほどなぁと思ってしまいました。 先の見えない世界をどう生きて行くか?という問題を抱えている現代人にとって本書はそのヒントになりえるかもしれないと、読了後にそんなことを考えております。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
子どもに示すべき道がわからない、多分、私が育ってきた時代の価値観は、もう、通用しない。模索して読んだ一冊。ネットの発達がパラダイムシフトをおこすだろうことは何となく感じる。若い人の「自分の気持ち至上」や「もの、金への執着のなさ」は来るべき時代の価値観で、それを「下流」と評するのは、まだ、近代の価値観でものを見ているから? 勉強して、大学行って、安定した会社に入るか、手に職つけてね!とは言えなくなったけど、じゃあ、〇〇して!って自信を持って見せるモデルは見つからない。子どもたち、自分で探しておくれ!フォトリ23冊目。
Posted by
現在進行中のパラダイムシフトの要点と未来予測が詰まった一冊。 21世紀前半の今は『情報(に対する解釈)余り・資源(環境)不足の社会』、これから重宝されるのは、、、 この先はぜひお試しあれ。 オモシロイ。
Posted by
ソフトな語り口なのでさらっと読めるが、内容は抽象的なので理解するためにはきちんと咀嚼しながら読まないと頭には入ってこない。 技術の進化、社会構造の変化に伴うパラダイムシフトが価値観を変える。その結果がいま「社会問題」と呼ばれている現象なのであり、それを引き起こす個々人の「気分」...
ソフトな語り口なのでさらっと読めるが、内容は抽象的なので理解するためにはきちんと咀嚼しながら読まないと頭には入ってこない。 技術の進化、社会構造の変化に伴うパラダイムシフトが価値観を変える。その結果がいま「社会問題」と呼ばれている現象なのであり、それを引き起こす個々人の「気分」は現在の価値観から評価するならば肯定されてしかるべきで、そもそも問題ですらないのだ、という超ポジティブシンキング。 このような時代の捉え方は、個人というレベルでみれば、価値観を間違ったもの、理想からかけ離れたものと捉えるのではなく肯定することで、常識から外れているのではという不安をはじめとした個人の精神的負担を軽くし、幸福をより身近に感じられるようにするだろう。(ただし社会全体の価値観はそうそう変えられないので、現在社会問題として起きている問題については、社会の仕組みとして短期、中期的くらいには対応していかなければならないと思う) 私自身も自分のことを「いまいち常識からずれているなあ」と思っていたが、著者の指摘する新しいパラダイムの中では割と普通なことのようだ。だったら自分としてはしあわせだし、まあいいか、と少し気楽に思える。 本書の最大の効用は、いま世間の常識からずれていると批判されている人に、それでいいのだというお墨付きを与え、精神の安寧を示すところにあるのかもしれない。
Posted by
今現在の貨幣経済社会は終わりを迎えていて、社会は評価経済社会に向かってパラダイムシフトしているらしい。原因はネットとのことだけど、なるほど確かにネット以前と以後では人の価値観は変わったと思う。先が見えない分大変だけど、面白い時代に生きているのは確かかもしれないな。
Posted by
目次 ・貨幣経済社会の終焉 ・パラダイムシフトの時代 ・評価経済社会とは何か ・幸福の新しい形 ・新世界への勇気 どこが参考になったのか ・評価経済社会とは人々の不安や不満をつかみ、最も効率よくそれを解消する手段を提案することによって、多くの人に影響を与え、尊敬と賞賛を得られる...
目次 ・貨幣経済社会の終焉 ・パラダイムシフトの時代 ・評価経済社会とは何か ・幸福の新しい形 ・新世界への勇気 どこが参考になったのか ・評価経済社会とは人々の不安や不満をつかみ、最も効率よくそれを解消する手段を提案することによって、多くの人に影響を与え、尊敬と賞賛を得られるのが評価経済競争社会。得られる利益は貨幣的利潤ではなく、評価利潤、つまりイメージ ・前提としてインターネットの普及による「高度情報化社会」の到来が挙げられる。これは情報の数が増えるというよりも、誰でも発信者になれるという点で、その際の「解釈」が増える社会が到来したことを示す。 ・そもそもメディアというものが記事という言葉を通じて、本質として「意図の強制」を行なってきた。これが個人として多くの人ができるとなると、だれでも影響を与える側になれるし、逆に受け手にもなる。その結果「受け手」は「与え手」を評価する。誰もが両方になれるために「評価」と「影響」を交換している。 ・評価資本が増大する条件として、価値観の提示、具体的要求、成果の報告が必要 ・評価経済社会での個人の振る舞いの特徴として、他人をその価値観で判断するということ、価値観を共有するもの同士がグループを形成するということ、個人の中で複数の価値観をコーディネートするということ、の3つがある。 どんなときに読み返したいか ・岡田さんが歴史を紐解いていった1・2章当たりは読んでみてもいいかと思った (読み終わったのが前過ぎるので・・・)
Posted by
人類の歴史は、3つの革命によって、引き返せない楔を打ち込まれた。 農耕革命、産業革命、情報革命 それぞれの時代に生き残る(サバイバル)のに必要なスキルを人々は学んできたが、現代社会ではどのような基準で生きるのがベストなのかを「評価経済社会」というキーワードを切り口に明快に分かりや...
人類の歴史は、3つの革命によって、引き返せない楔を打ち込まれた。 農耕革命、産業革命、情報革命 それぞれの時代に生き残る(サバイバル)のに必要なスキルを人々は学んできたが、現代社会ではどのような基準で生きるのがベストなのかを「評価経済社会」というキーワードを切り口に明快に分かりやすく現代を読み解くす良書。 面白かったポイント 人類の歴史には「引き返すことができない楔」が打ち込まれたポイントがある。というところが面白かった。 農耕社会では、作物の生産量が絶対で、それを左右するもの、例えば大地の恵みや水、太陽を「カミ」として崇める社会 自分たちが生き残るために食料を作る必要があり、その生産量に応じた集団が形成される。 その小集団は「自分たちが生産できる作物の量」に絶対的な価値を置き、それが達成される要素を守ろうとする仕組みを絶対とする社会 産業革命は、生産量が劇的に高められた世界で、それを生産できる工場やそこで働く労働者が中心になる社会 そこではどれだけ効率よく生産できるかが善となり、そのために社会インフラが整備された(例えば義務教育のような教育システムなど)その社会は、効率や科学技術の発展が善となり機能している 情報化社会では、社会全体が「情報」というネットワークで繋がり、一気に世界がひとつになっていく。 その中では工場労働に適した人材が善となるシステムの上で効率よく物や金を得るより以上に、情報の質や信頼性が善となる社会になる。 このパラダイムの違う世界ではそれぞれの価値観は混ざり合うことがないし、お互いがお互いを理解できる共通認識がずれてしまっていて、コミュニケーションの断絶がおこる。 いわゆる「幸せの尺度」が違うのである このようなパラダイムシフトによる社会の断絶を、うまく解釈する提言として、堺屋太一が提唱する「やさしい情知の法則」が使える その法則とは 「どんな時代でも人間は、豊かなものをたくさん使うことは格好よく、不足しているものを大切にすることは美しい、と感じる」 現代社会で豊かに存在しているのは「情報」そして、不足しているのは「心の豊かさ」である 評価経済社会とは、お金よりも物や人がその他大勢からどのように評価されているかが重要になる社会。 どれだけ自分自身が「私はこういう人だ」と主張しても、その他大勢からの評価と比べて何処かに違和感があると受け入れられない世界である。 大きなパースペクティブで歴史や地球全体を見つめて、社会全体を推し量る尺度のような提言をキーにすることで、これほど明快に現代社会を浮かび上がらせる事に成功している本も珍しいと思う
Posted by
ネット上でさらっとよめた。 オタクで有名な岡田さんの本。 うん、たしかにといったかんじ。 こういう風にライトに社会のわかりやすい解説が読めてしまうならもっと広がっててもいいんだけどな-。こういう思想。現象としては納得なんだけど依然として意識下ではマジョリティでもないような。。。 ...
ネット上でさらっとよめた。 オタクで有名な岡田さんの本。 うん、たしかにといったかんじ。 こういう風にライトに社会のわかりやすい解説が読めてしまうならもっと広がっててもいいんだけどな-。こういう思想。現象としては納得なんだけど依然として意識下ではマジョリティでもないような。。。 ほんと、オタクって2、3歩以上先にいっている。リアルでも暴れて欲しいところだが閉鎖性が高いコミュニティなんだろうか。
Posted by