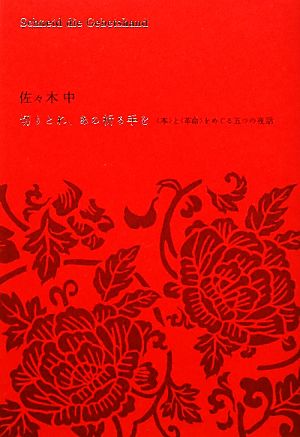切りとれ、あの祈る手を の商品レビュー
http://staygold1979.blog.fc2.com/blog-entry-568.html
Posted by
革命の本質とはテキストの書き換え、読み替えである。というところが目から鱗だった。 ルターの宗教革命での聖書の深い読み込みの姿勢が現在の科学、法学などの礎になっていることに感銘を受けた。 今で言うと何かの新聞記事に対して1次ソースも参照しろみたいな情報リテラシーにもつながるかもな。
Posted by
先日いただいた本を読了しました。 ジャンルは現代思想系、とでもいうのでしょうか。 佐々木さんが聴衆または聞き手に向けて 語り掛け続ける口語体中心で構成された本です。 自分ごときが評価できるレベルの本ではありませんでしたが、 素養のない者が読んでの評価ということで書きます。 哲...
先日いただいた本を読了しました。 ジャンルは現代思想系、とでもいうのでしょうか。 佐々木さんが聴衆または聞き手に向けて 語り掛け続ける口語体中心で構成された本です。 自分ごときが評価できるレベルの本ではありませんでしたが、 素養のない者が読んでの評価ということで書きます。 哲学、宗教系の教養がそれなりにないと、 枝葉末節だけでなく、本筋の裏のロジックがわかりづらい、 というような内容ではありました。 なので、自分には内容が半分もわかったかどうか怪しいです。 しかし熱量がすごい。それだけは伝わってきました。 ○○は終わった、というような表現はよく使われますが、 それが本当に著者は許せないんだなと思います。 お前が終わったという前に、お前の○○は始まってもいない、 そう言い放つのです。 本当の意味での読むという行為を怖がっているお前に、 終わりを語る資格などないと叫ぶのです。 テクストがただの文字情報という意味を超えた、 上のレイヤーにおける情報価値そのものとして息づき、 それこそがこれまでの人類を作ってきたのだし、 今の自分が生きていられるのもそのおかげなのだ。 そういうことを忘れずに生きることが大事だし、 だからこそすべての人は臆せずにその思いを書き残すべき。 その一足が道となり、誰かがそれに続くかもしれない。 そんな風に自分の中では捉えることができた本でした。 難しい本でしたが、面白かったです。 ただ、これをくれた友人はこの本で人生が変わった、 という風に言っていましたが、 自分は変わるほどには理解できなかったようです。 (謙遜抜きで) 非常に示唆に富んだ本だったことは間違いありません。 著者の他の作品も少し読んでみたいと思いました。
Posted by
大学受験のとき家庭教師がおすすめしてくれた本。始めてちゃんと読んだ哲学の本だったと今思う。彼女はとても頭がよくて、字が下手で、いつもちょうどいいテンポでキレのある言い方をしていた、そんな彼女にすごく憧れた。だからこの本を持ってるだけでそんなふうになれるのかなとずっと積読してた本。...
大学受験のとき家庭教師がおすすめしてくれた本。始めてちゃんと読んだ哲学の本だったと今思う。彼女はとても頭がよくて、字が下手で、いつもちょうどいいテンポでキレのある言い方をしていた、そんな彼女にすごく憧れた。だからこの本を持ってるだけでそんなふうになれるのかなとずっと積読してた本。 文学とは革命だ!
Posted by
偏向と誤解、悪意と無知。もはや社会の騒音でしかなくなったジャーナリズムの喧騒から遠く離れて。 読むこと。書くこと。生存率0.1パーセントの可能性が私たちの世界にもたらしたもの。 最終夜の『そして三八〇万年の永遠』は奇しくも世界の終末・人類滅亡論を粉砕する。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
・最近の現代思想系の本では最も好き。すばらしい才能の発見。東浩紀、宇野常寛などのグループから孤立している思想の形。 (印象的な箇所のまとめ) ・誰の手下にもならないし、誰も手下にしない。唯一の真の忠告者、孤独の声を聞くように。 ・わかってしまったら狂ってしまうような本を書く。 ・現代の文学は狭くなっている。かつて文学は聖書を書くこと、つまり法を書くこと、つまり掟を書くことだった。 ・革命にとって暴力は二次的なものに過ぎない。本当の暴力は法を書き換えること。 ・文学こそ革命の力。革命は文学からしか起こらない。 ・本の読めなさ、読みにくさに向き合う勇気。読めるわけがない本をそれでも読む。テクストの異物性、外在性、なまなましい他者性、無慈悲さ。 ・自分の言っていることが聖書であり、すべて正しいとなると、カルト、原理主義になる。 ・国家の本質は再生産、繁殖を保証すること。 ・中世解釈者革命。学者たちは法を書き続けた。法の解釈、注釈の膨大なテキスト。膨大なテキスト、文学が世俗化を起こした。宗教国家の時代から近代国家の時代へ転換。 ・現代において法は情報となった。膨大な情報のデータベースが私たちの生を形づくっている。 ・テクストが我々の体の動きを決めている。私たちはテキストの振り付けに従ってダンスしている。そのダンスの振り付けは、変えることができる。かつて中世解釈者革命が起こって、時代は変わったのだから、また変わることができる。
Posted by
革命の本体は暴力ではない。経済的利益でもなければ権力の奪取でもない。テクストの変革こそが革命の本体です
Posted by
ショーペンハウエル『読書について』、アドラーの『本を読む本』、最近のものだとエーコとカリエールによる対談集『もうすぐ絶滅するという紙の書物について』など、「本の本」というのはこれまで想像以上に多く著されてきた。書く人は往々にして読む人であり、読む人もまた多く書く人であることを考え...
ショーペンハウエル『読書について』、アドラーの『本を読む本』、最近のものだとエーコとカリエールによる対談集『もうすぐ絶滅するという紙の書物について』など、「本の本」というのはこれまで想像以上に多く著されてきた。書く人は往々にして読む人であり、読む人もまた多く書く人であることを考えれば、これも至極当然の成り行きなのだろう。じっさい本国でも亀井勝一郎や松岡正剛などの「読書の匠」が、自身でも多くの著作を残していることがその証左となる。 そんな玉石混淆ひしめき合う読書論の中にあって、『切り取れ、あの祈る手を』は異色の存在感を放つ。この本は、読み方を教えない。読むべき本も示さない。まして「読書で獲得した情報の整理」などという胡乱な末節を弄することなど決してしない。本書で佐々木中が試みたのは、「本は読めない」という命題が真であるという証明である。 「本」という概念に佐々木は革命の本質を見た。かつてフーコーがそうしたように、佐々木は様々な語の定義を、その源流を辿りながら遡及的に拡張してゆく。「本」とは、「文学」とは、「情報」とはこれまで何であり続けてきたか。「革命」は、これまで如何に成されて来たか。切り口は鋭く、語り口は鮮やかだ。『夜戦と永遠』を苦労して読んだ僕にとって独特の文体は彼の論旨によく馴染み、心地よさすら感じる。 文盲の聖者ムハンマドと本の母=クルアーンとの遭遇、ドストエフスキーをはじめとする文豪が参加した絶望的な「賭け」、唾棄すべき終末論の愚劣…など、本書で扱われてるテーマはどれも魅力的だが、特にローマ法大全の訳出作業に端を発し、ルターがその嚆矢となって革命を牽引した中世解釈者革命に関する著述は、そのままマクルーハンの記念碑的名著『グーテンベルクの銀河系』へと通じている。 娯楽としての読書からビブロフィリックな嗜好に至るまで、本書によって説明され得ることは多いだろう。それはこの本が「本」という壮大な試みに対する一つの書評であり、あとがきであるからだ。 本書で佐々木中に触れた誠実な読者は、きっと彼の主著『夜戦と永遠』をも手に取ることになるだろう。大部である。難解である。しかし、読まずにはいられないはずだ。それもまた一つの宿命である。 ちなみに、この本の文庫化は無いという。佐々木本人が本書の装丁をいたく気に入っており、曰く、内容同様に多くのものを語っているから、ということらしい。随分と頑固だとも思うが、しかしなるほど、白い紙を湛える焔のような紅は、確かに、とても美しい。
Posted by
読書とは革命である。 その言葉にとても強さを感じた。 日本人は無宗教の人が多いとよくいうがそんなことはないという意見がとても心に残っている。 難しそうなのにとても読みやすかった。
Posted by
「読書」と「思想」と「革命」についての本。 読む前は敷居が高いなーって思ってたけど、内容はそれほど難しくなく、読了後はやる気さえ出てきたような気がする。 「革命の本体、それは文学なのです。暴力など2次的な派生物に過ぎない。」 「本を読むという事は、下手すれば気が狂ってもお...
「読書」と「思想」と「革命」についての本。 読む前は敷居が高いなーって思ってたけど、内容はそれほど難しくなく、読了後はやる気さえ出てきたような気がする。 「革命の本体、それは文学なのです。暴力など2次的な派生物に過ぎない。」 「本を読むという事は、下手すれば気が狂ってもおかしくない。」 などなど、印象的な文も多かった。 終始圧倒され、衝撃を受けた。 そもそもこの本を読む人って、「読書=アイデンティティ」みたいな人が多いと思う。 そーゆー人が読んだら、必ず何かしらの影響を受けるような気がする
Posted by