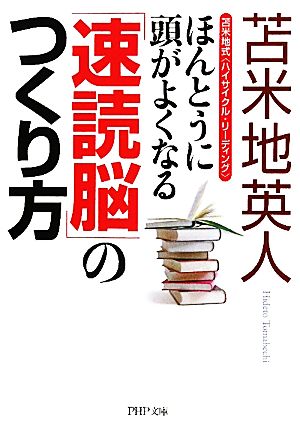ほんとうに頭がよくなる「速読脳」のつくり方 の商品レビュー
「速読」のお題で、ここまでユニークな論を展開できるとは。 「イメージ力の重要性絵を繰り返し訴えるとともに、最終奥義として別人格を獲得。さらには世界を平和にする方法まで」書かれている(笑)。 「読む本のジャンルは、小説がベスト」と書いてるのが意外だった。立花隆とかは、小説読むの...
「速読」のお題で、ここまでユニークな論を展開できるとは。 「イメージ力の重要性絵を繰り返し訴えるとともに、最終奥義として別人格を獲得。さらには世界を平和にする方法まで」書かれている(笑)。 「読む本のジャンルは、小説がベスト」と書いてるのが意外だった。立花隆とかは、小説読むのは時間の無駄と言ってたと思う。 読んでる行の1行先を意識に上げる、というのは、いま読んでる行に集中しないためには有効かもしれない。
Posted by
私は「速読」についてかなり不信があるというか、そんなことしてなんの意味があるの?というスタンスであり、この本を取った理由が、反骨精神とどんな胡散臭いことが書かれているんだろー?という思いからであるのだが、良い意味で裏切られた。 この本を要約すると、速読する方法は「頑張って読むこ...
私は「速読」についてかなり不信があるというか、そんなことしてなんの意味があるの?というスタンスであり、この本を取った理由が、反骨精神とどんな胡散臭いことが書かれているんだろー?という思いからであるのだが、良い意味で裏切られた。 この本を要約すると、速読する方法は「頑張って読むこと」と書かれており非常に納得いくものだった。そうだよね、頑張って読むことって大事だよねと常々思っているので、それを推してる筆者とこの本の内容に好感が持てた。 速読する方法に興味ある方におすすめ
Posted by
後半、速読の話どこいったー!? いやでもおもしろい本でした。 苫米地さんって恐竜が好きなんですねきっと。 正直言って、今の僕のレベルではまだこの本の内容の半分もわかっていないと思います。 この著者ちょっと頭が良すぎる気がします。 これも多分知ってるか知ってないかだとは思うんですけ...
後半、速読の話どこいったー!? いやでもおもしろい本でした。 苫米地さんって恐竜が好きなんですねきっと。 正直言って、今の僕のレベルではまだこの本の内容の半分もわかっていないと思います。 この著者ちょっと頭が良すぎる気がします。 これも多分知ってるか知ってないかだとは思うんですけど…そう考えるとなんだかワクワクします。 コーチングに繋がる話(というかむしろコーチングから繋がってきてる話)もたくさんあってもっともっと知りたいと感じました。 また読み返します。
Posted by
速読から「豊かな人生の送り方」に話がつかながっていったのには驚いた。しかし、著者人格になりきって読むことや、二足のわらじで豊かな人生を構築することには、大きく頷ける内容でした。
Posted by
帯表 あなたの知らない世界が待っている! ドクター苫米地発の文庫書き下ろし! 一字一句飛ばさず読める 思考が加速化する 夢が実現する 帯裏 私は本書で、速く読んで内容を理解できる速読術のテクニックを公開しました。 それはこれからの日本は知識の差で、幸不幸が決まってくると思うからで...
帯表 あなたの知らない世界が待っている! ドクター苫米地発の文庫書き下ろし! 一字一句飛ばさず読める 思考が加速化する 夢が実現する 帯裏 私は本書で、速く読んで内容を理解できる速読術のテクニックを公開しました。 それはこれからの日本は知識の差で、幸不幸が決まってくると思うからです。 世の中で成功するか、しないかは誰にもわかりません。 しかし、知識がなければ絶対に成功しないということはいえるのです。 今回紹介したハイサイクル・リーディングは、そのあなたの成功に役に立つこととなるでしょう。 (「おわりに」)より 見返し ◎「速読」は、幸せな人生へのパスポート! ・本気で速読術を必要とする人たち ・内容を素早く理解する速読術 ・変わる情報収集法 ・速読術と脳機能活性化の関係 ・二つの人格で見る新しい世界
Posted by
2010年発売の速読本です。 この本を読んでからしばらく速読の事を考えた事は無かったがいつのまにか自分の読むスピードが上がってることに気がついた。 これは著者が言っているゲシュタルトが構築されてきたのか単純にボキャブラリーが増えて知識が上り、論理性が上がったのかは定かではない。 ...
2010年発売の速読本です。 この本を読んでからしばらく速読の事を考えた事は無かったがいつのまにか自分の読むスピードが上がってることに気がついた。 これは著者が言っているゲシュタルトが構築されてきたのか単純にボキャブラリーが増えて知識が上り、論理性が上がったのかは定かではない。 この本が様々な速読のための技術が解説されていて抽象化が苦手な方とか情報処理が得意でない方のための役に立てる書籍だと思います。 文庫なので価格も安くコストパフォーマンスに優れています
Posted by
「ゲシュタルト構築」という表現がとってもしっくりきました。 ーーーーーーーー 筋トレをする時に、動かす筋肉の名前と働きを知り、その部分を使うことを意識するのが効果的なのと同じく、 読書中、次の行を意識下から上にあげてくることを意識する(→自分で普段のRAS(網様体賦活系)の...
「ゲシュタルト構築」という表現がとってもしっくりきました。 ーーーーーーーー 筋トレをする時に、動かす筋肉の名前と働きを知り、その部分を使うことを意識するのが効果的なのと同じく、 読書中、次の行を意識下から上にあげてくることを意識する(→自分で普段のRAS(網様体賦活系)の働きを操作できる)ことは、かなり重要なこと。ハイサイクルと同じく、速読の第一歩だと思います。 (ちなみに言うと、RASを知れば、気分が落ち込んだりぐるぐる考えてしまう時などに、うまくセルフコントロールできるようになるのではないかと思います。) 啓発本などには、こうすればいい!という内容がたくさん載っていますが、苫米地さんのこの本は科学的な説明がされていてその根拠が腑に落ちました。年単位で時間はかかると思いますが、実践後効果を感じられたら、またここに返信の形で書きたいと思います。 ーーーーーーー スキルを得る本については、実践した人に何らかの効果はあったか、あるいは変化がなかったか、という情報があれば、もっと実践しやすくなると思います。実践した人のもともとの状態、そして読後実践した後に感じる変化を、共有できればと思います。 腑に落ちたら、行動あるのみ!
Posted by
中々に尖った人材で、切り口鋭く身近にいたらお近づきになりたく無いタイプの人ではなかろうか。 本著は速読の本としては質の良いものだと思う。 情報量・知識量を高め、先読みし、クロックサイクルを上げることでハイサイクル・リーディングを身につける。よほど巷のハウツー本よりわかりやすい...
中々に尖った人材で、切り口鋭く身近にいたらお近づきになりたく無いタイプの人ではなかろうか。 本著は速読の本としては質の良いものだと思う。 情報量・知識量を高め、先読みし、クロックサイクルを上げることでハイサイクル・リーディングを身につける。よほど巷のハウツー本よりわかりやすい。
Posted by
2行読み、3行読み この本を1.5hで読むには、見開き1分 ハイサイクルトレーニング いつもより2倍の早さで読んでみる。他の行動も意識して速くする。 早口で本を読む ノンフィクションの方がトレーニングしやすい。 トレーニング方法 すべての行動を加速する 並列度を上げる メニュー1...
2行読み、3行読み この本を1.5hで読むには、見開き1分 ハイサイクルトレーニング いつもより2倍の早さで読んでみる。他の行動も意識して速くする。 早口で本を読む ノンフィクションの方がトレーニングしやすい。 トレーニング方法 すべての行動を加速する 並列度を上げる メニュー1秒決め 本の二冊同時読み 抽象度を上げる 読まなくていい本を見つける方法
Posted by
速読法の世界を脳神経学的に整理している。速読のためには、沢山の本を読み、速読に叶う予備知識を蓄えていることが根底には必要としている。巷で流行っている速読法は、潜在意識を利用したり、読み飛ばし的な読書法である。それでは文体を含めて読書の醍醐味や著者との対話に欠けてしまう。とても納得...
速読法の世界を脳神経学的に整理している。速読のためには、沢山の本を読み、速読に叶う予備知識を蓄えていることが根底には必要としている。巷で流行っている速読法は、潜在意識を利用したり、読み飛ばし的な読書法である。それでは文体を含めて読書の醍醐味や著者との対話に欠けてしまう。とても納得感のある説明だと思った。速読のコツは、意識的にクロックサイクルを早く上げて読み、さらに現在読んでいる文章の先読みを並行して行なうといういたってシンプルな手法であった。
Posted by