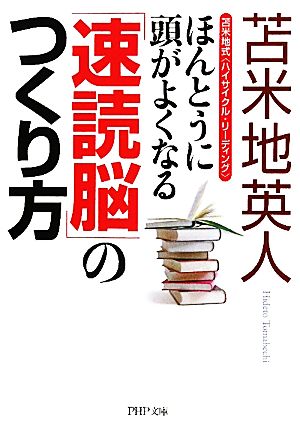ほんとうに頭がよくなる「速読脳」のつくり方 の商品レビュー
苫米地英人先生の本ということで購入。 「速読」について興味があったわけではなかったのだけども(かといって、全く興味がないわけではないが・・・)、苫米地論調が気に入っていたので手に取ってみた。 苫米地英人先生が在籍しておられたイエール大学大学院やカーネギーメロン大学大学院では、速...
苫米地英人先生の本ということで購入。 「速読」について興味があったわけではなかったのだけども(かといって、全く興味がないわけではないが・・・)、苫米地論調が気に入っていたので手に取ってみた。 苫米地英人先生が在籍しておられたイエール大学大学院やカーネギーメロン大学大学院では、速読を必須とする世界であったことが紹介されている。論文も含めて2000~3000冊の本を博士前期課程の2年間で読む必要があるから、1日30冊~50冊読まなければならない・・・とあるが、2年で2000~3000冊なのであれば、一日3~5冊の間違いか、あるいは2年で20000~30000冊という間違いなのか。いずれにせよ、苫米地先生は、読もうと思えば350ページの本を5分というスピードらしい(ゆっくり読む方がいいとも言っておられる)。 この本は、ただ早く読むためのハウツー本ではなくて、本を読む意義から丁寧に解説されている。 フォトリーディングやキーワードリーディングが主ではなく、『本は一字一句飛ばさずに読む。しかも早く読む』というスタンスでの読書法の紹介だ。 また、メディアリテラシーや人生論など、本を読むことに対する広い視野からの指摘がなされていて興味深く読めた。 ---------------- 【目次】 第1章 ハイサイクル・リーディングの世界 本気で速読術を必要とする人たち アメリカの大学院の厳しさ 速読術を人に教えるための最低限の資格 ほか 第2章 ハイサイクル・リーディングの技術 内容を素早く理解する速読術 読まなくていい本を見つけるための方法―フォトリーディングとキーワードリーディング 第3章 まもなく始まる情報革命 メディアの一大変革―キンドルとiPad 日本の電子書籍化の現実 電子化で滅びたアメリカの新聞業界 ほか 第4章 活性化した脳機能で夢を掴む 速読術と脳機能活性化の関係 イメージは正しく使う 成功のイメージのつくり方―脳は最高の献身をしてくれる ほか 第5章 お金の奴隷をやめよう!―究極の「二足のワラジ」 究極のイメージのつくり方 二つの人格で見る新しい世界 25世紀のために ----------------
Posted by
部分的には、まともなことも書いていたけど、話飛びすぎ、文章やっつけで書きすぎ。。まず読者の8割くらいが留学していた二年間に2000〜3000冊、つまり一日に30から50冊読まなければならなかったというところに気づかないんだろうな。その計算なら一日に3冊程度だろう。
Posted by
色々、速読本読んできたけど、それらで疑問に感じてた部分にかなりの部分答えてくれた、そんな速読本。 他の速読本を一通り読んでからこれを読むとより良いかもしれない。 他の速読法のウソ、を教えてくれる。 たしかにフォトリーディングやキーワードリーディングは使えるけれど、あまり実用的では...
色々、速読本読んできたけど、それらで疑問に感じてた部分にかなりの部分答えてくれた、そんな速読本。 他の速読本を一通り読んでからこれを読むとより良いかもしれない。 他の速読法のウソ、を教えてくれる。 たしかにフォトリーディングやキーワードリーディングは使えるけれど、あまり実用的ではない。 この本の中で紹介されている「先読み」というテクニック。次の文章を目にいれながら読んでいくという方法なんだけれど、これは他の本でもちょろっと紹介されていたりする。 けどこの本ではその方法の重要性とか、より具体的な方法がかなり短く、かつ簡潔に書かれてるから非常に良い。 ただ、他の部分に関していうと、前半100Pが速読法、後半100Pは人生観だとか、ちょっとマクロな視点というか、話が肥大するんで、一般の速読本よりは内容薄い。しかし他のどの速読本よりも説得力あるのは確か。 なのでまずは他の速読本読んで、それからこの本読んでみてほしい。
Posted by
読みたい本は山のようにあるですが、読書に当てられる時間が通勤時間と週末の限られた時間なので、速読したいという気持ちは常に持っています。 私が速読した場合、重要だと思われる情報を拾い上げるような読み方(スキャニング)になってしまうので、細かい点まで把握することは難しくなっていまし...
読みたい本は山のようにあるですが、読書に当てられる時間が通勤時間と週末の限られた時間なので、速読したいという気持ちは常に持っています。 私が速読した場合、重要だと思われる情報を拾い上げるような読み方(スキャニング)になってしまうので、細かい点まで把握することは難しくなっていました。 そのような私にとって、この本の帯に書いてあった「一字一句飛ばさずに読める」というのは十分に魅力的なフレーズでした。 また、この本を読む前から理解していましたが、速読を可能にする最大の条件は、読者がもともと持っている知識量(p35)であるとのことです。 「1行目を読んでいるときに2行目を意識する」という点をマスターしただけでも読むスピードが上がりそうだと思いますので、今後の読書で試して自分のスタイルを築いていく予定です。 速読のメリットは、何冊も著者の本を読むことで、著者の考え方と自分の考え方の複数の世界を持つことができるということが、私がこの本で得た最大の収穫でした。 以下は気になったポイントです。 ・読書には単なる情報収集以上の知的好奇心を満たすものがあり、新たな英知を発見する感動があるはず、人生を豊かにして、あなた自身を成長させる「きっかけ」を与えるのが読書をするという行為(p4) ・1か月に1冊の本も読まない人が全体の46%もいる、1-2冊程度が36%、3-4冊が10%、であることから、月に3冊読めば読書家という部類になる(p50) ・年収800万円以上の人は本代(月額購入費)は2910円、400-800万円:2557円、400万未満:1914円であり、読書量は年収に正比例する(p54) ・先読みの方法は、1行1行、目で追うのではなく、2行目も意識すること、あなたが文字を読むとき、読んでいる行だけが網膜に映っているのではなく、左右2、3行分は目に入っている(p59) ・1行読みをマスターする前は、1行を上中下の3つのパートにわけて読むこと(p61) ・言葉を読み上げた瞬間、その意味が脳内でイメージできるようにするのが早読みの目的、そのためには多くの本を早読みすべき(p69) ・脳内のイメージを「見たもの」とハイパーリンク化させるために、色や感覚(硬い、柔らかい等)のイメージ化をしておくと、見たものを感覚でとらえられるようになる(p90) ・フォトリーディングは、読まなくてもいい本を見つける、読むべき本を発見するためのフィルターとして使うテクニック(p108) ・読んでいてつまらないと思った本は速読できない(p114) ・知識とは、データとデータを意味づけしてつなげる力(認識力)である、同じデータを持っていても、関連付ける力がなければ知識にならない(p134) ・成功イメージの作り方は、基本は、自分が成功した姿を具体的にイメージすること(p154) ・あなたの会社が扱っていない商品を、会社が旬出する可能性のない国にいかに売るかをイメージする(p167) ・速読(ハイサイクル・リーディング)で何冊も本を読むと、著者になりきることが可能になり、著者の視点で物事を見聞きして判断することができる、それと同時にもともとの人格での判断も同時にでき、2つの世界を獲得したことになる(p196) 2011年10月30日作成
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
速読できるようになる→IQが上がる→高まったIQで世界平和について考えよう!と言う壮大な一冊。今まで読んだ速読本の中では私的に1番読むのが早くなったのがこの本で挙げられている「先読み」の技術でした。少し速度を上げたいな、と思っている人ならお勧め。フォトリーディングや視野を拡げたりするトレーニングよりも地味だけど現実的です。
Posted by
知識量が基礎になければ速読はできない。ただ、脳機能を活性化させることで速読を実現するテクニックは身につける事はできる。「イメージする力」が全てを叶える基礎となるっとまとめる苫米地さんの思考は刺激的。初、彼の本デビュー!
Posted by
6/14借。昔から興味があった速読。何冊か速読本を買ってみたことはあるが漠たる不安と疑問が残っていた。それがこの本で解消されつつある。やはり速読の前提として知識(量)が必要。文章のイメージ化も不可欠。フォトリーディングを単に批判するだけでなく、その使い道にも言及。懐も深い。
Posted by
3回読んだ。 早く読もうと意識すること。 読んでいる行の前も視界に入れ、先読みすること。 前提となる知識の強化。 一番頭をきたえるのによい読み物は小説。
Posted by
はじめに書いてしまうと「速読術」の本ではない 速読のテクニックらしきものも一応は紹介されているけど「何だ、そうだったのか」と拍子抜けしてしまいます 本書は全5章構成となっています 第1章「ハイサイクル・リーディングの世界」は著者が速読出来ることでどれだけ素晴らしい成果をあげたの...
はじめに書いてしまうと「速読術」の本ではない 速読のテクニックらしきものも一応は紹介されているけど「何だ、そうだったのか」と拍子抜けしてしまいます 本書は全5章構成となっています 第1章「ハイサイクル・リーディングの世界」は著者が速読出来ることでどれだけ素晴らしい成果をあげたのかの自慢話 第2章「ハイサイクル・リーディングの技術」は速読のテクニック解説 しかし特別この本でないと体得できないものも感じられません そして3章以降は速読と関係ない話が展開されていきます 本のタイトルから遠く離れた内容に進んでいき最後に速読と結びつけていますが話題が飛躍し過ぎでまとまりがない 再読して気付いた第2章の最後の一説 「自分の成長を感じるうえでも、つまらないと思った本はいったんやめ、面白い本を探すことをお勧めします。」 …と読んだ時に「何だ、そうだったのか」と拍子抜けしてしまいました
Posted by
「ほんとうに頭がよくなる「速読脳」の作り方」 アメリカの大学では、毎日数十冊の本を読みこなさないと 授業について行けないという。多くの本を読みこなすことによって 速読の力もついてくるのだ。 知識がないと速読はできない。多くの知識があるからこそ その行のさきに何...
「ほんとうに頭がよくなる「速読脳」の作り方」 アメリカの大学では、毎日数十冊の本を読みこなさないと 授業について行けないという。多くの本を読みこなすことによって 速読の力もついてくるのだ。 知識がないと速読はできない。多くの知識があるからこそ その行のさきに何が書かれているかが読めるのである。 本を読まない人が多い今日。月4冊読むだけで、情報勝者になれる。 速読は読まなくてもよい本を見つけることに意義がありそうだ。
Posted by