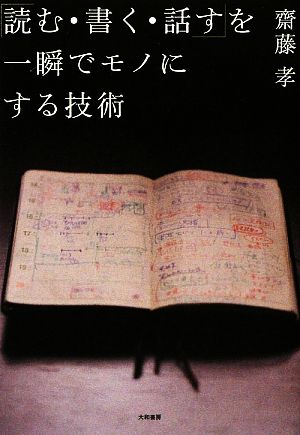「読む・書く・話す」を一瞬でモノにする技術 の商品レビュー
・読書の3色ボールペン活用術 青→客観的に見て重要な場所 赤→客観的に見て最も重要な場所 緑→主観的に見て自分がおもしろいと思った場所(反発・興味など) ・読書は買ったその日が最高の読書チャンス ・一人ひとりの暗黙知をグループ→会社 ・自分の言葉で再生できれば、情報を自分化した...
・読書の3色ボールペン活用術 青→客観的に見て重要な場所 赤→客観的に見て最も重要な場所 緑→主観的に見て自分がおもしろいと思った場所(反発・興味など) ・読書は買ったその日が最高の読書チャンス ・一人ひとりの暗黙知をグループ→会社 ・自分の言葉で再生できれば、情報を自分化した。 ・見えない真意を汲み取り、イマジネーションを広げる。 ・批判を先立たせない、はじめから批判しない。 ・ひとつの批判、考え方の中には必ず対比が隠れている→視点移動
Posted by
どんなにコンピューターが進歩しても、情報を組み合わせたり、ある角度でまとめたり、さらにはそれを進化させ、同時に進化も進め、人間性の形成に組み込んでゆくことは人間には敵わないのである。 わずかずつでも、確実に自己形成を実現させるには、自分の頭に情報を蓄え、良質のデータベースを築き上...
どんなにコンピューターが進歩しても、情報を組み合わせたり、ある角度でまとめたり、さらにはそれを進化させ、同時に進化も進め、人間性の形成に組み込んでゆくことは人間には敵わないのである。 わずかずつでも、確実に自己形成を実現させるには、自分の頭に情報を蓄え、良質のデータベースを築き上げることだ。 そのためには読書が効果的であり、得た知識で自分の頭の中を検索できるようになると、コメント力や話す力も鍛えられる。 読書法にも工夫が必要だ。
Posted by
知的生産術についての本。昨今のネット検索→コピペですませるようなレポートを嘆き、情報の氾濫している世の中だからこそ、自分をくぐらせて独自の視点・編集したアウトプットが重要なのだ、と。その知的生産術についてのヒントを書いている。 要はやっぱり「編集」なんだなぁ、と思った。 あと、自...
知的生産術についての本。昨今のネット検索→コピペですませるようなレポートを嘆き、情報の氾濫している世の中だからこそ、自分をくぐらせて独自の視点・編集したアウトプットが重要なのだ、と。その知的生産術についてのヒントを書いている。 要はやっぱり「編集」なんだなぁ、と思った。 あと、自分は「コメント力」なんてあんまり関係ないかなぁと思ってたけど、これすなわち知的生産力、と。訓練が必要なのだと少し反省。
Posted by
◎ 「重要なことは、けっして使い尽くすことのない資本をつくることだ(=「知の資産」、ゲーテ)」(49頁) 生産性を上げるには「時間の密度感覚」が不可欠(91頁) リスペクトできる脳内スタッフを3人ぐらい持つと、偏らず、一貫性がありながら、バランス感覚もある考え方ができるように...
◎ 「重要なことは、けっして使い尽くすことのない資本をつくることだ(=「知の資産」、ゲーテ)」(49頁) 生産性を上げるには「時間の密度感覚」が不可欠(91頁) リスペクトできる脳内スタッフを3人ぐらい持つと、偏らず、一貫性がありながら、バランス感覚もある考え方ができるようになる(129頁) ・偉大な先行者を見つけ、そのひとの世界を完全吸収しようというくらい相手を知り、ことあるごとに、彼らならばどう考えただろう、というように引き寄せて考える。 鵜呑みにした情報はどうしても吸収性が低い。「ここは、おかしいんじゃないか」とところどころにクエスチョンマークを付けながら読んでいく(130頁) 共感と批判。順番を間違えない(132頁) 「3色記憶法」(144頁) 青・・・客観的に見て、まあ重要な箇所 赤・・・客観的に見て、最も重要な箇所 緑・・・主観的に見て、自分がおもしろいと感じたり、興味をいだいたりした箇所 ・スケジュールにも応用できる。枠で囲うことがポイント。準備時間も意識。 ・予定のない時間、自分で好きに使える時間を緑で囲む。メリハリをつける。 どう頭をひねっても、誰でも思いつきそうな企画しか出てこないという人は、日頃から情報に緑色をつけることに長けていない。情報を読んでいるとき、自分の感性をうまく羽ばたかせることができない(152頁) ○ 自分検索トレーニング 「自分の好きな映画ベスト3は何か」とか「自分を伸ばしてくれた言葉を、出来事とともに思い出してみよう」などと自分に問いかけ、短い時間内にさぁーっと書き出すというようなことをやってみる(43頁) 「サーチライト読み」問いのラインナップをつくる(80頁) ・サーチ力を鍛えるためには、常に問いをたくさんもっておくこと。心に引っかかる。 誰かに「話す」という機会をつくる(同期、勉強会)(93頁) 読みながら、ここは大事だと思う言葉に出会ったら、その言葉と、出てきた頁を書き出しておく(103頁) ・キーワードで本全体を要約できるようにする ・表紙裏に書き出す 目次を拡大コピーし、書く項目の要点を書き込む(106頁) 手帳を眺める(162頁) ・ある仕事に費やすことができる時間をぱっと読み取り、加速の度合いを調整することは、質的にも量的にも仕事をこなす力をぐんと伸ばす。 紹介された情報はその場で書きとめる(163頁) ・人名、事柄、日付をセットで記憶することを習慣づける スケジュール帳、ノート1冊。ノートには日付を書き込む(186頁) ・スケジュール帳のフリースペースはアイデアメモ書き。 ・決定事項は、レジュメ等に書き込む。 ● 検索はしない→する情報、時間を限定する。 自分の頭や感性を鍛えながら、高密度の情報データソースを自分の頭の中につくる。(27頁) 「YOUたち、仕事のことでケンカするなんて、かっこいいね」(35頁) ・個人意識とグループ意識を共存 ・ケンカの原因、ケンカの大本を指摘 ・届く言葉でほめる ・整理し、記憶するには、相手に問いかける形のほうがいい(54頁)「そのとき社長はなんて言った?」 情報にもニオイがある → 五感を働かせてひきよせることが重要。(58頁) 理解するのには、「わかるなぁ」という感じが大きな役割を果たす(113頁) ・自分の経験に関連づける ・経験は最高の説得力を持っている(197頁) 企画書を書く場合は、プラスのポイントばかりを書くのではなく、マイナスも書くべき(200頁) ・リスクを認識し、回避を考える。 違和感を持ちながら、時間を過ごしていると、いつもどこかにその違和感が働いていて、思いがけないタイトルを引き寄せてくるものだ。違和感こそ鋭い感度を持つ、情報アンテナ(203頁)
Posted by
■情報術 1.情報をひきよせるアンテナは、課題を持ち、それを考えていると、しだいに立ってくるものだ。 2.自分の中の情報をひきだす作業、すなわち、検索をしなければ、情報を収集しておこうという気持ちも刺激されない。 3.学術書や実用書など知識を主体にした本、情報を提供してくれる本は...
■情報術 1.情報をひきよせるアンテナは、課題を持ち、それを考えていると、しだいに立ってくるものだ。 2.自分の中の情報をひきだす作業、すなわち、検索をしなければ、情報を収集しておこうという気持ちも刺激されない。 3.学術書や実用書など知識を主体にした本、情報を提供してくれる本は、目次はその本の中身を表すガイドマップになっている。 4.雑誌の記事を一つ読んだら、何か一つ、アイデアを思いつくことを自分に課す。手帳のフリースペースに何かテーマを書き、時間があるときには、そこにどんどん、そのテーマから思いつく企画を書いてていく。
Posted by
齋藤 孝先生著作の本は自分に合っているので、迷わず読む。憑依するほどにのめり込むように、といアドバイスはさすが!
Posted by
齋藤先生がこれまでに出した「読む」「書く」「話す」技についての書籍を一冊にまとめた内容。 渾身の決め台詞はなかったけれど(大方は既出)、ぴぴっときたのはこれ。 本は泥を黄金の雲に変える。 先生の表層意識でさらっと書き流したものなので、突きつけられるような迫力は残念ながらなし。...
齋藤先生がこれまでに出した「読む」「書く」「話す」技についての書籍を一冊にまとめた内容。 渾身の決め台詞はなかったけれど(大方は既出)、ぴぴっときたのはこれ。 本は泥を黄金の雲に変える。 先生の表層意識でさらっと書き流したものなので、突きつけられるような迫力は残念ながらなし。 ハック系として読むなら悪くない。
Posted by
インプット力、アウトプット力を高めたいと思って、ここ数年何十冊も見てきましたが、 今週は斉藤孝氏のこの本を手に取ってみました。 構成は、 1:選ぶ力をつける5つの手法(日頃の自分の問題意識、情報との出会い(一期一会)) 2:本をとことん使う7つの手法(自分の型が出来るまで読み込...
インプット力、アウトプット力を高めたいと思って、ここ数年何十冊も見てきましたが、 今週は斉藤孝氏のこの本を手に取ってみました。 構成は、 1:選ぶ力をつける5つの手法(日頃の自分の問題意識、情報との出会い(一期一会)) 2:本をとことん使う7つの手法(自分の型が出来るまで読み込む) 3:記憶を深める5つの手法(自分の言葉で再生) 4:道具を使いこなす5つの手法(色分け、手帳への応用、スケジューリング・ファイリング、ノート術) 5:編集力をつける3つの手法(自分との経験とからみ合わせる、編集力、人からの情報) となっております。 斉藤孝氏の頭の整理のされ方、良さはかなわない、とテレビを見てても思うわけですが、 ここまで至るには相当苦労されて現在のスタイルを気付きあげたことが分かります。 全てを真似するわけでなく、この中から少しでも自分にフィットしたことを実際行動することが大切なのだと 思いました。 とにかく気になったことはメモするようにされているそうですが、そのメモを見て、私もぴぴっときたことを 2つメモしておきます。 ・ジャニーズ事務所の若いタレントたちが、コンサート前に喧嘩をしていた際のこと。 ジャニー喜多川社長が通りがかり、「YOUたち、仕事のことで喧嘩するなんて、かっこいいね」と言って去った。 ・プロデユーサー小林武史氏は、多くのアーティストの卵を見ていくことで、 「この人はどんな音楽スタイルにして、どのように育てるといちばんよく伸びるか、世の中にフィットするか ほとんど瞬時にわかる」そうです。
Posted by