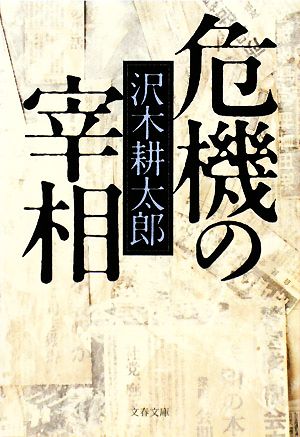危機の宰相 の商品レビュー
沢木耕太郎は深夜特急しか読んだことがなかったので、池田勇人を支え日本の高度経済成長を支えた田村敏雄、下村治の物語は当時の時代のワクワクするような雰囲気を感じながら(難しさも感じながら)楽しく読むことができた。 しかし、この本の素晴らしさは、下村治の息子の下村泰民が書いた「解説 ...
沢木耕太郎は深夜特急しか読んだことがなかったので、池田勇人を支え日本の高度経済成長を支えた田村敏雄、下村治の物語は当時の時代のワクワクするような雰囲気を感じながら(難しさも感じながら)楽しく読むことができた。 しかし、この本の素晴らしさは、下村治の息子の下村泰民が書いた「解説 父が見た「危機の宰相」」にあるのではないだろうか?この本の見事なサマリーであるだけでなく21世紀の世界においてこの本がどのように受け入れられているかを見事に解き明かしていると感じた。 この文章により、もう一度読んでみたいという気持ちが非常に高まった。
Posted by
「沢木耕太郎」が、「池田勇人(はやと)」の経済成長テーマだった「所得倍増」を巡るプロセスを描いたルポルタージュ作品『危機の宰相』を読みました。 「城山三郎」が78歳で国鉄総裁になった「石田礼助」の人生を描いた作品『粗にして野だが卑ではない―石田礼助の生涯』を読んだのですが、「石...
「沢木耕太郎」が、「池田勇人(はやと)」の経済成長テーマだった「所得倍増」を巡るプロセスを描いたルポルタージュ作品『危機の宰相』を読みました。 「城山三郎」が78歳で国鉄総裁になった「石田礼助」の人生を描いた作品『粗にして野だが卑ではない―石田礼助の生涯』を読んだのですが、「石田礼助」を国鉄総裁に強く推薦したのは「池田勇人」だったんですよね… そんなこともあり、本書を選択、、、 「沢木耕太郎」作品は、8月に読んだ『檀』以来なので、約1ヶ月半ぶりですね。 -----story------------- あの時、経済は真っ赤に熱をはらんでいた 安保闘争の終わった物憂い倦怠感の中、日本を真っ赤に燃え立たせる次のテーマ「所得倍増」をみつけた3人の敗者たちのドラマ 1960年、安保後の騒然とした世情の中で首相になった「池田勇人」は、次の時代のテーマを経済成長に求める。 「所得倍増」。 それは大蔵省で長く“敗者”だった「池田」と「田村敏雄」と「下村治」という三人の男たちの夢と志の結晶でもあった。 戦後最大のコピー「所得倍増」を巡り、政治と経済が激突するスリリングなドラマ。 ----------------------- 1977年(昭和52年)7月に『文藝春秋』で発表された作品に300ページ近くの加筆をして2006年(平成18年)に単行本として刊行された作品の文庫化作品です。、、、 宰相「池田勇人」とブレーン「下村治(エコノミスト)」、「田村敏雄(宏池会事務局長)」… 彼らの大蔵省での敗者(ルーザー)としての軌跡を追いながら、「所得倍増」と言う夢を如何にして現実させたのかがのプロセスが克明に描かれた作品です。 ■序章 ささやかな発端 ■第一章 黄金時代 ■第二章 戦後最大のコピー ■第三章 第三のブレーン ■第四章 敗者としての池田勇人 ■第五章 敗者としての田村敏雄 ■第六章 敗者としての下村治 ■第七章 木曜会 ■第八章 総理への道 ■第九章 田文と呉起 ■第十章 邪教から国教へ ■第十一章 勝者たち ■第十二章 やがて幕が下り ■終章 世界の静かな中心 ■あとがきⅠ ■あとがきⅡ ■主要参考文献 ■解説 父が見た「危機の宰相」 下村恭民 政治と経済… うーん、個人的に苦手な二大テーマなので、ちょっと辛かったですね、、、 でも、1960年(昭和35年)の日米安保という時代に「岸内閣」の後を受けて組閣され、1964年(昭和39年)の東京オリンピックの時代に幕を閉じた「池田内閣」において、「池田勇人首相」と、そのブレーン「下村治」、宏知会事務長「田村敏雄」の三人に焦点をあて「所得倍増計画」というのは何だったのか、この政策がいかにして生まれ、日本の高度経済成長をどのように導いていったのかについて、理解を深めることができた作品でした。 自分が体験していない時代だし、歴史の教科書ではほとんど学んでいない時代なので、ほとんど知識がない時代なんですよね、、、 戦後の復興期のあと、自然体やなりゆきで高度成長期があったわけではなく、彼等の理念や夢や志が政策を生み出し、それに国民が共感することが高度成長を促すことになったんでしょうね… 勉強になりました。 また、三人とも大蔵省官僚としては不遇な道を辿り、それぞれ業病と闘い、捕虜生活に苦しみ、死病に苦しんだ経験があり、キャリアと人生において大きな挫折を経験した敗者(ルーザー)であったという共通点も運命を感じますよね、、、 『海賊とよばれた男』、『粗にして野だが卑ではない―石田礼助の生涯』に続き、明治人の気骨が感じられる作品でした。 経費をプライベートなことに流用して、必要経費だと説明するような現在の政治家とは違うよなぁ。
Posted by
難しかった。 上昇期の日本。向かっていく方向をハッキリ示せるリーダーと、優秀なブレーンがいたということか。
Posted by
そんなにこの作家の経歴を知らないので、ほー、こんなところに手を出してたのか、と意外感あり。そしてそこから本能的になのか、その筋には進まなかったことも妙に納得。 ともあれ内容はなかなか面白いです、そして分かってはいるけれどもますます日本は斜陽なんだな、、、と得心する次第です。
Posted by
深い本だった。10年ほど前、異国に住んでいた時に途中まで読んでいたが読了できていなかった。今回は約4日間で読了。引き込まれるように読み進めた。直前に読んだ「テロルの決算」とほぼ同時代。関連性もあり、より興味を惹いた。1960年を中心に、総理大臣とそのブレーン的存在2人の3人が主人...
深い本だった。10年ほど前、異国に住んでいた時に途中まで読んでいたが読了できていなかった。今回は約4日間で読了。引き込まれるように読み進めた。直前に読んだ「テロルの決算」とほぼ同時代。関連性もあり、より興味を惹いた。1960年を中心に、総理大臣とそのブレーン的存在2人の3人が主人公。発表は1977年の「文芸春秋」誌。単行本化はその29年後の2006年。発表時、そして刊行時は、その業界では話題になったようだ。あとがきにすごく重要なことが書かれている。「文芸春秋」への発表直後、「危機の宰相」の方向に向かうか、「一瞬の夏」の方向へ向かうかの分かれ道があったらしい。結局「一瞬の夏」の方向に向かい、その選択は読者である私にとってもよかったと思うが、「危機の宰相」の方向に進んでいたらそれはそれで楽しめたと思う。政治家について詳しくなかったがすごく興味を持った。かつて立派な政治家がいたことがよくわかる。今の政治家でこの本を読んでいる人はどれだけいるのだろうか?そういう人はどのように感じるのだろうか?沢木さんが今の政治家について書くとしたら、どんな感じになるのだろうか、興味はつきない。取材などは相当に大変だと思うが今の政治家についてもぜひ書いてほしいと思ったりした。
Posted by
解説にもあったが、日本という国の青春の本。 その意味では、坂の上の雲に通じる。 富国強兵と所得倍増計画。 しかし、池田勇人についてほとんど知識がなかった。 少なくとも本作では理想的な保守政治家として描かれており、非常に魅力的な宰相だが、吉田茂、田中角栄はもちろん、岸信介、佐藤栄...
解説にもあったが、日本という国の青春の本。 その意味では、坂の上の雲に通じる。 富国強兵と所得倍増計画。 しかし、池田勇人についてほとんど知識がなかった。 少なくとも本作では理想的な保守政治家として描かれており、非常に魅力的な宰相だが、吉田茂、田中角栄はもちろん、岸信介、佐藤栄作などよりも知名度は低い。 それ自体が、この国の知的な悲劇だと思う。
Posted by
令和になって読んでもっとも驚くのは、こんなふうに情熱をもって、「尽忠報国」の精神で働ける政治家がちゃんと日本に存在していたのだということ。 いまの政治家の実情を知っているわけではないが、そんな姿勢でまつりごとをしていれば絶対にこんなふうにはならないのではないかと、思えてならない。...
令和になって読んでもっとも驚くのは、こんなふうに情熱をもって、「尽忠報国」の精神で働ける政治家がちゃんと日本に存在していたのだということ。 いまの政治家の実情を知っているわけではないが、そんな姿勢でまつりごとをしていれば絶対にこんなふうにはならないのではないかと、思えてならない。 下村治のゼロ成長理論への転換と、三島由紀夫の「世界の静かな中心であれ」を絡めた段には、常々自分が感じていることに非常に近いことがらが語られていたことにも膝を打つ思いがした。 経済大国であるという誇大妄想、これからも「高度成長」できるという嘘をかがげながら権力闘争に明け暮れる政治屋たち、「終活」を考える気のないこの国で自分たちはどう生きるべきなのか、今一度歴史に学ぶべきなのかもしれない。
Posted by
▼1960年の安保闘争の終盤。首相だった岸信介さんは、私邸をデモ隊に何重にも包囲されてしまいました。そして、防衛庁長官の赤城宗徳さんを呼びつけ、自衛隊の出動を要請。しかし、赤城さんがこれを断固拒否。「日本人同士を戦わせて、流血するわけにいかない」。▼沢木耕太郎さんは、この時に自衛...
▼1960年の安保闘争の終盤。首相だった岸信介さんは、私邸をデモ隊に何重にも包囲されてしまいました。そして、防衛庁長官の赤城宗徳さんを呼びつけ、自衛隊の出動を要請。しかし、赤城さんがこれを断固拒否。「日本人同士を戦わせて、流血するわけにいかない」。▼沢木耕太郎さんは、この時に自衛隊が首相を守るため、という大義名分でデモ隊と戦っていたら、その後の政治は決定的に変わっていただろう、と述べています。恐らく自民党政権は遠からず倒れ、所得倍増計画も無かったことになります。ちなみに岸信介さんは、弟が佐藤栄作首相。娘婿が安倍晋太郎首相。孫が現在の安倍晋三首相。うーん。身分制度?歌舞伎?▼「危機の宰相」沢木耕太郎。1977年に雑誌掲載、単行本は2006年。文春文庫。「所得倍増」を担った、政治家・池田勇人、官僚・下村治、田村敏雄という3人の主人公の履歴足跡人間を描きながら、「所得倍増」というドラマを戦前からの近代史の中で描いたもの。▼言ってみれば自民党の戦後政策を賛美する内容、とも言えますが、きちんと読んでみればそういう狙いの本ではありません。日本の近現代史、そして評伝ノンフィクションとして、えらいこと面白かったです。▼本筋と関係ないですが、池田首相と担当の新聞記者たちの関係で、「記者たちが首相のエッセイや論文のゴーストライターをやっていた」という記述が。やっぱりなあ。
Posted by
池田勇人を支えた人物にも焦点をあてたドキュメントです。 池田総理の所得倍増計画と田中角栄の日本列島改造って夢がありましたよね。
Posted by
1964年の東京オリンピックを頂点とした日本の高度経済成長の立役者は、時の内閣総理大臣【池田勇人】(1960年7月から4年間在位)であった。京都帝国大学法学部を卒業後、大蔵省で税務署長として地方廻りをするが、奇病(落葉性天疱瘡)にかかり7年間の闘病生活を余儀なくされる。偶然にも大...
1964年の東京オリンピックを頂点とした日本の高度経済成長の立役者は、時の内閣総理大臣【池田勇人】(1960年7月から4年間在位)であった。京都帝国大学法学部を卒業後、大蔵省で税務署長として地方廻りをするが、奇病(落葉性天疱瘡)にかかり7年間の闘病生活を余儀なくされる。偶然にも大蔵省に復職、その14年後には政界入りを果たす。池田内閣時代の経済成長の影では、浅沼稲次郎刺殺事件、『風流夢譚』掲載の嶋中邸襲撃事件、ライシャワー大使刺傷事件、大規模鉄道事故、炭鉱ガス爆発事故、ケネディ大統領暗殺事件等が起きている。
Posted by