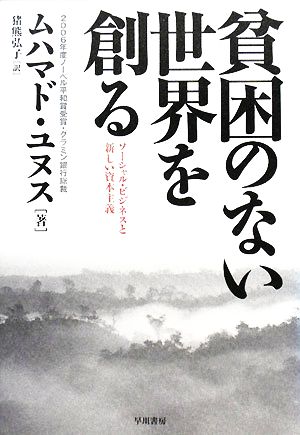貧困のない世界を創る の商品レビュー
かの有名なマイクロクレジットの最初、グラミン銀行を作った方の本です。 この人、ただの銀行マンかと思いきや、それ以前に経済学者だったんですね。 本書は銀行の経営についての本ではなく、貧困経済について語った本になっています。 そこには多くの知らないことが語られており非常に参考になりま...
かの有名なマイクロクレジットの最初、グラミン銀行を作った方の本です。 この人、ただの銀行マンかと思いきや、それ以前に経済学者だったんですね。 本書は銀行の経営についての本ではなく、貧困経済について語った本になっています。 そこには多くの知らないことが語られており非常に参考になりました。
Posted by
マイクロクレジット(無担保少額融資)で農村部の貧しい人々の自立を支援する手法で、バングラデシュの貧困削減に大きく貢献し、2006年にノーベル平和賞を受賞した、ムハマド・ユヌス氏の著作。 株主の利益の最大化ではなく、社会的利益の最大化を目標とする「ソーシャル・ビジネス」により、...
マイクロクレジット(無担保少額融資)で農村部の貧しい人々の自立を支援する手法で、バングラデシュの貧困削減に大きく貢献し、2006年にノーベル平和賞を受賞した、ムハマド・ユヌス氏の著作。 株主の利益の最大化ではなく、社会的利益の最大化を目標とする「ソーシャル・ビジネス」により、会社を持続可能にする収益を保ちながら社会貢献ができるという形態で、CSR(企業の社会的責任)や慈善事業とは異なる概念である。 フランスの食品メーカーダノン社と、バングラデシュの栄養失調の子供を救うために、会社に利益を残さず(この本の発売の段階では、少しの利益がダノン社に残るよう設計されているらしい)、ビジネスを行うに至った経緯が紹介されている。 非常に印象的だったのが、貧困が存在している原因として、自分たちが人間の能力を過小評価した世界の半分を無視するような枠組みを築きあげたからだ、としている。 ・ビジネスの概念…利益だけが人間の原動力になる。 ・融資資格の概念…自動的に貧しい人々を排除する。 ・企業家精神の概念…人々の大部分の創造性を無視する。 ・雇用の概念…人間を活発な創造者ではなく受け身の容器にする。 貧困が存在するのは、貧しい人々の能力の不足のためではなく、むしろこれらの知性の失敗のためなのである。 貧困は、もはや遠い世界の問題ではなく、日本国内の問題にもなっている。 一度、標準のレールから外れたら、二度とレールに戻れない日本の仕組み。 理由は、確かにユヌス氏があげた上記4つの概念にしばられているからではないか。 世界から貧困をなくすために、私にできることは何か? 人間は、達成したいと思うことを達成する力がある。 心がけからでも、できることはあると思った。
Posted by
グラミン銀行の創設者が貧困撲滅への取り組みや方策について論じた本。発展途上国などで見られる貧困をいかにして無くしていくかといった著者の取り組みや考えは非常に興味深いものだった。
Posted by
友人がグラミンの学生代表として働いているので興味が出て読んでみた。 ユヌスが語るなかで一番興味深いことが、人間の本当の特性である。従来の経済学の理論は人間性について、根本的に単純化しすぎたイメージを描いているとユヌスは述べる。そのイメージというのが、あらゆる人間は利益を最大にした...
友人がグラミンの学生代表として働いているので興味が出て読んでみた。 ユヌスが語るなかで一番興味深いことが、人間の本当の特性である。従来の経済学の理論は人間性について、根本的に単純化しすぎたイメージを描いているとユヌスは述べる。そのイメージというのが、あらゆる人間は利益を最大にしたいという願望で純粋に動機づけられるといものだ。ユヌスはこれは人間の本当の特性ではないという。 彼が言う人間の根深い特性のひとつが、他の人々のためによい行いをしたいという願望だという。この願望を満たすのがマイクロクレジットを含むソーシャルビジネスであり、これからの時代においてソーシャルビジネスは大きな足がかりを築くのだという。 母校の部活の監督をやっていたときを振り返れば、チームがトーナメントを勝ち上がっていったことよりも、保護者や選手に感謝の念を言われたときが一番やりがいや達成感を感じたのを思い出す。ユヌスが語るように、他の人々のために何かを行うことが人間の特性のひとつなのかもしれないし、その特性を生かすことが本当の幸せであるのかもしれない。
Posted by
貧困のない世界を創るにはソーシャルビジネスと呼ばれる社会的な利益を考えている企業が必要だと言うこと。そしてこの世界ではどういう企業がそういう事を行っているのか。本書ではグラミン銀行から展開される様々なビジネスについて触れられている。 これを読んだことにより、自分でもやってみたい...
貧困のない世界を創るにはソーシャルビジネスと呼ばれる社会的な利益を考えている企業が必要だと言うこと。そしてこの世界ではどういう企業がそういう事を行っているのか。本書ではグラミン銀行から展開される様々なビジネスについて触れられている。 これを読んだことにより、自分でもやってみたいと思うことがありました。それは「ソーシャルストック市場」というものです。今、世界には多くの営利企業のためのマーケットが存在します。東証とかロンドンとか。逆にソーシャルストック市場は、ソーシャルビジネスを行う企業だけが上場出来る取引所と言うものです。この取引所を作ってみたいと思いました。そのためにはソーシャルビジネスがどういうものかということを正確に定義することが大事だと。 営利企業と比べると違いはわかりやすいソーシャルビジネス、しかし、ソーシャルビジネスと社会的企業、これは同じではない。社会的企業にソーシャルビジネスは含まれると本書にはある。 ソーシャルビジネスの特徴は投資家兼所有者という点にある。これにより、ビジネスがもたらす社会的恩恵の有効性と効率を確立する中で生まれる利益を、基金の源泉とする要素を持っているのだそう。つまりNPOのように寄付に頼らない理由、寄付に変わるのが恩恵という存在。以上のような話はおれはソーシャルビジネスの定義には十分じゃないかと思う。 また若い人が起業をするにあたり、既存の資本主義的システムの中にあるものには魅力がない。世界中の消費商品にアクセス出来てしまうとそうなる。その空白を埋めることがソーシャルビジネスである。 これは確かに単に起業をすると言う漠然としたイメージを脱却するモチベーションとなり得そうである。 そして、大富豪が利益を追求して作り上げた資金の余りでソーシャルビジネスに投資しようという考えに至るのは自然な流れ。人は、根にある「人のために」と言うことを無視した利益追求型(PMB)では間が埋まらない、ソーシャルビジネスはこれを埋める。らしい。 じゃあはじめから、ということである。 初めからソーシャルビジネスとPMBを分けないためには持続可能である事が重要。それにはソーシャルビジネスという目的上の性質に関係なくPMBと同じくらいの経営をする必要がある。「神は細部に宿る」って話で本書には説明されている。やはりそこはビジネスである以上当然だと思う。よくある「慈善事業でやってんじゃねえ」ということなのかと。社会のためとはいえ金をとる以上然り。 ソーシャルベンチャーキャピタル、ソーシャルビジネスファンドのようにソーシャルビジネスを支援する民間の組織が重要。もちろん社会貢献市場も。 これは今の日本の地合いを思うと考えずにはいられない。ただでさえベンチャーを叩こうとする風土ゆえ、そういうのを支える専門的な組織は重要だと思う。 メディア的なことを言えばソーシャルビジネスジャーナルみたいなのが出来てきてもおかしくないみたいなことが書いてありましたが、これに関してはいずれ出版の形態として、よりミニマム(?)な形として変化していくと考えられる。つまり、より個人での発信になってくのではないか、ということである。 経済指標であるダウジョーンズについても触れられている。ソーシャルダウジョーンズとPMBダウジョーンズという二つが出来て、両者が上げた日は世界が良い方に動いた日と言うことになる。 これはとてもわかりやすく、いいアイデアだと思いました。 ソーシャルビジネスとITが導く世界の国境や距離を縮める話が出てきてました。おれも常々想い描いています。いろんな格差を埋める方法であることは誰もが認めている事実みたいですね。 最後の方に書かれていました。信号を守ることは個人の自由を制限するものの、道をスムーズに走ることに貢献している。天然資源を制限するのもそれと同じなんだそうです。まあそうですね、好き放題にやって上手くいくわけはないですから。 そういうとこ含めてソーシャルビジネスがなんなのか、貧困を博物館送りにすることには何が必要か。しかしそれだけにとどまらない細やかな現状の把握。なかなか密度の濃い本だと思いました。 一読の価値あり。是非。 ※目次はブログの方に載せてます。ここじゃhtml書けないので。 http://celsus-draco.jugem.jp/?eid=807#sequel
Posted by
【自分のキーセンテンス】 世界の総所得の94%は、40%の人々にしか行渡らず、残る60%の人々は、世界の総所得のわずか6%で生活しなければならない。 世界人口の半分は1日あたり2ドル以下で生活している。 一方でおよそ10億人が、1日あたり1ドル未満で生活している。 Socia...
【自分のキーセンテンス】 世界の総所得の94%は、40%の人々にしか行渡らず、残る60%の人々は、世界の総所得のわずか6%で生活しなければならない。 世界人口の半分は1日あたり2ドル以下で生活している。 一方でおよそ10億人が、1日あたり1ドル未満で生活している。 Social Businessの存在は、お金とは別の意味で豊かな生活を求めている学生やその他の人々に、もう一つのキャリアと人生の道を与えるものになるだろう。 Social Businessは慈善事業ではない。 Social Businessは自己持続的である。 この本は、 Social Businessの重要性と、 Social Businessがもたらす、もたらした新たな経済学の考え方を与えてくれる。
Posted by
ソーシャルビジネスは利益を発展投資に費やす仕組みのため、手元に収益の入らないビジネスであることを知る。最初はなかなか受け入れられなかったということは想像しやすい。こういう仕組みづくりを人として造ったユヌス氏は本当にノーベル平和賞に相応しい方だと思った。また、ヨーグルト会社のダノン...
ソーシャルビジネスは利益を発展投資に費やす仕組みのため、手元に収益の入らないビジネスであることを知る。最初はなかなか受け入れられなかったということは想像しやすい。こういう仕組みづくりを人として造ったユヌス氏は本当にノーベル平和賞に相応しい方だと思った。また、ヨーグルト会社のダノン社の社長さんのご理解は、見習いたいと感じた。人を見る目というか、ユヌス氏の考えにほぼ賛同し、全てを任せるという姿勢は、資本主義を超えた次ぎの時代の何かを感じた。グラミン銀行の仕組みがうまく回り始めるまでの苦労と仕組みを確立させるための知恵は努力の結果だと感じた。 アショカ財団やバングラディッシュの現状など知識もつきます。
Posted by
(2009/10/9再読終了)うーん、やっぱりスゴイ。ソーシャル・ビジネス・ファンド、是非実現して欲しいものである。 (2009/1/25読了)今まで何冊か貧困に対する”傾向と対策”を語る本を読んだが、どれも先進国の側からの援助ほ方法論の域を出ていなかった。が、本書は途上国自ら...
(2009/10/9再読終了)うーん、やっぱりスゴイ。ソーシャル・ビジネス・ファンド、是非実現して欲しいものである。 (2009/1/25読了)今まで何冊か貧困に対する”傾向と対策”を語る本を読んだが、どれも先進国の側からの援助ほ方法論の域を出ていなかった。が、本書は途上国自ら発展する方法論。「貧困のない世界を創る」方法として著者が提唱する方法論は、ソーシャル・ビジネス。利益を最大化することを目的とする従来のビジネスではなく、原価は回収しつつ(あくまでビジネスであって慈善事業ではない)、利益は全て社会の発展のために配分する。
Posted by
貧困は、不完全な経済システムのせいで生まれたものである。 人は月へ行きたいと思い、月へ行ったように、 貧困は受け入れ難いものであると認めれば、無くす事ができる。貧困は仕方ないものと受け入れている事に問題がある。
Posted by
(2009.05.14読了) 著者は、2006年度のノーベル平和賞受賞者です。 著者は、「貧困のない世界を創る」という題名からわかるように、バングラデシュで貧困を抜け出す手助けを行う活動に携わっている。さらに、バングラデシュで行った活動を世界に広げようとしている。 産業革命以来?...
(2009.05.14読了) 著者は、2006年度のノーベル平和賞受賞者です。 著者は、「貧困のない世界を創る」という題名からわかるように、バングラデシュで貧困を抜け出す手助けを行う活動に携わっている。さらに、バングラデシュで行った活動を世界に広げようとしている。 産業革命以来?世界各地で、富める人たちは、貧しい人たちを何時までも貧しいままで留めておくための仕組みを編み出して、富の独占をはかって来た。 その仕組みとは、貧しい人に原料を貸して、生産したものを納めさせて、生きるに必要な最低限の手間賃を与えるというものです。 生活用品が欲しい場合は、富める人のところで用意した売店で、付けで買わせるという方式をとります。貧しい人には、文字も計算を教えず、富める人の思うがままに、言いくるめることができます。 そういう意味で、知識とは、力でもあるのです。勉強嫌いのあなた、(僕もそうかも)損をしていますよ。(物事を損得で考えるのも、心の貧しさ、とか言われると、・・・) ●ソーシャル・ビジネスの原動力(79頁) 人々は世界について心配し、お互いのことを心配しあっている。人間は、出来ることなら仲間である他の人間の生活をよくしたいという本能的な自然な願望を持っている。チャンスが与えられれば、人間は貧困や病気、無知、不要な苦しみのない世界の方に住みたいと思うだろう。だから、人々はチャリティーに何十億ドルもの金を寄付し、財団を設立し、NGOやNPOの運営を始め、数えられないくらいの時間のボランティア活動を買って出て、ときには社会的なセクターにおいて比較的給与が低い仕事に自分の生涯を注いでしまうのだ。 ●企業家精神の普遍性(104頁) 教科書によれば、ただ一握りの人々だけが、ビジネスチャンスを見出す才能を持ち、そのチャンスの源に思い切って近づく勇気を持っているというのだ。 これに反して、世界の最も貧しい人々の間で注意深く観察を続け、グラミン銀行やその他の団体での数十年の体験で確かめてきた私に言わせれば、企業家としての能力は実際には普遍的なものである。ほとんど誰でも、自分の周りでビジネスチャンスを認識できる才能を持っている。 ●人間は経済学的側面のみではない(114頁) 人間は、ただの労働者ではないし、ただの消費者や企業家でもない。誰もが、親であり、子供であり、友人、隣人、市民なのである。彼等は家族について心配し、彼らが住むコミュニティの世話をし、他人からの評判や他人と自分との関係について真剣に考えている。 人々を貧困から抜けださせための活動を行う中で、銀行や電話会社、インターネット、教育、福祉、栄養改善の合弁事業、等を設立発展させてきた。 ただ、営利目的ではないため、従来の経済や法律とはかみ合わない部分が出てくるので、工夫して、法律等を変えてゆかなければならない。そういう意味では、新しい経済の概念が生み出されてきているともいえる。 平和賞と合わせて経済学賞も与える必要がありそうだ。 (2009年5月19日・記)
Posted by