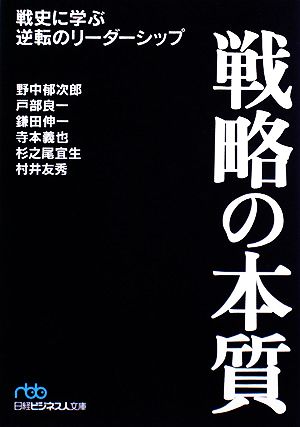戦略の本質 の商品レビュー
兵力で劣る軍が戦略の力でいかに勝利していくかを6つのケース分析を用いて導きだしている本。相手に対して不利なリソースをベースに戦う為に、相手の出方に対して上手く戦略を練り上げ勝利した、という書き方が多い。よって戦略論の分野でいうゲーム理論的な視点が強く含まれていると感じる。 リーダ...
兵力で劣る軍が戦略の力でいかに勝利していくかを6つのケース分析を用いて導きだしている本。相手に対して不利なリソースをベースに戦う為に、相手の出方に対して上手く戦略を練り上げ勝利した、という書き方が多い。よって戦略論の分野でいうゲーム理論的な視点が強く含まれていると感じる。 リーダーの資質が戦略の本質を語る上で非常に重要であるとされており、本質を見抜く力、コンテクストを読む力を持ったリーダーが逆転をもたらすとしている。特に、勝利したリーダーはみな戦場に出向き、現状を把握しながら戦況の本質を見抜いていたという事実は、企業においても経営者がいかに現場を把握しているかが成功のカギであることを示唆する内容であると考えられる。 ケース分析ということで、n数の問題が常に付きまとう。一般性の問題については、前作「失敗の本質」と合せて読むことである程度解決できるかもしれない。
Posted by
20年近く前に出版された「失敗の本質―日本軍の組織論的研究 」1991年中公文庫(戸部 良一ほか著)の続編ともいうべき書。 戦争は敵対する意志の不断の相互作用である。クラウゼヴィッツの言葉である。この本は、8つの戦いを分析しながら、改めて戦略の必要性を考えるもの。戦争のみなら...
20年近く前に出版された「失敗の本質―日本軍の組織論的研究 」1991年中公文庫(戸部 良一ほか著)の続編ともいうべき書。 戦争は敵対する意志の不断の相互作用である。クラウゼヴィッツの言葉である。この本は、8つの戦いを分析しながら、改めて戦略の必要性を考えるもの。戦争のみならず、日本の閉塞状態を打破し、逆転を可能にすべき戦略本質を明らかにするヒントを与えてくれる。
Posted by
戦史に学ぶ戦略論。 それぞれちゃんと分析されてるし、逆転を成し遂げたリーダーシップについての解説も納得いくものだったけど、前作「失敗の本質」に比べるとインパクトが弱い気が。
Posted by
「失敗の本質」の続編に位置づけられる戦史集。前回は第二次世界大戦で何故日本軍が負けたのか、にフォーカスしていたが、今回は同時期および東西冷戦期から、典型的に逆転が現れた6つの戦史をピックアップし、何故日本軍は逆転戦略を採用できなかったのかを考察する本。 戦史ものとしては十分に面...
「失敗の本質」の続編に位置づけられる戦史集。前回は第二次世界大戦で何故日本軍が負けたのか、にフォーカスしていたが、今回は同時期および東西冷戦期から、典型的に逆転が現れた6つの戦史をピックアップし、何故日本軍は逆転戦略を採用できなかったのかを考察する本。 戦史ものとしては十分に面白い。毛沢東の反「包囲攻伐」戦やチャーチルのバトルオブブリテンなど、不利な状況からリーダーシップが発揮され、敵の強みと弱みを冷静に見切りながら見事な作戦を展開した事例を採り上げ、しかもそういう部分にフォーカスしてコンパクトに述べていく。熱のこもった筆致も前作を彷彿とさせるものがあった。 6つの戦史を解説した後に「戦略の本質」の普遍化を試みているが、この辺は議論のあるところだろう。10命題のうち前半の方、目的の明確化や言葉の重要性といった部分には異論も少なかろうが、「義」とか「賢慮」などの命題は戦史事例に依拠しておらず、筆者の哲学的考察に過ぎない。 また本書の戦略はビジネスにも応用できるかのように書かれているが、あくまで国家間戦争という特殊な世界での話。しかも20世紀の、国家間の戦闘行為が成立していた頃の事例だから、現代に置き換えれば情報化とか、非対称戦争などの要因を加味する必要がある。その辺は割り引きつつ、戦史として存分に楽しめば良いのではと思う。
Posted by
戦略というフレーズが苦手すぎて、 逆に学んでみようと手に取った一冊ですが、 なかなか読み進められていないまま、今日に至っています。
Posted by
読もうと思ったまま単行本を読む機会を逸していたが、文庫化されていたので、読んでみました。これは、滅多にない本です。戦争での実例を通じて、本当の戦略を説いている。とにかく具体的で、経営学の学者が書いているのだが、軍事評論化の戦争論のようにも感じられるくらい、とにかく詳細で迫力がある...
読もうと思ったまま単行本を読む機会を逸していたが、文庫化されていたので、読んでみました。これは、滅多にない本です。戦争での実例を通じて、本当の戦略を説いている。とにかく具体的で、経営学の学者が書いているのだが、軍事評論化の戦争論のようにも感じられるくらい、とにかく詳細で迫力がある。それを通じて、戦略とは結果的には優先順位の付け方であり、それだけで、軍、そして国の生死が決まる様子が肌感覚でわかる本。これは戦略に興味がある方だけではなく、一般の人にも読んでみてもらい良書です(なので、文庫化されたのでしょうね)。
Posted by
ビジネス書ですが、いわゆる経営戦略の本ではないです。 実際の戦争において、転機・逆転をテーマに、戦争で勝利する際にみられる逆転の契機について分析されています。 一回読んで理解するというよりは、ときどき読み返して、本質をみる考え方を学ぶ書にしたい本です。 姉妹編というか、同じ著者で...
ビジネス書ですが、いわゆる経営戦略の本ではないです。 実際の戦争において、転機・逆転をテーマに、戦争で勝利する際にみられる逆転の契機について分析されています。 一回読んで理解するというよりは、ときどき読み返して、本質をみる考え方を学ぶ書にしたい本です。 姉妹編というか、同じ著者で、「失敗の本質」もあります。 戦争における失敗の原因について分析しており、こちらも考えさせられるものがあります。
Posted by
複数の著者が「逆転」にフォーカスして戦争についての考察を書いている。 中東戦争や共産党についての話は面白かった。 けどほかの本を読んでも書いてある事実なのかなぁ。 戦略の本質という、本題について適切に述べた本かについては疑問。
Posted by
戦略とは相手との相互作用によるダイナミックな性質をもったものだというのが興味深い。ヘーゲルをあげて戦略とは矛盾していること(相手のが兵力が上で勝てない)をアウフヘーベンして突破口を見つけ出すといっているが少々強引な気がせんでもない。矛盾しているということとはニュアンスが違うので...
戦略とは相手との相互作用によるダイナミックな性質をもったものだというのが興味深い。ヘーゲルをあげて戦略とは矛盾していること(相手のが兵力が上で勝てない)をアウフヘーベンして突破口を見つけ出すといっているが少々強引な気がせんでもない。矛盾しているということとはニュアンスが違うのでは。個々の解釈によっては(我が軍のが機動性にたけているect)勝てると思えばその時点で矛盾ではないのであるし。 サダド大統領の長期的パースペクティブには感動した。 また大戦略には善が追求されていなければその戦略はうまくいかないというのには納得させられた。その善というのは自分だけの価値ではなく、社会、他人との対話の中から醸成されたものでなければならないというのも興味深い。 自分も大戦略を立てねば。地球市民として、社会にとっての善、さらには未来の社会にとっての善に適合した大戦略を立てねば。そのためには世の中(背後にある大きな企図)を察知するだけの想像力をまずは磨かねば。
Posted by