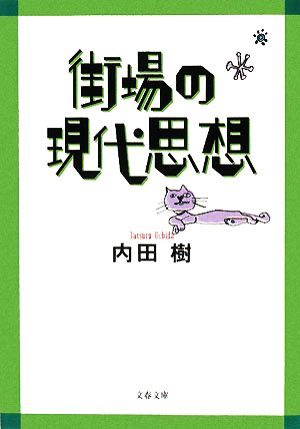街場の現代思想 の商品レビュー
内田さんの考え方は好き。なんというか、哲学的な事をさらっと話してくれて教養が深まったなーと感じさせてくれつつ、こういう言い方もあるのかと、いつか使ってやろうと思える金言に満ちてる気がする。ともかく好き。
Posted by
"就職"だの"結婚"だのといった、 相談者の身近な問題から、 あれよあれよという間に現代思想にまで連れて行ってもらえる本。 とにかく論法が巧みなので、 気が付けば物事を俯瞰から見ている気分。 もしかしたら、 レッドブルよりも翼を授けてく...
"就職"だの"結婚"だのといった、 相談者の身近な問題から、 あれよあれよという間に現代思想にまで連れて行ってもらえる本。 とにかく論法が巧みなので、 気が付けば物事を俯瞰から見ている気分。 もしかしたら、 レッドブルよりも翼を授けてくれるかもわからない。
Posted by
文章の構成に理解力がついていかず、内容に知識がついていかず。だからまた読んでみたい!大学生なんかは読んでみるといい気がする!
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
落ち込んでいる時に、ジムのトレーナーに「参考になるよ」とこの著者を薦められて。とにかく読んでみようと本屋にあった本からチョイス。 最初は、文化資本の話で、求めていた内容と違っていたが、それなりに面白かった。 転職についての悩みは、残念ながら図星って感じ。 バレンタインからの「祝」の儀式の話は、目からウロコだった。 最後の「生きることの愉しさ」。こんな考えに初めて触れた。死を覚悟することで、生きることの意味が身にしみてくる。 「自分がどういうふうに老い、どういうふうに病み衰え、どんな場所で、どんな死にざまを示すことになるのか、それについて繰り返し想像すること。 困難な想像ではあると思うれど、君たちの今この場での人生を輝かすのは、尽きるところ、その想像力だけなのである。
Posted by
「お金について」「転職について」「結婚という終わりなき不快について」「他者としての配偶者について」「学歴について」「想像力と倫理について」といった十五のお題に対する、人生相談の皮をかぶった、現代思想の講義である。 フリーターとかバレンタインのチョコとか学歴詐称とか、表層的には私た...
「お金について」「転職について」「結婚という終わりなき不快について」「他者としての配偶者について」「学歴について」「想像力と倫理について」といった十五のお題に対する、人生相談の皮をかぶった、現代思想の講義である。 フリーターとかバレンタインのチョコとか学歴詐称とか、表層的には私たちがよく知っている「現代」の事象を扱っているけれども、そこで語られている内容は、(ほぼ)いつでも、どこでも、誰にでも適用できる、普遍性の高い知見なのだ。
Posted by
P.17-12 「文化資本の差」による「二極分解」 →P.18-14 「他の人たち」とは「共通の話題がない」 →P.18-15 「新しい階層社会」の出現 P.22-1 「文化資本」には、「家庭」において獲得された趣味や教養やマナー(「身体化された文化資本)と、「学校」において獲...
P.17-12 「文化資本の差」による「二極分解」 →P.18-14 「他の人たち」とは「共通の話題がない」 →P.18-15 「新しい階層社会」の出現 P.22-1 「文化資本」には、「家庭」において獲得された趣味や教養やマナー(「身体化された文化資本)と、「学校」において獲得された知識、技能、感性(制度化された文化資本)の二種類がある。 →P.24-6 文化資本の差はこの「ゆとり」、あるいは「屈託のなさ」のうちにある。(中略)P.25-1 芸術作品は「好き」か「嫌い」か、「ほしい」か「ほしくない」かという皮膚感覚レベルで享受されるものである。 P.34-5 「文化資本を獲得するために努力する」というみぶりそのものが、文化資本の偏在によって階層化された社会では、「文化的貴族」へのドアを閉じてしまうのである。 P.34-10 「努力しないで、はじめから勝っている人が『総取り』する」というのが文化資本主義社会の原理である。 P.45-8 「プチ文化資本家」たちの嫉妬と羨望のいりまじった「おおお!」という「よけいな身ぶり」が文化資本を基礎づけるのである。 P.43-7 「距離のパトス」(by ニーチェ)というのは、「こいつらだけとは一緒にされたくない」という激しい嫌悪感が人間に向上心をもたらす、という考え方のことである。 P.54-6 「クール」というのは、私的な定義によれば、自分の立ち位置をかなり「上空」から見下ろせる知性のあり方である。 P.66-7 「文化ってようするに暇つぶしみたいなものですよね」 P.74-3 「向上心は必ずしも人を幸福にしない」。幸福の秘訣は「小さくても、確実な、幸福」(@村上春樹)をもたらすものについてのリストをどれだけ長いものにできるか、にかかっている。 P.83-3 「敬語」というのは、「自分に災いをもたらすかもしれないもの」、権力をもつものと関係しないではすまされない局面で、「身体をよじって」、相手からの直接攻撃をやり過ごすための生存戦略のことだ。 P.93-13 お金は交換のために、コミュニケーションのためにある。 P.111-10 あらゆる組織は―世界帝国から資本主義企業まで―多様性を維持しているときに栄え、「栄えている」という事実ゆえに均質的な個体を結集させ、結果的に組織としての多様性を失って滅びる、ということである。 P.126-5 知性というのは「自分の愚かさ」に他人に指摘されるより先に気づく能力のこと P.162-12 結婚は(中略)理解も共感もできなくても、なお人間は他者と共生できるということを教えるための制度なのである。 P.226-5 私たちが自分に課すべき倫理的規範は(中略)社会の全員が「自分みたいな人間」になっても、生きていけるような人間になることである。 P.235-12 私たちが「価値あり」と思っているものの「価値」は、それら個々の事物に内在するのではなく、それが失われたとき私たちが経験するであろう未来の喪失感によって担保されているのである。
Posted by
良著や、心に留まる文章の条件は、 「これは私のことを書いている!」、もしくは 「こんなこと書いていいの!?」との感想を抱けるか否かだと思う。 (思春期にそういう読書体験をした少年少女は、秘密めいた興奮を覚え、 本好きへの道を一歩踏み出してしまうんじゃなかろーか) 前者の『言い当...
良著や、心に留まる文章の条件は、 「これは私のことを書いている!」、もしくは 「こんなこと書いていいの!?」との感想を抱けるか否かだと思う。 (思春期にそういう読書体験をした少年少女は、秘密めいた興奮を覚え、 本好きへの道を一歩踏み出してしまうんじゃなかろーか) 前者の『言い当てられた!』という慄きを この本では、嫌というほど味わわされた。 『自分は、生まれつきの文化貴族でも、 文化的教養が全く不足している階層でもない、 その間にぶら下がっている「プチ文化資本家」だ』との 自覚からスタートする、【「一億総プチ文化資本家」戦略】(P36) 『自分がその存在を知らないことさえ知らなかったこと』に 偶然出くわすための場所であることが、 大学のあらまほしき姿であると語った【学歴について】(P204)。 倫理的規範について語った、【想像力と倫理について】(P211) *** 上記の文章が与えてくれる、 むき出しの己の姿を浮き彫りにされ、えぐられるような妙とはまた一味違って、 社会学的読みものとして非常に面白かったのは、【敬語について】(P78)。 なんで敬語を使わなくちゃいけないの?という問いに対する回答の体裁で この文章は書かれている。 「敬」という感じの原義は、「身をよじる」。 自分を傷つける可能性のある、 『自分より力のある存在』と関わらねばならぬ時には、 身をよじって危険を避けねばならない。 ナマの自分の言葉で喋ることは、危険なことである。 岡野玲子作『陰陽師』に登場するエピソード等を引用しながら、 巧みに語られる内容は、おさまりよく腹に落ちてくる。 (余談だが、『陰陽師』のこのエピソードは、 黒川伊保子の『怪獣の名はなぜガギグゲゴなのか』にも登場している)
Posted by
やはり内田さんの著書は良い。 特に際立っていたことを数点。 ・「敬語」についての記述。「敬語とは自己防衛の手段である」 ・「死ぬことは良いことか?悪いことか?」 ・世間の人の99パーセントは自分の給料は不当に安いと信じている。 ・「正しい判断をするにはどうしたらよいか?」→...
やはり内田さんの著書は良い。 特に際立っていたことを数点。 ・「敬語」についての記述。「敬語とは自己防衛の手段である」 ・「死ぬことは良いことか?悪いことか?」 ・世間の人の99パーセントは自分の給料は不当に安いと信じている。 ・「正しい判断をするにはどうしたらよいか?」→「できるだけ決断はしないほうがよい」 ・高等教育において一番大切なこと ・想像力とは何か ・なぜ人を殺してはいけないのか?←ここまで論理的に説明している文章は(恥ずかしながら)読んだことがなかった
Posted by
一応、社会論の体は取っているが、内容的には哲学に近い。 池田晶子のソクラテスシリーズに通ずるものがあります。 街場のメディア論でも触れられていた「交換・交易」の延長にある、 「贈与」についての考察が面白い。 バレンタインチョコレートをもらえない男子を「祝」と「呪」の語義から論じ...
一応、社会論の体は取っているが、内容的には哲学に近い。 池田晶子のソクラテスシリーズに通ずるものがあります。 街場のメディア論でも触れられていた「交換・交易」の延長にある、 「贈与」についての考察が面白い。 バレンタインチョコレートをもらえない男子を「祝」と「呪」の語義から論じている。 この節は短く難解であるが、 人間のコミュニケーションの根源を語っているようで、とても味わい深い。 返礼義務。災いのコントロール。 道祖神と悪霊退散のトレードオフとしてのお供え物。 まず先に贈りものをしたところに、贈り物は供えられる。 すんげぇな、たっちゃんはよぅ。
Posted by
著者の作品は二冊目。内容が多岐に渡り、著者の知識の豊富さと圧倒的な読書量、人を引き込む言葉遣いに今作もあっさりと読了。しかし胸の内に残るものは多い。 今回特に印象的だったTopicは、敬語について、と、結婚という終わりなき不快について。もちろん他の内容も十分に楽しんで読めたのだが...
著者の作品は二冊目。内容が多岐に渡り、著者の知識の豊富さと圧倒的な読書量、人を引き込む言葉遣いに今作もあっさりと読了。しかし胸の内に残るものは多い。 今回特に印象的だったTopicは、敬語について、と、結婚という終わりなき不快について。もちろん他の内容も十分に楽しんで読めたのだが、特に印象的だったのが上記二本。 自分の普段悩んでいることから、あんまり気にしていなかったことまで、具体的な例を用いつつ答えに近いヒントを多く提示してくれる著者の本。もう一度読み返したい、と思える本です。
Posted by