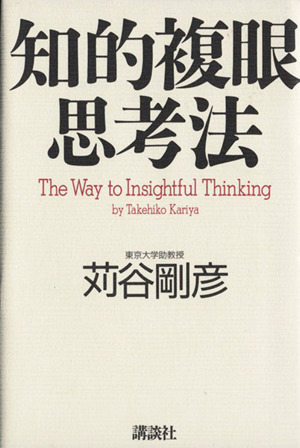知的複眼思考法 の商品レビュー
ある情報における、自分とのかかわりについて、それがどのような意味を持つのかを冷静に捉える。 客観的な記述と主観的な記述。 この場合の暗黙の前提とは何か。 常に反論を意識する。 とくに、自分なりに問題を立て、それを解くスタイルは重要である。問題の立てかたの独創性と、それを解明...
ある情報における、自分とのかかわりについて、それがどのような意味を持つのかを冷静に捉える。 客観的な記述と主観的な記述。 この場合の暗黙の前提とは何か。 常に反論を意識する。 とくに、自分なりに問題を立て、それを解くスタイルは重要である。問題の立てかたの独創性と、それを解明するときの論理展開の精密さ・緻密さ、さらには、論理の根拠をきちんと示しているかどうかが重視されるのである。 ある問題がクローズアップされることで、別の問題がその陰に隠れて見えにくくなってしまうことがある。
Posted by
2010.11.2 最近、考えることが上手くできないというのが課題なので、読んでみた。 結論、ここに書いてあったことを丁寧に実行してみようと思う。 まずは、読書の仕方を変える。 読書も「量が質を生む」ということで、割と早いスピードで読んできたけど、一冊、一冊丁寧に読むことに...
2010.11.2 最近、考えることが上手くできないというのが課題なので、読んでみた。 結論、ここに書いてあったことを丁寧に実行してみようと思う。 まずは、読書の仕方を変える。 読書も「量が質を生む」ということで、割と早いスピードで読んできたけど、一冊、一冊丁寧に読むことに決めた。 学生で時間のあるうちに、読書や文章化の基本的な力を身につけよう。
Posted by
ゼミで半強制的に読まされた一冊(笑)でも今となってはすごく自分のためになる本。これからの人生もっと大切になってくるのではないかと思うぐらい、私は何回も何回も読み返しています。
Posted by
レポートを書くときには「問いを立てる」ことが必要です。でも,そもそもどうやって問いを立てればいいのか,という入り口で行き詰まっている人が,実は多いのではないでしょうか。この本は物事を多角的に捉えることで,さまざまなな気づきが起こることを実感させてくれる一冊です。その気づきこそが,...
レポートを書くときには「問いを立てる」ことが必要です。でも,そもそもどうやって問いを立てればいいのか,という入り口で行き詰まっている人が,実は多いのではないでしょうか。この本は物事を多角的に捉えることで,さまざまなな気づきが起こることを実感させてくれる一冊です。その気づきこそが,あなたの問いを深めるきっかけを作ってくれると思います。
Posted by
第4章「複眼思考を身につける」がとくに参考になった。斬新な思考法があるというわけではないが、解説が丁寧なのがよい
Posted by
ステレオタイプに物事を判断せずに色々な角度から検証しましょう。ということを一番言いたかったのだと思う。 まあ当たり前といえば、当たり前な気もしますが・・・。具体例も多いし、簡単な文章で分かりやすいので堅苦しさはない。 でもやっぱり分厚さの割りにちょっと物足りなかった。
Posted by
大学生なら、3回は読むべし。と教授に進められた本。 本当に読む価値あり。 実践すれば、真の批判的思考が身につく。
Posted by
理系よりの学科を卒業していて、小論文を書いたことがあるなら既知の内容。 それ以外の人には、オススメできる本だと思う。
Posted by
常識にとらわれないために情報を吟味する癖を付けないと 対象の情報を細分化したり、抽象化したり 情報提供者の意図を考慮したり、そもそものデータを疑ったり 出来てることもあるし、出来てないこともあり
Posted by
以下のHPをきっかけに、手にとる。 http://dain.cocolog-nifty.com/myblog/2006/05/post_0cc9.html#search_word=%E8%A4%87%E7%9C%BC%E6%80%9D%E8%80%83 評判どおりの良書。常識...
以下のHPをきっかけに、手にとる。 http://dain.cocolog-nifty.com/myblog/2006/05/post_0cc9.html#search_word=%E8%A4%87%E7%9C%BC%E6%80%9D%E8%80%83 評判どおりの良書。常識にとらわれずステレオタイプにはまらない 複眼的思考の実践方法が述べられている。 前例、基準、規制は往々にして、基準制定時の前後の文脈から 切り離されて事実が一人歩きしてしまう。 例えば、「偏差値」「やる気」「過労死」といった言葉が実体化してしまう。 本質を探るには、実体化した言葉を使わない、主語を分解、異なる立場から 考えるなどして複数の視点を持つべきであると説く。 具体的方法としては、以下のことをあげている。 1 関係論的見方を行う。 ・「〇〇化」(〇〇になる、なっていくというプロセス)として 問題をとらえる。→〇〇を主語としてとらえない。 ・プロセスを見るために、関係をみる。 2 逆説の発見をする。 ・これから行おうしていることが、どんな副産物を産み出す可能性があるか広い 範囲で考える。 ・実行することの抜け道がないか考える。 ・実行することが集まった場合の意味付け ・計画や予測することの表明自体が、現実に影響を与えるか考える。 (マルクスの共産主義革命の予測) 3 「問題を問うこと」を問う ・なぜそれが問題であるかに着目する。 ・同じ問題でも視点によって捉え方が異なることに注目する。 ・問題のクローズアップによって隠れてしまう問題がないかに 目を向ける。 ・問題の文脈に目を向けるために、 ①問題を立てることによって、誰が得をするか、損をするか ②問題がとけたらどういう影響があるかを、考える。 そういえば、「火車」のクレサラ問題も個人の問題だけではなく 周辺の社会環境などへも視点を向けなければならないとの記述が あった。複眼的思考の1例であろう。
Posted by