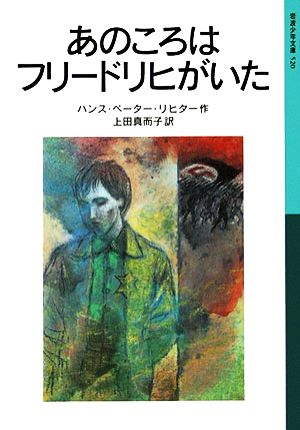あのころはフリードリヒがいた 新版 の商品レビュー
教科書に長いこと載っている作品ですね「ベンチ」。 この「ベンチ」が自分が生徒だった頃、そして先生になった今、とても印象深い作品なのですが、今年始めて授業の中でシッカリ『あのころはフリードリヒがいた』を使ってみようと思い立ちました。近隣の図書館をめぐり、どうにか4冊ほど手に入れまし...
教科書に長いこと載っている作品ですね「ベンチ」。 この「ベンチ」が自分が生徒だった頃、そして先生になった今、とても印象深い作品なのですが、今年始めて授業の中でシッカリ『あのころはフリードリヒがいた』を使ってみようと思い立ちました。近隣の図書館をめぐり、どうにか4冊ほど手に入れまして、色々と考えてみたわけです。 この本の実に面白い(不謹慎な意味ではなく、本の作りとして)ところは、「ベンチ」を学習した後にこの本を手に取ると、「ぼく」が何人なのか、フリードリヒはどうなるのか、といった謎が解けるようになっているんですね。 目次を読み、最初と最後の話をさっと見た時に、「ああそうか」という気付きがたくさん見つかる。 教育出版が指導書にいけしゃあしゃあと「学習者一人につき1冊この本を用意したい」とか書いているのを見た時は「出版社から幾らもらったんだ」と思いました(し、未だに無茶言うんじゃねえよとは思う)が、「本を読みたい、他の短編を読みたい」、そう思わせる力のある素晴らしい作品だと感じます。 今まで「ベンチ」単体で扱ってきたことが申し訳ないようなもったいないような気持ちになる昨今です。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
ああひどいひどい わたしこれ読んだことなかったんだなー読んだことあるけど忘れてるだけかと思った 生まれたときから仲良しの同じアパートに住むフリードリヒとともにすごした少年時代 それはちょうどナチスによるユダヤ人迫害がはじまって頃・・ ユダヤ人じゃない少年から見た生々しい迫害 昔はこわかったし嫌だったからあまり見なかったけど 最近気になるのは全部読んだから、大体知識としては知ってることばかりだったけど、 あらためて、本当にひどいし、かわいそうで涙が出た でも気の毒だと思ってても、主人公やそのお父さんみたいに、家族のために(自分のために) 助けてあげることができないひともたくさんいたんだなあと 助けたりつきあったりしたら自分も強制収容所に入れられるってなったら、助けたくても助けられないものかもしれない 『本泥棒』のお父さんも、決死の思いで手助けしていたし 自分がその立場にいたら・・と思うとなかなか非難はできないな でも主人公が他の家のユダヤ人の家を破壊するのを手伝って率先してやってしまったところとかは 子どもだしなんかフラストレーションとか若気の至りとかなんかわからなくもないけど、でも先生の話とか(泣けた)フリードリヒのこととか知ってるんだから、 そこはそういうことは絶対してほしくなかった けどそれでもやっちゃったってところが、あの時代なのかな、とも思う 最後も悲しかった かわいそうで泣けた これであらかたユダヤ迫害関連の代表作は読んだかな、もういいかな と思ったけどいちばん有名なアンネの日記 あれの完全版を読んでないと気づいちゃったので それも読まないとな・・
Posted by
悲しい話だ。 ユダヤ人というだけで差別されていく友人をドイツ人の少年の目を通じて記している。 周辺の裏切りや態度の豹変も見事に描かれている。
Posted by
読み終わった後も心にしこりが残っている気がする。 読書感想文ででた課題がこの本だったのだが、子供でもわかるような悪い事を淡々と綴っていたのが印象にのこっている。 特に、「僕」がユダヤ人の工場にあるものを破壊するシーンを読んでいて、「僕」が集団心理に惑わされてしまったのではないかと...
読み終わった後も心にしこりが残っている気がする。 読書感想文ででた課題がこの本だったのだが、子供でもわかるような悪い事を淡々と綴っていたのが印象にのこっている。 特に、「僕」がユダヤ人の工場にあるものを破壊するシーンを読んでいて、「僕」が集団心理に惑わされてしまったのではないかということと、自分だったらどうなるかを考えて背すじが凍ったようになった。 とても胸が痛くなる本だった
Posted by
河合隼雄「こころの読書教室」推薦図書。中学生向け。ユダヤ人迫害のノンフィクション。主観を入れずに書かれているのが、一層生々しい。2015.9.6
Posted by
ハッピーエンドが好きです。登場人物のがんばりが報われる物語が好きです。しかし世の中そんな話ばかりでないことも知っています。 戦時中のドイツでの物語。ドイツ人のぼくが見た友人のユダヤ人フリードリヒの生涯。ユダヤ人迫害の様子が、ドイツ人の目から淡々と描かれています。 つらい展開が見...
ハッピーエンドが好きです。登場人物のがんばりが報われる物語が好きです。しかし世の中そんな話ばかりでないことも知っています。 戦時中のドイツでの物語。ドイツ人のぼくが見た友人のユダヤ人フリードリヒの生涯。ユダヤ人迫害の様子が、ドイツ人の目から淡々と描かれています。 つらい展開が見えているため、手に取ることを躊躇していました。思い切って読んでみると、静かな文章がスルリと胸に迫り、つらさに目を背けることなく読むことができました。重い内容のものを読ませることができるのも小説の力なのでしょう。 まだ平和だった幼年期から書かれているため、世の中の変わりようがはっきりと感じられます。 徐々におかしな方向へと進む社会。気が付けば暴動に参加していたことへの恐怖。差別意識が日常化する怖さ。友人を救いたいのに救えない無力感。 これは昔あるところであったことだけでは括れない問題でしょう。現代の日本でも大きな問題として存在するでしょう。 ぼくの感情描写を表立たせないことにより、読み手に考える余白が与えられます。
Posted by
あの頃、ごく普通の市民たちが「洗脳された」かのようなイメージをずっと持っていたけれど、そうではなく、主人公一家のように、自分の家族とユダヤ人の友人たちの命を天秤に掛けなければならない極限の状況の中で、心を失わず、懸命に踏みとどまろうとした人たちも確かにいたのだという、ごく当たり前...
あの頃、ごく普通の市民たちが「洗脳された」かのようなイメージをずっと持っていたけれど、そうではなく、主人公一家のように、自分の家族とユダヤ人の友人たちの命を天秤に掛けなければならない極限の状況の中で、心を失わず、懸命に踏みとどまろうとした人たちも確かにいたのだという、ごく当たり前のことに気づくことができた。 作品は、主人公「ぼく」の目線で淡々と語られていく。 「ぼく」の目を通して、私たち読者は当時のドイツの様子を垣間見ることができる。 また、ユダヤ人の習慣やユダヤ教の儀式のようすも細かく描かれており、「ぼく」と同じように興味深く読み進めた。 フリードリヒが学校を去ることになった時のノイドルフ先生の言葉と、「ぼく」があまりにも自然に暴動を「する側」に回ってしまった場面(多くの人が、このように狂気の渦に巻き込まれていったのだろう)の2つが最も印象的だった。 レビュー全文 http://preciousdays20xx.blog19.fc2.com/blog-entry-455.html
Posted by
ヒトラー政権下のユダヤ人について幼なじみの僕をとおしてみた世界。 こころの読書教室の推薦本。 C8397
Posted by
◆ヒットラーユーゲントの熱心な一員だった作者が筆を抑えて記さざるを得なかった文章。その意志の強さに言葉を失う。◆同じアパートで一週違いで生まれた「ぼく」と「フリードリヒ」の17年間(1925〜42)。幼児のころから、一つずつ二人の違い(=ユダヤ人の徴)が記されていく。作者は、出来...
◆ヒットラーユーゲントの熱心な一員だった作者が筆を抑えて記さざるを得なかった文章。その意志の強さに言葉を失う。◆同じアパートで一週違いで生まれた「ぼく」と「フリードリヒ」の17年間(1925〜42)。幼児のころから、一つずつ二人の違い(=ユダヤ人の徴)が記されていく。作者は、出来事のみを感想や判断を挟み込むことなく淡々と記す。従って、それを判断しそれによって巻き起こる感情は、読み手自身の責任で引き受けるしかない。重い重い読書だった。◆フリードリヒを失った「ぼく」のそれからは『ぼくたちもそこにいた』に続く。 ◆中学校国語教科書掲載「ベンチ」以外は初読。中学生のころは、読んでも(あるまじきこととは思っても)こんなに辛くはなかった。それは、私が幼かったということ。作中の「ぼく」と同じように。 ◆集団心理が変わっていくのが、そして理性ある人々も生活を守るために行動を変えざるを得ないところが、物凄く怖い。 ◆ムスコが初めて〈教科書で続きを読まずにいられなくなった〉本。 私も彼らと同じ年代で読んでおけばよかった。ちゃんと作品がムスコに伝わっているかどうかは不安だけれど、今の彼の心で受け止められるだけ受け止めることが大事なのだとも思う。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
「われわれに対する偏見というのはもう二千年もの昔からあるんです。~この偏見は中世ならユダヤ人にとって命の危機を意味していましたよ。しかし、人間は、その間に、少しは理性的になったでしょうからね」 「ぼくたちの仕事が気に入ったら、ほかの人にも紹介してくれるだろ。」 「ぼくといっしょにいるところを見つかったら、かのじょは収容所ゆきなんだもの!」 「ああ、そうなんだ。だから不安で不安で、つい興奮してしまうんだ。こわい!死にそうなほどこわいんだ!」 「わたしにお恵みを与えてくださるならば、死だ。でなければ、いいようのない苦しみだ。だがその危険は、わたしに迫っているだけではない。わたしをかくまい、家に入れてくれた人たちにも、危険が迫っている。」 『兵たちには憐れみの心など、獲物への欲望のもとに、枯れつくしてしまっていた。家々に踏みこみ、生けるものすべてをなぶり殺し、死者をはずかしめた。~およそ価値あるとみれば盗み、さもなければ形をとどめぬまでに殺したり焼き払ったりした。』 人間は良くも悪くも状況に合わせてどんな風にでも適応してしまう生き物で、自分の中に醜悪さがあることは知らないより知っておいたほうがいいことだと思う。後は多分自分から離れて自分を見ることと他人が鏡である意識かなあ、と子供ながらに考えた記憶。
Posted by