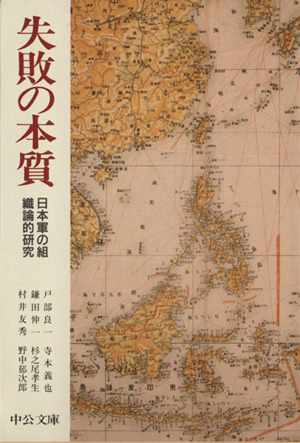失敗の本質 の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
1.失敗の事例研究 ①ノモンハン事件(失敗の序曲) ・作戦目的が曖昧 ・中央と現地のコミュニケーション不足 ・情報の受容や解釈に独善性 ・戦闘は過度の精神主義 ★初めての本格的な近代戦 ★大本営は明確な指示を出さず「察して」 ★関東軍は大本営に内緒で作戦計画、大本営の方針を無視 ★歩兵の逐次投入、火力の軽視 ②ミッドウェー海戦(海鮮のターニングポイント) ・作戦目的の二重性 ・部隊編成の複雑性 ・不測の事態への対応力のなさ ★戦闘は錯誤の連続、より失敗の少ない方が勝つ ★目的は「米空母群を誘い出し航空決戦にて撃滅すること」であり「ミッドウェー攻略」そのものが目的ではなかった。この山本五十六の意図が現場レベルまで理解されてなかった。 ③ガダルカナル作戦(陸戦のターニングポイント) ・情報の貧困 ・戦力の逐次投入 ・米軍の水陸両用作戦に有効に対処できず ・陸軍と海軍が連動できず ★戦略的グランド・デザインの欠如 ★帝国陸軍は中国の重慶攻略を主軸におき、対米を念頭においていなかった。そのためガダルカナルの重要性を理解できず明確な戦略を立てることができなかった。 ④インパール作戦(賭の失敗) ・しなくてよかった作戦 ・戦略的合理性を欠いた作戦が実施されるに至った ・人間関係を過度に重視する情緒主義 ・強烈な個人の突出を許容するシステム ★牟田口司令官の個人的な想いから無茶な作戦を結構 ★直属の上官である河辺すら止められず ★コンティンジェンシープランを軽視 ⑤レイテ沖海戦(自己認識の失敗) ・"日本的"精緻を凝らした独創的作戦計画 ・参加部隊(艦隊)が任務を十分把握しきれず ・統一指揮不在 ★栗田艦隊謎の反転 ⑥沖縄戦(終局段階での失敗) ・作戦目的が曖昧 ・戦略持久か?航空決戦か? ・大本営と沖縄現地軍との認識のズレ、意思の不統一 2.失敗の本質 ■戦略上の失敗 ・曖昧な戦略目的 ・短期決戦の戦略志向 ・主観的で「帰納的」な戦略策定 ・空気の支配 ・狭くて進化のない戦略オプション ・アンバランスな戦闘技術体系 ■組織上の失敗要因分析 ・人的ネットワーク偏重の組織構造 ・属人的な組織の統合 ・学習を軽視した組織 ・プロセスや動機を重視した評価 3.失敗の教訓
Posted by
解説不要なほど著名な本ですが、経営者や組織運営に携わっている人には本当に必読な本だと思います。 環境に適応しすぎて学習棄却ができず、自己革新的な組織になれなかったことが真因と分析しています。 不明確な指示や目的、相手戦略の軽視と自軍の過大評価、人的融和を重んじてしまったため組織と...
解説不要なほど著名な本ですが、経営者や組織運営に携わっている人には本当に必読な本だと思います。 環境に適応しすぎて学習棄却ができず、自己革新的な組織になれなかったことが真因と分析しています。 不明確な指示や目的、相手戦略の軽視と自軍の過大評価、人的融和を重んじてしまったため組織として適切な判断や行動が取れなかった(取らなかった)ことなど。 この本が書かれた41年前にも、既に日本企業の変革に疑問を呈してますが、それからさらに40年近く経つ今日も、示唆に富むことばかりです。繰り返しになりますが、必読の書です。
Posted by
本書は、旧大日本帝国陸海軍がいかに失敗を繰り返し、崩壊をしてしまったのか?「敗北の記録」を徹底的に分析・研究することによって、大小種類問わず日本の「組織」というものに重要な教訓を与えてくれるものです。 本書は、旧日本軍が敗亡のきっかけとなったノモンハン。ミッドウエー。ガダ...
本書は、旧大日本帝国陸海軍がいかに失敗を繰り返し、崩壊をしてしまったのか?「敗北の記録」を徹底的に分析・研究することによって、大小種類問わず日本の「組織」というものに重要な教訓を与えてくれるものです。 本書は、旧日本軍が敗亡のきっかけとなったノモンハン。ミッドウエー。ガダルカナル。インパール。レイテ。そして沖縄という大東亜戦争中における六つの作戦の失敗がどのようにして起こり、日本が敗亡して行ったのかをケーススタディーとし、詳細な研究・分析・考察を加えたものです。まず一番の対象としているのは経営者向けの本であるといえます。 『失敗』の中にこそヒントは多く隠されているものなのかもしれません。実のところをいうと、僕自身もまた、20代のときに大きな失敗をして、現在もほぼ毎日のように 『なぜあの時失敗したんだ…。』 と自分の内部を抉り出すことが毎日一回はあるわけですが、本書を読んで自分がなぜあの時失敗したのかがおぼろげながら見えてきたような気がしました。 それはさておき、本書を読んでいてつくづく思うのは、日本人の持つ「欠点」というものが詳細にあぶりだされていて、「組織」で動くとかくも同じ失敗をしてしまうのか…。ということを幾度も思い知らされてしまうのでありました。 組織の究極の姿は軍隊であり、旧日本陸海軍もまた然りでありまして、今の日本人よりもずっと優秀であったわけですが、なぜ国を滅ぼすまでになってしまったのか…。ミッドウェイでは敗北の結果を国民に示さず、ガダルカナルでは戦力を逐次投入し、インパールでは「イチかバチか」の賭けに出てあえなく敗れ去り、レイテでは情報・通信の不備により「武蔵」を失うなどの大きな損失を受ける。そして、沖縄戦では大規模な地上戦が行われ、民間人にも多くの死傷者を出す…。 失敗の記録を研究するということで、読みながらだんだん気落ちしてくるのですが、やっぱり多かれ少なかれ 「自分にもあったなぁ…。」 ということを痛感させられるのでありました。 本書の記録には膨大な数の「犠牲」の上に成り立っていることを読んだ後に悟り、また 『優秀な人間たちが集まってもなぜこういう失敗が起こるのか?』 という疑問をこれからも問い続けるために、本書を読んだ意義は本当に深いと思っております。 ※追記 本書の著者の一人である野中郁次郎氏は2025年1月25日、肺炎のため死去しました。89歳でした。この場をお借りしてご冥福をお祈りいたします。
Posted by
陸軍の白兵銃剣主義、海軍の艦隊決戦主義という日露戦争の成功体験から制度や技術や武器が相互補完的に強化されすぎ、新しい環境に直面した時、変革を起こせず失敗した。つまり、日本軍の自己変革能力の欠如が失敗の本質があったという内容。 その通りだが、現代の誰でも陥いる失敗であると理解すべ...
陸軍の白兵銃剣主義、海軍の艦隊決戦主義という日露戦争の成功体験から制度や技術や武器が相互補完的に強化されすぎ、新しい環境に直面した時、変革を起こせず失敗した。つまり、日本軍の自己変革能力の欠如が失敗の本質があったという内容。 その通りだが、現代の誰でも陥いる失敗であると理解すべき。敵や未来を完全に見通す事は不可能で、集めた情報の中で最善と思う策をとった結果陥る失敗。 これを避ける為にはリーダーは自律的価値判断ができる人、つまり損得ではなく責任をとれる人をリーダーに選ぶ事。 メンバーも自らの仕事にプライドを持って自律的に働く事、というドラッカーの言葉につながる。
Posted by
大東亜戦争における日本軍は、環境の変化に合わせて自らの戦略や組織を主体的に変革することができなかった。日清・日露戦争での「白兵銃剣主義」「艦隊決戦主義」の成功体験が、大東亜戦争の際の日本軍の環境適応を妨げていた。第一次世界大戦を最前線で経験していないのも大きい。 また、戦略策定は...
大東亜戦争における日本軍は、環境の変化に合わせて自らの戦略や組織を主体的に変革することができなかった。日清・日露戦争での「白兵銃剣主義」「艦隊決戦主義」の成功体験が、大東亜戦争の際の日本軍の環境適応を妨げていた。第一次世界大戦を最前線で経験していないのも大きい。 また、戦略策定は戦略的合理性ではなく組織内の人間関係の融和の結果の妥協の産物としてなされていた。勝利のために合理的な戦略を立てるシステムを構築しているアメリカ軍に敗北するのも当然と言える。
Posted by
この本を知らなかった自分が恥ずかしいくらいの名著だった。 日本軍が大東亜戦争中に犯した6件の戦闘上の大失敗を分析し、組織としていかに未熟だったかをつまびらかにする。ノモンハン事件、ミッドウェー海戦、ガダルカナル島、インパール作戦、レイテ海戦、そして沖縄戦。それぞれ名前は知っていた...
この本を知らなかった自分が恥ずかしいくらいの名著だった。 日本軍が大東亜戦争中に犯した6件の戦闘上の大失敗を分析し、組織としていかに未熟だったかをつまびらかにする。ノモンハン事件、ミッドウェー海戦、ガダルカナル島、インパール作戦、レイテ海戦、そして沖縄戦。それぞれ名前は知っていたが、展開を俯瞰したことはなく、よく掴むことができた。 特にインパール作戦やガダルカナル作戦はひどい作戦の代名詞のように扱われすぎていて、まじめに振り返る気にもならない人も少なくないのではないか。けれど、そのひどい作戦が実行された背景を知れば知るほどに、数千、数万の命こそ懸かっていないにせよ、同じような展開で物事が進んでいく事例はいまも身近にある気がしてならなかった。 それだけで申し分ないのに、さらに問題は組織や戦略自体に内在されていたこと、加えてそれが今日の日本の組織にも改善されないまま引き継がれていることまで指摘する。慧眼というほかない。 昭和59年に書かれた本だという。当時は戦後40年目を迎えようとしていたころ。それからさらに40年がたった。80年前の事象について書かれた本なのに、いま日本の各所にあるさまざまな組織がどのように運営されているかが気になって仕方ない。その時間を飛び越えた感覚が面白くもあり、心配でもある。 自分も組織に属する一人として、失敗の道をひた走っていないか、少なくともコンティンジェンシー・プランはあるか、声を上げやすい雰囲気が維持できているかなど、この本で学んだことには気を配っていきたい。
Posted by
日本軍の組織論的研究から導き出される失敗の本質は、今の組織にも置き換えられる。とても示唆に富む一冊だった。 特に印象に残ったのは「適応は適応能力を締め出す」ということ。
Posted by
思考が硬直したトップの判断で、簡単に数万人亡くなっているのは悲しい。内容が重いので、真面目に読んでしまった。
Posted by
おっもしろかったー!1番印象的だったのは“コンティンジェンシープラン(不測の事態に備えた計画)がなかった”ってところ。いまだに「失敗した時のことを考えるのか」って空気あるときあるよね。
Posted by
会社でよく失敗学の参考にと挙がる本。生死を賭けた戦争と会社の組織論を対比するのは無理があるのではと思ったが、共通する点は結構あるような印象。ただ、よく会社で紹介されるショボい事例とは大分gapがある(意味あるのかアレ)。後半の今後の日本に向けてで、まだこの頃はバブル期のイケイケの...
会社でよく失敗学の参考にと挙がる本。生死を賭けた戦争と会社の組織論を対比するのは無理があるのではと思ったが、共通する点は結構あるような印象。ただ、よく会社で紹介されるショボい事例とは大分gapがある(意味あるのかアレ)。後半の今後の日本に向けてで、まだこの頃はバブル期のイケイケの日本が残ってるが、今の日本の状況を見ると...。時代を感じる。
Posted by