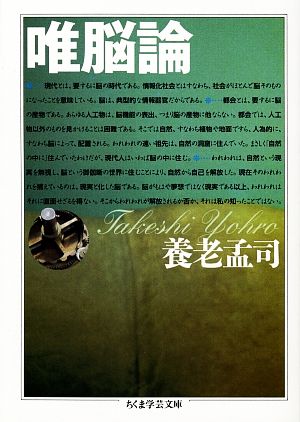唯脳論 の商品レビュー
解剖学者である作者な…
解剖学者である作者ならではの資料です。脳がなければ、人間は成り立たない!!
文庫OFF
バカの壁は、この本を…
バカの壁は、この本を読んではじめて理解できる。
文庫OFF
人間がもたらす活動、…
人間がもたらす活動、そして人間の機能 それは全ての中心は脳である! 筆者は解剖学者でもあり、豊富な資料で分かりやすかった
文庫OFF
現代社会は全て「脳」が創り出したモノである。 この本を読んだ直後にホームセンターに用事で行ったのですが、人間ってすげえってなりました。
Posted by
「エネルギーを巡る旅」に人間は脳化社会を作っていると記述があった事から、20年ぶりに読んでみた。後半は理解できない部分が多かったが、環境問題を論じる人が理性的でないように感じるのは、そもそも自然と脳つまり理性は対立するのが本質だから当たり前とはさすが養老先生。
Posted by
視覚と聴覚の連合、これが意味する内容の考察が興味深い。また、この感想を書く行為も脳による行為であることを自覚し、我々が脳社会の住人であることを想起する。
Posted by
唯脳論とは何か。その定義に先ず惹きつけられる。ヒトの歴史は、「自然の世界」に対する、「脳の世界」の浸潤の歴史。ヒトが人である所以は、言語、芸術、科学、宗教等のシンボル機能により、物財の交換、創造が為されること。また、差異を説明しようと、言わば神学論争のような決着のつかぬ、相互の説...
唯脳論とは何か。その定義に先ず惹きつけられる。ヒトの歴史は、「自然の世界」に対する、「脳の世界」の浸潤の歴史。ヒトが人である所以は、言語、芸術、科学、宗教等のシンボル機能により、物財の交換、創造が為されること。また、差異を説明しようと、言わば神学論争のような決着のつかぬ、相互の説得を為すこと。ユヴァルノアハラリを彷彿させる論であり、寧ろ、これがオリジナルではとも感じさせられた。 都会が脳の産物であり、それを別著ではデジタル化とも表現していたが、確かに、最早、都市には自然は略残されいないのだろう。制度や建築物、あらゆる人間の営為は、確かに全て人工物だ。数少ない自然は、天候や災害、それと著者の愛する虫位だろうか。だから唯脳論なのかと、分かりやすい。 また、脳と心の関係性についての解説も秀逸。これは、構造と機能で表される。つまり、心臓と循環、肺と呼吸のような事だ。解剖学ならではの視点かと思うが、確かに循環や呼吸を心同様に切り出す事は出来ない。実物は構造の方なのだから。 数多ある養老孟司の著作、主張の原点とも言える代表作。これは、古典としても読むべきだろう。
Posted by
『バカの壁』(2003年、新潮新書)以前に書かれた著作では、著者の代表作といえる本です。 著者は、「ヒトの活動を、脳と呼ばれる器官の法則性という観点から、全般的に眺めようとする立場を、唯脳論と呼ぼう」と述べています。ただし唯脳論は、「世界を脳の産物だとするものではない」と注意が...
『バカの壁』(2003年、新潮新書)以前に書かれた著作では、著者の代表作といえる本です。 著者は、「ヒトの活動を、脳と呼ばれる器官の法則性という観点から、全般的に眺めようとする立場を、唯脳論と呼ぼう」と述べています。ただし唯脳論は、「世界を脳の産物だとするものではない」と注意が付されています。こうした誤解は多かったようで、「解説」を執筆している澤口俊之も、本書が「世界は脳の産物だ」という主張をしているものと誤解をしていたことを告白しています。なお、この点についての著者の主張を正確に理解していたのは池田晶子で、『メタフィジカル・パンチ―形而上より愛をこめて』(2005年、文春文庫)のなかで的確な批評が提示されています。 「唯脳論」の中心的な主張はむしろ、「ヒトの作り出すものは、ヒトの脳の投射である」という著者のことばに、明確に示されているといってよいと思います。いわゆる心脳問題については、心臓と血管系の機能が循環であるように、脳の機能が心であるという主張が語られており、そうした立場から視覚系の機能と聴覚系の機能を区別して、人間の言語についての独自の考えが展開されていますが、心の哲学などでかまびすしく論じられている問題についての唯脳論の立場からのくわしい議論が提出されているわけではありません。 たとえば著者は、「われわれは、背中がカユイ時に、背中のことについてなにかを知っているのではない。脳についてなにかを知っているのである」と断言しますが、「脳についてなにかを知っている」にもかかわらず、それを「背中についてなにかを知っている」のだという思い込みが生じている以上、われわれは「背中についてなにかを知っている」ということがどのようなことであるのかを理解しているはずです。心の哲学では、志向性をめぐる議論においてこのような問題がさかんに論じられているのですが、本書にこうした問題のこたえを見いだすことはむずかしく、「文系と理系の対立を脳に還元してみる」という著者の企図はかならずしも成功しているとはいいがたいように思います。
Posted by
養老先生の本は、この本から読み始めるのがオススメです。先生の書かれる本に通底する考え方、物の捉え方が書いてあります。
Posted by
”現代とは、要するに脳の時代である。情報化社会とはすなわち、社会がほとんど脳そのものになったことを意味している。脳は、典型的な情報器官だからである”(本書p007より) この一文で始まる本書は、脳科学がここまで人口に膾炙する前、1989年に発表され、これからは”脳の時代である”...
”現代とは、要するに脳の時代である。情報化社会とはすなわち、社会がほとんど脳そのものになったことを意味している。脳は、典型的な情報器官だからである”(本書p007より) この一文で始まる本書は、脳科学がここまで人口に膾炙する前、1989年に発表され、これからは”脳の時代である”ということを喝破した一冊である。『現代思想』に月1で連載された論考がベースになっており、脳を巡り様々なテーマが綴られていくが、その人文社会学までも射程圏内にある著者の知性の幅広さと、解剖学者としての長年の経験に基づくその知性の深さという、2つの力が見事に結実した知的論考と言える。 私が本書を手に取ったのは、敬愛する菊池成孔が「自身が選ぶ100冊」的な文章の中で選んでいた1冊であったからである。その選出の理由がよく分かったのは本書において言語と音楽、リズムについて記されている章を読んでからであった。 人間が言語を獲得した1つの仮説として「自分の発語を自分で聴く」というフィードバックサイクルの存在を提示した上で、同様のメカニズムが音楽においても存在していること(いうまでもなく楽器の演奏においては、常に自らの音を聴き、他人の音と合わせた上で音量・ピッチ・トーン・テンポなどを調整するというフィードバックが常に働く)を示す。その仮説を裏付ける材料として、失語症と失”音楽”症(理由なく急に楽器の演奏ができなくなる)は、脳内の近接領域の機能不全から起こっている・・・、という議論の流れなど、音楽愛好者にとってはこの上なくスリリングな知的興奮を味わわせてくれる。
Posted by