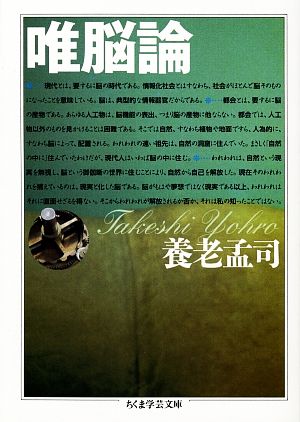唯脳論 の商品レビュー
ヒトの作るものはヒトの脳の投射。 社会の構造も、脳の機能の投射となる。 視覚/聴覚と運動の関係。人間が出力するものの様態を考える上での根幹になっている。
Posted by
今考えていること、哲学や社会学を通っていたが、なにか、あっけなくまとめてもらえた感覚だ。一連の終わりみたいな位置だった。少しの間、読書がライトになりそうだ。脳ね。いや体ね。社会も世論も本音と建前ではもううまく出来上がるわけがない。性も死も伏せててなにを語れるんだと。無理に決まって...
今考えていること、哲学や社会学を通っていたが、なにか、あっけなくまとめてもらえた感覚だ。一連の終わりみたいな位置だった。少しの間、読書がライトになりそうだ。脳ね。いや体ね。社会も世論も本音と建前ではもううまく出来上がるわけがない。性も死も伏せててなにを語れるんだと。無理に決まってる。食を語って埋葬を語らず。死も体もなし。死んだら画面から消えるゲームの世界。読後にちょっと思った。言わなかったことが言いたかったことだったり、ヒトに信念があるから自然は復讐するんだと、それを理解しない風潮はより悪化していると感じさせた。
Posted by
・意識とは、脳が脳のことを考えることだ ・下等生物には、意識がなくて、人間に意識があるのは、脳が進化してきた過程にある ・末梢神経と脳の神経細胞は地図関係にある (だから足がない人も足が痛むことがある) ・言語でも知覚言語と音声言語で違う
Posted by
現代社会は脳が社会に反映されている、いや脳そのものになったという当時としては斬新であったと思われる31年前にあたる平成元年出版の著作。 脳と社会に纏わることの証左を様々挙げながら、また特に著者の専門である解剖学の専門的な知識にも及んで、解説にもある通り、時々起こるような脳ブームの...
現代社会は脳が社会に反映されている、いや脳そのものになったという当時としては斬新であったと思われる31年前にあたる平成元年出版の著作。 脳と社会に纏わることの証左を様々挙げながら、また特に著者の専門である解剖学の専門的な知識にも及んで、解説にもある通り、時々起こるような脳ブームのきっかけとなった本である。後に著書のヒット作「バカの壁」に繋がる代表作。 もちろん脳科学にも近接領域があって、心理学や哲学の文系よりの分野を巻き込んむが、その端緒になったようだ。 私たちは脳の中に住んでいる、という指摘をされると理解できる、というように人々が気付かないが本質的なことを著者の養老孟司は言ってくれるので結構長いこと著者のことが好きだ。本質や思い込みを指摘してくれることも大事だが、今東京では喫煙しにくい状態になっているのだが、養老孟司は喫煙者でありそこもいい。
Posted by
著者の博識を直感的な表現で記述されると、それが何を意味しているのか、バカの壁が高い者にはなかなか理解することは難しい。
Posted by
唯脳論とはなにか◆心身論と唯脳論◆「もの」としての脳◆計算機という脳の進化◆位置を知る◆脳は脳のことしか知らない◆デカルト・意識・睡眠◆意識の役割◆言語の発生◆言語の周辺◆時間◆運動と目的論◆脳と身体
Posted by
昔、ヒトは洞窟に住んだり、森で獣を捕まえたり、自然の中で生きていたが、文明が進むにつれ、建築物や道路、街路樹に囲まれた社会を作っていった。この社会は脳の大脳皮質が生み出した幻想。▼都会に住んでると、周囲のあらゆるモノゴトは単なる記号や情報にしか見えなくなってくる。自然から切り離さ...
昔、ヒトは洞窟に住んだり、森で獣を捕まえたり、自然の中で生きていたが、文明が進むにつれ、建築物や道路、街路樹に囲まれた社会を作っていった。この社会は脳の大脳皮質が生み出した幻想。▼都会に住んでると、周囲のあらゆるモノゴトは単なる記号や情報にしか見えなくなってくる。自然から切り離されたデジタル世界に生きてる錯覚になる。でも、ネットとかで生々しい死体の写真や「九相詩絵巻」を見ると、「あぁ、ヒトも自然の一部なんだ」「あらゆる意識を生み出すのは脳という身体の器官なんだ」と気づいて背筋がゾッとする。心地よい幻想から目が覚めて、生々しい自然の中にいることに愕然とする。隠されるものは、一皮剥いだ死体、すなわち異形のものである。しかし、それがヒトの真の姿である。なぜなら、われわれがいかに進歩の中へ逃走しようと、それが自然なるものの真の姿だからである。ヒトを生み出したのは、その自然である。『唯脳論』1989 *********************** サヴァンのカレンダー計算能力、眼前の景色を完全に記憶するカメラ・アイ、演奏された曲をその場で覚える、桁の大きい素数を順次追う能力。これら能力はヒト社会では役に立たない。要求されるのは言語を使って他人と共有する力。p.165『人間科学』2002 機能は場所が決まっていない。肺の場所は決まっているが、呼吸の場所は決まっていない。心臓の場所は決まっているが、循環の場所は決まっていない。筋肉の場所は決まっているが、運動の場所は決まっていない。脳の場所は決まっているが、意識の場所は決まっていない。▼人間は自分の内臓に発生するがん細胞を感知できない。人間が感知できるのは外界。※ブラックジャックが自分で自分を手術したのは、客体でない自分の内部を客体化している?『からだを読む』2002 元気な自分と死にそうな自分は別の人。死ぬのは私ではなく別の人。死体は私にとって想像ではなく、平たい現実。▼フツーの顔を何枚も重ねていくと美人(特別)になっていく。当たり前の極限がノーベル賞。▼与えられた自然状態に対して、人間社会がやり遂げたことを考えれば、日本は世界でも模範的な国家のひとつ。p.242『人生論』2004 感覚の世界ではすべてが違うが、言葉の世界ではすべてが同じ。言葉の「リンゴ」は赤くても青くても、大きくても小さくてもリンゴ。マンガはその「違う」と「同じ」をつなぐところに位置している。感覚の世界が地面で「同じ」の世界が天井で、そこに唯一絶体の神がある。p.34。人間は12兆個の細胞からできたものすごく複雑なもの。人間の複雑さに比べたら、原爆なんておもちゃみたいに簡単。そういう簡単なものに、ややこしいものをこわす権利はない。p.143『マンガをもっと読みなさい』2005 人は眠るとき意識が切れている。起きていると意識がある状態が続き、眠っている間は意識は切れている。死ぬということは最後に意識が切れてもう戻ってこない状態をいう。人生は点線。▼人が抱く死への恐怖は生前のものであって、死後は意識はなく死への恐怖もない。『養老訓』2007 現代人の悩みは人間関係の比重が大きすぎる。人間関係が肥大しすぎている。家族がどうだとか、友達がどうだとか。▼自然がない。花鳥風月。気ままな猫。方丈記。人間はあくまで自然の一部であり、自然の世界が縮小しすぎるのは良くない。▼日本人は7割が自分は無宗教と思っている。無宗教の「無」は仏教の無。『未来を変える選択』2012 理系と文系の違いよりも、野外か実験室かの違いが大きい。『文系の壁』2015 同じの世界:見えているものが同じ,意識,数学,一神教,グローバル,イコール。違うの世界:見えているものが違う,感覚,芸術,多神教,ローカル,ノットイコール。現代社会は「同じの世界」に偏り,バランスを欠いている.たとえば,「白」という文字.これは意識でとらえると白色,感覚でとらえると黒色(文字は黒色だから).鴨川はつねに鴨川だと思っているが,流れている水は常に違う水.私はつねに私だと思っているが,人の身体は物質的には7年で入れ替わって違うものになる.人間はイコールを理解できるが,動物はできない.猿の話.朝三暮四(ちょうさんぼし)目先の違いに囚われて,実際は同じであることに気付かない.都市社会はエアコンで「同じ」気温,照明で「同じ」明るさ,石の床は「同じ」堅さ.「違う」「変化」は排除される。人間関係は「同じ」が好まれ,「違う」「変化」は嫌われる.生身の人間は常に変化する.その「違い」や「変化」が面倒臭い.いらない.となる。*ペットは「死ぬ」から飼うのを嫌がる人がいるが,これも「死ぬ」という自然の「変化」を嫌う現代人の特徴なのかも.『遺言』2017
Posted by
たぶん養老さんの伝えていることの0.5%くらいしかわかってない。それでも面白いと思った。難しいけど、その着眼点にハッとさせられたりひやっとしたり。 もうぜんぶがぜんぶ、脳に支配されてるじゃんって思った。自分で考えたって思ってることも、嬉しいという感情も、行動も、そしてこの社会も、...
たぶん養老さんの伝えていることの0.5%くらいしかわかってない。それでも面白いと思った。難しいけど、その着眼点にハッとさせられたりひやっとしたり。 もうぜんぶがぜんぶ、脳に支配されてるじゃんって思った。自分で考えたって思ってることも、嬉しいという感情も、行動も、そしてこの社会も、ぜーんぶ。脳にとって都合のいいことが快感になって、脳にとって都合のいい方向に人間が進んでいく。 唯一死ぬことだけは脳は制御できない。これが唯一の自然。どんなこともぜんぶ脳に戻されるから、なんだかもう何も信じれないというか、考え始めると学習も思考も人生もぜんぶが取るに足らないことに思えてくるんだけど、一方で、だから、自分の脳を満足させてやるように生きようと思ったり。 もっと「経験」をつんだら、もうちょと理解できることが増えそうだから、本棚の見えるところに大事にとっておいて、また数十年後読み返そう。 (メモ) 唯脳論 ヒトの活動を、脳と呼ばれる器官の法則性という観点から、全般的に眺めようとする立場を、唯脳論と呼ぶ。 この本でわたしが述べようとするのは、文科系ひおける言葉万能および理科系における物的証拠万能に頼るだけでなく、すべてを脳全体の機能へ改めて戻そうとする試みである。だから、「唯脳論」なのである。 脳は「物(構造)」 心は「機能」 機能は構造から出てこない 身体の他の臓器と脳の決定的な違いは、脳には自己言及性があるということ。 自己言及性とは、自分で自分のことを考えること。(つまり、意識) それゆえに自己参入の矛盾を生じさせる。 →ラッセルの逆理、リシャール数 末梢を十分支配しない神経細胞は死ぬ 相手のない、あるいは相手に不足のある神経細胞は、間引かれてしまう。 →この前提から意識の発生を考える 受け取る側の脳だけが進化の過程で勝手に大きくなることはない。 では大きくなった理由は、 神経細胞が脳の中でできるだけお互い同士つながり合うことによって、お互いに「末梢」あるきは「支配域」を増やす。それによってお互いを維持する。(機能的に言うなら互いに入力を与え合う) 脳内の神経細胞が増加し、外部からの入力、あるいは直接の出力の「量」だけに依存するのではなく脳の自前の、あるいは自慰的な活動に、神経細胞の維持が依存するようにになったとき、意識が発生したと考えられる。 意識がそう言うものだとすれば、その単純な生物学的意味とは、神経細胞の維持である。
Posted by
シンプルにもう一回読みたい。難しかったが、脳の存在意義について、自分にはない考えを取り込むことができた。
Posted by
「心も社会も脳の機能である」。この本は脳の解説書ではないと著者は言う。しかし広く深く脳に関わりのあるさまざまな話題を取り上げている。心身二元論などのまやかしは胡散霧消し、脳が心を作りだした。この社会も世界もわれわれの脳が作り出したものである。構造と機能。視聴覚系と運動系。現在の脳...
「心も社会も脳の機能である」。この本は脳の解説書ではないと著者は言う。しかし広く深く脳に関わりのあるさまざまな話題を取り上げている。心身二元論などのまやかしは胡散霧消し、脳が心を作りだした。この社会も世界もわれわれの脳が作り出したものである。構造と機能。視聴覚系と運動系。現在の脳科学はこの本が書かれたときよりもより一層脳が世界を作り出していることを解き明かしつつあるようだ。
Posted by