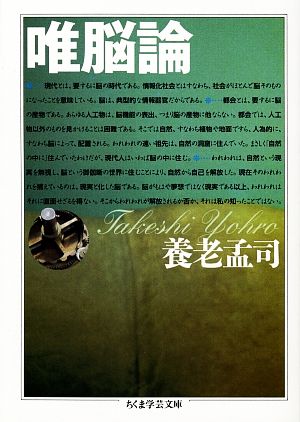唯脳論 の商品レビュー
書いてる内容は凄く難解なのにスラスラ読み進んでいく興味深い脳みそ。ヒトを考えることは脳みそを考えることなのか。興味深い。
Posted by
養老氏の著作の原点? 解剖学者という視点から明快に説明されており わかりやすい 脳 機能 回路⇒思考 意識と話が進む 現代の脳が優位な背景を 知ることができる
Posted by
評判の割に、脳科学の側面からそこまで精神てものには突っ込んでない印象。論っていうにはちょっともんやりするよな感じ。
Posted by
残念ながら、自分が理解するにはまだ程遠い。 他の書物を読み耽ってから再挑戦。 以下項目抜粋。 ・ヒトが人である所以 ・心は脳から生じるか ・自己言及性の矛盾 ・死体は存在するか ・神経系とはなにか ・脳の構成要素 ・神経細胞のはたらき ・計算能力について ・脳に起こることだけが...
残念ながら、自分が理解するにはまだ程遠い。 他の書物を読み耽ってから再挑戦。 以下項目抜粋。 ・ヒトが人である所以 ・心は脳から生じるか ・自己言及性の矛盾 ・死体は存在するか ・神経系とはなにか ・脳の構成要素 ・神経細胞のはたらき ・計算能力について ・脳に起こることだけが存在する ・「考える主体」は要らない ・眠りは生の一形式 ・意識の生物学的意義 ・言語の身体性 ・失「音楽」症 ・時間と自己同一性
Posted by
たぶん4年ぶりくらいの再読。 ようやく少しずつ分かるようになってきたような気がする。 でも、養老さんの知識の量や考えの深さが半端無いから言われていることがなかなか理解できない。 わたしの脳の中に養老さんの脳の中にあるのと同じ構造がなく、その機能が働かなければわかるということは...
たぶん4年ぶりくらいの再読。 ようやく少しずつ分かるようになってきたような気がする。 でも、養老さんの知識の量や考えの深さが半端無いから言われていることがなかなか理解できない。 わたしの脳の中に養老さんの脳の中にあるのと同じ構造がなく、その機能が働かなければわかるということはない。 ただ、学習によって脳は変化するから、もし今回すこしはわかったような気になれたとしたらこの4年間でわたしの脳も少しは変化したのかもしれない。 それにしても養老さんは素敵だ! Mahalo
Posted by
脳は脳のことしか知らない、他の臓器もまたしかり、っていう発想は斬新す。言われてみればなるほどだけど、どうしても、人間は脳中心で動いてる、って観念にとらわれてしまうし、それが当たり前と思ってしまうから。でも、当たり前を疑うことに興味津々な今日この頃、唯脳論も魅力的な理論に思えました...
脳は脳のことしか知らない、他の臓器もまたしかり、っていう発想は斬新す。言われてみればなるほどだけど、どうしても、人間は脳中心で動いてる、って観念にとらわれてしまうし、それが当たり前と思ってしまうから。でも、当たり前を疑うことに興味津々な今日この頃、唯脳論も魅力的な理論に思えました。
Posted by
僕では理解が難しい。でも、とても興味深い内容でした。 何度も読み返して、理解したいと思える本だと思います。
Posted by
脳の身体性を自覚させられる本。客観性は「外部」に存在するのではなく、「脳」に存在するという当然の事実に気付かされただけでも価値あり。
Posted by
脳のことについて考えているのは自分の脳、というループに迷いこんだ。ヴェラスケスの絵が印象に残っている。
Posted by
一読。よくわからない所も多。印象深かった所など、思いつきメモ。 心は脳の機能である、という。 それならば、筆者は言っていないが、逆から言えば、脳は心の構造である、ともなるはずである。どっちから言ってもよいのだと思う。「脳と心もまた、同じ「なにか」を、違う見方で見たもの」...
一読。よくわからない所も多。印象深かった所など、思いつきメモ。 心は脳の機能である、という。 それならば、筆者は言っていないが、逆から言えば、脳は心の構造である、ともなるはずである。どっちから言ってもよいのだと思う。「脳と心もまた、同じ「なにか」を、違う見方で見たもの」(p.30)だというのなら。にもかかわらず唯心論でなくて唯脳論を説くのは、唯脳論という語り方に利便性があるからなんだろうと思う。つまり、「構造」ということ。 ヒトなら同じ構造の脳を持っているはずである。だったら脳を調べれば、ヒトに「普遍」の形式、変化する中身を容れる、あるいは支える枠組みを把握できる。そして脳は物としてがんとしてそこにある。だったら把握するのに助かるはずである。たぶんそういうようなことだろうと思う。 「脳は脳のことを知る。知るとすればそれ以外にはない(p.112)」「意識にとって存在することは脳に起こることだけ(p.102)」。私が知っているのは、私に起こっていることだけ。私に起こっていることだけを、私は知っている。なんだ、常識じゃないか。なるほど古代人だって知っていておかしくない。 脳に起こるのは、外界の事物との出会いの反応の過程。もうひとつは、脳に出会う脳の反応の過程。脳は、脳以外のものに対して応答するだけでない。脳自身にも応答する。脳は脳にひとり語りする。思考とは、脳に反響するこだまである、とか言ってみたい気分になる。 筆者は直接は言っていないけど、いや「唯脳論はじつは身体一元論(p.41)」ともいっているから、以下みたいに考えてよいかもしれない。 実際日常的には、考えるだけでなくて、しゃべったり、頭をかいたり、お茶を淹れたり、脳内だけでこだまがおこるのでなくて、脳を「電話交換局」として、足の子指から耳の裏まで、体中にこだまが起きている。「思う」すなわち脳内の局所的反響は、私の一部にすぎない。脳は身体の一部にすぎないので。とすると、筆者の言葉(p.119)をもじるなら、たぶんこうなる。「私が存在すると言語で表現される状態、すなわち、私が身体を使う、つまり行為すると言語で表現される状態である。なぜなら、行為することこそ典型的な身体の「意識的機能」、つまり「身体が身体を知っている状態」であるから。」。ロボットは一生懸命働いているけれどたぶん自分が黙々となにか製品を製造していることをしらない。 私の身体、身体の私、私が身体。一つ目は、脳の、脳以外の身体への優位性、二つ目は、脳は抹消の奴隷、三つ目は心身一如、か。身体は、いつの間にか、あった。脳は気付いたら生まれていた。だったら、一つ目は言えない。脳は身体に所有されている。しかし、本当は、別に中枢と末端が主従関係にあるわけでもないから、奴隷ということもない。私が脳に局在しているわけでもない。両者が調和して十全に全身体が機能している所が、心身一如ということか。
Posted by