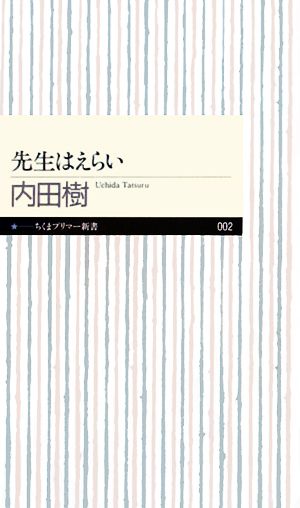先生はえらい の商品レビュー
誤解の余地があるからこそコミュニケーションに意味がある、正解はあってはならない、というのが目から鱗だった。言われてみればそうだよなあ。と納得。
Posted by
内田氏のこの著作『先生はえらい』を自分なりに解釈すると、学ぶ側(学生、生徒)は、 「自分は何を知らないか、できないか」を適切に言うことができない状態を適切だとしている。 そして、先生は、その「何か=知識」を教えてくれるものではなく、 「スイッチ=媒介装置」の役割をすることが適切だ...
内田氏のこの著作『先生はえらい』を自分なりに解釈すると、学ぶ側(学生、生徒)は、 「自分は何を知らないか、できないか」を適切に言うことができない状態を適切だとしている。 そして、先生は、その「何か=知識」を教えてくれるものではなく、 「スイッチ=媒介装置」の役割をすることが適切だと、 つまり、教師は、知識を教授する、しないは、あまり学ぶ側にとって真に必要とせず 学ぶ側が何を知りたいかを自己に問いかけるような存在になるべきだということです。 学ぶ側が、あっ自分自身は、こういう「知」を知りたいんだ、勉強したいんだと、 心の底から思える状態ではあれば、教師の役目は半ば終了し、 学ぶ側は、以後、自発的に学ぶ。 今、学校の授業はシラバス方式(いつ、何を、どう教えるを開示したもの)になっているらしい。 これは、先生を知識提供サービス者とし、勉強する側は消費者とする、 まさに、ビジネスの論理で教育を考えている。 これをやっちゃおしまいよという言葉がありますが、 内田氏曰く、お終いなのでしょう。 つまり今の状況は、学ぶ側にメリットがあるように思えるが (だって知識を効率的に分かり易く教えてくれるんだから)、 しかし、実はあまりメリットがない。 そもそも、教育に対してメリット、デメリットを考えしまうこと自体が、 ナンセンスなのだろうと思う。 結局は知識の過多で点数をつけられるから、仕方ないかもしれないが、 これでは、今も昔も大量の勉強嫌い(点数をつけられ、順番をつけられることが嫌だと思うこと) を生んでしまうように思う。 こういう社会的損失をしっかり把握したほうがいいんじゃないだろうか。 ただ、現に、これではいかん!と思って動き出している先生は多数いる。 ビジネスの論理に負けないで、是非、頑張っていただきたい。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
本書は中高生を対象にした新書ですが、大人にとっても十分読みごたえのある、深い内容の本です。特に教える立場にある人にとってはかなり痛い所をつかれた部分もあるのではないかと思います。 同じことばを語りかけても、聴き手の受けとる情報は同じではない、人それぞれ解釈が違う、という筆者のことばは、正直身につまされました。 学生にはつい「わかりましたか?」と聞いてしまいますが、この質問がいかに愚かなものであったか。こちらの伝えたい意図と違う理解をしていたとわかったときは「やっぱりわかってなかった」とがっかりするのも、こういうからくりがあるとわかれば今後の対処の仕方も違ってきます。 その他、コミュニケーションに関してもいろいろな気付きが得られ、とても学ぶところの多い本でした。
Posted by
内田樹センセイ的 けむりにまく忍術。 『先生はえらい』と言っても、 そんじょそこらのえらさとは違うのである。 『えらい』と誤解することで、えらさがわかるということだ。 つまり、誤解する生徒が もっとえらいのだということらしい。 先生はつねに謎をもっていてわからないことを知っている...
内田樹センセイ的 けむりにまく忍術。 『先生はえらい』と言っても、 そんじょそこらのえらさとは違うのである。 『えらい』と誤解することで、えらさがわかるということだ。 つまり、誤解する生徒が もっとえらいのだということらしい。 先生はつねに謎をもっていてわからないことを知っているはずだ。 そのように 生徒が 誤解してくれることで 先生は 成り立つ。 内田樹センセイの 脱線力というか 雑談力が 実にある。 どうも、ここでは 一般的な教育の場面での 先生と生徒を言っていないようだ。 この本は 高校生中学生を対象にしていると言われるが、 高校生中学生は 先生を選べない。 そして ここでは『生徒』という概念は現れない。 内田樹は『「えらい」の構造分析を通じて、 師弟関係の力学的構造が解明』 されれば、といっているので 『先生と生徒』ではなく 『師匠と弟子』との関係を語っているのだ。 つまり、微妙に話を 変えているのだ。 師弟関係を述べているので 本来この本の題名は 『師匠はえらい』と言うべきだ。 それを間違えて 教師が 『先生をえらい』と誤解してくれることを見通している。 本のマーケティングで言えば 『えらいと言われない先生』が顧客ターゲットだ。 それで、なんとなく けむりに巻かれて 自分は それなりに えらかったんだと 納得するのだ。大いなる誤解と言うべきなのだ。 もう少しいえば 中高生に読ませるならば 『生徒はえらい』にしなければならないが それをしないところに 内田樹センセイのあざとさがある。 『うざい』『だるい』『めんどくさい』 という生徒が読むはずがないからである。 弟子は 師匠を選ぶことができる。 つまり、それは 教祖と弟子との関係にも広がっていく。 張良と黄石公の沓を落とす話も、師匠と弟子の関係を説明する。 弟子は 師匠のやっていることを 弟子が納得しやすいように 理解する。 それを発展させれば、 間違った教義を唱える教祖も えらいのである。 多様性があっていいのだ。とさえ言い切ってしまう。 謎めいている 教祖ほど えらい人はいないからである。 なぜ、オウム真理教が 高学歴の弟子を たくさんつくれたのかを ここでは解き明かしている。 そのような危険性をはらんだ えらいの構造の説明なのである。 結局 内田樹センセイが えらいんだ と思うことで、 免許皆伝となるのだ。 さぁ。するんだ。内田樹センセイに 五体投地を!
Posted by
先生は、知識や技術を教えるだけではなく、生徒に課題を与えて、自らから考えさせることで、新たな考えを気づくことが大切であることが分かった。それは、コミュニケーション全般について言えることが分かった。張良への兵法伝授について、よく表していると思った。
Posted by
この本を読んだことに深い意味はない 笑。そのひとからなにを学ぶかは明確でそのひとがわたしに何を教えるか明確だ。しかしある時、思ってもいなかったことも学んでいることに気がついた。それはわたしが勝手に学んでいる。こんなことまで学ぶのかと驚いた。師弟関係は本質的には弟子の美しい誤解やら...
この本を読んだことに深い意味はない 笑。そのひとからなにを学ぶかは明確でそのひとがわたしに何を教えるか明確だ。しかしある時、思ってもいなかったことも学んでいることに気がついた。それはわたしが勝手に学んでいる。こんなことまで学ぶのかと驚いた。師弟関係は本質的には弟子の美しい誤解やら妄想に基づいて成り立ち、それにより学び成長をする。笑。内田氏、すんごい遠回りして最後に「先生はえらい」でしめてくれている。見事!
Posted by
7誤解が生み出すコミュニケーションについて、教育を軸に展開する。言葉は常に過不足で、ちょっとしたズレや誤解が容認されるからこそ、開けた、生きたコミュニケーションが可能になる。今までの会話観を鮮やかに覆す。マルセル・モースの贈与論を説明するサッカーの例えも秀逸で、言われてみればサッ...
7誤解が生み出すコミュニケーションについて、教育を軸に展開する。言葉は常に過不足で、ちょっとしたズレや誤解が容認されるからこそ、開けた、生きたコミュニケーションが可能になる。今までの会話観を鮮やかに覆す。マルセル・モースの贈与論を説明するサッカーの例えも秀逸で、言われてみればサッカーのルールもとても面白いものに見えてくる。
Posted by
『待ち』に居着いている人間は、絶対に相手の先手を取ることができないからです。(中略) 謎を解釈する立場というのは、謎をかけてくる人に対して、絶対的な遅れのうちに取り残されるということです。 やられたー! オレ、『居着いて』たわー^^;
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
内田先生が中学生くらいに向けて書いている、先生という存在について。 しかし、全教育関係者が必読だと思う。 人によって、えらい先生は違う。それは同じことを言われても捉え方が人によって違うから。 それゆえ、ある先生をえらいと思うかどうかは、受け手次第。「先生運」というものはない。 コミュニケーションとは本質的に、誤解に基づいている。 学びは何かの対価として得られるものではない。 「定量的な技術」を教える場合と、「技術は定量的ではないということ」に気づかせる違い。 定量的な技術を学ばせることが教育のすべてとなっている節がある。だから記憶に残る先生は少ないのでは? 学ぶ側のスタンスについての話だが、学ばれる側にも問題は多い。
Posted by
どんな先生がえらいんだろう。スーパーティーチャーなんていう制度を作っているところもあるそうですが、確かに、ものすごく授業がうまい先生がいます。話がおもしろい。分かりやすい。授業アンケートなんかを見てもほとんどの生徒に指示されている。しかし、どうも著者が考えているえらい先生とはそう...
どんな先生がえらいんだろう。スーパーティーチャーなんていう制度を作っているところもあるそうですが、確かに、ものすごく授業がうまい先生がいます。話がおもしろい。分かりやすい。授業アンケートなんかを見てもほとんどの生徒に指示されている。しかし、どうも著者が考えているえらい先生とはそういうのではないようです。はじめの方はずっと恋愛の話です。「蓼食う虫も好き好き」とか「あばたもえくぼ」とか。きっとそうなんです、どんな先生であっても、受け手の生徒の側がその先生から多大な影響を受けるというようなことがあれば、その生徒にとってその先生はえらいという存在になるのでしょう。中盤から哲学の話になっていくのですが、優しいことばで書いてありながら、内容的にはかなり難しくなります。でも、そこらあたりがおもしろいところ。なんだかよく分からないからこそ、一生懸命読もうとか、授業を聴こうという気にもなるのでしょう。分かりきった授業なら、生徒は寝てしまいます。逆に全く分からないとまた寝てしまう。そのバランスが難しい。万人にとってえらい先生はそうそういないでしょう。でも、あなたにとってえらい先生なら、あなた自身の心の持ちようで、すぐ見つかるはずです。あなた自身が主体的に学ぼうとすれば、きっと「先生はえらい」と思えるようになるでしょう。卒業生のお母様から頂きました。
Posted by