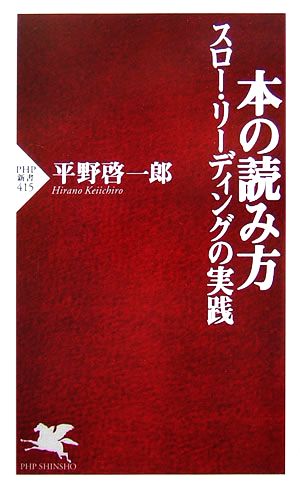本の読み方 の商品レビュー
スロー・リーディングの効能と理論、そして実践。効能と書いたのは、前半にはこんな風に読めたらカッコイイだとか、ゆっくり本を読むことは役に立つだとか、直接的な有用性を説く部分がいくつもあって「一般の社会人向けの本を書くのは大変だな」と同情したから。 前半の理論編にて、速読は読書では...
スロー・リーディングの効能と理論、そして実践。効能と書いたのは、前半にはこんな風に読めたらカッコイイだとか、ゆっくり本を読むことは役に立つだとか、直接的な有用性を説く部分がいくつもあって「一般の社会人向けの本を書くのは大変だな」と同情したから。 前半の理論編にて、速読は読書ではなく単なる情報処理、読書は無理なく読める範囲で充分であり、それ以上は無意味ですらある、とまあズバズバと言い切っていく様は爽快。焦って本を読まずともいいんだな、と肩の荷が下りた。お陰でこの本もゆっくり自分のペースで読んだので、新書なのに1週間かかったのだが(笑)随分充実した時間だったように思う。後半の実践編では読者と共に実際に作品をスロー・リーディングしていき、その楽しみを教えてくれる。いち読者としてはもちろん、創作者の端くれとしても参考になる本だった。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
「量より質」、「速読より遅読」、「読んだ」という経験を大事にすべき、といった内容でした。「読む」だけではなく、「書く」ことにも活かせそうな気がしました。文章を書くことが苦手な方にも、勧めたいです。 「誰かに本の内容を説明することを前提に読む」という読み方がありましたが、ブログでの本紹介やブクログでのレビューを書く癖をつけることで、より一層「読み」が深まるかと思いました。私もやってみます。多分……。
Posted by
本の書いている表面のことしかなぞれなくて、すぐに内容を忘れてしまうのだが、この本に書かれたスローリーディングでどこまで読み込めるか試してみたくなった。
Posted by
平野啓一郎先生の初期の作品である「葬送」を読み始めたところだった。 しかし、これが私レベルではとてつもなく難解で、読み進めるのが難しくなった。 そこで、同じ平野啓一郎先生のこの新書を読んでみた。 お恥ずかしながら、新書を読むのは初めての経験だった。 この本はとても良かった。...
平野啓一郎先生の初期の作品である「葬送」を読み始めたところだった。 しかし、これが私レベルではとてつもなく難解で、読み進めるのが難しくなった。 そこで、同じ平野啓一郎先生のこの新書を読んでみた。 お恥ずかしながら、新書を読むのは初めての経験だった。 この本はとても良かった。 国語の先生などが解説するより、よりリアルに受け入れることができた。 特に気に入ったのがカフカの「橋」を引用し、解説した部分で、声を上げて笑ってしまった。 読み方がとても面白い! あぁ、こんな風に読むのか! 作家ならではの着眼点で、とてもとても興味深く読み進められた。 スローリーディングの本なのに、こちらはとても引き込まれ、あっという間に読んでしまった。 これではダメだと、再読中(笑)
Posted by
【小説は必須】 著者は小説を例にあげていますので、小説についてスロー・リーディングを推奨しています。 わたしもいままで何回か速読を試みましたが、読後、本を読んだ気がしません。全く読了感がありません。内容に関してもなんとなくわかったような、わからないような感じです。 ただ、いわ...
【小説は必須】 著者は小説を例にあげていますので、小説についてスロー・リーディングを推奨しています。 わたしもいままで何回か速読を試みましたが、読後、本を読んだ気がしません。全く読了感がありません。内容に関してもなんとなくわかったような、わからないような感じです。 ただ、いわゆる速読をしなくても、ビジネス書の場合、何冊も読んでいると読む速度が自然に速くなります。 速くなる理由は2つあります。 ひとつ目は、例えば「玉石混淆」と書かれていれば、じっくり考えることなく瞬時に意味がわかります。しかし、「玉石淆混」と書かれていても「玉石混淆」と読み取ってしまいます。 ビジネス書は何回も同じ言葉が現れますし、「玉石淆混」と書かれることはありませんので、この四文字は見た瞬間に意味まで理解できます。 このように何回も出てくる言葉や件はパッと見た瞬間に理解できてしまいます。 これが読む速度が速くなるひとつ目の理由です。 二つ目は、すでに既知の項、段落あるいは章は読まずに飛ばすことができます。章を飛ばすとかなり速く一冊の本を読み終えることができます。また、小説とは異なり読み飛ばしても文脈がおかしくなることはありません。 小説はそうはいきません。既知の部分はありませんし、同じ文章が現れることもありません。表現も繊細なため、さらっと読み流すこともできません。しかし、読み終えたあとの何とも言えない読了感があります。 これが小説のいいところです。活字のみで人物の表情、周りの状況が映像として頭に思い浮かべることができるのです。こんなにすごいことはありません。 すばらしい!
Posted by
スロー・リーディングを提唱するとともに、著者自身によるスロー・リーディングの実演がおこなわれています。用いられているテクストは、夏目漱石『こころ』、森鷗外『高瀬舟』、カフカ『橋』などの小説や、フーコー『性の歴史Ⅰ 知への意志』で、それぞれのテクストの一節を抜き出して、スロー・リー...
スロー・リーディングを提唱するとともに、著者自身によるスロー・リーディングの実演がおこなわれています。用いられているテクストは、夏目漱石『こころ』、森鷗外『高瀬舟』、カフカ『橋』などの小説や、フーコー『性の歴史Ⅰ 知への意志』で、それぞれのテクストの一節を抜き出して、スロー・リーディングのテクニックがじっさいにつかわれる場面に焦点をあてて説明がなされています。 速読が「前へ、前へ」というイメージで読んでいくことであるとすれば、スロー・リーディングは「奥へ、奥へ」というイメージで読んでいくことだと著者は述べています。このことはとくに、著者による『高瀬舟』読解の実演に、よく感じられるように思います。『高瀬舟』は「安楽死」というテーマのもとで理解されることが多いのですが、著者は『高瀬舟』の一節から「献身」と「諦念」という主題をつかみ出し、鷗外の小説群をつらぬくテーマであった「足るを知ること」へのつながりへと踏み込んでいます。
Posted by
一冊一冊を味わい尽くして読む方法を教えてくれる本。 小説の読み方は、参考になった。今までの読み方では、味わいつくせていなかったと思った。 読んだ小説を、もう一度読み直してみようと思った 『なぜ?』と考えながら、著者と会話しながら読むことの大切さを学んだ。 速読にあき、一冊の...
一冊一冊を味わい尽くして読む方法を教えてくれる本。 小説の読み方は、参考になった。今までの読み方では、味わいつくせていなかったと思った。 読んだ小説を、もう一度読み直してみようと思った 『なぜ?』と考えながら、著者と会話しながら読むことの大切さを学んだ。 速読にあき、一冊の本から多くのことを学びたい人にオススメである。
Posted by
ロランバルト、 構造の全体を視野に入れて読むこと、言葉の迷路をさまようことを、方向を持った探求に転じるのだ。 読書を"楽しむ"秘訣は、速読コンプレックスから解放されることにある。 速読の後に残るのは、単に、読んだという事実だけである。 今の自分を肯定してくれる...
ロランバルト、 構造の全体を視野に入れて読むこと、言葉の迷路をさまようことを、方向を持った探求に転じるのだ。 読書を"楽しむ"秘訣は、速読コンプレックスから解放されることにある。 速読の後に残るのは、単に、読んだという事実だけである。 今の自分を肯定してくれる本ばかり読んでいては、益々視野を狭めていくことになる。 即どくかの知識は、単なる志望である。p34 aruimide ,読書は、読み終わったときにこそ始まる。 理解率70%の罠ぁ。 助詞、助動詞 ある作家のある1つの作品の背後には、さらに途方も無く広大な言葉の世界が広がっている 再読、再読、再読、再読を生きよう。
Posted by
副題の「スローリーディング」という言葉通り、速読などの「量の読書」に異を唱え、より楽しい読書のかたちを示した本。 違和感のある個所はその違和感をおしてでも作者が主張したかった何かがある、など普段は時々は気付いたり、気づかなかったりとぼんやりやっている作業をここまで綿密にできれば...
副題の「スローリーディング」という言葉通り、速読などの「量の読書」に異を唱え、より楽しい読書のかたちを示した本。 違和感のある個所はその違和感をおしてでも作者が主張したかった何かがある、など普段は時々は気付いたり、気づかなかったりとぼんやりやっている作業をここまで綿密にできれば確かに楽しいかもしれない。
Posted by
本を読むスピードが遅いことがコンプレックスだった。本はできるだけ速く、できるだけ多く読まなければならない、と焦りながらいつも読書していた。 著者は「読書は量でなく質」と説く。これまでの自分の、がんじがらめの考え方に気づかされた。 特に、以下のテクニック(というか心構え)が参考に...
本を読むスピードが遅いことがコンプレックスだった。本はできるだけ速く、できるだけ多く読まなければならない、と焦りながらいつも読書していた。 著者は「読書は量でなく質」と説く。これまでの自分の、がんじがらめの考え方に気づかされた。 特に、以下のテクニック(というか心構え)が参考になった。 ・書き手の気持ちで読む ⇒音楽と一緒で、何気なく聞き流すより、プレイヤーとして耳を傾けると素晴らしい演奏に気づきやすい。 ・後で誰かに説明するつもりで読む ⇒「なんとなくわかったつもり」で読み流してきた文章、これまでにいくつあったことか。誰かに説明できなければ理解したとはいえない。わからなければ何度でも読む。 これからは、これまで以上に時間をかけて、じっくりと本を味わいたいと思う。読み終えた本も、もう一度じっくり読み直したくなった。
Posted by