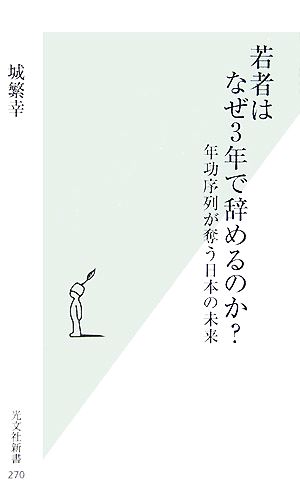若者はなぜ3年で辞めるのか? の商品レビュー
日本の勤労体系 「年功序列」 について書かれた本。 タイトルの付け方がうまい。誰でも、一度は手に取ってみたくなるのではないだろうか。内容も実に明確。ただ、少し男性的であるのが気になる。女性の観点からも書くともっと良いのかもしれない。ただ、もっと複雑になると思うが。 200...
日本の勤労体系 「年功序列」 について書かれた本。 タイトルの付け方がうまい。誰でも、一度は手に取ってみたくなるのではないだろうか。内容も実に明確。ただ、少し男性的であるのが気になる。女性の観点からも書くともっと良いのかもしれない。ただ、もっと複雑になると思うが。 2006年初版だが、内容に納得できてしまうのは、 いまだ日本が「石橋を叩いて渡る」精神が抜け切れてないという事なのかもしれない。 「叩いて壊す」ぐらいの覚悟が必要なのかもしれない。
Posted by
年功序列が色濃く残る(おそらく日本一?)組織で働いている身としては、非常に興味深いテーマについて書かれた新書です。 個人的には、官庁というのは、意思決定において、ロジックだけではなく政治的要素が絡む割合が非常に高い組織であるため(だって行政機関ですもの)、年功序列というシステム...
年功序列が色濃く残る(おそらく日本一?)組織で働いている身としては、非常に興味深いテーマについて書かれた新書です。 個人的には、官庁というのは、意思決定において、ロジックだけではなく政治的要素が絡む割合が非常に高い組織であるため(だって行政機関ですもの)、年功序列というシステムには一定の合理性があると思います。当選回数で発言力が決まる、そんな政治システムを所与の前提として考える方がおかしい、と反論されそうではありますけどね。 ただ、天下りに批判的な人は省内にも非常に多いと思っています。自分も、天下りできる年齢まで勤めるのかどうか、現時点では全く分かりません(他方、2、3年で転職するつもりもありません)が、天下りは廃止すべきだと考えています。 公務員の人事制度は、残念ながらようやく改革が始まりかけているというのが正確なところでしょう。日系企業の多くが成果主義を導入しようとしつつも、本質的には年功序列のシステムが残ってしまっているというのは本書の指摘通りだと思います。それほどまでに、年功序列システムというのはこの国にどっしりと根を下ろしています。 本書が更に指摘するように、人事コースの複線化、というのが今後の日本式人事システムを考えていく上でもキーになることは間違いないでしょう。多様なキャリアのあり方を、組織の内外含めて社会全体として作り上げていくことの重要性を、強く認識する必要があります。 我々、若い世代も積極的に意見を提示していくべきだな、と思ったのでした。
Posted by
2013.01.08読み終わり。 2006年ものだが、今読んでも当てはまることが多く感じた。むしろ、今の方がより当てはまるのかもしれない。 筆者は、働く動機についてのことを書かれているが、他のレビューでもあるように私も特に今のレールを降りる気は現状ない。 最近、結婚し子どもも産ま...
2013.01.08読み終わり。 2006年ものだが、今読んでも当てはまることが多く感じた。むしろ、今の方がより当てはまるのかもしれない。 筆者は、働く動機についてのことを書かれているが、他のレビューでもあるように私も特に今のレールを降りる気は現状ない。 最近、結婚し子どもも産まれたが、レールをいざ飛び出したとして、リスクが非常に高く付きまとう。 確かに今の既得権保持の為の情勢は納得できるが、中々難しいと思う。 余計に結婚や子どもとか考えられなくなってしまうのではないだろうかとも思う。 そして、基本的に銀行など昔は花形で今は変わったというような文章あるが、今私が勤めている会社から比べてれば、今だって充分給料もらってる(実際の地銀勤務の友人と比較)。 目的意識を高く持ち、自ら考えてやりたいことに真っ直ぐ進むのも大切だが、人によって大切にするものも違うと思う。 いずれにせよ、考えさせられる本だった。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
第1章 若者はなぜ3年でやめるのか? わがまま、甘い、我慢できない言われるけど、なにも僕らだけが悪いんじゃないんですよー!企業の選考が、そんな僕らを生み出してるんです。 第2章 やる気を失った30代 おっちゃんらも大変なんやで。成長が横ばいなって、ずっと続いてたレールが突然途切れたもんだから。若い頃の約束とちゃうやん、そらヤル気も起きませんわ。 第3章 若者にツケをまわす国 新卒採用削減、派遣社員増加、年功序列で年取った管理職の給与を賄うために、僕らは痛い目にあっとるんです。それに貴方たちはじっとしてれば退職金と年金を貰える生活が送れるだろうけど、僕らにはその保障も無いんすよ、なのに保険料あがるでしょ?もう子育てどころじゃないですよ。なぜこれから死に行く人の手当が厚く、子育て世代、生まれくる子供に厳しいんだろう。もうやってらんねーっすわw 第4章~6賞 年功序列の光と陰 なぜ、こんな仕組みを好むのか?その答えは、日本の教育にある。 ほとんどの人がそんな仕組みの中で働かなければならない、じゃあ僕らはどうしたらいいんだろう? 年功序列という昭和的価値観が生み出した、若者の苦しみ。 不透明な人事システムだったけど、こんなに理不尽なんだと読んでいて思った。 では、僕たちに何が出来るのか。 後半ではどう行動を起こすべきか具体例を挙げながら、働く理由を取り戻す糸口、若者がなすべき事を提案している。 不満があるなら、自分で変えてくしかない。 冷静に会社の仕組みを見る視点と、行動を起こす勇気をもらった一冊。
Posted by
うちの会社も半数は非正社員で構成されている。 人件費を削減するための有効な手段。 必要となれば簡単に募集。 余剰が出れば、契約更新お断り。 年をとった人も、若い人もいるが、 それぞれの事情で勤めている彼ら。 雇用側からすればもっと頑張って欲しいと思い、 雇われ...
うちの会社も半数は非正社員で構成されている。 人件費を削減するための有効な手段。 必要となれば簡単に募集。 余剰が出れば、契約更新お断り。 年をとった人も、若い人もいるが、 それぞれの事情で勤めている彼ら。 雇用側からすればもっと頑張って欲しいと思い、 雇われている側からすれば、そんなにはやりたくない。 モチベーションをどうやって維持すればいいのだろう。 どこを目指せばいいのだろう。 自分もアルバイトから採用されて20年。 次第に雇用側に染まってきて、 でも、若い彼らの明日をサポートしてあげたい、とも思う。 中年の明日も不安だけど、若者の未来がせつなく思えてくる。 この本をバスの中で読みながら向かった忘年会。 滅多にしたことがないけど、若い連中を連れて飲みに行ったりした。
Posted by
「年功序列が諸悪の根源」というスタンス. このシステムが機能していた時代は,年功序列によって敷かれたレールに従うだけでよかった.現在はこのレールが崩壊しかけている.そしてこのレールは乗り続けても地獄,降りても地獄というものである. すなわち,乗り続けた場合も上が詰まっているた...
「年功序列が諸悪の根源」というスタンス. このシステムが機能していた時代は,年功序列によって敷かれたレールに従うだけでよかった.現在はこのレールが崩壊しかけている.そしてこのレールは乗り続けても地獄,降りても地獄というものである. すなわち,乗り続けた場合も上が詰まっているため出世できるのはわずか. 一方,レールから降りても必ず成功できるわけではない.また新卒至上主義のため元のレールに戻ることは困難. 若者にできることは「声を上げること」と「働く目的を考えること」
Posted by
売れた本だけに面白い。 とくに第四章年功序列の光と影の部分は、光の部分しか見ることができなかったのですごく参考になった。 最終的に著者は「年功序列の企業にいても食べることには困らないと思う。でも仕事にやりがいや賃金を求めるならば…」と独立や起業をすることをオススメしているのだけど...
売れた本だけに面白い。 とくに第四章年功序列の光と影の部分は、光の部分しか見ることができなかったのですごく参考になった。 最終的に著者は「年功序列の企業にいても食べることには困らないと思う。でも仕事にやりがいや賃金を求めるならば…」と独立や起業をすることをオススメしているのだけど、やっぱりレールを降りる勇気はない。
Posted by
この本を読んで、 「働くこととはー」 ということを真剣に考えなければならないと思いました。 今までは年功序列制度が機能していたためなんとなく働いててもそれなりのポストと給料が与えられていた。 しかし、今は年功序列はなくなりつつあり、自分達はその恩恵を受けることはできない。 「何の...
この本を読んで、 「働くこととはー」 ということを真剣に考えなければならないと思いました。 今までは年功序列制度が機能していたためなんとなく働いててもそれなりのポストと給料が与えられていた。 しかし、今は年功序列はなくなりつつあり、自分達はその恩恵を受けることはできない。 「何のために働くのか-」 年功序列制度が崩壊し、成果主義にシフトしつつある今でこそ、自分の人生を楽しく送るために働くと意識していきたいです。 終身雇用の保証がなくなってしまったのなら、せめて仕事に楽しさを求めるくらいの権利は与えられてもいいのではと若者の立場から思います。 社会にまだ出てない学生の私にとって衝撃的な内容でありましたが、働くことについて真剣に考えるきっかけとなりました。 ぜひとも平成生まれの私達若者世代に読んで欲しい一冊です。
Posted by
結構前に書かれた本、いまさらながら読んでみる。家の本棚にあったのさ。 タイトルがいい。「なんで最近の若者は会社をすぐ辞めるんだろう」とか「フリーターはけしからん!」と思っているサラリーマンのおじさん世代に受けそうなタイトル・・・でも、副題が著者の本当に言いたいことの訳だ。こん...
結構前に書かれた本、いまさらながら読んでみる。家の本棚にあったのさ。 タイトルがいい。「なんで最近の若者は会社をすぐ辞めるんだろう」とか「フリーターはけしからん!」と思っているサラリーマンのおじさん世代に受けそうなタイトル・・・でも、副題が著者の本当に言いたいことの訳だ。こんな本書いちゃうなんて(しかも若干30すぎってくらいで)、きっとやり手のお兄さんなんだろうと想像した。 内容そのものは新書としてさらっと読めて賢くなったような気分になるものだ。年功序列社会の弊害、よくわかりました。 しかし、問題はこの本に出てくる例には、女が一人もいないこと。女の場合はあまりに複雑すぎて書けなかったのか? それにつけても、日本の雇用形態のこの急激な変化・・・おじさん世代(うちの親の世代だ)だけが恩恵を受けるこのシステム・・・選挙は明日だけど、どうにかなるんであろうか。
Posted by
『若者はなぜ3年で辞めるのか?』 なかなか惹かれるタイトルだ。 「銀行員」や「公務員」といったいわゆる安定職種が幅を効かせたのは今は昔。 それは年功序列型という、慢性化の劣化が著しいからだ。 銀行員なんていまや外資系企業が進出してきて実力行使でなくては生きながらえないし、公務...
『若者はなぜ3年で辞めるのか?』 なかなか惹かれるタイトルだ。 「銀行員」や「公務員」といったいわゆる安定職種が幅を効かせたのは今は昔。 それは年功序列型という、慢性化の劣化が著しいからだ。 銀行員なんていまや外資系企業が進出してきて実力行使でなくては生きながらえないし、公務員の抜本的基盤となる年功序列型制度が傾きかけていからだ。全くもって埒も無い。 それでもいましがたそういう職種が幅をきかせているのは、案に「平穏」と「安定」に飢えている「不安定時代」の烙印を押印していることを浮き彫りにしている。 「石の上にも三年」とかいう諺が存在するが、その「三年」とはつまり、故人が企業の将来性を吟味する熟考する最良な尺度だからこんな諺が産まれたのではないだろうか? 昭和的価値観を幼児教育のときから叩きこまれたいわゆる「団塊の世代」の固執観念と、実力本位でのし上がる現代成人が培った「成果主義」との間の確固たる相違の溝が埋まらず、その今までのツケが衝突へと発展しているのが今の現代社会の縮図のようなものとして思えてならない。まさに欺瞞だ。そこに突然右も左も分からないままに放り込まれた者の立場はどうなるんだ? 誰が責任をとってくれるんだ? 「雇用問題」「年金問題」「税金問題」……先人が遺した莫大なツケは後世後世へと脈々と受け継がれていく。 焦ってはならない、抗ってはならない、媚びへつらってもいけない、そして行動をしなくてはならない。見定めることが最重要課題だとおもう。 『若者よ、働く理由を取り戻せ!』
Posted by