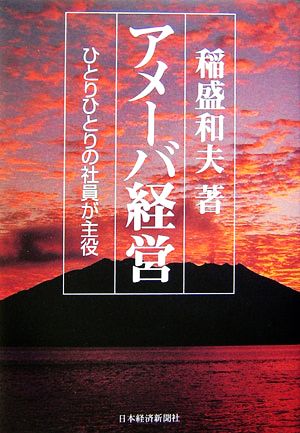アメーバ経営 の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
アメーバ経営の本質や稲盛和夫氏の理念が良く分かる書である。高収益体質を築くために氏が拘った要素は、<市場感度×会計の透明•可視化×経営視点>と表せる。ポーターは競争戦略の要轍とは、全く違う事をするか、同じことを違うやり方でし続けるか、二つしか無いとしたが、アメーバ経営は京セラが値下げ競争の激しいセラミクス業界において生き残って来たように、後者に重点が置かれている。そこでは、「製造部こそ利益の源泉」(p176)と言うように、製造部門にいかに市場のダイナミズムに触れさせ、コスト管理の場ではなくプロフィットセンターに転換するのか、まさに「技術屋経営者」ならではの発想がある。 要するに、一つの独立した事業体として成り立つように部門を分ける。そして、市場を会社内にビルトインするため、外部に加え内の取引で利益を出しつつ互いに競争し、全体としての会社の利益を増やそうと言うものだ。その公正な働きのために、京セラではどのような仕組みを採用しているかを説明している。これはこれから働く企業が「アメーバ経営」を採用している事もあり、非常に参考になった。 前回読んだ、『実学』では、会計を経営で使えるようにタイムリーに可視化することを模索する中で、それぞれの従業員に採算を意識した経営者視点で働くことの必要(全員参加型経営)を説いていた。本書では、一歩進んで、具体的にどのように付加価値を出すのか、市場感度×会計の可視化の角度から説明する。 本書を読んで感じるのは、この経営システムでも、営業と製造間の軋轢が完全には解消できないことだ。だから政治的な存在として、より上位の「公平」なる経営者が必要とされる。しかし、取引が公平か否かはどう決められるのだろうか。外部の市場における情報は営業の方が持っているだけに、製造部門はどのように自らの製品の正確な価値を見極められるのだろうかという問題が生じる。 ここから、なぜ氏が「値付けこそ経営の本質」というのかも理解できる。というのも、関係部門が納得する値段で、かつ市場でも闘える値段を付けることがこの仕組みの成否を決するぐらい大事だからだ。内部での根付け交渉の場が公平な市場を反映するには、必ず外部市場の情報の共有が必要になる。そして、生の情報を共有するためには、セクションではなく会社の理念を信奉し、使命感を持った、調整能力が高い現場を知る経営幹部が必要となるということだろう。この点では日本の政治も経営も変わらぬ指導者像が必要とされる。突っ込みどころはあるが、面白い!!
Posted by
読んでいると「こんな各従業員に依存した経営管理うまくいくかよ」と思ってしまうが、うまくいっているのでなにも言えない アメーバ経営を事細かに解説というよりは稲盛さんの経営哲学書といった感じで働く人は全員意識として持っているべきことが繰り返し書いてある 自分はそのスタンスで何度も読も...
読んでいると「こんな各従業員に依存した経営管理うまくいくかよ」と思ってしまうが、うまくいっているのでなにも言えない アメーバ経営を事細かに解説というよりは稲盛さんの経営哲学書といった感じで働く人は全員意識として持っているべきことが繰り返し書いてある 自分はそのスタンスで何度も読もうと思った ほんとに自社で実践したいと思ったら、これを読んでこの経営管理システムの真意を十分にくみ取る必要がある そうじゃないと形だけのアメーバ経営になってしまいかねない
Posted by
稲盛和夫の実学を合わせて読みたいと思いました。 各部門事で収益を認識する発想はとても感銘したが、なかなか成果が見えにくい研究開発部門に対しての評価基準はやはり難しいと思った。
Posted by
アメーバ経営は、本当によく考えられた手法。 当たり前だと思っていたことへの疑問を逃さず、本質的な点を大切にした経営手法。さすが稲盛さん、すごい! 備忘録 •過去の数字でなく生きた数字 •アメーバによる社内売買 •社員の理解を得るために実態をできる限り開示 •成果主義は短期的に良...
アメーバ経営は、本当によく考えられた手法。 当たり前だと思っていたことへの疑問を逃さず、本質的な点を大切にした経営手法。さすが稲盛さん、すごい! 備忘録 •過去の数字でなく生きた数字 •アメーバによる社内売買 •社員の理解を得るために実態をできる限り開示 •成果主義は短期的に良いが、長期的には心を荒廃させる •アメーバ経営による経営者意識の育成 •適切な人材がいるから新事業に進出する •アメーバ体制で、打てば響く組織に •総付加価値➗総労働時間=時間当たり採算 •当座買いの原則 •売値ー原価=利益 つまり、市場価格ありき。客が値段を決める •利益の源泉は製造にある意識の徹底 •原材料をどれだけ使ったかでなく、どれだけ買ったかで経費考える •潜在意識にしみわたる程強く持続した願望をもち、四六時中考える【強い願望と使命感】 •チーム目標は、即座に口に出る程メンバーに徹底させる •リーダーは、なんとしてでも達成させるという強い意志必要 •営業の使命とは、客が喜ぶ値段を見抜くこと •会社全体としての視野に立ち、人間として何が正しいのか。それが判断基準
Posted by
存在は知っていたが今まで読まなかった本。経営哲学から組織、管理会計、人材育成のあり方に落ちてくる。個別のファンクションではなく、企業という一つの有機体が血を通わせ筋肉をつけ永続的に生き抜くにはどうすればいいかというの命題に対する一つの解。
Posted by
京セラ・KDDIの創業者である著者が自身の経営哲学を語っている。なぜ京セラが小さな工場から日本を代表するグローバル・カンパニーになれたのかが分かる。 著者の考えは極めてシンプル。「売り上げを最大に、経費を最小にすれば、利益は最大になる」なんて当然だけど、それを実現するのは難し...
京セラ・KDDIの創業者である著者が自身の経営哲学を語っている。なぜ京セラが小さな工場から日本を代表するグローバル・カンパニーになれたのかが分かる。 著者の考えは極めてシンプル。「売り上げを最大に、経費を最小にすれば、利益は最大になる」なんて当然だけど、それを実現するのは難しい。著者は簡潔な会計システムと優れたマネジメントでそれを実現してきた。 いちばん印象に残ったのは「能力を未来進行形でとらえる」という部分。「今はできないけど、必死に努力すればできるようになる」という決して珍しくはない考え方。でも、常にこうやって考えるのは簡単じゃない。その考えを習慣づけることが成功につながるんだと思う。
Posted by
アメーバ経営とは、京セラの稲盛会長が生み出した経営手法で、組織を50人程度のアメーバ(小集団)に分けて、アメーバを「時間当り採算(付加価値)」で評価する経営手法。 アメーバ経営自体は、大学生の時に習いましたが、社会人経験を積んでから経営学の本を読みなおすと気付きが多いので、もう...
アメーバ経営とは、京セラの稲盛会長が生み出した経営手法で、組織を50人程度のアメーバ(小集団)に分けて、アメーバを「時間当り採算(付加価値)」で評価する経営手法。 アメーバ経営自体は、大学生の時に習いましたが、社会人経験を積んでから経営学の本を読みなおすと気付きが多いので、もう一度読んでみました。 本書に書いていることを実現できれば、稲盛会長の狙い通り「市場に直結した部門別採算制度」、「経営意識をもつ人材の育成」「全員参加経営」は実現できそうと思いました。ただし、部門を細かく分けることにより、部門間の対立や部分最適になりがちな部分をどのように排するのかという重要になると思いますが、本書では、フィロソフィを持った上位責任者が裁くのみの記載であり、その部分が曖昧かなと思ったりしました。 実際のところは、京セラは強固な縦割りの事業部があり、その中で組織が分割されていること、体育会ノリの縦社会という話なので、そのあたりのデメリットが問題になることは少ないのかなと思ったりもします。 「時間当たり採算=(売上-経費)/労働時間」ということは知っていましたが、「経費に人件費をなぜ含まないのか」、「労働時間で割る理由」について、明確に説明されていて、その部分が気づきでした。 高付加価値を生み出すことに注力して働かないといけないと思いました。
Posted by
管理部門についてどう考えているか、ちょっと気になって読んでみました。アメーバ経営の根幹を支えているようですね。 ビジョナリーカンパニーに感銘を受けてるものとしては、こういう稲盛教ともいわれる(らしい)、経営理念に共感ある一方で、このとおりに強く達成を求められるとしんどいよなあ...
管理部門についてどう考えているか、ちょっと気になって読んでみました。アメーバ経営の根幹を支えているようですね。 ビジョナリーカンパニーに感銘を受けてるものとしては、こういう稲盛教ともいわれる(らしい)、経営理念に共感ある一方で、このとおりに強く達成を求められるとしんどいよなあとか思う自分もいますよと。 それにこんなにいいことばかり書いてある会社の実態はろくなことないというのも、結構な確率であたるマーフィーの法則のひとつではなかろうかと思われる。 時間当りの考えというのはいいと思う。生産性を捕捉できますからね。労働時間がサービス残業といわれるものも含めカウントされてるならば。 また、ここは管理会計と財務会計をどうしてるのか気になった。現金主義サイコーみたいなノリでしたが、財務会計はそれように別個に組んでるのかしら。さらにリサーチしていきたい。 組織づくりの考えもまったくその通りだと思う。組織の構想を必要な機能から作り込んでいくという至極当たり前だと思われるけど、この辺はもっと考え込んでいきたい。
Posted by
会社内部を採算性管理できるレベルまで細分化し、損益計算と時間あたりの採算性を実現しているらしい。それを可能にしているの経営管理システムの運用すれば良いだけでなくフィロソフィを備えたアメーバリーダーが経営者マインドをしっかり持って覚悟を決めて取り組む必要があるらしい。ということがお...
会社内部を採算性管理できるレベルまで細分化し、損益計算と時間あたりの採算性を実現しているらしい。それを可能にしているの経営管理システムの運用すれば良いだけでなくフィロソフィを備えたアメーバリーダーが経営者マインドをしっかり持って覚悟を決めて取り組む必要があるらしい。ということがおぼろ気ながらわかった気がする。でも直接部門の各工程がアメーバとして機能しているみたいだが、間接部門が独立したアメーバになっているかは読み取れなかった。むしろ間接部門費は直接部門の各アメーバに配賦され、その配賦が膨らむと直接部門アメーバから指摘される仕組みらしい。直接と間接が同じ事業(工場)ならわかるが、国内と海外に別れていても機能するのだろうか。。開発部門はアメーバになる、もしくは組み込まれることは可能なのだろうか。。いろいろ疑問が残るな。
Posted by
【目的】経営管理手法を学ぶため 【要約】 まとめ→時間あたり採算性(1時間でどれだけ付加価値を生み出したのか)を採用することで、誰がどれだけ利益を生み出したかをクリアにした メリット:さらに組織を一つのアメーバとして分割(独立採算制に)することにより、各アメーバ(組織)が一つの...
【目的】経営管理手法を学ぶため 【要約】 まとめ→時間あたり採算性(1時間でどれだけ付加価値を生み出したのか)を採用することで、誰がどれだけ利益を生み出したかをクリアにした メリット:さらに組織を一つのアメーバとして分割(独立採算制に)することにより、各アメーバ(組織)が一つの会社のような意識で採算を意識することができる デメリット:製造と営業が自分達が儲けようとして対立する 対策:製造の生産金額の10%が営業の儲け→営業も製造側と協力する 不満点:具体的な手法はあまりかかれていない。哲学的な表現が多いため実態に活かすことは難しそう。
Posted by