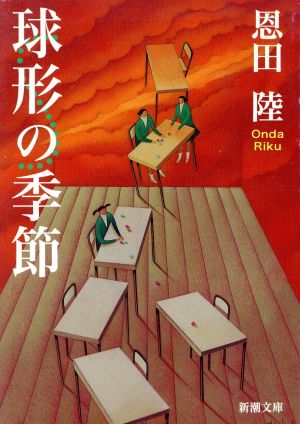球形の季節 の商品レビュー
世界がズレて見える、ぞっとするのに懐かしい既視感 初めて読んだのは中学生のころ しっかりオチのつく物語ばかり摂取していたので、最終的な展開にエッ?と戸惑ったのを覚えている。 夜のピクニックや六番目の小夜子などは読んだことがないが、自身の体験と重ねて感情移入しやすかった。その後何回...
世界がズレて見える、ぞっとするのに懐かしい既視感 初めて読んだのは中学生のころ しっかりオチのつく物語ばかり摂取していたので、最終的な展開にエッ?と戸惑ったのを覚えている。 夜のピクニックや六番目の小夜子などは読んだことがないが、自身の体験と重ねて感情移入しやすかった。その後何回か読み返したが、やはり引き込まれる。
Posted by
『球形の荒野』ではない。『球形の季節』だ。 『六番目の小夜子』に続く恩田陸の2作目だが、恩田陸としてはすでに完成しているんだけど、でも、まだまだ途上みたいな?w 続く『不安な童話』やその次の『三月は深き紅の淵を』になると、逆に(プロとして)暗中模索しているのが窺えるんだけど、これ...
『球形の荒野』ではない。『球形の季節』だ。 『六番目の小夜子』に続く恩田陸の2作目だが、恩田陸としてはすでに完成しているんだけど、でも、まだまだ途上みたいな?w 続く『不安な童話』やその次の『三月は深き紅の淵を』になると、逆に(プロとして)暗中模索しているのが窺えるんだけど、これは、自分が書きたいのはコレ!(というよりは、今はコレしか書けない?)みたいな勢いがあって、そこがいいんだと思う。 確か、『六番目の小夜子』のあとがきで、著者は“「少年ドラマシリーズ」のオマージュとして書いた”みたいなことを書いていたが、これもまさにそんな話。 すごくそそられる展開に対して、結末は尻すぼみという流れは「赤外音楽」に近いw (もっとも、「赤外音楽」は怖すぎて最後まで見られなかったのでw、あくまで原作の結末) ただ、この話って。それなりの結末をつけたら、逆につまんなくなっちゃったんじゃないかなーという気もするかな。 というのも、どうやらこの話の真相というか、底流にあるものは、晋や静の世界らしいんだけど、この話にその世界観でそれなりの結末をつけられてもなーという気がするのだ。 その世界観って、普通に考えればホラーやファンタジーだし。 もしくは、変な屁理屈もってきてSFにするというものあるとは思うんだけど、でも、そういう話になっちゃたら、主人公がみのりというキャラクターでいいの?ということになると思うのだ。 この話の魅力は、みのりというどこにでもいる平凡な女子高生と、その周囲のやっぱり平凡な人たちが暮らす谷津という、やっぱりこれもどこにでもある平凡な東北の小さな町に起きる、“日常の”不思議な出来事という、あくまでそのレベルの話なところにあるんだと思う。 解説では、ファンタジー云々と語られているけど、そうではなくて。 言ってみれば、「日常の謎」として解釈してしまうなら解釈できてしまって(だって、ほとんどの人は晋たちの世界は知らないわけだもん)、後に誰もが「あの時のあれって不思議だったなー」と思い出すみたいな、たんなる淡い青春譚と読めるからこそ、読者(特に恩田陸のファン)は惹きつけられるんだと思うのだ 例えば、変な話、心霊スポットに行ったところで、何もないことが普通なわけだ。 でも、それだとつまらないから、写真に写った水滴を「オーブだ!」とみんなで共有することで思い出にする。 と言ってしまったら身も蓋もなくなってしまうけど、でも、これってそういう誰しもの青春にあった出来事の話として読んだ方が楽しめる気がする。 ていうか、恩田陸の小説の魅力って、そこなんだろう。 プロットで書く小説全盛(なのかどうかは知らないw)の中、書くことで想像がどんどん膨らんで、ストーリーが勝手に動き出すタイプの作家の小説というのは独特の魅力があるし。 なにより、読んでいて面白い。 恩田陸という作家は、その極端なパターンなんだろうw とはいうものの、この小説、青春譚として読むには、主人公であるみのりの存在感が妙に薄いんだよなー。 それこそ、みのりの関係ないところで、話がどんどん展開されていく。 だからって、話を展開していく登場人物たちも、その展開の必要に応じてちょこっと出てくるだけだから、やっぱり存在感がなくて。 際立つ登場人物がいないことで、さらにみのりの存在が希薄になっていくような気がする。 それも青春なんてそんなものと言ってしまうなら、確かにそうなんだろうけど。 とはいえ、これは小説なわけでw 個人的には、みのりと久子の二人を主人公に書いたら、ストーリーがもっと締まったんじゃないのかなーなんて思った。
Posted by
6番目の小夜子、夜のピクニックで期待しすぎたかな? ちょっと合いませんでした。登場人物のエピソードが小出し過ぎて 少し間をおいて読み始めると誰が誰だったか分からなくなりました。 そうなるとストーリーどころではありません。ただ面白いエピソードは 有ったので惜しい感じです。
Posted by
学園もの、ホラー、ということで小夜子に近いかな?と思ったのであんまり期待しないで読んだ。だからか割と楽しく読めた。 確実に人ではない何かが関与している土地だと分かっているから、未知の存在がいるというだけでホラー感あってとても良い。 最初のアンケートのやつがよくわからなくて、読み...
学園もの、ホラー、ということで小夜子に近いかな?と思ったのであんまり期待しないで読んだ。だからか割と楽しく読めた。 確実に人ではない何かが関与している土地だと分かっているから、未知の存在がいるというだけでホラー感あってとても良い。 最初のアンケートのやつがよくわからなくて、読み進めているうちにちょっとずつ面白くなっていった。 自分も東北出身だけど正直地元には全く魅力を感じていないので、気持ちとしては久子に近いかなと思ったけど、晋に入れ込んでいく彼女は嫌いだなと思った。でもこういうところは普通の高校生だなぁとリアルさを感じた。 読み進めてページ数が少なくなっていくのにこの展開の感じは…とある種の予感があった。これは夜の底は〜で感じたあれと同じだ。その予感通り恩田作品あるあるな終わり方をしたのでそこまでがっかりしてないです。むしろ小夜子よりずっとすっきりしてると思う。 仁さんはきっと教会に行ってしまうんだろうな。
Posted by
田舎とかだとよくありそうな感じの内容です。 登場人物の魅力がたまりません!! 皆んなどこか大人っぽい感じで私個人としては好きなストーリーと登場人物の性格に惹かれてしまいます!!
Posted by
1990年代2作目「球形の季節(1994年)」 1作品目に続き、田舎、高校生が主人公。怨念に一見的な偶然を重ね(必然)、無念をはらすという作品と感じた。 この後、全寮制作品も出てくるし、著者は高校生時代に思いが深いのだとしみじみ感じる。 情報がない時代だと、アリバイ工作が簡単...
1990年代2作目「球形の季節(1994年)」 1作品目に続き、田舎、高校生が主人公。怨念に一見的な偶然を重ね(必然)、無念をはらすという作品と感じた。 この後、全寮制作品も出てくるし、著者は高校生時代に思いが深いのだとしみじみ感じる。 情報がない時代だと、アリバイ工作が簡単だが、情報化社会では簡単に位置情報でさえ、わかってしまう。仮想情報が完璧に出来たら、それはそれですごいけど。 昔懐かしい作品といえる。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
ある噂が広がる中、噂の出所を突き止め解決する話。かと思いきや、これは事件を解決する話ではなく、祈りながら待ち続ける人達の話。 . それぞれが進んで行こうとする、重大な場面で、クライマックスの直前で物語があっさりと終わってしまい、「うわ!」と思わず声に。
Posted by
噂、おまじない、、って聞くとワクワクする。そんな何かを期待させてくれるような雰囲気が溢れているから好き。 ただ、何度も読んでいるのに、この物語が伝えようとしている本質のようなものにたどり着けていないような気がする。 そういう感覚もまた私にとっては魅力的なのかも。
Posted by
導入は意識が文章に入っていかず、眠気との戦いだったが、徐々に、先に読んでいた常野物語と似た世界観が展開され、のめり込んでいった。それにしても、恩田ワールドは、文字だけで叙情風景を描き出すのがなんてうまいのだろう。
Posted by
まず各章の中のセリフからとった章タイトルのつけかたがかっこいい。噂を効果的に使っており、向こう側の世界が出てくるものの全体をこちら側にとどめながら雰囲気を盛り上げる手腕は新鮮だった。噂は人々が語りたいから広まるという説明はなるほどと思わせられた。だから「ノーライフキング」で子供た...
まず各章の中のセリフからとった章タイトルのつけかたがかっこいい。噂を効果的に使っており、向こう側の世界が出てくるものの全体をこちら側にとどめながら雰囲気を盛り上げる手腕は新鮮だった。噂は人々が語りたいから広まるという説明はなるほどと思わせられた。だから「ノーライフキング」で子供たちに死の噂が広まるのは彼らが潜在意識の中で死を身近に感じていたからだということが今更ながら納得できた。東北の眠ったような町という設定や次々起こる事件の配し方が効果的。「十六番目の小夜子」も読んでみよう。
Posted by