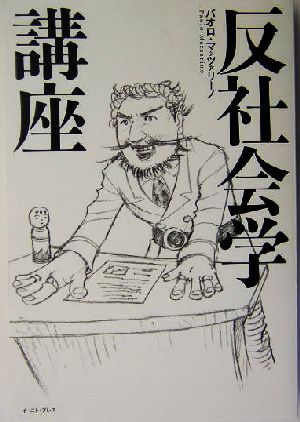反社会学講座 の商品レビュー
タイトルどおりの社会学へのカウンター。古い書籍だけど、実は現在でも罷り通ってる欺瞞の多いこと、多いこと。
Posted by
メラビアンの法則が嘘だとかいろいろ書いてある。いろいろ参考になった。社会人がスーツを切る理由とか挨拶をしないといけない理由など。
Posted by
知識・ノウハウの相続というところを読んで「ロバートキヨサキ」を思い出しましたがその後本書にもロバートキヨサキと金持ち父ちゃんの話があり、笑えました。
Posted by
「イギリス人はふにゃふにゃ」、「昔の日本人は偉くなかった!」などの一刀両断は読んでいて気持ちが良い。 まぁ、マスコミが発表する類いのものが、どれだけ適当なリサーチで作られているのか実感。 大事なのは、その数字に惑わされないで背景を深く探ること。
Posted by
そこらじゅうにある「ふれあい○○」に気持ち悪いものを感じていたが、こんなことも調べるとオドロキの結果がでるのね。データで語られるのでまんまとのせられてしまう。それがダメだと著者はいうけれど。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
我らが卓郎さんがブログで紹介していたもの。面白かった。こういう『世論に騙されるな』みたいな本、好きだわ。でもこの人はきっと、自分が書いていることでも、素直に信じちゃダメよ、と言ってるんだと思う。関係ないけど、「日本人とユダヤ人」を読んだときを思いだした。面接の練習で最近読んだ本として挙げたら、先生に別なのにした方がいい、って言われたよな。これも面接で答えちゃまずそうな本だ。日本人は江戸時代からフリーターが多いとか、金持ちの道楽息子にたくさん金を使ってもらって公平にするのだ、とか面白い。続編も読んでみよう。
Posted by
※感想は2004年の初読時のもの できがいい章は、すでに社会学自身や経済学側からとか、他の人から批判があったところです(苅谷剛彦とか、松谷明彦とか)。視点はいいんだけど、ツッコミはアマアマです。でもそんなことはどうでもいいんです。とにかく勢いがあって、ぱらぱらめくっただけでな...
※感想は2004年の初読時のもの できがいい章は、すでに社会学自身や経済学側からとか、他の人から批判があったところです(苅谷剛彦とか、松谷明彦とか)。視点はいいんだけど、ツッコミはアマアマです。でもそんなことはどうでもいいんです。とにかく勢いがあって、ぱらぱらめくっただけでなんかしったかできそうなにおいがするのが素敵っす。 なにより表紙がいいですね。吉田戦車。しかも1色鉛筆書き。そこにそこどけじゃまだといわんばかりの大いばりで、明朝体の「反社会学 講座」(反社会学、で行替えするのもいい)。白地の表紙だからこそ、見返しはまオレンジではではでに。目次の前に、こけおどしの警句を一発。くそ。遊びやがって。楽しいだろうなぁ、こういう本つくるのは。 というわけで、正直、いい本です。『完全自殺マニュアル』とか『磯野家の秘密』とおなじ意味で、すごーくいい本です。読者としては★3つ。作り手としては★5つ。で、★は間をとりました。これはシャレの本なんだから。「社会学の本」として評価するのはヤボってもんでしょ。天晴れ。
Posted by
愉快な語り口で読みやすかった。「反・社会学」というよりもむしろ「反社会・学」という印象。だがこれは、読者がどのような「社会学」の環境に属しているかで変わってくるものだと思う。個人的には、冒頭の「注意」でも述べられているとおり、社会学の視座を用いた入門書的な側面もあったように思う。
Posted by
「反社会学の不埒な研究報告」 パオロ・マッツァリーノ 二見書房 2005年 面白かったです。 「武士道」「葉隠れ」は読んだことないのですが、これらがありがたがられていることは よ~く知ってるので、世間のブームのいい加減さを知る手段になるかもしれません。 古典は古典として楽しむこ...
「反社会学の不埒な研究報告」 パオロ・マッツァリーノ 二見書房 2005年 面白かったです。 「武士道」「葉隠れ」は読んだことないのですが、これらがありがたがられていることは よ~く知ってるので、世間のブームのいい加減さを知る手段になるかもしれません。 古典は古典として楽しむことは本当に大切なことだと思います。 でも、現代でそれらをソースにして、自分の生活に役立てている人は頭がよいかもしれません。 それをありがたがって、万が一成功したのなら、それもありかもしれません。 でも万人がうまくいくはずもないのでしょう。 186ページの「武士道は忘れた頃にやってくる」で「日本/権力構造の謎」 カレル・ヴァン ウォルフレン 早川書房 1994年について触れていますが、 外国から見た日本ということでも興味深いですし、 「論理的に思考したり、当を得た質問をしないように(子どもの頃から)教育される」と いうのは納得してしまいました。 「和を乱すから許されない」なるほどね~今の職場で当てはめると、わかりやすいわ~ 読んでみるべきか、いやますます暗くなりそうなのでやめとくかな。 先日、テレビで放送していた「北の零年」も納得な章でした。 サムライ(男)の人の役立たずっぷりに頭がイタイ。ま、それが狙いの映画なんでしょうけどね~
Posted by
反社会学も社会学のウチ、という最初に書いてあることさえ読み取れていないアマゾンのレビューを見ながら嫌らしい笑みをうかべるという楽しみ方が出来る本。著者の確信犯っぷりはイタリア人というよりエゲレス人。
Posted by