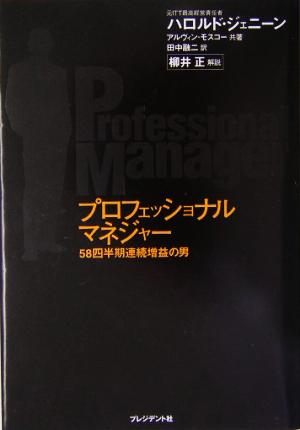プロフェッショナルマネジャー の商品レビュー
米巨大コングロマリットITTを1959年から率い58四半期連続増益を成し遂げた著者の経営論、哲学。ファーストリテイリング柳井会長が教科書とまで言う宣伝は全くの虚飾無しと読了して確認した。コングロマリットのCEOではあるがミドルマネジメントにとっても付加価値は大きい。毎年読み返そう...
米巨大コングロマリットITTを1959年から率い58四半期連続増益を成し遂げた著者の経営論、哲学。ファーストリテイリング柳井会長が教科書とまで言う宣伝は全くの虚飾無しと読了して確認した。コングロマリットのCEOではあるがミドルマネジメントにとっても付加価値は大きい。毎年読み返そう。 「本を読む時は、初めから終わりへと読む。ビジネスの経営はそれとは逆だ。終わりから始めて、そこへ到達するためにできる限りのことをする」「経営者は経営しなくてはならない」
Posted by
楠木建の「戦略読書日記」で紹介されていた本。名経営者の著書はだいたい外れがないので、相当期待して読んだが、「真面目かっ!」と突っ込んでしまいたくなるほどまじめすぎる内容で、正直面白くなかった。 尋常ない勤勉な人で驚くほかない。 唯一、面白いなあと思ったのは、エグゼクティブの机は...
楠木建の「戦略読書日記」で紹介されていた本。名経営者の著書はだいたい外れがないので、相当期待して読んだが、「真面目かっ!」と突っ込んでしまいたくなるほどまじめすぎる内容で、正直面白くなかった。 尋常ない勤勉な人で驚くほかない。 唯一、面白いなあと思ったのは、エグゼクティブの机は汚い、と言い切っていること。これは楠木氏も解説者の柳井氏も触れていた。 「私が反対するのは、きれいな机のエグゼクティブのオフィスの様子とか机の上の状態よりむしろ、彼の心的態度に対してである。きれいな机は科学的経営への、ビジネス・スクール仕立ての方式への、データ整理保存への、過度に厳格な時間配分への、機構化した権限委譲への、そしてまた未来が自分のプラン通りのものを生み出すという当てにならない確信に基づいた無保証の自信と独りよがりへの固執を象徴している。そんなものを、夢にも信じてはならない。」
Posted by
2025-01-02 二度目の読書 2018-10-06 米国の経営者の自伝。ユニクロ柳井社長推薦。経営者の教科書として最良の書籍。経営の秘訣は終わりから始めて、そこへ到達するためにできる限りのことをすること
Posted by
Amazonで上位にランクされていたので読んでみた。 相変わらず、和訳の本は読みにくいと思う。 外国人の名前は頭に入らないし、「彼」とは誰のことなのか読み返さないとわからない。 「マネジャー」「エグゼクティブ」「リーダー」が何なのかを理解してから読むべきだった。 経営の基本も知ら...
Amazonで上位にランクされていたので読んでみた。 相変わらず、和訳の本は読みにくいと思う。 外国人の名前は頭に入らないし、「彼」とは誰のことなのか読み返さないとわからない。 「マネジャー」「エグゼクティブ」「リーダー」が何なのかを理解してから読むべきだった。 経営の基本も知らない私が読む本ではなかった。
Posted by
企業経営者の心構えを書いた本。原題は「MANAGING」で、邦題は中間管理職狙いでしょうか。。 無知で大変恐縮ながら、著者が長年CEOを務めたアメリカのITTって、コングロマリットの元祖的な存在で、シェラトンホテルやエイビスレンタカーが傘下にあったんですね。NTT似の何かかと思っ...
企業経営者の心構えを書いた本。原題は「MANAGING」で、邦題は中間管理職狙いでしょうか。。 無知で大変恐縮ながら、著者が長年CEOを務めたアメリカのITTって、コングロマリットの元祖的な存在で、シェラトンホテルやエイビスレンタカーが傘下にあったんですね。NTT似の何かかと思ったら、全然通信事業者じゃない(笑 コングロマリットって、今でこそ「選択と集中」やら「シナジー効果が!」とか言われて時代遅れな感がありますが、ポートフォリオを適切に選択し、経営改善をやっていくという意味では悪くないのかも。恐ろしく乱暴な表現では、投資ファンド(アクティビスト?)のちょっと持分も口出しも多いバージョン? 読んでみると、時代の差を凄く感じます。 本著で「ガッツのある」と表現される働き方は「成果が出るまで根性でやるんだよ!」的な印象だし、テレックスとか紙とかアルコール中毒とか、時代を感じます。。 とは言え、企業経営には情緒的態度、やり遂げる根性が重要とする著者の論が間違いだとも思わないので、読んでみて損ではないのかも。 全体的に、間違ってはいないけど、日本企業でも既にある程度取り入れられているんじゃないかな…?という感じの内容でした。一部はまぁうちの会社には無理かなと思っちゃうところもありましたが。。 ファストリの柳井社長が愛読されているようで、まえがきと解説を書かれています。 なお、翻訳は超読みやすい訳ではないですが、概ね良好でした。「季員会」というめずらしい誤植があったけど。
Posted by
そもそもITTなる会社を知らないので、ハロルド・ジェニーンなる人がどれだけすごいことをしたのか皆目検討がつかず、この人の言葉に従うべきかがわからない。柳井正の座右の書のようなことだったので買ってみたが、先のとおり今は存在しないITTなる会社を成功させた人の本らしいが、今は存在しな...
そもそもITTなる会社を知らないので、ハロルド・ジェニーンなる人がどれだけすごいことをしたのか皆目検討がつかず、この人の言葉に従うべきかがわからない。柳井正の座右の書のようなことだったので買ってみたが、先のとおり今は存在しないITTなる会社を成功させた人の本らしいが、今は存在しない会社なのだし結果論としては大した経営をしていなかったとも言えると思う。ジャックウェルチにしても結局今のGEの体たらくを招いた責任はあるだろうし、企業経営などというのはその時だけで判断できる訳ではないと思う。内容の点から言うと、経営者たるもの24時間365日働かなくてはダメだというもっともなことと、マイクロマネージメントが大事だといういかにもアングロサクソン的なことが書いてある。チームワークももちろん大事だし、しかしながら人事評価はとにかく冷徹にするということで、とても日本企業には向かないような内容。この本の内容とは真逆の日本的経営がもてはやされた時代もあったことを考えると、結局は経営に答えなどないのだと思う(本書でもそのようなことは言っているが。。。)。とにかく、この本を読むと自分は経営者にはなりたくないし、向いていないと思うし、またこのような人の下では息もできないので働きたくもないと思う。柳井正が信奉しているらしいので、ユニクロもそんな会社なのだろうか?
Posted by
「経営とは、ゴールを決めてそれに向かってやるべきことをやることである。」 元ITT最高責任者で、58期連続増益をあげたハロルド・ジェニーンの経営論。柳井さんがおすすめしているので読んだことがある人も多いだろう。 彼の経験を元に、経営論が書かれた本。マネージャーになる前に読んでおく...
「経営とは、ゴールを決めてそれに向かってやるべきことをやることである。」 元ITT最高責任者で、58期連続増益をあげたハロルド・ジェニーンの経営論。柳井さんがおすすめしているので読んだことがある人も多いだろう。 彼の経験を元に、経営論が書かれた本。マネージャーになる前に読んでおくと良い。
Posted by
2年ほど前に「読め」と言って渡されていたんですが、ようやく読みました。 至極まっとうな内容だとは思いますが、読むことになった経緯が経緯なだけに、複雑な思いをしながら、読み進めました。 さて、どうやって自分の中で折り合いをつけていきましょうか。 ちなみに、最後に、ユニク...
2年ほど前に「読め」と言って渡されていたんですが、ようやく読みました。 至極まっとうな内容だとは思いますが、読むことになった経緯が経緯なだけに、複雑な思いをしながら、読み進めました。 さて、どうやって自分の中で折り合いをつけていきましょうか。 ちなみに、最後に、ユニクロの柳井さんの文章が載っていますが、こちらは、この本のエッセンスを知る上で最適だと思います。 時間がない方は、まずこちらから読んでもいいかもしれません。
Posted by
・本を読むときは、 はじめから終わりへと読む。ビジネスの経営はその逆。終わりから始めて、そこへ到達するためにできる限りのことをするのだ ・リーダーシップが発揮されるのは、言葉より態度と行為においてである ・経験とは、なにか新しいことを発見し、学び、能力の成長をもたらすプロセス...
・本を読むときは、 はじめから終わりへと読む。ビジネスの経営はその逆。終わりから始めて、そこへ到達するためにできる限りのことをするのだ ・リーダーシップが発揮されるのは、言葉より態度と行為においてである ・経験とは、なにか新しいことを発見し、学び、能力の成長をもたらすプロセスである
Posted by
・⭐️本を読む時は始めから終わりへと読む、ビジネスの経営はそれとは逆だ、終わりから始めてそこへ 到達するためにできる限りのことをするのだ ハロルド ジェニーン ・⭐️「経営はまず結論ありき」、結論に至る方法を考えられる限り考え、いいと思う順からまず実行する。 ・⭐️ビジネスは結果...
・⭐️本を読む時は始めから終わりへと読む、ビジネスの経営はそれとは逆だ、終わりから始めてそこへ 到達するためにできる限りのことをするのだ ハロルド ジェニーン ・⭐️「経営はまず結論ありき」、結論に至る方法を考えられる限り考え、いいと思う順からまず実行する。 ・⭐️ビジネスは結果でしか評価されない ・実地により学習する
Posted by