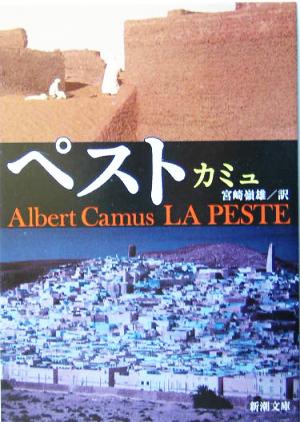ペスト の商品レビュー
まさにコロナ禍と同じ状況。 出かけたまま街が急に閉鎖されたらーー家族を案じて戻るだろうか、戻れるが再び出ることはできない。家族は戻ってきてほしいだろうか。 この「追放」がいつまで続くか、わからない中で、自分で期限を決めて期待するのもそうならなかった場合も悲しみも多い。そのため、人...
まさにコロナ禍と同じ状況。 出かけたまま街が急に閉鎖されたらーー家族を案じて戻るだろうか、戻れるが再び出ることはできない。家族は戻ってきてほしいだろうか。 この「追放」がいつまで続くか、わからない中で、自分で期限を決めて期待するのもそうならなかった場合も悲しみも多い。そのため、人々は何も考えなくなる。 予告して閉鎖したら不平不満もでなかったと思うが、一時を争っていた。 隔離生活の中、次に再会できるのほ全快もしくは死亡したとき。 ペストが収まったときに、大切な人はそばにいるだろうか。元の生活に戻れるだろうか。 自分の力ではどうすることもできない「不条理」を描く。
Posted by
昔の作品だが今のコロナの状況とシンクロしているのですんなり理解できた。物語の人々の行動もおもしろいくらい今のニュースと似ていて、人間の本質はいつの時代も変わらないんだと思った。 登場人物がそれぞれに個性と役割があってとても魅力的。文章は読みにくいが読むべき作品だ。
Posted by
この本ほど、2020年〜2021年の現在と、小説の舞台の内容が比較されるものはないではないだろうか。 ペストと新型コロナ。 病原体の違いはあっても、現在私たちが置かれている状況と余りに酷似した物語は、この2つを横に並べて間違い探しを試みるのも一興というほどだ。 伝染病への対策...
この本ほど、2020年〜2021年の現在と、小説の舞台の内容が比較されるものはないではないだろうか。 ペストと新型コロナ。 病原体の違いはあっても、現在私たちが置かれている状況と余りに酷似した物語は、この2つを横に並べて間違い探しを試みるのも一興というほどだ。 伝染病への対策が後手後手に回り、現実を直視できず決断の鈍い政府。長引く自粛期間(物語では外出禁止令に近いか)における人々の心情。死者は家族に顔を見せることもできず埋葬されていく。 ペストの場合、新型コロナとは違い高い致死率と罹患した際の苦痛があるため、私達の現状と比較すると何とまあ我々は気が抜けているのだろうと思い知らされる。 それが新型コロナの最も恐ろしい点であるのだろうけども。 今この小説を読むとどうしても我々の現状との比較という観点で読んでしまうが、新型コロナ以前ではロックダウンされ、死の恐怖がすぐそばにありながら人間の心理はどのように動くのかということが主題だっただろう。 新型コロナ以前に読んでおきたかった、と強く思う。 なぜなら描かれた人間の心理についても、今の我々のものとの比較として読んでしまうから。
Posted by
人間を打つ殻竿の音 週何人の報道が毎日の死者数の報道へ 観光旅行の破滅 ペスト 繰り返し レコード 足踏み 個人的なものを断念する 一般化された考えしか持たなくなっていく人々 抽象 毎日が死者祭 何気に競技場に来たときのゴンザレスの描写が良い
Posted by
カミュは,第二次大戦で罪もない人達がなすすべもなく死んでいったという不条理について,それをペストという疫病になぞらえてこの小説を書いたのだと勝手に想像するのだが,コロナ禍に襲われた現代社会の右往左往と重なる.近代に入ってからこのようなペストの大流行はなかったと思われるので,想像で...
カミュは,第二次大戦で罪もない人達がなすすべもなく死んでいったという不条理について,それをペストという疫病になぞらえてこの小説を書いたのだと勝手に想像するのだが,コロナ禍に襲われた現代社会の右往左往と重なる.近代に入ってからこのようなペストの大流行はなかったと思われるので,想像で書かれているはずなのだが,流行当初の役所の縦割りの弊害,信じたくない気持ち,その後の社会の麻痺等々,今世界で起こっていることを予言したとしか思えない.いや,カミュの時代にはまだスペイン風邪大流行の記憶は残っていたはずなので,そこがベースになっているのか. やや哲学めいた面もあるので,一気に読みすすめるというわけにはいかないが,読んでよかったと思える名作には違いない.
Posted by
ペストの物語というよりかは人間の心理状態を描写した物語だった。 心の葛藤とか何も出来ない苦しさとか何も感じれなくなってしまうぐらいの疲れとか"ペスト"という得体の知れないものに対して人の気持ちがどう変わっていくのか、自分なりの答えがある人や見つかる人もいれば、...
ペストの物語というよりかは人間の心理状態を描写した物語だった。 心の葛藤とか何も出来ない苦しさとか何も感じれなくなってしまうぐらいの疲れとか"ペスト"という得体の知れないものに対して人の気持ちがどう変わっていくのか、自分なりの答えがある人や見つかる人もいれば、ずっと探し求めている人もいれば、色々な感情や思いが出てくる話だった。 実際自分が同じ状況だったらどうしただろうかと考えさせられた。
Posted by
COVID19の拡大で奇しくも圧倒的な同時代性を手に入れた本作「ペスト」。言うまでもないことだがCOVID19の存在を前提とせずともいつの時代も読む人の心に大きな瘢痕を残し続けてきた大名作だと思う。 理屈も因果も通用しない圧倒的な不条理としては何もペストでなくても地震や台風などの...
COVID19の拡大で奇しくも圧倒的な同時代性を手に入れた本作「ペスト」。言うまでもないことだがCOVID19の存在を前提とせずともいつの時代も読む人の心に大きな瘢痕を残し続けてきた大名作だと思う。 理屈も因果も通用しない圧倒的な不条理としては何もペストでなくても地震や台風などの災害、戦争など他の題材も採用されうる。巻末解説にもあるようにこれをカミュ自身の対ナチス闘争の体験を下敷きにする見方ももちろん理解できる。 しかし、今この時代を生きる我々には感染症が災害、戦争といった他の災厄とは大きく性質が違うのが実感としてある。 ロックダウンがもたらす別離。デマの流布とお守りがわりの似非科学。意味のない統計への異常な関心と無関心。自粛警察と自粛疲れ。自分の生活を完膚なきまでに破壊された人々と逆に社会にコミットしていく人。我々が今まさに感じ、考えていることが1947年に書かれたこの小説に克明に記されている。 終わりの見えないこの日々の救いを求めて読む小説ではないと思う。それでもこの小説が改めて評価される所以は不条理を前にして、際立つ人間の実存に深い共感を抱くからだろう。本作はリウー、タルー、グラン、コタール、ランベール、パヌルーと多種多様な人物が織りなす群像劇だ。リウーの高邁な職業倫理に感嘆し、タルーの過去に暗澹とした想いを抱き、グランの健気な仕事ぶりに心を動かされ、ランベールの人間臭さに共感し、コタールの狂気に恐怖し、パヌルーのラディカルな信仰心に驚愕する。どの人間をとっても全面的でないにせよ共感できる部分がある。 2021前半にして、ベスト3に入る作品。大切に読んでいきたい。
Posted by
新型コロナ下での閉塞した生活と重ね合わせて、カミュの代表作の一つを手に取った人が多いと思います。私もその一人ですが、若き日に「異邦人」を読んだ時とはまた違った印象で、何というか、「ペスト」が象徴しているものが何なのか、色々と問いの残る読後感でした。
Posted by
読むのに疲れたが、いろいろな人間心理が書いてあり、読み進めていくうちに一人一人のことが気になり、社会の様子描写もわかりやすく読み進められた。
Posted by
本箱から、取り出して来た1冊。 平成21年6月20日 71刷の文庫本である。 このコロナ禍で、この本の読者が、増えているとか・・・ もう、数十年前に斜め読みしていたのだが、再度読み返してみて、カミュの不条理の哲学というものに触れた。 ベルナール・ルウーが、階段口で、1匹の鼠に...
本箱から、取り出して来た1冊。 平成21年6月20日 71刷の文庫本である。 このコロナ禍で、この本の読者が、増えているとか・・・ もう、数十年前に斜め読みしていたのだが、再度読み返してみて、カミュの不条理の哲学というものに触れた。 ベルナール・ルウーが、階段口で、1匹の鼠に躓いたことから、発端である。 小さな出来事が、大きな禍となって、町を覆っていく姿は、今、この世界の国々で、起こっている状態であろうと、思うと、今まで読んでいた時よりも、凄みが、強い。 58頁の広東で、4万の鼠が、住民よりも先にペストで、死んだ。と書かれている。 その1匹のネズミの長さが、30㎝として・・・四万匹を並べると、どれ位の長さになるか・・・迄考えている所なんて、悠長に書かれていると、思う。 グランが、リウーに、ぎりぎりの場合、《しかし》と《そして》とどちらかを選ぶかという事は容易だが、《そして》と《それから》をどちらからすると難しくなり、《それから》《次に》になると、ますます難しくなる、と言う。 ちょっとした、言葉の言い方なのだが、なるほど・・・と、思いながら、文章を印刷して発表するには、騒ぎが、終息した後では、何もならないのだけど。 子供の病死の場面は、なんとも読みづらい。 昔、斜め読みしたのも、この部分である。 そして、書かれた時に、戦争の体験によって、死に対して考えが、違っている。 この伝染病ペストは、殺戮のない戦いであると、そして、敵対的人物は、誰もいない。 最後のペスト菌は決して死ぬことも消滅することも無いものであり・・・と書かれており、どこかの幸福な都市にかれらを死なせに差し向ける日が来るであろう。と・・・ 予言者の様な言葉で、締めくくられている所が、なんとも今の現代の様な気がしてならない。
Posted by